

連載 パンデミックに対応可能な安定操業
-石油・化学工場での自動化の課題と解決策-
第11回 スタートアップ/シャットダウン自動化とパンデミック対策
1.はじめに
前回は通常運転時において,「フィールド業務を自動化/効率化することで夜間フィールド無人化を目指して,パンデミック時の不足人員を補う方策」について解説しました。今回は「プラントのスタートアップ/シャットダウンの自動化とパンデミック対策」について解説します。ここでいうシャットダウンは緊急停止のことではなく,図1に示すようなノルマルシャットダウンを意味します。
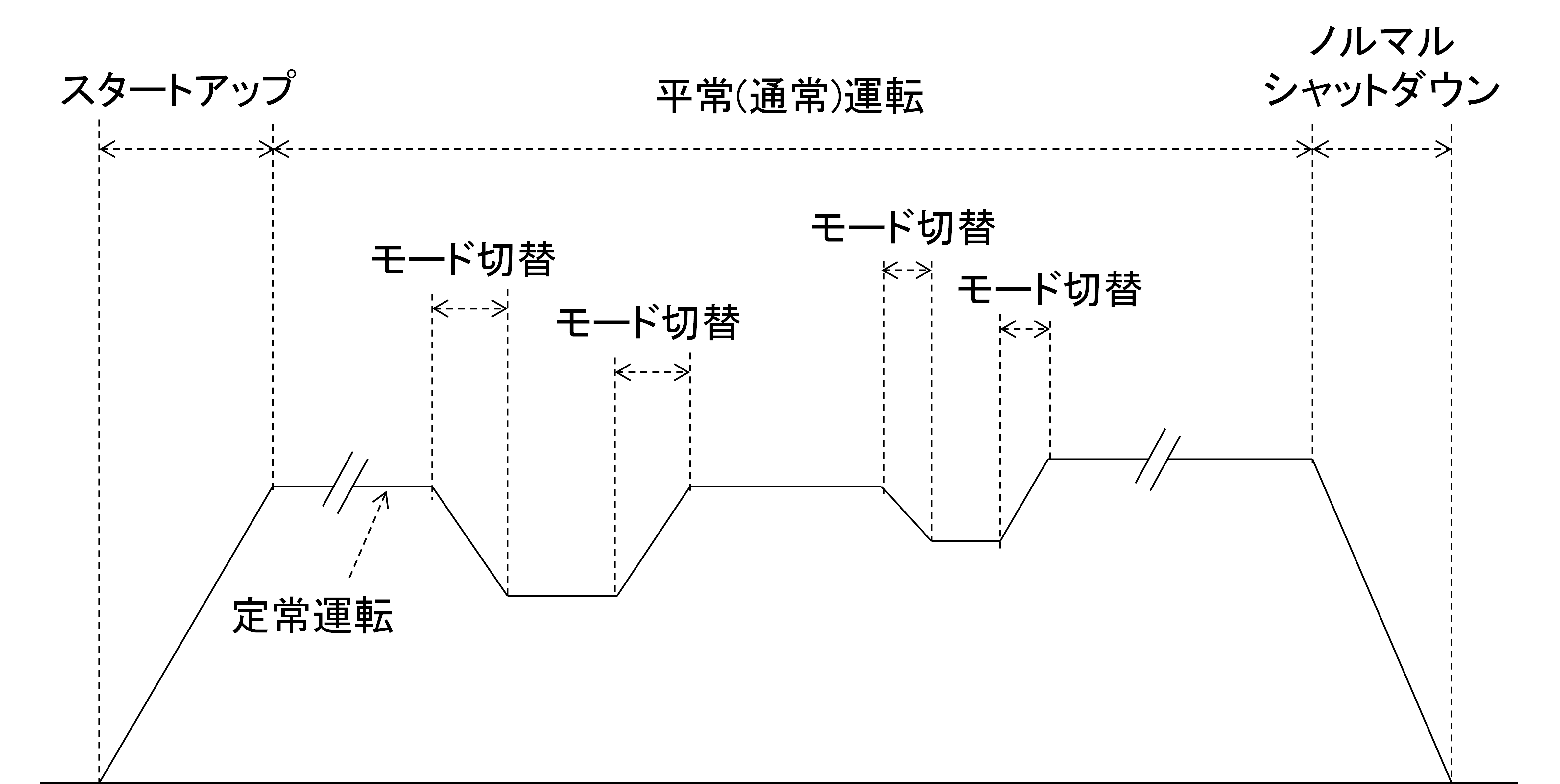
パンデミック時にスタートアップ/シャットダウン操作が発生した場合は,少ない人員にて操作を実行する必要があり,できるだけ自動化を行い,人の負担を減らす必要があります。しかしながら,スタートアップ/シャットダウンの自動化は言われて久しい課題であり,実現できていないのも事実です。
そこで,ここではその必要性を今一度考え,具体的な実現方法を提案することにします。
2.スタートアップ/シャットダウン自動化の必要性について
近年プラントの長期連続運転が実現してきており,図1に示すようなスタートアップとシャットダウンの間隔が長くなり,その操作頻度が減ってきている状況にあります。
スタートアップ/シャットダウン操作では,事故トラブルが発生する確率も多く,ベテラン,経験者による操作を必要とせざるを得ないのも事実です。しかしながら経験者,ベテランであっても操作頻度が少ない現状では,必ずしも安全を確保した操作が可能とは言えません。
こうした観点からは,スタートアップ/シャットダウンにおいては,操作ガイダンスを含めた自動シーケンス化が期待されます。
また,昨今プラントオペレーションでの人材の確保の問題がクローズアップされてきています。働く環境の近代化,IT化の推進の観点からも期待されている課題と考えます。
3.スタートアップ/シャットダウン操作の現状と今後の自動化の方向
3.1 スタートアップ操作の現状と今後の自動化の方向
表1は,スタートアップ/シャットダウンの現状と今後の自動化の方向をまとめたものです1,3)。
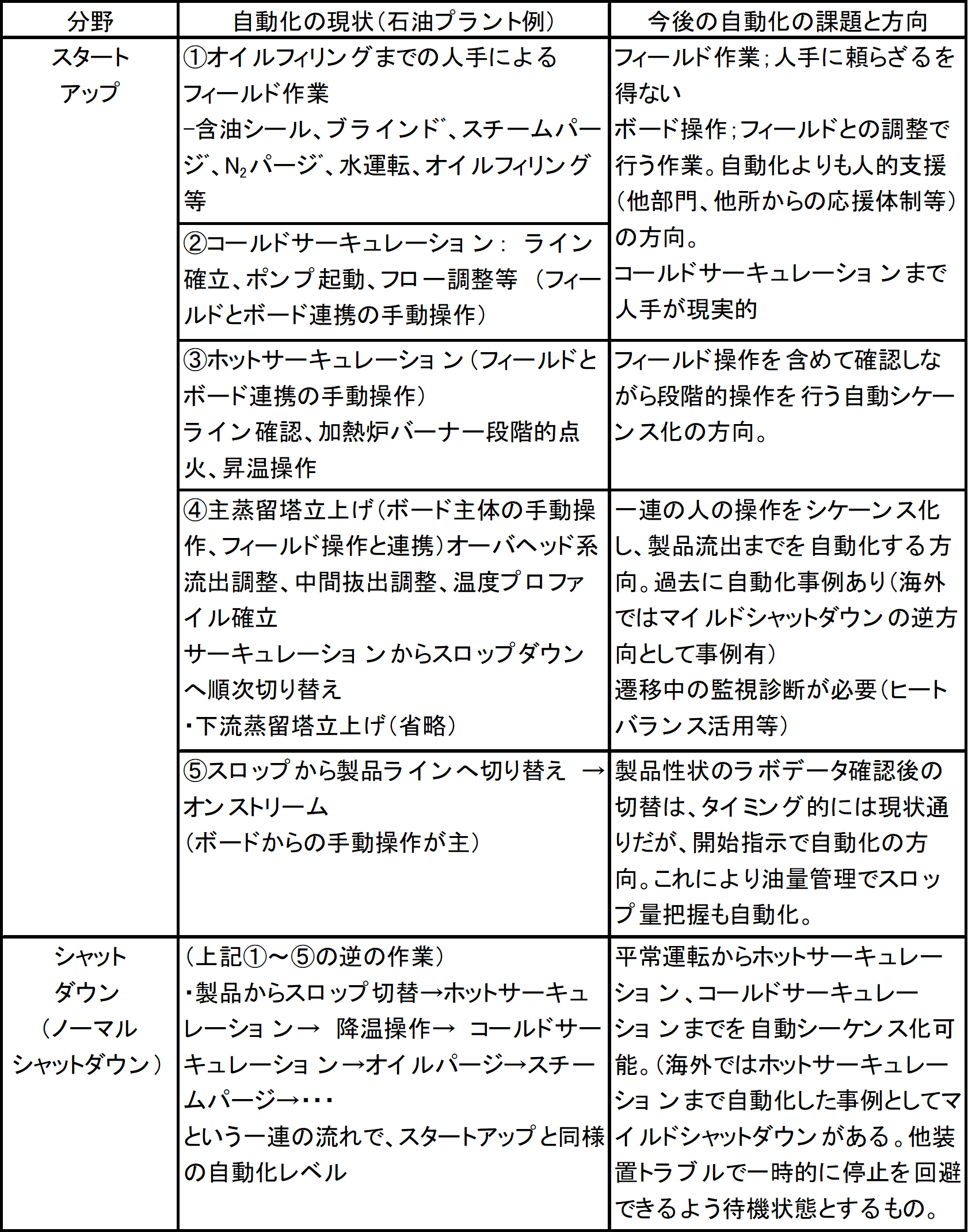
スタートアップ/シャットダウンでは,その段階に応じて多くの作業と操作があることは周知の通りです。そこでどの段階の作業でどこをIT化,自動化していくのかを明確にしながら進める必要があります。
スタートアップ操作の現状としては,まず表1の中の①は,オイルフィリングまでの各種作業であり,人手によらざるを得ないもので,自動化の対象外の作業となります。
これらの作業は,現在計器室内にP&Iの紙を大きく広げて,たとえば多数のドリップファンネルのシールやブラインドポイントが実施済かどうか等を確認のマークを記入しながら作業が進められています。これらはIT化,DX化という視点からP&IをCAD化して大型スクリーンに映し出し,ドリップファンネルやブラインドポイントの実施確認済のマーキング等が行えるような取り組みが期待されていますが,プラントの自動化とは異なる分野なのでここでは割愛します。また,機密テスト,水運転,オイルフィリング前のスチームパージ等々もその類となります。
次に②は,オイルフィリング後,配管,機器からの漏れなどの各種安全確認を人手で行いながら実施するコールドサーキュレーションという操作です。この操作はフィールドとボードの連携を取りながら,現場でのポンプ起動,その際のラインのエアー抜き等を含めて,順次行っていくものとなります。この②の操作も人手によるものが多く,自動化の対象とするのは現実的ではありません。
③の操作は,ホットサーキュレーションという段階の操作です。コールドサーキュレーションが確立した後,加熱炉に火を入れ,段階的に昇温していく操作になります。この段階からはDCSからの遠隔操作が可能なものが多く,ボード負担を軽減するため,ガイダンスを含めて自動シーケンス化していく対象となってきます。
たとえば,加熱炉のバーナ点火,調整等のフィールド作業との連携がありますが,そのような人手の作業のチェック確認を含めてガイダンスを出力し,ボードでの確認操作を行いながら進めて行くことで,操作ミスを防ぐことが可能となるような自動シーケンスが期待されます。
④は,加熱炉下流の反応塔の調整や蒸留塔を順次立上げていく操作で,現状では経験のあるボードオペレータがDCSからの遠隔手動調整で,現場でのフィールドオペレータと連携を取りながら,製品の留出を行う段階です。立上げ途中での留出した製品ラインの流体はスロップラインへ排出し,スロップタンク(製品でない流体を一時的に貯蔵するタンク)に流れて行きます。
蒸留塔の立上げ操作は,経験のあるベテランに委ねられるもので,非定常作業と位置付けられます。しかし,これらのほとんどの操作は,一定の手順等に分解して形式知化できるもので,自動化が可能な操作と言えます。
⑤は,スロップタンクへ流れている製品性状が規格値に入ったことが確認されたら,スロップラインから製品ラインへ切替える操作となります。
ここでの操作自体は簡単な切替えとなりますが,スロップ量を把握する油量管理という視点からは,多くの手作業が発生してきます。この対策としては,本連載のモード切替え自動化の部分で解説した「ワーク管理システム」を活用することで,スロップ量把握のシステム化を含めた自動化が可能となります1)。
3.2 シャットダウン操作の現状と今後の自動化の方向
シャットダウン操作においては,スタートアップ操作の①から⑤までの作業をほぼ逆向きに,段階を踏んで行う形となります。したがって,自動化の方向もスタートアップ操作のそれとほとんど同じになってきます。
3.3 海外でのスタートアップ/シャットダウン自動化の状況
海外では,ホットサーキュレーションから立上げ,立下げを完全自動化した例を,既に某仏製油所で見ることができます。上流の装置がトラブルで停止した時,中間タンク容量の問題で,二次装置の稼働も維持することが難しくなるので,二次装置を停止してしまうのではなく,定常運転からホットサーキュレーション状態までをシーケンスで自動化した事例です。上流の装置が回復したら,ホットサーキュレーションから自動シーケンスで定常状態まで短時間に立ち上げることができるようにしたものです。
ちなみにこの自動化は,当時DCSの上位の位置づけでシーケンシャルな操作を効率的に導入できるようなツールがなかったこともあり,SIS(安全計装システム)に相当するシステムで組まれたものです。
4.スタートアップ/シャットダウン操作自動化の実現方法の提案
以上述べてきましたように,スタートアップ/シャットダウン操作については,表1に示した③のホットサーキュレーション以降について,ガイダンスを含めた自動シーケンスにより,オペレータをサポートする形が今後実現する方向と考えます。表1を要約してわかりやすくしたものを図2に示しました。
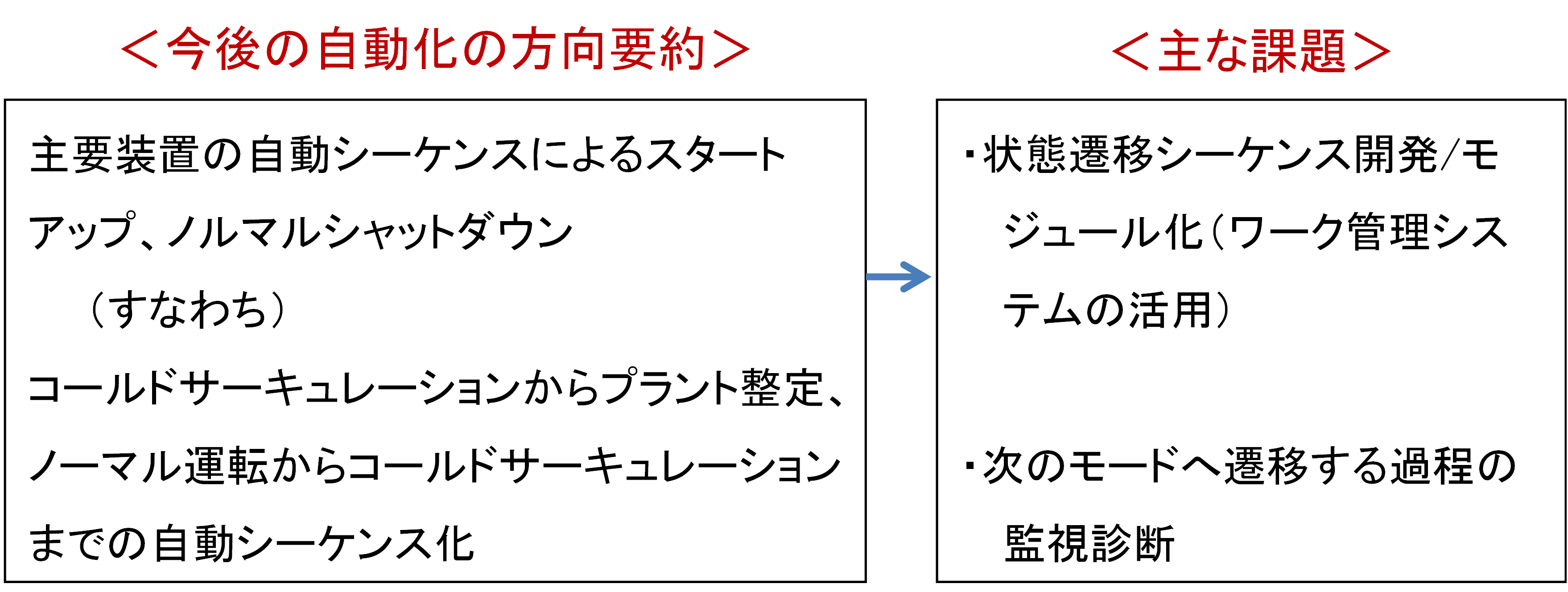
図3にあるモード切替えについては,その自動化の必要性と実現方法について,本連載で解説してきました。モード切替えの各種操作は,パターン化できるがゆえにモジュール化が可能となり,したがって自動シーケンス生成が可能となり,その実現のためのシステムとして「ワーク管理システム」1)を示しました。
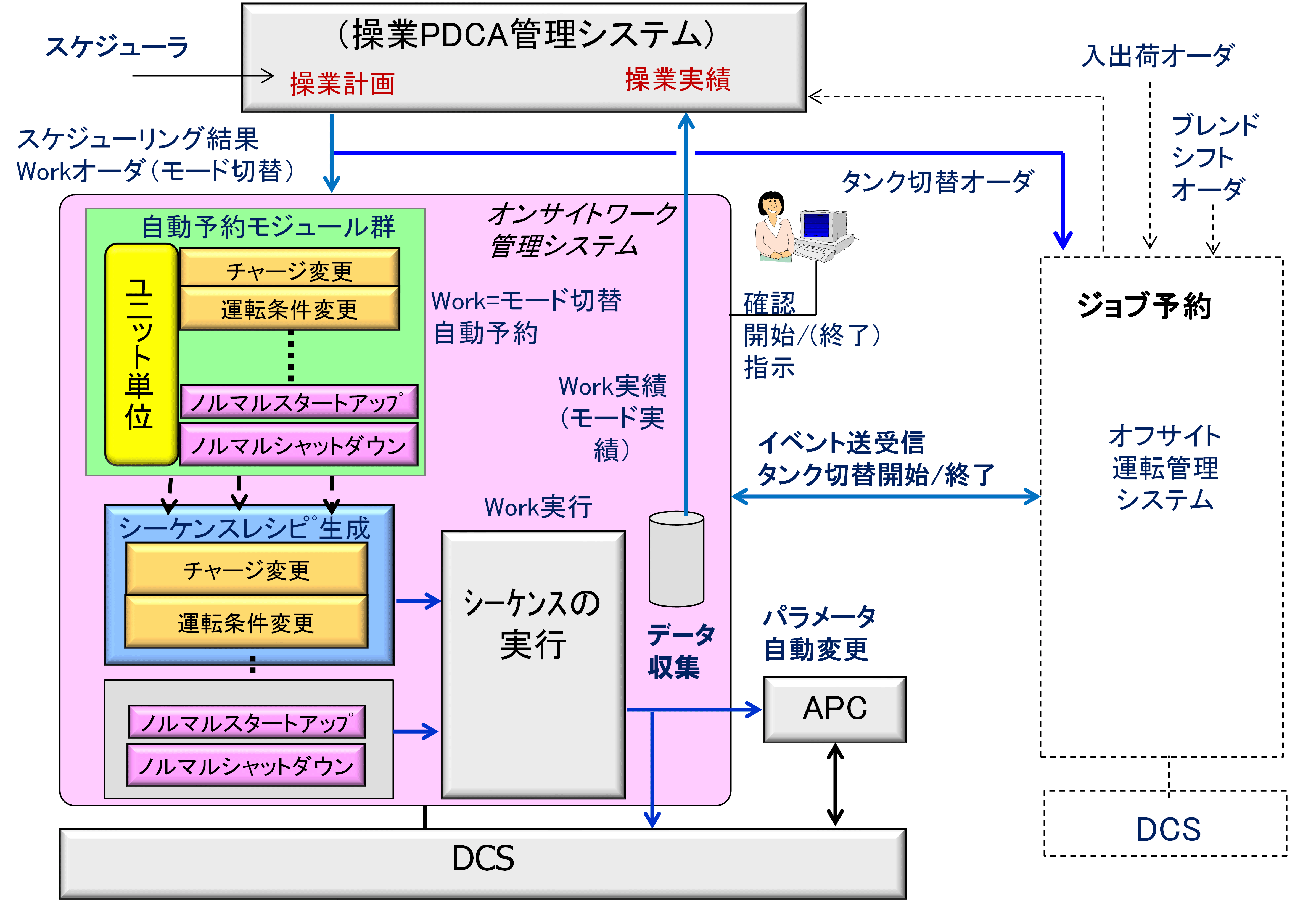
スタートアップ/シャットダウンで,ホットサーキュレーションから立ち上げまでの操作は,全ての操作が定型化したものであり,いわゆる形式知化できるものです。これらの操作の各段階がモード切替え操作の繋がりと考えることができ,「ワーク管理システム」の枠組みの中で,ガイダンスを含めて自動シーケンス化することが可能となります。
図3にワーク管理システムの中にスタートアップ/シャットダウン操作の項目を加えた形を概念的に示しました。
SIS(安全計装)で組む方法もありますが,ノルマルスタートアップ/シャットダウンは緊急操作ではなく,平常運転中のモード切替え操作と同等であると考え,筆者が本連載で提案している「ワーク管理システム」に組入れることを推奨します。 ノルマルスタートアップ/シャットダウン操作は,いくつかの定型のモード切替え操作が連続したものと考えることができるからです。 5.スタートアップ/シャットダウン操作時の異常監視機能の1案 スタートアップ/シャットダウン操作はいくつかのモード切替え操作の繋がりで構成されます。モード1から2の状態へと遷移する際の監視機能について,本連載で,人が行っているチェックに類似している「ヒートバランスの観点からのチェック,監視」が有効であることを述べました。もう一度それを図4に示します1)。 図4,5はチャージアップというモード切替え時の加熱炉まわりの運転監視の方法を示しています。状態1から2へ遷移する過程で,ヒートバランスを取れば,熱収支がゼロであるはずで,そのバランスチェックを人と同等に常時監視することができ,比較的容易に実現できます。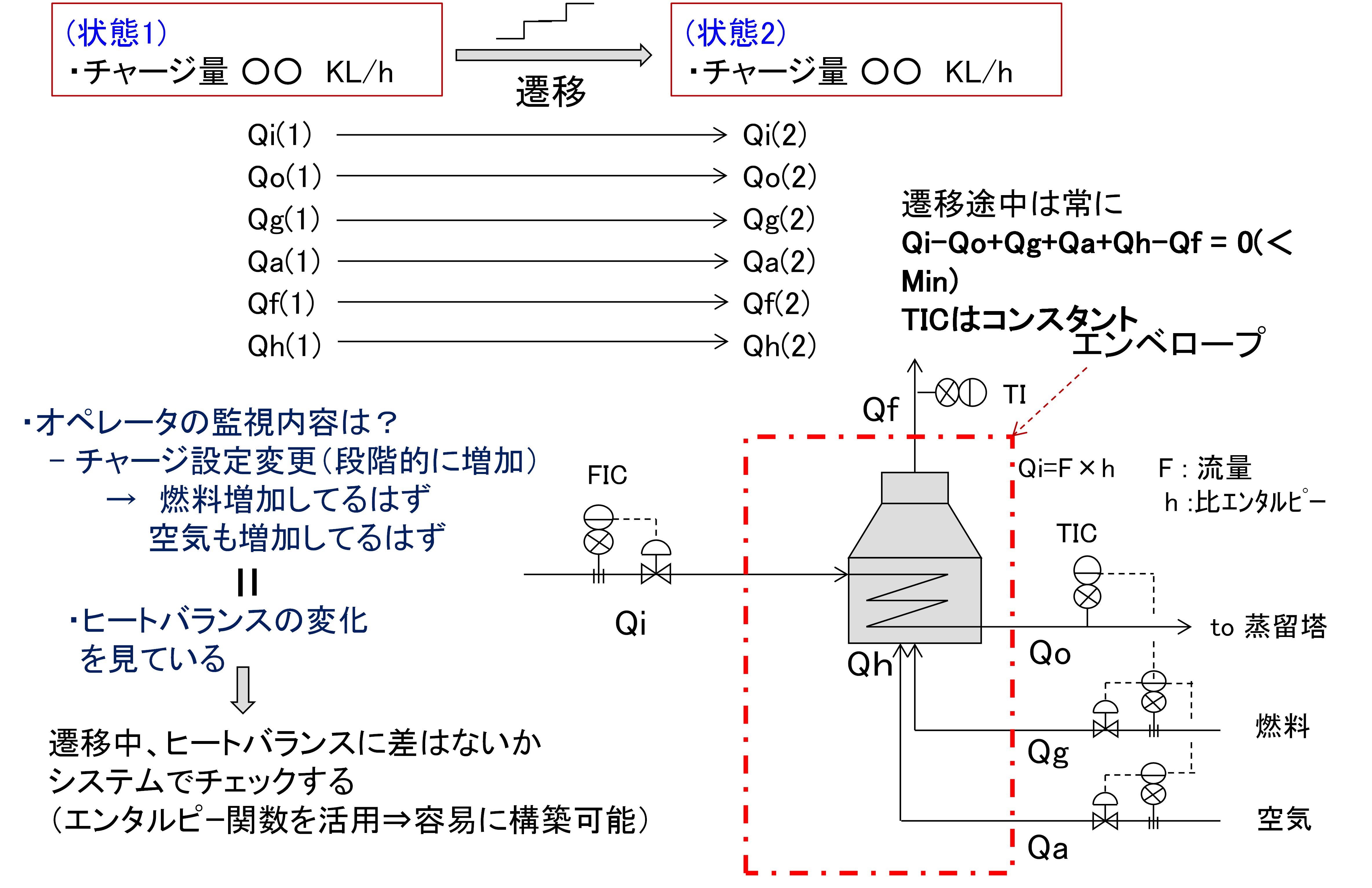
図4 「チャージ量変更」操作のヒートバランスチェックによる加熱炉監視手法の案

たとえば,遷移途中は常に,
Qi-Qo+Qg+Qa+Qh-Qf = 0(<Min)
が成立しているのが「正」となりますが,この式でQgとQaで同時に片方がプラス方向へ,もう片方が同じ量だけマイナス方向へ動いても,ゼロが成立するので,「正」と判断してしまいます。
極めて希ではありますが,このような誤診断が発生しないとは言えません。これを防止し,さらに信頼性を上げるための方法として,ヒートバランスベクトルによる診断を提案します。図4にも示していますが,人が監視しているのは「各熱量の関係性」である,ということです。
すなわち,図5に示すように,「各熱量が相互にある関係性を保ちながら遷移する」という点に注力しなければなりません。お互いの関係性が規範となる軌跡(遷移線)の途中のいずれかに合致していれば「正」と判断することができます。
こうしたチェックを容易に表現する方法として,数学的な手法で,「ヒートバランスのベクトル軌跡」を考えることができます。この軌跡のどこかに乗っていれば「正」となり,ヒートバランスだけの誤判断を防止できます。
ベクトル軌跡の考え方による実装が難しければ,コンピュータ内で遷移途中のパターンをいくつか作っておいて近似的に照合する方法もあります。
ベテランの操作をヒートバランスベクトルとして表し,時間的なファクタを入れれば,信頼性の高い監視機能を実現することが期待されます。
このヒートバランスベクトルの考え方は,蒸留塔の立上げ経過を監視することなどにも適用可能となってきます。
6.スタートアップ/シャットダウンの自動化とパンデミック対策
感染症等のパンデミック時に,プラントオペレーションに携わる人員の確保が難しい状況が発生した場合に,プラントトラブル等で緊急停止して事態を収拾する方法もありますが,緊急停止までは必要なく,ノルマルシャットダウンで一時停止してまた立ち上げたいという事態がないとは言えません。
このような時,ノルマルシャットダウン操作が,ガイダンス付きで自動化されていれば,オペレータの負担を軽減し,安全なプラント停止が期待できます。
また,ノルマルシャットダウン/スタートアップにはベテランの知見が必要ですが,パンデミック時のみならず,オペレーション環境改善の視点から人材確保につなげるためにも,今後できるだけ自動化していく課題であると考えます。
7.おわりに
今回は「スタートアップ/シャットダウン自動化とパンデミック対策」について解説しました。プラントのノルマルスタートアップ/シャットダウンの自動化は,かなり以前に挑戦的に適用された事例はありますが,そこから未だに普及,実現に至らず,長年の課題となっていることは周知の通りです。
パンデミック対策を機会として捉え,人材確保の視点からも,スタートアップ/シャットダウン自動化は今後具体化していくべき課題と考えます。
次回は,「プラント操業でのDX化,AI活用のポイント」について述べることにします。
〈参考文献〉
1)本田達穂:「連載講座:パンデミックに対応可能な安定操業:石油・化学工場での自動化の課題と解決策(第4回);モード切替えの自動化と実現可能な仕組みと手法」,『計装』,Vol.65,No.9(2022)
2)本田達穂:「特別記事;石油石化プラントでの残された課題と解決策」,『計装』,Vol.64,No.7(2021)
3)本田達穂:「残された自動化の課題と今後の対応策」,『2020計装制御技術会議資料(日本能率協会主催)』