

連載 パンデミックに対応可能な安定操業
-石油・化学工場での自動化の課題と解決策-
第10回 夜間フィールド無人化を目指したパンデミック対策
1.はじめに
前回は「モード切替え自動化によるボード負荷軽減とパンデミック対策」,すなわちボード操作の効率化による負荷軽減で,感染症等緊急事態でいざという時に,ボード業務を効率化して不足人員を補う少人数オペレーション体制について解説しました。
今回は,フィールド業務を自動化/効率化することで夜間フィールド無人化を目指して,パンデミック時の不足人員を補う方策について解説します。
2.フィールドオペレータ人員の現状
図1はフィールドオペレータの人員の現状を調査したグラフで,1人がカバーするプラントの規模(制御出力数/フィールドオペレ―タ)を示しています。
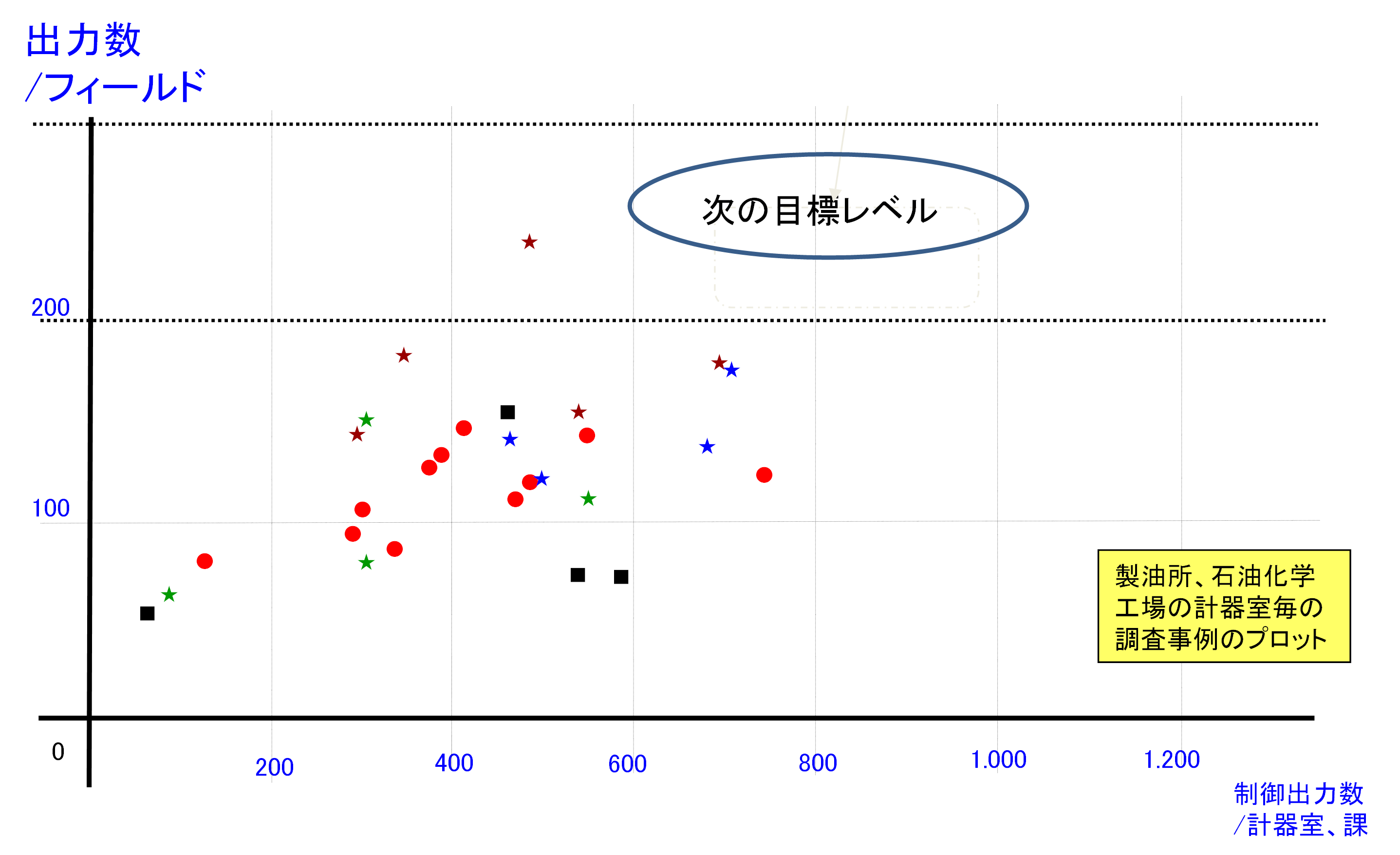
現状は約500出力数の規模のプラントを4~7名でカバーしている状況となっています。過去にはこの倍以上の人数であったものから,自動化とDCS化,計器室統合化等により,国内,欧米等の先進国ではここまでの少人数化が実現してきています。
1シフト(1直)の人員は,交代制で4または5グループがあるので,1シフト当りの人員を1名削減することは,4~5名の少人数化に繋がります。
パンデミック等の緊急的事態に際して,プラントの安全を確保しながら操業を継続するためには,1シフトの人員を1時的に少なくしてカバーできるかどうか,という課題に向き合うことになります。
3.フィールドオペレータの負荷軽減(夜間無人化)へ向けたアプローチ
表1は,これからの目標とするシフト体制を示しています。ボード人員の解決策については,前号で示しましたが,フィールドオペレータの人員については,フィールド作業をできるだけ削減し,人員を現状の半分程度までにし,なおかつ夜間は無人化していくのがこれからの目指す姿と考えます。
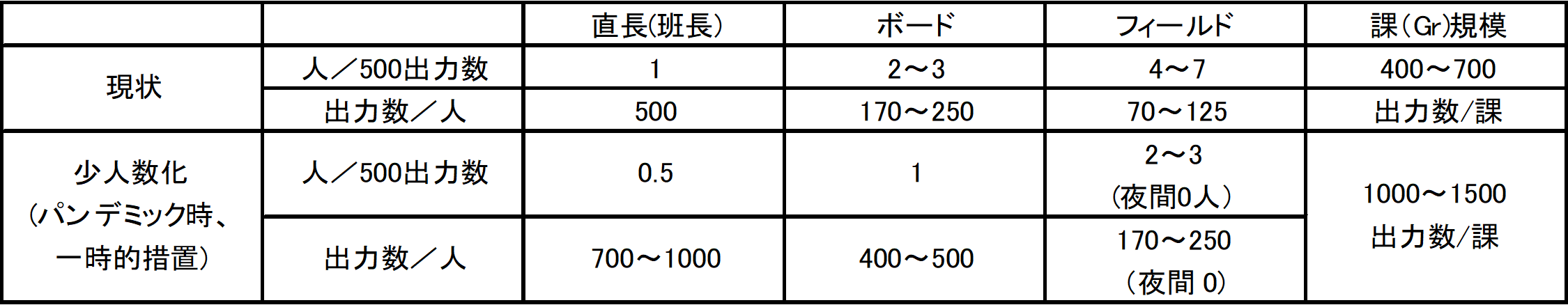
オペレーション体制を考える際,忘れてはならないことは,通常時の負荷軽減だけでなく,緊急時に必要な人員を確保できているか,という視点です。
通常時のフィールド業務には,図2に示すように,日常定期点検,日常操作,データ採取,異常発見と対処,運転条件変更等があり,それぞれの業務に際してフィールド人員が少人数化した場合,すなわち2~4人/シフト(夜間は無人化)になった場合に生じる問題点を洗い出し,それを解決するための必要な対応策を検討することになります。
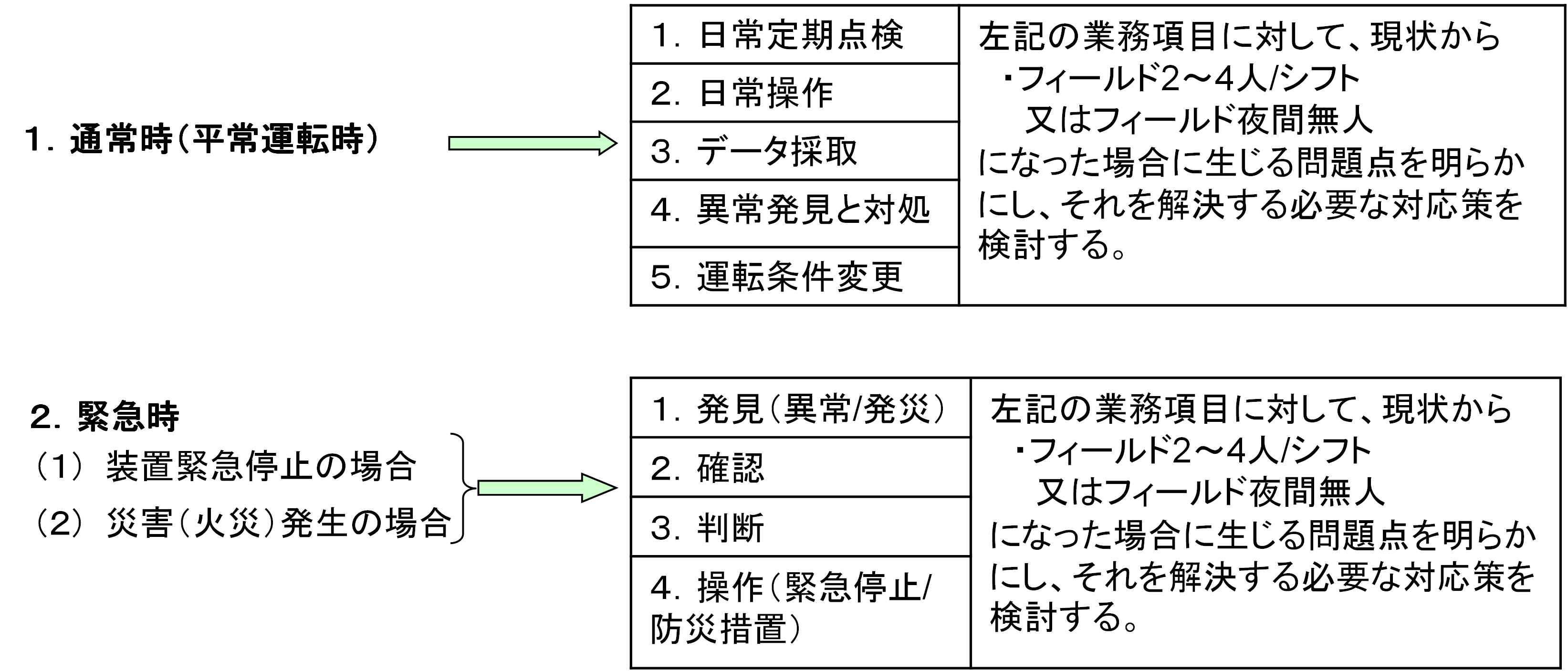
また,緊急時には,発見,確認,判断,操作(緊急停止,防災措置)の各業務について,フィールド人員が2~4人/シフト(夜間は無人化)になった場合に生じる問題点を洗い出し,それを解決するための必要な対応策を検討する,といった取り組みが重要となります。
以下に,通常時と緊急時のそれぞれについて,フィールド業務の内容と具体的な対応策について解説します。
4.通常時フィールドオペレーションにおけるパンデミックでの操業継続の為の対応策
4.1 通常時のフィールド業務内容現状
表2に石油/石化プラントオペレーションで,通常時(平常運転時)のフィールド業務の現状での具体的な項目例を示しました。
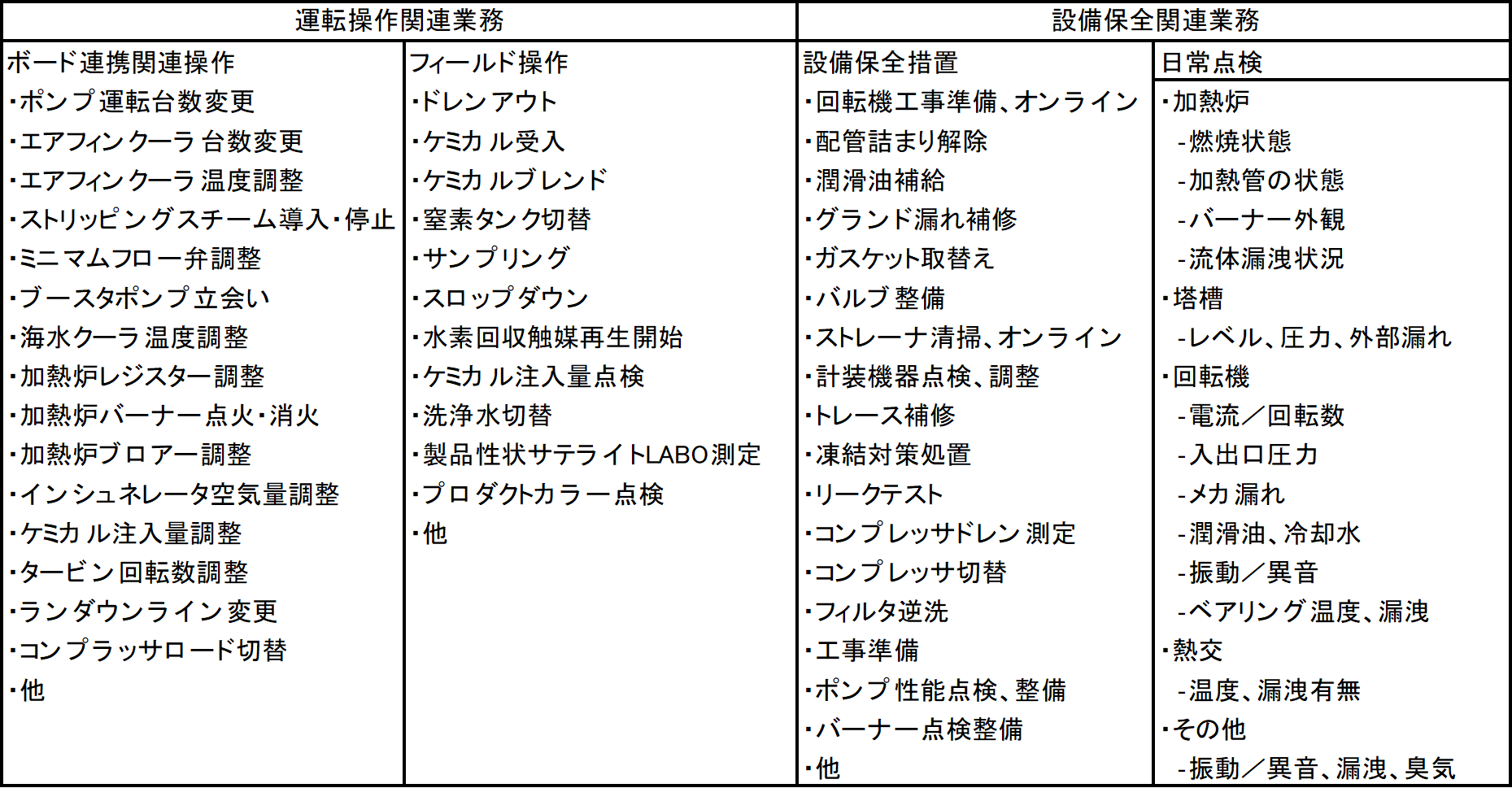
大きく分類して,ボード連携関連操作,フィールドでの手動操作,設備保全措置,日常点検の4つがあります。これらの分類で表2に示した具体的な各業務項目に対して,少人数化(または夜間無人化)した場合の問題点はないか,問題点があればその対応策を検討することで,目標を実現することができます。
以下に対応策の例を説明します。
4.2 パンデミック時における通常時(平常運転時)のフィールド業務軽減へ向けた対応策
通常時(平常運転時)において,パンデミック等でのフィールド人員不足を補うためには,図3に示すような具体的な対応策が必要となります。すなわち,シフト体制において,2~4名/シフトとし,かつ夜間はフィールド人員0体制を実現するための方策として,次の項目を挙げることができます。
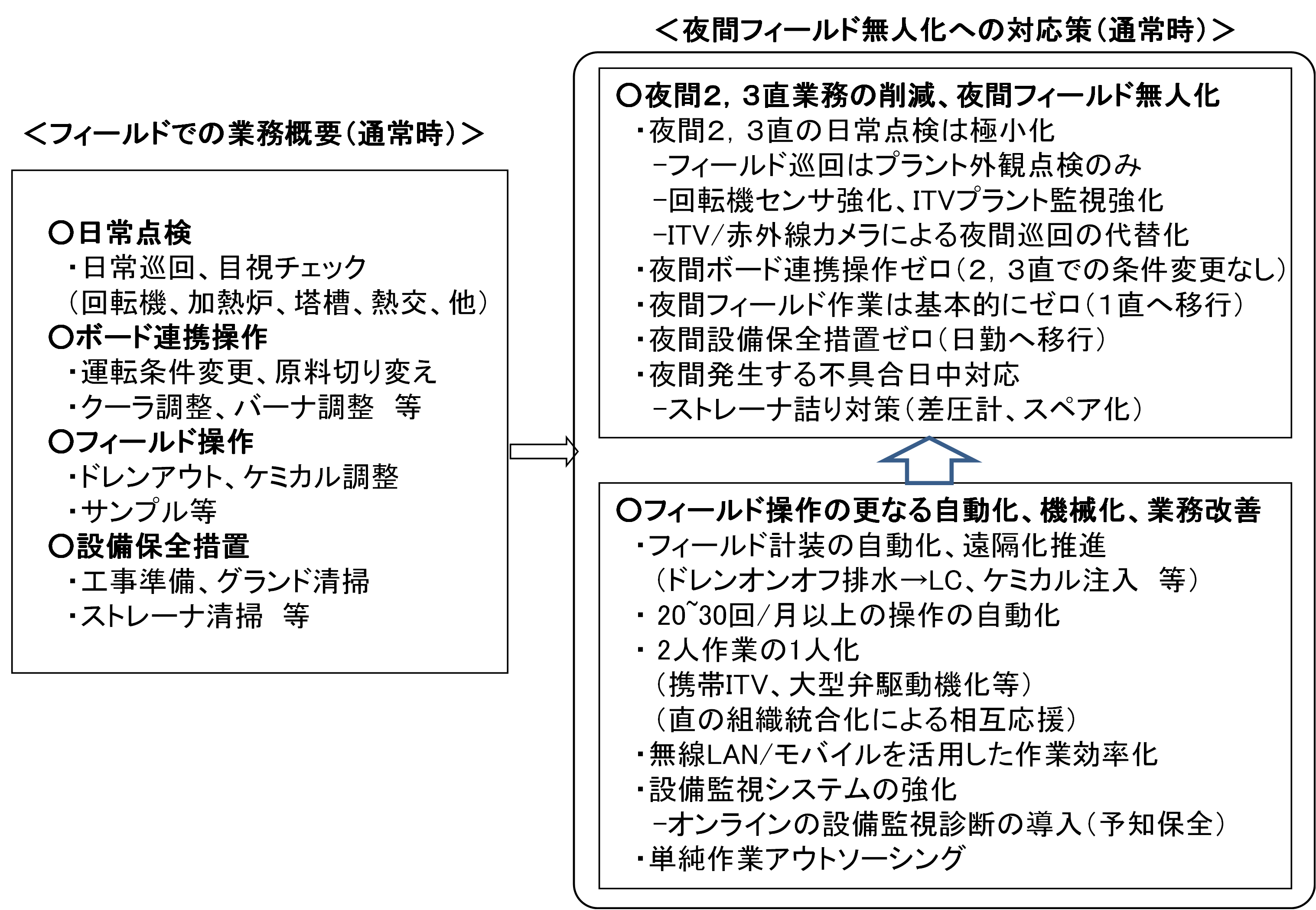
1)夜間の日常点検の極小化
フィールド巡回では,データ採取等はなく,巡回しながら外観点検のみにすることが必要で,国内の製油所/工場では既にこのレベルまでは到達しているところが多くあります。人の五感を補完するものとして,回転機等のセンサによる異常監視,ITVによる外観異常監視の強化を行い,夜間の日常点検を極小化する必要があります。
巡回点検では,こうした監視システムを強化してもどうしても人の五感に代わる機能として十分とは言えない部分があり,安心を得るまでには至っていません。これを克服する対策として,ITVをさらに強化し,漏れ等の早期発見に備えて熱を感知できる赤外線カメラで補強する方策が有効となります。
このような対応策により,パンデミック時には一時的な措置として,夜間巡回点検をなくすことは可能になると考えます。
2)夜間ボード連携操作ゼロ対策
また,フィールドでのボード連携操作に関しては,夜間での運転モード変更は行わない等の業務見直しで対応することが有効です。
3)夜間フィールド作業の昼間への移行
さらに,フィールドでの手動操作で代表的なケミカル(薬品)注入調整等は,自動化するか昼間の作業に移行するといった対策が必要となります。
4)夜間設備保全措置業務の昼間への移行
設備保全措置に関連する作業については,自動化できるものが少なく,昼間の作業への移行を行うといった業務見直しが必要です。
5)その他
どうしても夜間2人作業が発生する場合は,1人で操作できるように,大型バルブ操作の自動化,他装置シフト人員からの応援等で対処します。
以上のような対応策で,通常時での夜間フィールド無人化を着実に実現していくことが可能となります。
5.緊急時パンデミックでの操業継続のためのフィールドオペレーションの対応策
通常時での少人数化,夜間フィールド無人化が実現できたとしても,緊急事態で適切な対応が取れなければ,その体制は現実のものとはならず,砂上の楼閣と言われても仕方がないことになります。
緊急時には,発見,確認,判断,操作(緊急停止,防災措置)の各業務について,少人数化した体制で問題がないかを検討し,対策を講じる必要があります。その中で主なものを下記します。
夜間では,日勤のマネジャークラスの人がいないので,プラントに異常を認識した際,緊急停止措置を実行する判断を直長に委ねる考え方はどうしても必要になります。また,緊急停止措置を取った場合に,火源を絶ち,原料供給を絶ち,脱圧する等の一時措置は一般的に安全計装(SIS;Safety Instrumented System)で自動化されていますが,小型ポンプ停止等の二次措置は人手で行うのがこれまでのやり方となっています。少人数化し夜間フィールド無人化したケースでは,二次措置に人手を割けず,災害の危険性を排除できなくなります。
夜間フィールド無人化を実現するためには,緊急停止の二次/三次措置の自動化(現場自動化も含む)または別部門からの応援等の対策を講じ,机上シミューレーション,訓練等で現実的な対策としなければなりません。
緊急停止し再立ち上げする際,プラントが冷えた後,再び加熱されていく際発生する多くのフィールド作業があります。プラントからの漏洩を防止するためホットボルティング(熱でボルトが伸びることで漏洩につながるのを防止するためのボルトの増し締め)等がそうです。
これを避けるための方策の一つとして,欧州の某製油所での事例として「マイルドシャットダウン」というものがあります。マイルドシャットダウンとは,自動シーケンスによりホットサーキュレーションまでプラントを徐々に停止していく自動操作を言います。再度プラントを立ち上げる場合はホットサーキュレーションから自動シーケンスにより立ち上げていく方法となり,自動スタードアップとなります。夜間フィールド無人化を実現するには,マイルドシャットダウンも重要な検討課題の一つと捉え,どの装置に適用するかを含めて検討されることを推奨します。
6.おわりに
前回のパンデミック対策としてのボードオペレーションの少人数化対応に続き,今回は「夜間フィールド無人化を目指したパンデミック対策」について解説しました。
フィールド業務の効率化を検討する際には,自動化やシステム化だけに目を向けるのではなく,昼間の日勤作業に移行するといった業務改善・業務効率化の視点も重要となります。TPM等の業務改善活動の一環として進めるのも効果的です。
本稿での具体的な対策例を参照頂くことで,必ずやパンデミック時の一時的な措置として,「夜間フィールド無人化」は実現できるものと考えます。そしてこれを契機に,「常時夜間フィールド無人化」の実現につなげていければと期待します。
次回は,「スタートアップ/シャットダウンの自動化とパンデミック対策」について解説します。
〈参考文献〉
1)本田達穂,「連載講座:少人数化によるプラント操業を目指して(第6回);フィールド業務の少人数化:第1ステップ」,『計装』,Vol.54,No.10(2011)
2)本田達穂,「連載講座:少人数化によるプラント操業を目指して(第7回);フィールド業務の少人数化:第2ステップ」,『計装』,Vol.54,No.11(2011)