

連載 パンデミックに対応可能な安定操業
-石油・化学工場での自動化の課題と解決策-
第8回 CO2オンライン見える化を含むリアルタイムなエネルギー管理
1.はじめに
前回は,モード切替え自動化の3つ目の波及効果として,「モード締め/時間締めを活用した操業管理の革新」と題して,情報の垂直連携による操業計画実績比較のリアルタイムな見える化の実現について解説しました。今回はモード切替え自動化の4つ目の波及効果として,「CO2オンライン見える化を含むリアルタイムなエネルギー管理」について解説します。
現状の用役管理では月間の燃料消費に関する計画実績比較という形となっており,後追いの管理とならざるを得ません。これに対して,DX化の掛け声の元,情報連携を強化することで,リアルタイムに用役バランスを見える化し,都度用役バランス修正による対応ができるような姿が望まれます。さらに,用役消費の視点だけでなく,エネルギー管理として,装置エネルギー利用効率,CO2管理を含めたものを,リアルタイムに見える化し,都度対応できることが今後の目指す姿となります。
モード切替え自動化によって,モードごとの用役消費実績が把握できるようになることが,目指す姿を実現する際の1つの重要なポイントとなります。また,昨今のカーボンニュートラルへ向けては,CO2発生予測/実績管理での効率的な計算方法についても言及します。
2.エネルギー管理の現状
現在,エネルギー管理は,図1に見るようにエネルギー管理ではなく用役管理と称して,燃料や電力の消費量実績を元に行われていて,月単位の計画実績比較となっているのが実状です。これでは後追いの管理と言わざるを得ません1,2)。
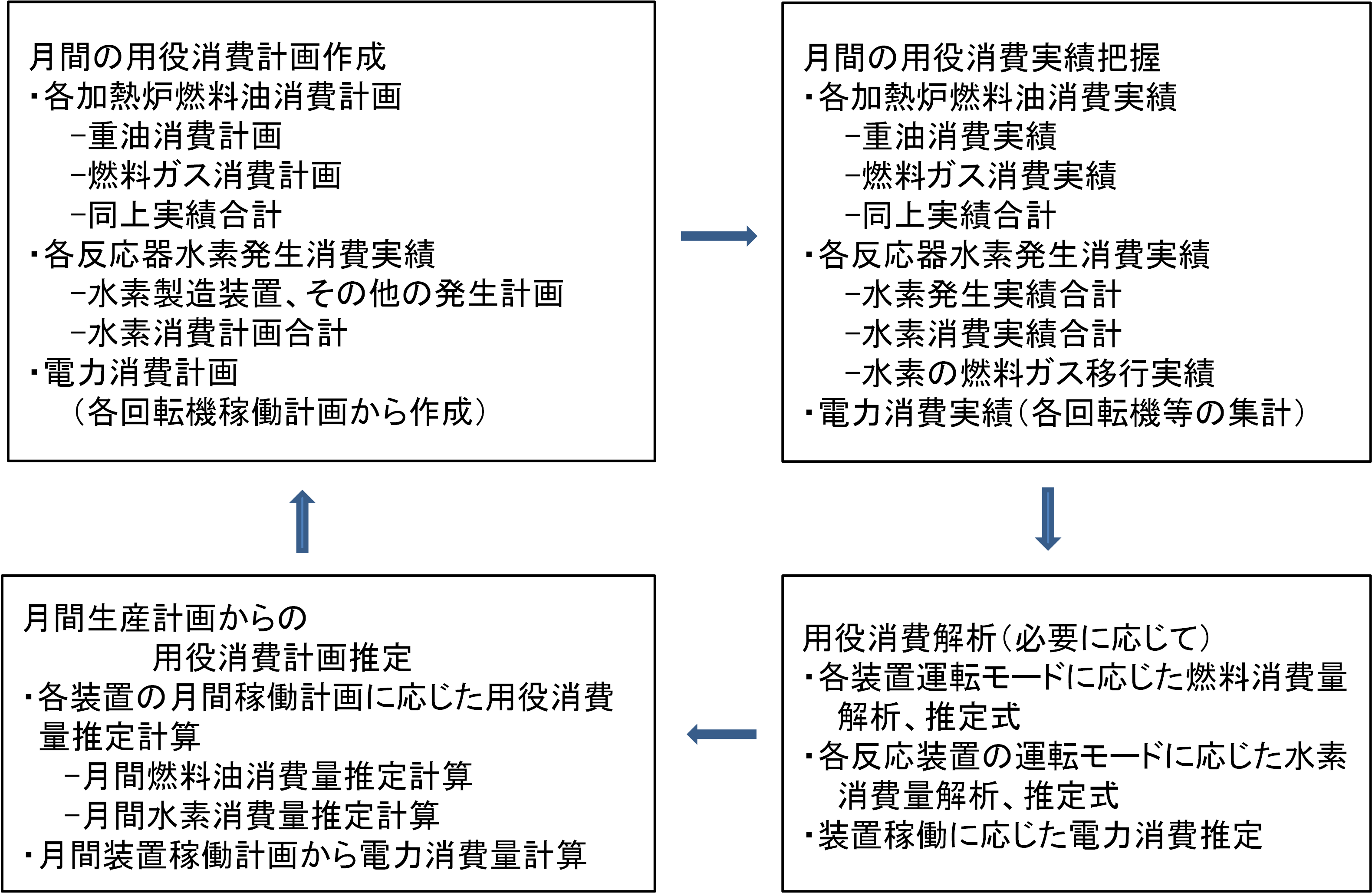
本来リアルタイムな燃料バランスが見える化できて,都度の燃料選択や対応が取れるというのがあるべき姿ではないでしょうか。
燃料バランスとは,燃料ガスヘッダのガスの量や性状(カロリ)が各装置の運転モードの組み合わせで変化するので,フレアにガスが逃げないように燃料油や石炭等の燃料消費とリアルタイムにバランスを取ることを意味します。
エネルギー管理業務の中で,エネルギーロスや効率のリアルタイムな見える化,装置運転モードの組み合わせによる燃料ガスの性状等の把握分析が必ずしも十分ではないのが現状と言えます。
3.リアルタイムなエネルギー管理を目指した場合の問題点と解決策
3.1 運転モードによる燃料ガスヘッダのガス発熱量の変動と対応策
現状では燃料ガスヘッダ内のガス成分,量は一定ではなく,常時変化します。図2に示す燃料ガスヘッダへは各装置から発生するオフガスが流入してきます。それらの流入量と各加熱炉での消費量はそれぞれ各装置の運転モードによって変化します。したがって加熱炉入口の燃料ガスの成分は時々刻々と変化しており,それに応じて発熱量も変化します。
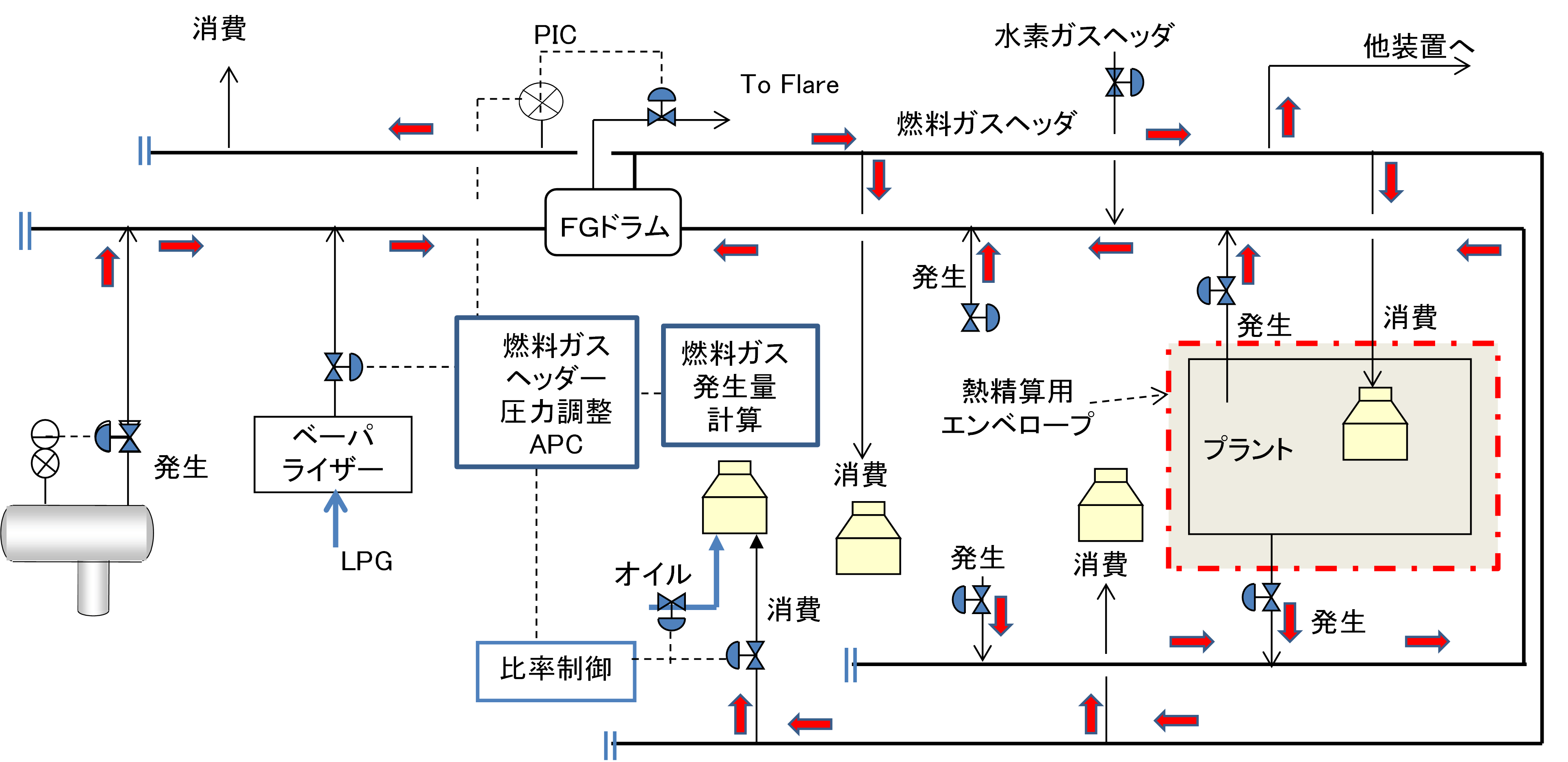
現状では加熱炉入口の燃料ガスについて,ある時刻でのサンプルを何回かに分けて採取して,ラボ分析した性状から発熱量を把握しています。リアルタイムでの把握からは程遠い状況となっています。
例として,某装置でのいくつかの槽から燃料ガスヘッダへ流れるオフガスの性状分析値を表1に示しました。
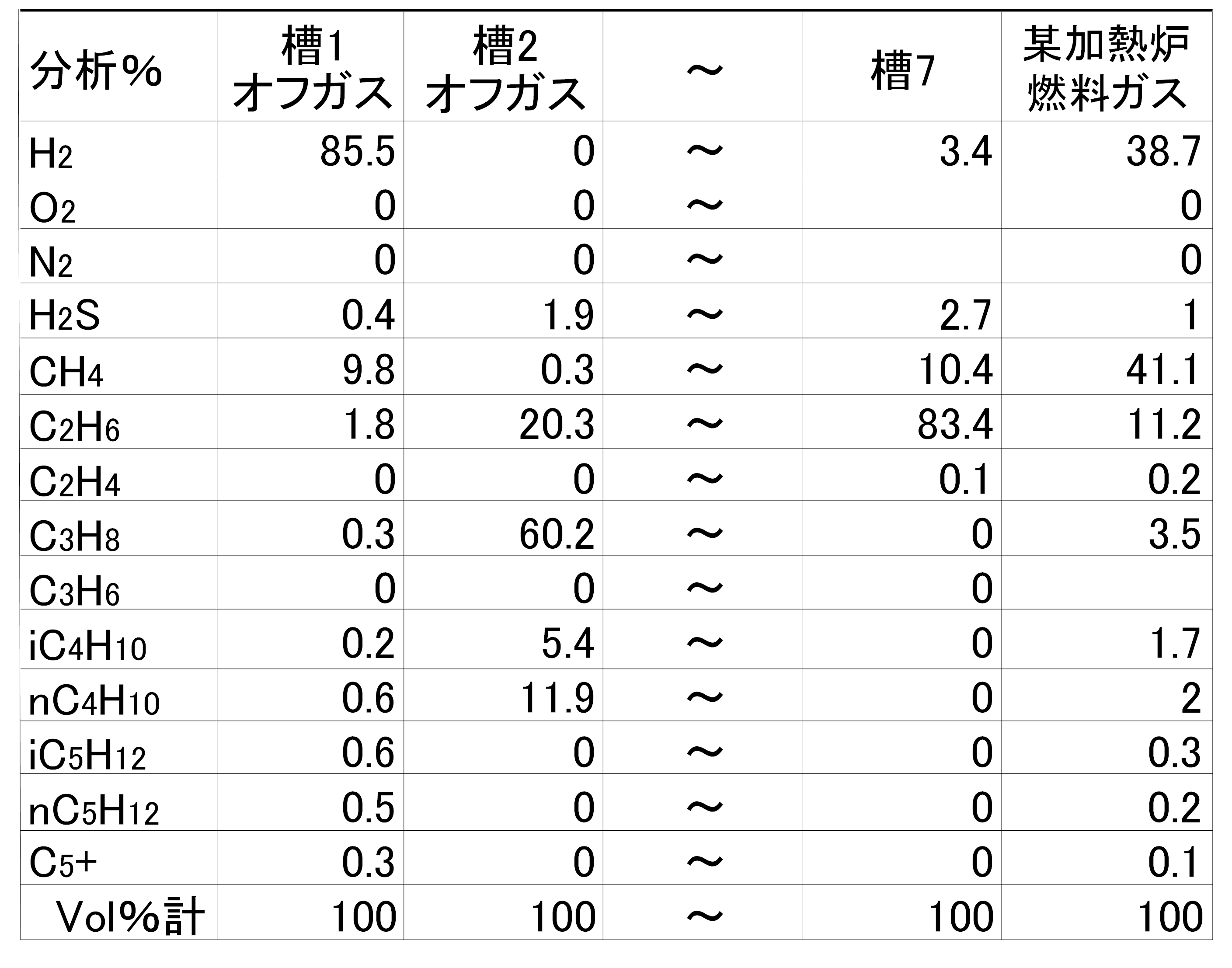
コーカ装置(重質油を分解し,コークスを副生)では,水素でのコークスの切り出しでバッチ的に水素を注入し,その水素の排出先は燃料ガスヘッダという形が取られているので,燃料ガスヘッダの性状は大きく変動します。
こうした時々刻々と燃料ガス性状が変動することへの対応策を次に示します。
装置の各槽から燃料ガスヘッダへの流入量は,圧力制御弁のCv値と開度,前後の圧力差から計算できます。また,各加熱炉へ流れる燃料ガスの性状は,発生と消費からヘッダ内の性状分布としてオンラインで求めるソフトウェアが適用可能なので,調節弁等の設備の追加設置は不要となります。
燃料ガスヘッダの性状分布が見える化できると,オンラインで各加熱炉入口の燃料ガスの成分がわかるので,Excelアドイン関数を用いて,リアルタイムで加熱炉入口の発熱量[KJ/NM3]を計算できます3)。また,合わせて加熱炉/ボイラ等からのCO2排出量をオンラインリアルタイムに高精度で計算することができます。
このオンラインの推定発熱量計算値で,加熱炉の燃焼制御の安定化を図ることも可能となります。
また,燃料ガスの変動は装置モード切替えごとに変化するので,これを吸収し,フレアへの放出を自動的に防止する方策として,図2に示すような,1つの加熱炉をオイル/ガス混焼としてオイル/ガスの比率制御を行う形が必要となります。
3.2 オンラインでのエネルギー利用効率
先にも言及しましたが,現在は用役の消費計画実績管理は行われていても,エネルギー管理という観点からは十分ではありません。
図3に装置の運転でのエネルギーの種類と「エネルギー利用効率」の計算式を示しました。
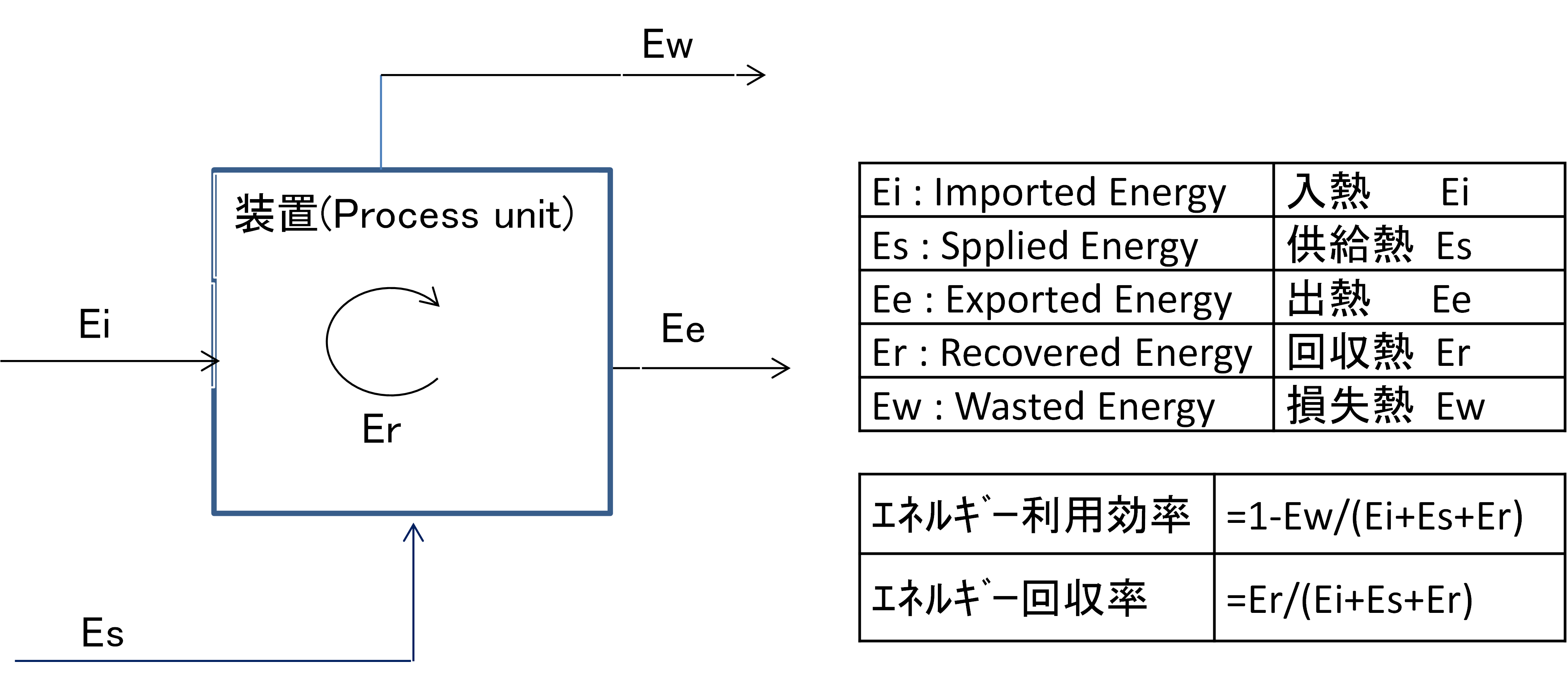
すなわち,装置から出入りするエネルギーを拾い出して同一のエネルギーの尺度(単位)で数値化し,計算に使用します。一般的に尺度としては[KJ/h]が用いられます。エネルギーとしては流体の持つエンタルピー(保有熱または顕熱とも言う),燃焼熱,蒸気等の熱がほとんどですが,電力も含めて評価します。
この装置からのエネルギーの出入りを数値化するのが熱精算で,ここからエネルギー利用効率が算出される点は注目しなければなりません。省エネのための運転目標や設備の改善は結果としてエネルギー利用効率に現れてくるので,有効な評価ファクタとなります。
3.3 オンラインの熱精算へ向けて
エネルギー利用効率をオンラインで見える化しようとした場合,いくつか解決すべき課題があります。
装置の熱精算は大変だというイメージは,現状において拭いきれないものがあります。図4に装置の熱精算を行う上でのエンベロープと出入りの項目をわかりやすく示しました。
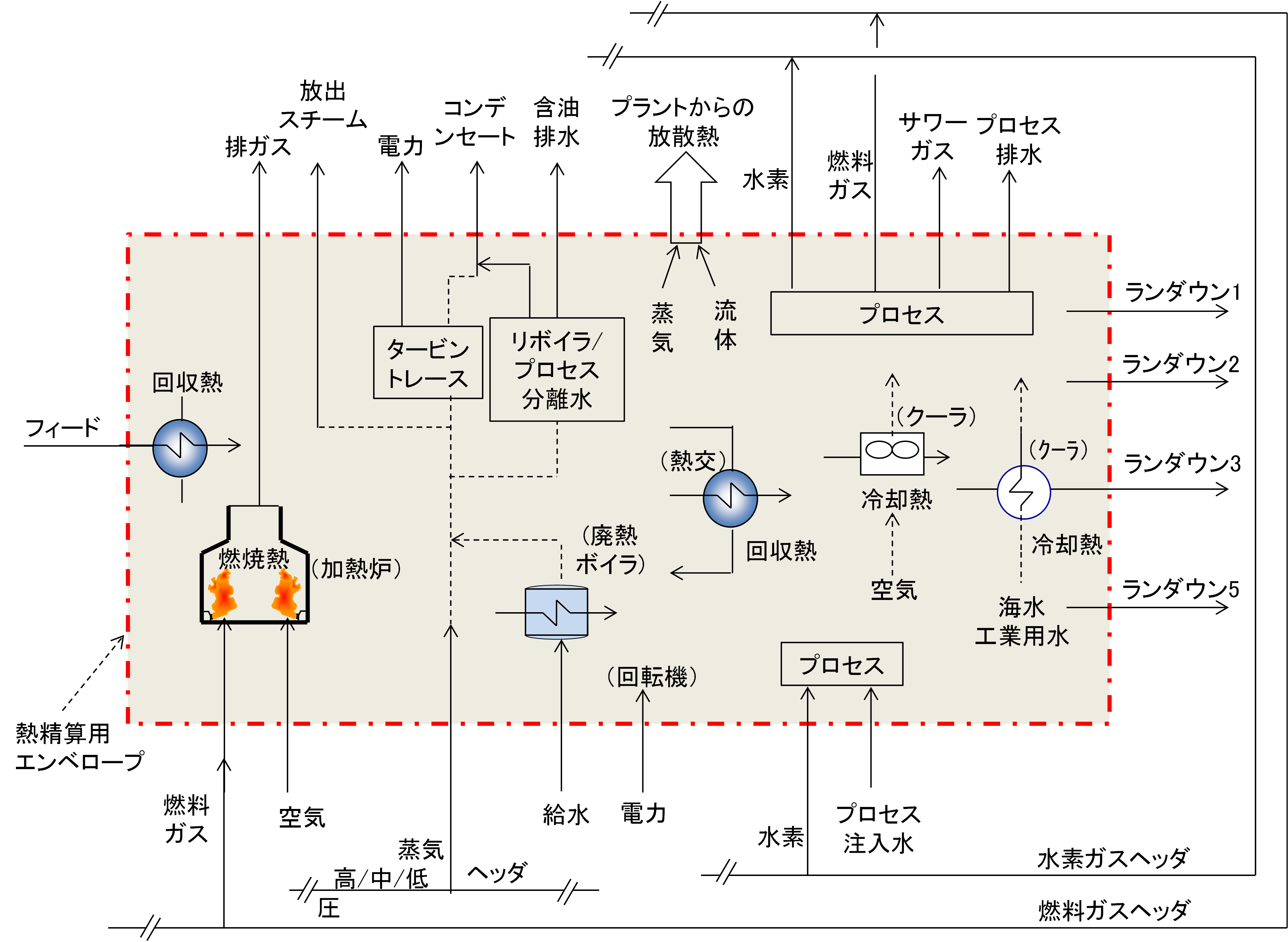
項目数の複雑さと熱量計算の難しさが感じられ,まして時間ベースのリアルタイム化等はとても考えられないと思われるかもしれません。その要因としては,大きくは3つあると考えています。
(1)は熱量計算における各流体の比エンタルピー[KJ/kg]の把握であり,これが一番のネックとなっています。
(2)は燃料ガス,水素等の用役発生/消費の変動とそれに伴うに燃料ガス発熱量の変動。
(3)は(1),(2)にも共通して言えることですが,センサが設置されていなくて,リモートデータがない場合の問題です。
(1)の比エンタルピーのオンラインでの把握は,Excelアドイン関数の活用により解決できます1)。
(2)の燃料ガスヘッダの変動については,3.1で解説しました。
(3)のセンサがない場合の対応策としては,
・データ処理からの推定
・無線センサの設置
・超音波蒸気流量計の活用
・大気のオンライン温度,湿度計の設置
等があります。
4.エネルギー管理のあるべき姿とは
ここでは,最初に製油所/化学工場でのエネルギー管理の目指す姿について説明します。
4.1 エネルギー管理の現状と目指す姿
現状の用役管理は,生産管理とリンクして水素,燃料,蒸気,電力に代表される用役の発生量と消費量を計画し,実績を管理する業務です。
現時点では,用役計画/実績比較管理のPDCA(Plan Do Check Action)サイクルは月単位で行わざるを得ないのが通常であり,後追いの実績管理となっており,都度アクションに繋げるまでには至っていません。
したがって図5の目指す姿においては,リアルタイム性,時間ベースのエネルギーの見える化が求められています。
これからのエネルギー管理は,図5に見るように,生産計画で各装置の稼働(通油量と運転モード)が決まれば,それに応じて燃料ガスの発生量,各用役消費量を統計的に求めた近似式から推定します。生産計画での運転モード切替えに応じた燃料ガスの発生,燃料消費の実績を統計的に解析し,近似式化して計画を作成する方法です。また,Excelアドイン関数を活用することでCO2排出量の予測値(計画値)も容易に実現できます。
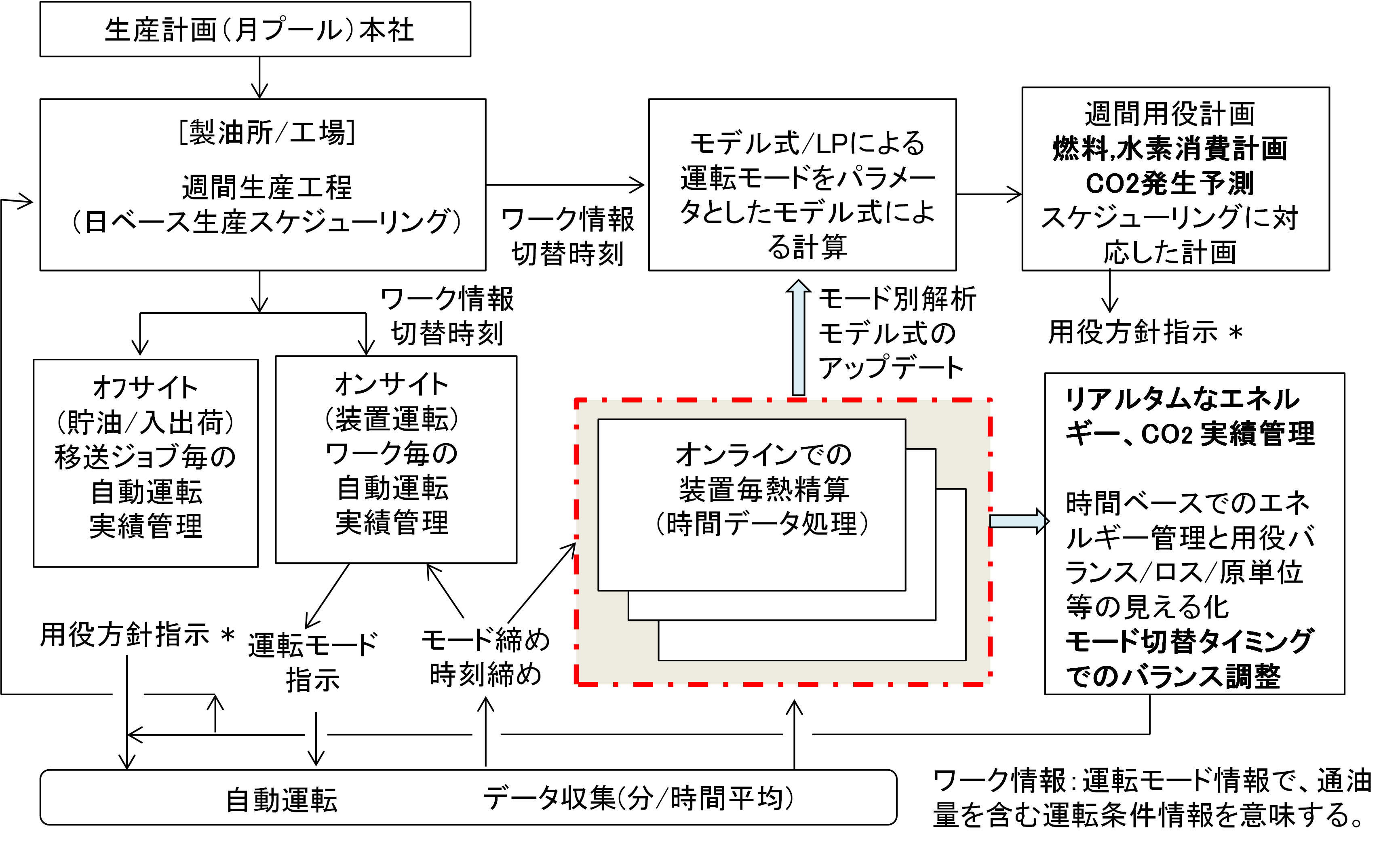
・生産管理スケジューラからの装置ワーク情報(運転モードとモード切替時刻)を取り出し,生産指示情報の電子化を実現する。
・生産指示に応じた,時間ベースでの燃料ガスの発生消費,装置熱精算のオンライン化とそれに基づくモード別締め処理,モード別のモデル式のアップデートを実現する。
・CO2発生予測/実績管理を見える化する。
等となります。4.2 用役管理,装置熱精算を包含したエネルギー管理
図5で示すように,エネルギー管理の目指す姿は,従来の用役管理に加え,熱精算によるエネルギー消費の見える化したものを合せたトータルを意味する概念と考えます。この方が省エネ法のエネルギー管理者の役割からも適合しているからです。
製油所/工場内の燃料,電気,蒸気を含めた熱量というものをエネルギーとして捉え,その使用状況,エネルギー利用効率を求めるのが装置の熱精算です。また,装置用役原単位も熱精算の中で精度良く求めることができます。
4.3 装置熱精算の目的,狙い
装置熱精算の目的,狙いは次のようになります。
・運転モードごとの熱精算を行い,モード別の解析と近似式を作成し,生産計画にリンクした用役計画作成の精度向上に役立てる。
・時間ベース,すなわちリアルタイムでの熱精算の見える化により,バランスロス調整を実現する。
・装置の熱診断が可能となり,同一基準で熱精算を行い,他所,他社との比較において省エネの切り口を見つける。
・省エネ対策での前後比較,装置熱収支の経年変化を把握する。
・製油所/工場全体の熱収支を把握する。
・プロセスに関する技術知識の向上,省エネ意識の啓蒙に繋げる。
実際の熱精算とはどのようなものかを示す意味で,従来手法により行われた熱精算結果を表2に示します。
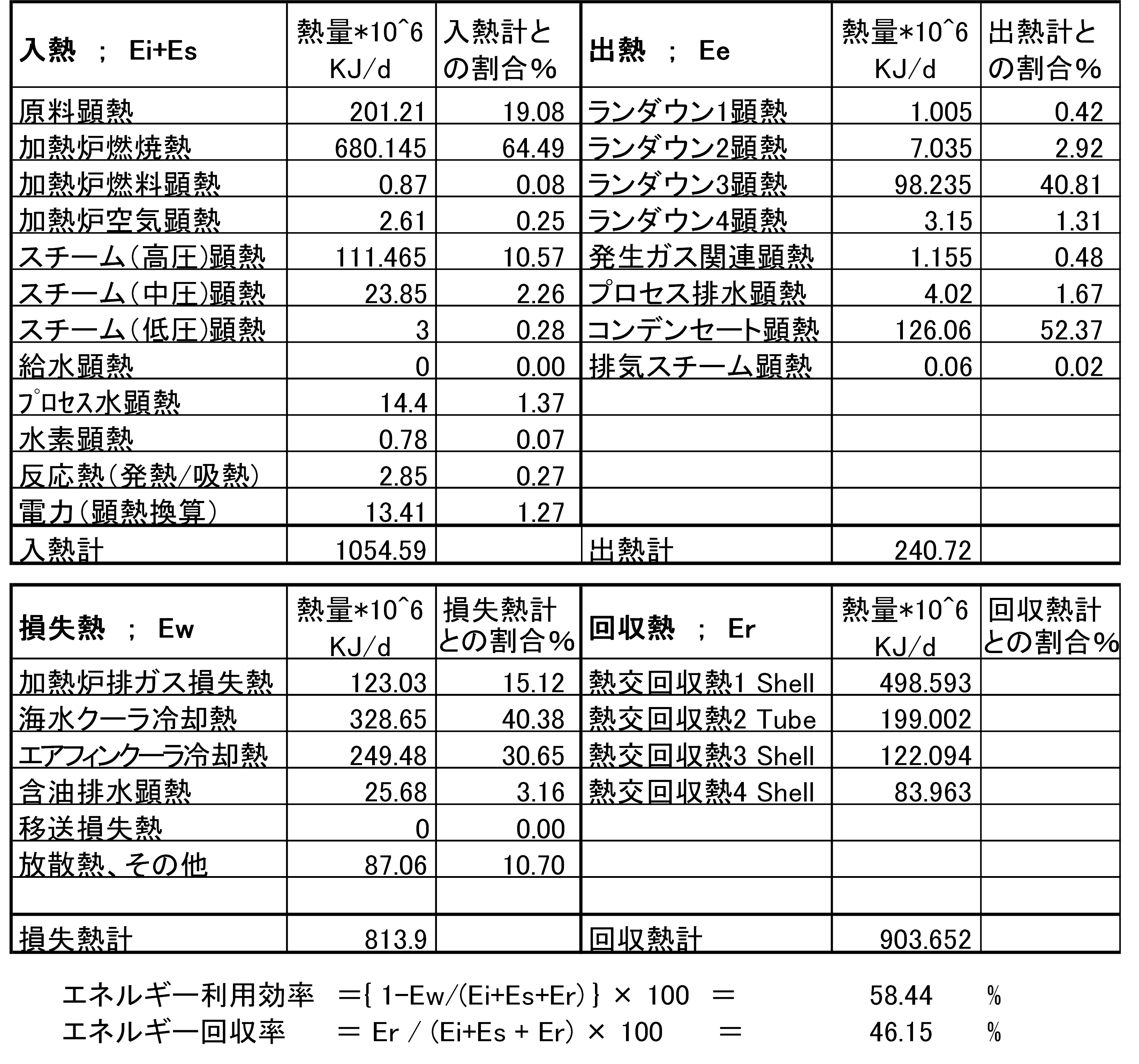
もし熱精算がEXCELエンタルピーアドイン関数を活用することでオンライン化されたならば,リアルタイムでのエネルギーの見える化が実現できるだけでなく,運転モード,フィード量等のパラメータに応じた用役の発生/消費量のより精度の高いモデル式が得られ,エネルギー管理の実現と精度向上に貢献できることになります。
4.4 カーボンニュートラルへ向けたCO2発生予測実績管理
今後のプラント操業において,エネルギー管理の一貫としてCO2発生予測実績管理が求められてくることは避けられません。この計算で簡便かつ精度を確保した方法として,エンタルピーExcelアドイン関数1)の中の炭素/水素比を計算する関数を活用する方法があります。また既に解説した燃料ガスヘッダのオンライン性状分布計算を元に,Excel関数の機能の1つであるガス分子量(対空気比重)からもCO2発生量を計算することが可能で,オンライン化に向けて有効かつ容易な実現方法となります。
生産計画スケジュールからのCO2発生量予測値の計算には,このような手法が必要かつ有効となります。またCO2実績値計算では,集合煙突等でのCO2分析値等を活用する必要があると同時に,燃料消費量から排ガス量計算を含めて,同様のExcel関数の活用によるCO2のリアルタムな把握を含めた実績計算が有効な方法となります。
5.おわりに
今回はモード切替え自動化の4つ目の波及効果として,「CO2オンライン見える化を含むリアルタイムなエネルギー管理」について解説しました。
用役管理を含むエネルギー管理は,用役消費についての月単位の計画実績管理となっており,現時点ではエネルギーのオンライン見える化という観点からは決して十分な形となっていません。IoT/AIの時代に相応しいエネルギー管理とは,比エンタルピーを計算できるExcelアドイン関数を活用する等の対策により,図6に示したサンキーダイアグラムで,時間レベルでのエネルギー使用状況が見える化されるものであると考えます。それにより用役管理のPDCAサイクルが時間レベルで実現できることに繋がります。
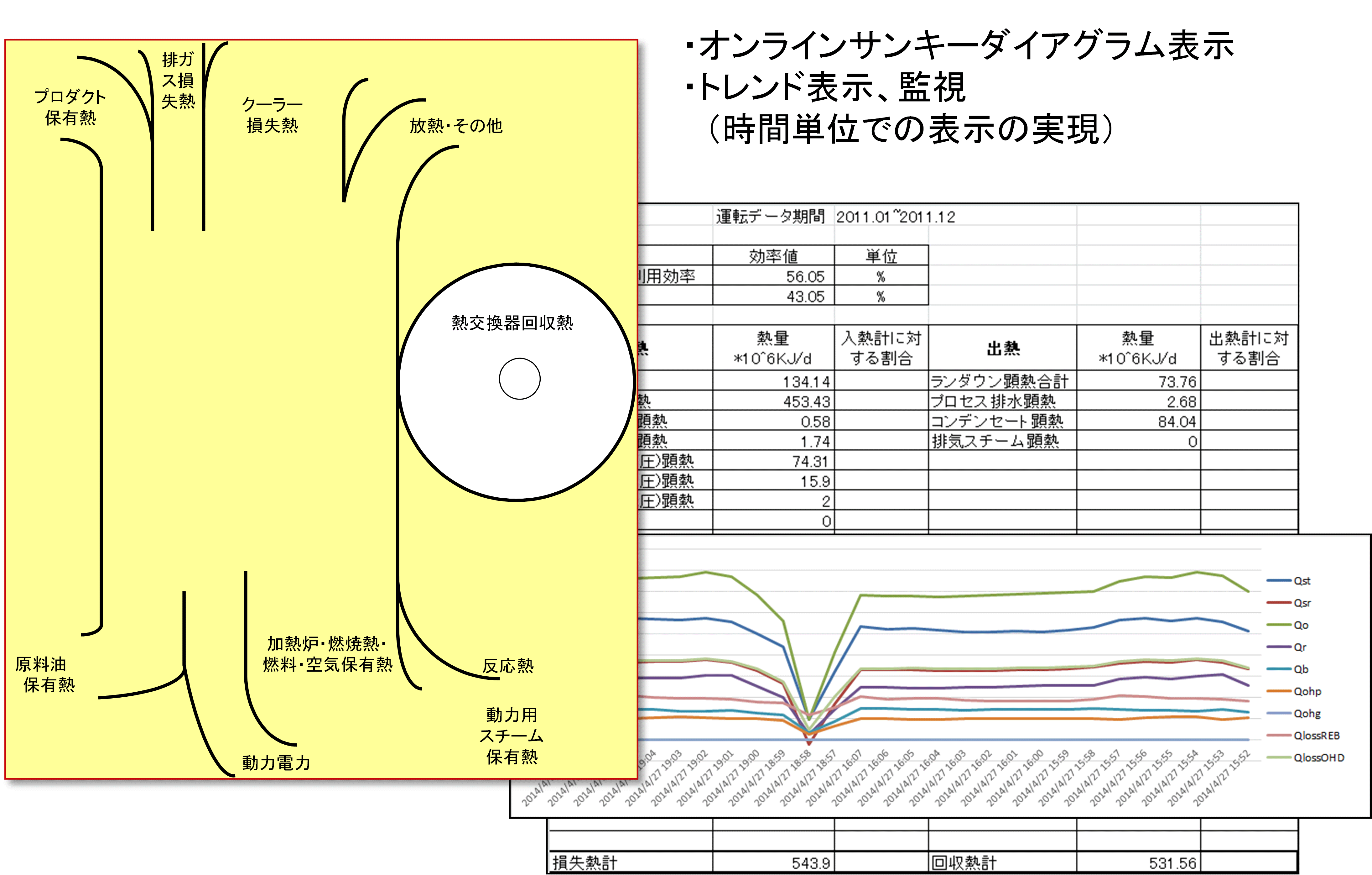
そのためには,装置運転モードごとの燃料ガス発生量,性状が把握されていることが必要で,モード切替え自動化によるモード締めデータがキーポイントとなるのは言うまでもありません。
さらに,昨今のカーボンニュートラルへ向けては,CO2発生予測/実績管理が必要で,比エンタルピーを計算できるExcelアドイン関数の1つの機能(炭素/水素比計算)を活用するのが有効な方法となることも併せて解説しました。
次回は,「モード切替え自動化によるボード負荷軽減とパンデミック対策」について解説します。
〈参考文献〉
1)本田達穂:「特別寄稿;IoT/AIを駆使したプロセスオートメーションの将来像」,『計装』,Vol.63,No.1(2020)
2)本田達穂:「特別記事;石油/石化プラントでの残された自動化の課題と今後の方向」,『計装』,Vol.64,No.7(2021)
3)本田達穂;「連載;長期安定操業での新たな実践的データ活用法;第1~16回」,『計装』,Vol.63,No.2(2020)~Vol64,No.5(2021)