

連載 パンデミックに対応可能な安定操業
-石油・化学工場での自動化の課題と解決策-
第7回 モード締め/時間締めを活用した操業管理の革新
1.はじめに
前回は,モード切替え自動化の2つ目の波及効果として,水平連携であるオンサイト/オフサイト連動したAPC(高度制御)について経済効果を含めて説明しました。
今回は,モード切替え自動化の3つ目の波及効果として,「モード締め,時間締めを活用した操業管理の革新(垂直連携)」について,その具体的な仕組み,方策について解説します。
現状の操業管理業務において,情報技術を活用したシステムによる支援は必ずしも十分ではありません。昨今DX化が叫ばれている中,システム更新に際してもこれといった改善が見えず,単なるハードの置き換えにならざるを得ない現状があります。本稿に示すような,よりリアルタイムな見える化,情報連携(データ連携)の強化という視点からの改善を推し進めることができれば,大きな業務変革と経営効果が期待できます。
2.操業管理関連のシステムに起因する現状業務の問題点
2.1 財務会計のための操業管理システム
現状の操業管理(生産計画実績管理)システムは実務で発生する生産実績,品質確認書や税務帳票等の多くの事務作業をシステム化し,業務効率化に効果を発揮してきていることは事実です。財務会計に必要な生産実績を計算集約し,上位ERPシステムに送信し,入出荷実績とその帳票類等の事務計算と帳票作成等を機械化するといった機能も含んでいます。
しかしながら,操業のPDCA(Plan,Do,Check,Action)のために必要な情報の見える化や支援機能が必ずしも十分でなく,図1に示すような多くの問題点が存在します1,2,3)。
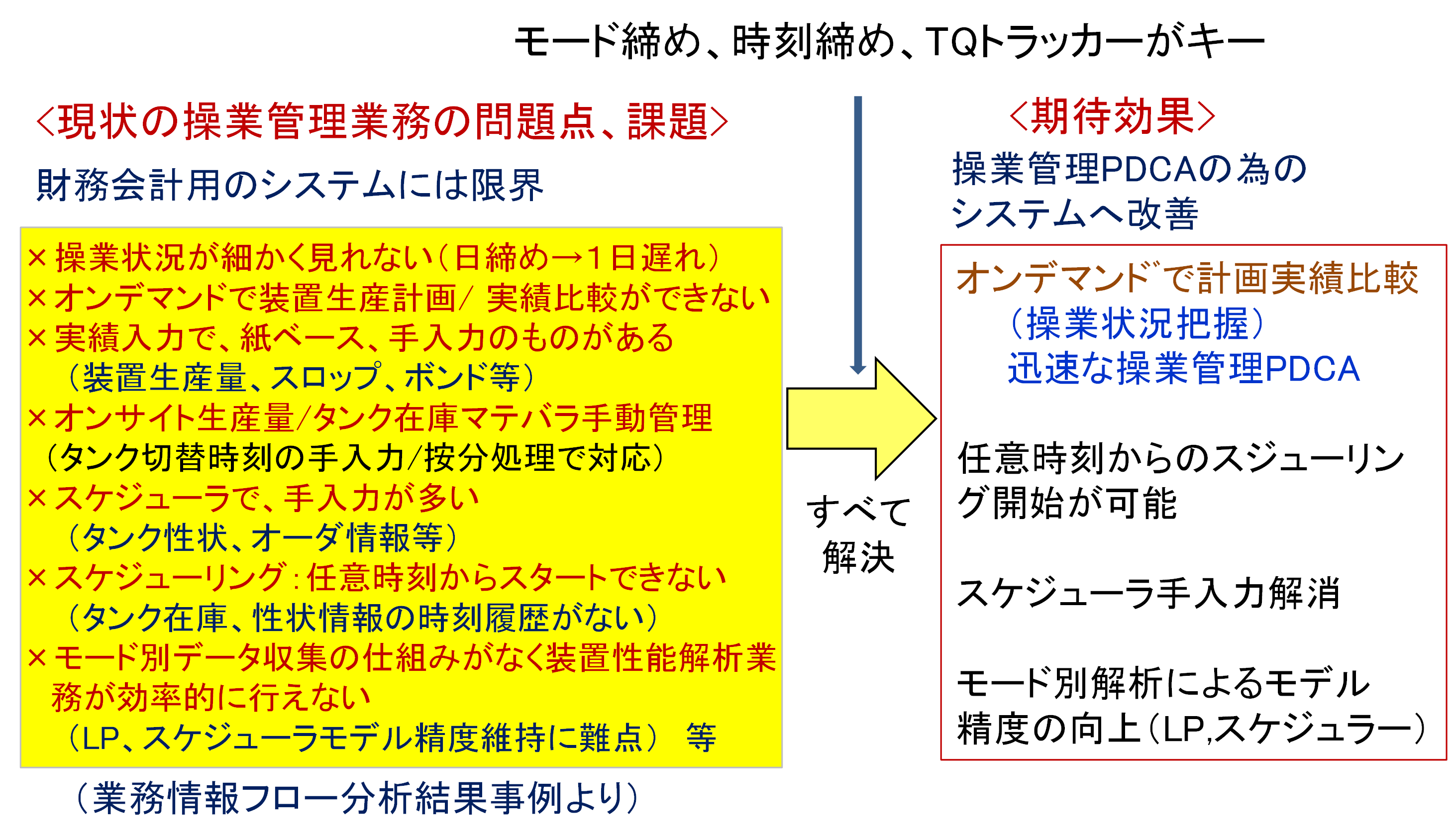
以下に各問題点について説明します。
2.2 操業状況が細かく見えない
現状の操業管理システムは,オンサイトの生産実績(各装置からのランダウンラインからの生産量実績)は定時での1日1回の締め処理データの伝送であるため,現時点でどのように生産がなされているかという操業状況を把握することができません。1日のうちのどこかで装置の異常による生産量の変動があっても,翌朝になっても状況が見えず,連絡を受けてはじめてと状況が把握できるというのが現状です。これを解決するには時間単位の実績把握,時間レベルでの生産量変化の見える化と予測が望まれます。
2.3 オンデマンドでの生産計画/実績比較ができない
時間レベルの装置生産量実績が把握できていない上に,生産指示(計画)であるモード切替えの実績データが上がってこないので,現時点での生産計画に対する生産実績の比較ができないのが実状となっています。このようなリアルタイムなデータは財務会計には必要がないし,生産計画実務者も必要に駆られながらも強く求めてこなかったというのが要因と考えられます。
多くの産業が生産状況把握のリアルタイム化が進んでいる中,大型装置産業である石油・石化工場では改善がなされて きませんでした。そこには部門ごとのシステム改善は進められても部門間の情報連携に着目した改善は進めにくい状況があったとも考えられます。 2.4 装置生産実績は日締め以外は個別に手作業 現在,装置の生産実績としては,1日1回の定時での締めデータしか得られていないので,それ以外の実績把握は人手で行われ,手入力となっています。たとえば,ボンド運転実績,スロップ処理量等がそうです。また,解析のためのある期間のモード実績データ等も手作業で把握するしかありません。 2.5 装置生産量とタンク在庫のマテバラチェック管理は手作業 装置側でモード切替えがあれば,それに付随してタンク切替えが発生します。しかし,現状はモード切替え時刻を含めた量や品質の変化する時点の切替え情報(時刻,切替え時点の締め処理等)がデータ化されていないし,0時等の定時に1回の締めデータしかないので,装置からのランダウン積算量とタンクが受け入れた量のバランスチェックを自動で行うことができず,計器室では手作業で確認がなされています。 たとえば,ある時刻にモード切替えで装置チャージ量変化があったとします。そのままあるタンクにランダウンさせていたものが,オフサイト側でタンク満杯で別のタンクに切替えジョブが実行された場合を考えます。最初からランダウンを受けていたタンクの受入れ実績は,モード切替え前の流量から切替え後の流量の合計として計算しようとしても,何時にモード切替えがあったかの電子情報データがないので,手動で時間による比例配分計算で装置からのランダウン積算量を計算し,タンク在庫増加分と比較する方法しかとれません。 しかし,実際にはモード切替えでランダウン流量が変化している場合が多いこと等を考えると,このような方法ではマテバラチェックの精度も荒っぽいものにならざるを得ません。また,その計算の手間は不要な負荷になっていると言わざるを得ません。 2.6 スケジューラは手入力が多い スケジューラは各装置運転モードのスケジュールを入力し,生産量と入出荷量のタイムスケジュールに従ったタンク在庫の変動をシミュレートするツールで,時間レベルでそれぞれの動きを見ることができるものです。生産量に対してタンク在庫が不足したり,オーバしたりしないように装置運転モード切替えスケジュールをガントチャート上で修正して再試行するという具合に,生産スケジュールのケーススタディを行うものです。 この中ではタンク内性状も加味され,一種の生産バランス高速シミュレータということができます。 図2に見るように,入力データとしてタンク性状がありますが,ランダウン受入中のタンク性状はデータがないので過去の実績からの経験値を手入力しています。そのほか,入出荷量,装置モード切替え情報等も合わせて手入力することで開始準備ができます。 このように手入力が多いので多くのケースを行うことが難しい状況です。改善課題として,できるだけ手入力を少なくするための情報連携が必要です。また,スッケジューラ入力に必要な受入中のタンク性状推定もTQトラッカーの活用が期待されるところです。 2.7 スケジューラが任意時刻からスタートできない 前述したように,現状は日締めデータしかないので,シミュレータの開始時刻は定時締め時刻(0時等)とならざるを得ません。 装置の変動や入出荷量の変動等が発生した場合,これからの工場の生産をどうするのか,スケジューラで将来予測によるケーススタディをして今後の生産方針を立てるということが必要になります。 しかし,シミュレータの開始時刻ははるか前の時刻(締め時刻:0時等)から行わざるを得ないのが現状です。 時間単位の生産実績とタンク性状データ(推定値)があれば,任意の時刻からのスケジューラのシミュレーション開始が可能となり,スケジューラは生産戦略上の強い武器となるはずです。 2.8 モード別データ収集の機能がなく,装置性能解析が非効率 本社サイドの生産計画で運用するLP(Linear Programing)内のモデル式,工場サイド運用するスケジューラ内の生産量や性状に関するモデル式は,各工場が評価した運転モードごとの性能計算式が組み込まれています。 現状では,単なる日締めデータのみで,モード別の運転データが得られてないので,工場では各装置の各モードにおける安定した状態でのデータを採取して,性能データとしています。これにはそれなりに手間と労力を要しています。また,瞬時値なので積分的な生産実績の視点からは精度上必ずしも満足できるものではありません。 3.操業管理の革新へ向けた改善策 以上述べたように,元来財務会計,税務用に開発された現在の操業実績管理システムには,操業のリアルタイムなPDCAのためのシステムとしては,多くの問題点を含んでいます。 図3には,操業(運転と生産計画,入出荷)全体に関わる残された自動化の課題解決策をまとめてあります。その中で操業管理システムの位置づけがわかります。 前述の操業管理に関わる問題点を解決するためのキーポイントは,オンサイト生産量の締め処理の改善(モード締め/時間締めの導入),受入中タンクの性状推定を実現するTQトラッカー(仮称)の2つとなります。 3.1 モード締め/時刻締めへの改善 オンサイトワーク管理システムによるモード切替えの自動化を行えば,システムによるモードごとの生産量を計算処理し,上位システムへ送ることができます。 図4に,現状の日締めからモード締め/時間締めへの改善内容を示しました。各装置からのランダウン量の実績としてモードごとの生産量(切替から次の切替えまでの積算量),各時間ごとの生産量を上位システムへ送る形となります。 生産計画とは,以前にも言及したようにオンサイト装置群のモード切替え指示ということに外なりません。その指示に対する実績を見えるようにするということです。そこから計画//実績比較が実現します。 さらに,時間ごとの生産量実績を見える化できることから,迅速な変化への対応が可能となります。 3.2 TQトラッカーによる受入中タンクの性状把握 TQトラッカーによる受入中タンクの性状推定は,スケジューラへのタンク性状の自動入力を可能にします。この点は次のスケジューラの運用で重要な改善策となります。 その他のTQトラッカーのメリットは前号および前々号を参照下さい4,5)。 3.3 スケジューラ本来の目的を得るための改善 操業管理のPDCAでスケジューリングは最も重要な作業となります。しかしながら,スケジューラには手入力が多い上に,任意の時刻でのシミュレーションのスタートができないといった問題点を示しました。 これを解決するために,既に述べたモード締め,時間締めに加え,図2に示すようなデータ連携の改善が必要となることは言うまでもありません。 4.操業管理のあるべき姿の実現 図5に操業管理のあるべき姿を示しました。その開発にあたっての要点,および運用とメリットについて以下に解説します。 4.1 操業PDCA管理システム開発にあたっての要点 既存の財務会計のための操業実績管理システムは既存のままで活用します。既存のデータベースを拡張するか専用のデータベースサーバを追加し,時間ごと,モードごとの積算実績を蓄積する形とします。操業PDCA管理のためのアプリケーションサーバも追加する形です。大きなハード/ソフトの追加変更は発生しません。 操業PDCA管理システムのデータはKL単位で十分です。財務会計のようにリットル単位まで合わせ込むような処理は不要となります。 ソフトウェア開発としては,標準的なツールを用いて,主にトレンド表示を活用することになります。主要なトレンドの種類を図6に示しました。 すなわち,いかに容易にリアルタイムな生産予測を見える化し,計画/実績比較と変化への修正計画の内容が一目瞭然となるようにできるかがポイントなります。開発にあたっても開発内容,構成等から容易なものとなっており,開発費用もさほど要しないことが推察できます。 4.2 操業PDCA管理システムの運用(操業管理のあるべき姿)とメリット 以下に操業PDCA管理システムを活用した操業管理のあるべき姿を示します。図5に示すような生産情報の流れに沿った業務となります。 ・操業管理とオペレーションをシステム連携する観点から,スケジューラからの出力である運転指示(モード切替え)情報がワーク管理システムに渡され,モード切替えやタンク切替えが自動的に実行されます。 ・その結果をオンサイトの操業実績として時間ごと,モードごとの実績として操業実績DBに上げます。
・オフサイトジョブの実績は既存の操業実績DBに上げられます。 ・そのデータから計画実績比較を見える化したトレンド表示で,生産計画に対して再スケジュールの必要性を検討し,必要であればすぐにその時刻からの再スケジューリングが実現できるようにします。(図6) ・その再スケジュール結果と実績とのトレンド比較を見ることができるようにします。 このような操業PDCA管理システムによって得られる経済効果を図6に示しました。 近い将来,さらなる安価な原油(原料)で需要を満足できる見通しを示し,スポット的な原油/原料調達について,製造部門から需給調整/原油(原料)調達部門への要望が可能となり,より柔軟で迅速な需給管理が可能となります。また,より精度の高い将来在庫の予測を実現することで,製品の現地買い(現地での他社製品の購入),中間製品の製油所/工場間転送要否の見極めによる転送費用の削減といった大きな経営効果を期待できます。 さらに,ある工場での装置トラブルが他工場の生産計画修正を余儀なくされるケースでは,いち早く各工場で再スケジューリングが可能となり,より適正なロスの少ない全社での生産調整修正が実現できるようになります。 すなわち,工場内だけではなく,もう一つ上の本社サイドの需給調整をより迅速かつ柔軟にすることに繋がり,より大きなメリットを生む改革が期待できます。 5.おわりに 今回は,モード締め/時間締めを活用した操業管理の革新について,その方法とメリットについて解説しました。操業計画とオペレーションの情報連携(垂直連携)がモードをキーとして行われるところがポイントとなります。 今後DX化という方向の中で,このような工場内のデジタル化を推し進めることで,本社サイドでの集計を行い,さらなる大きな需給調整の迅速な管理ループを実現することが,DXとしてなすべきことと考えます。 次回は,モード切替え自動化の4つ目の波及効果として,「CO2管理を含むリアルタイムなエネルギー管理へ」について解説します。 〈参考文献〉 1)本田達穂:「特別寄稿;IoT/AIを駆使したプロセスオートメーションの将来像」,『計装』,Vol.63,No.1(2020) 2)本田達穂:「特別記事;石油/石化プラントでの残された自動化の課題と今後の方向」,『計装』,Vol.64,No.7(2021) 3)本田達穂:「残された自動化の課題と今後の対応策」,『2020計装制御技術会議資料』(日本能率協会主催) 4)本田達穂,「連載5回;パンデミックに対応可能な安定操業;タンク切替えのオン/オフ自動連携とTQトラッカー」,『計装』,Vol.65,No.10(2022) 5)本田達穂,「連載6回;パンデミックに対応可能な安定操業;オン/オフ連携したAPCとその経済効果」,『計装』,Vol.65,No.11(2022)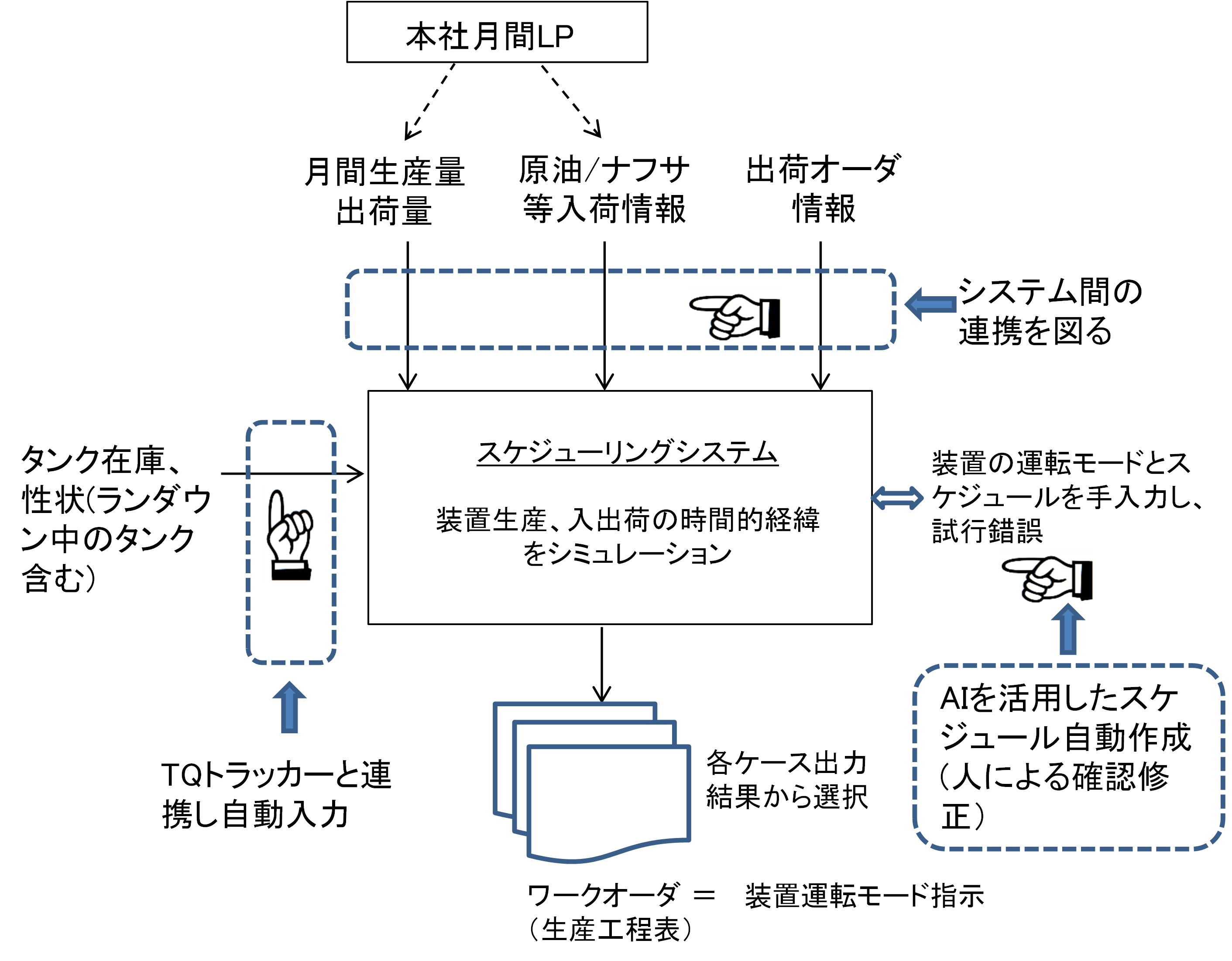
図2 スケジューラの情報連携の問題点と解決策
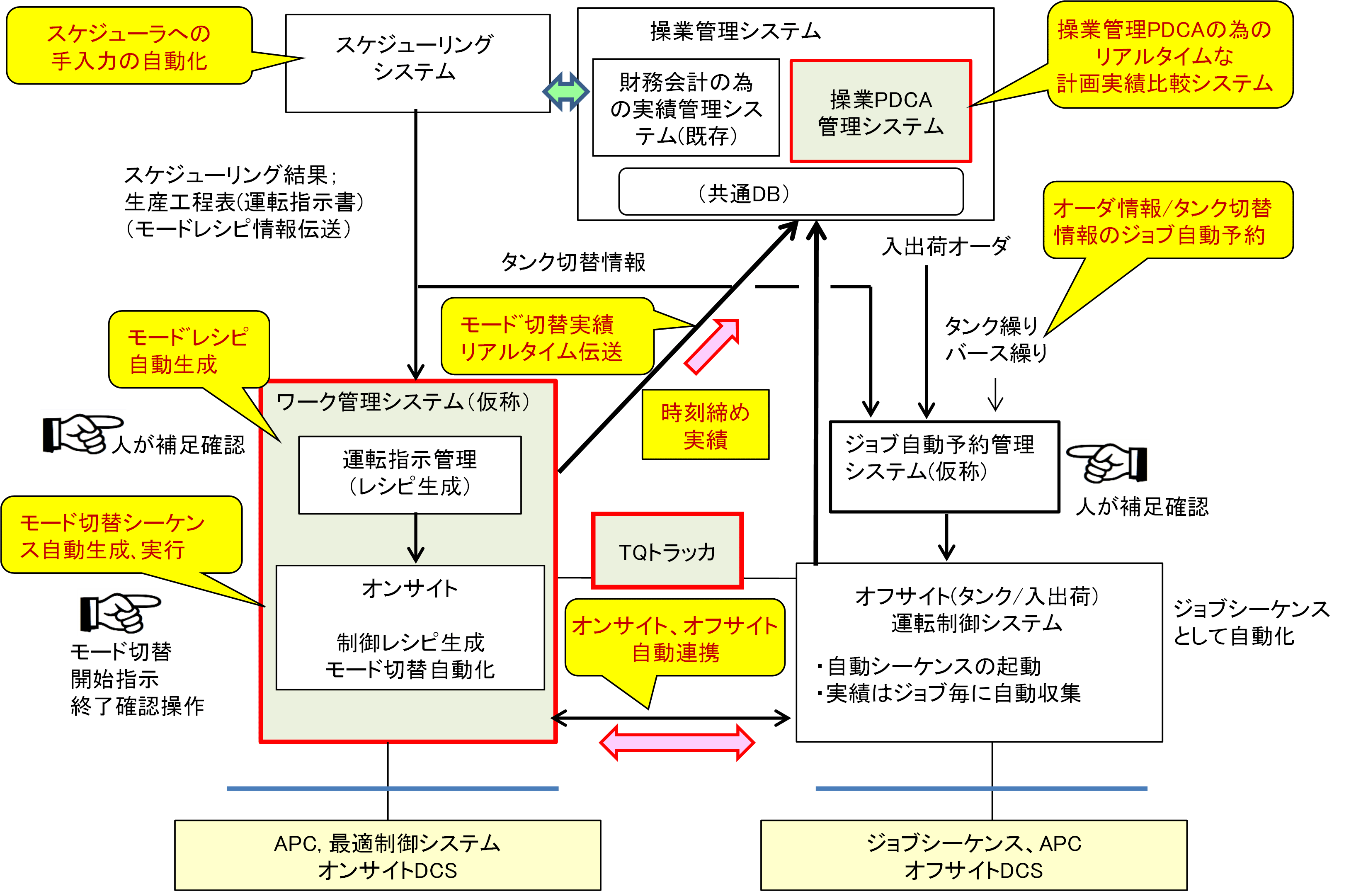
図3 オペレーション自動化、操業管理での課題と解決策(石油/石化を例に)
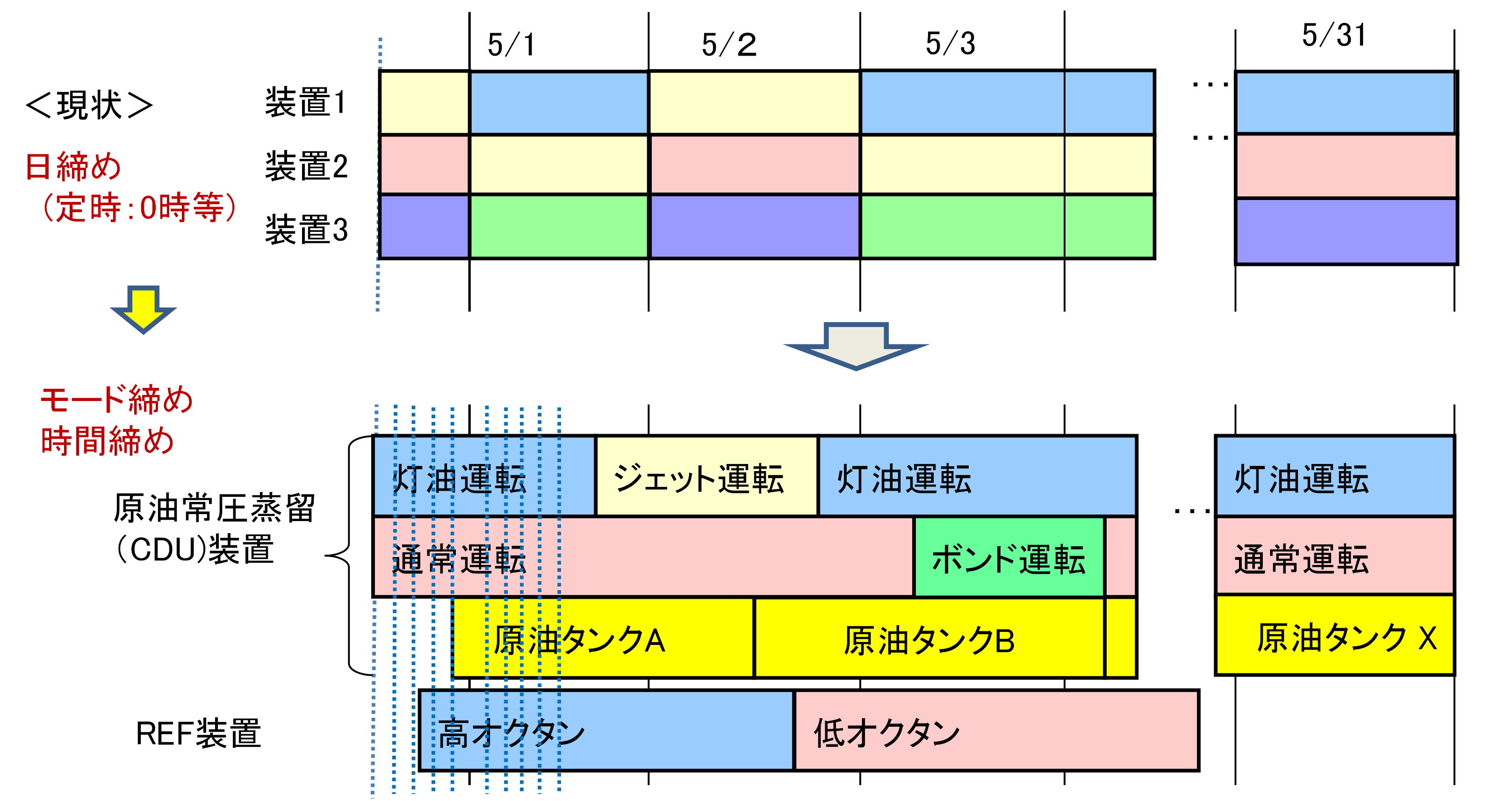
図4 連続プラントでの実績締め処理の現状とモード締め/時間締めへの改善
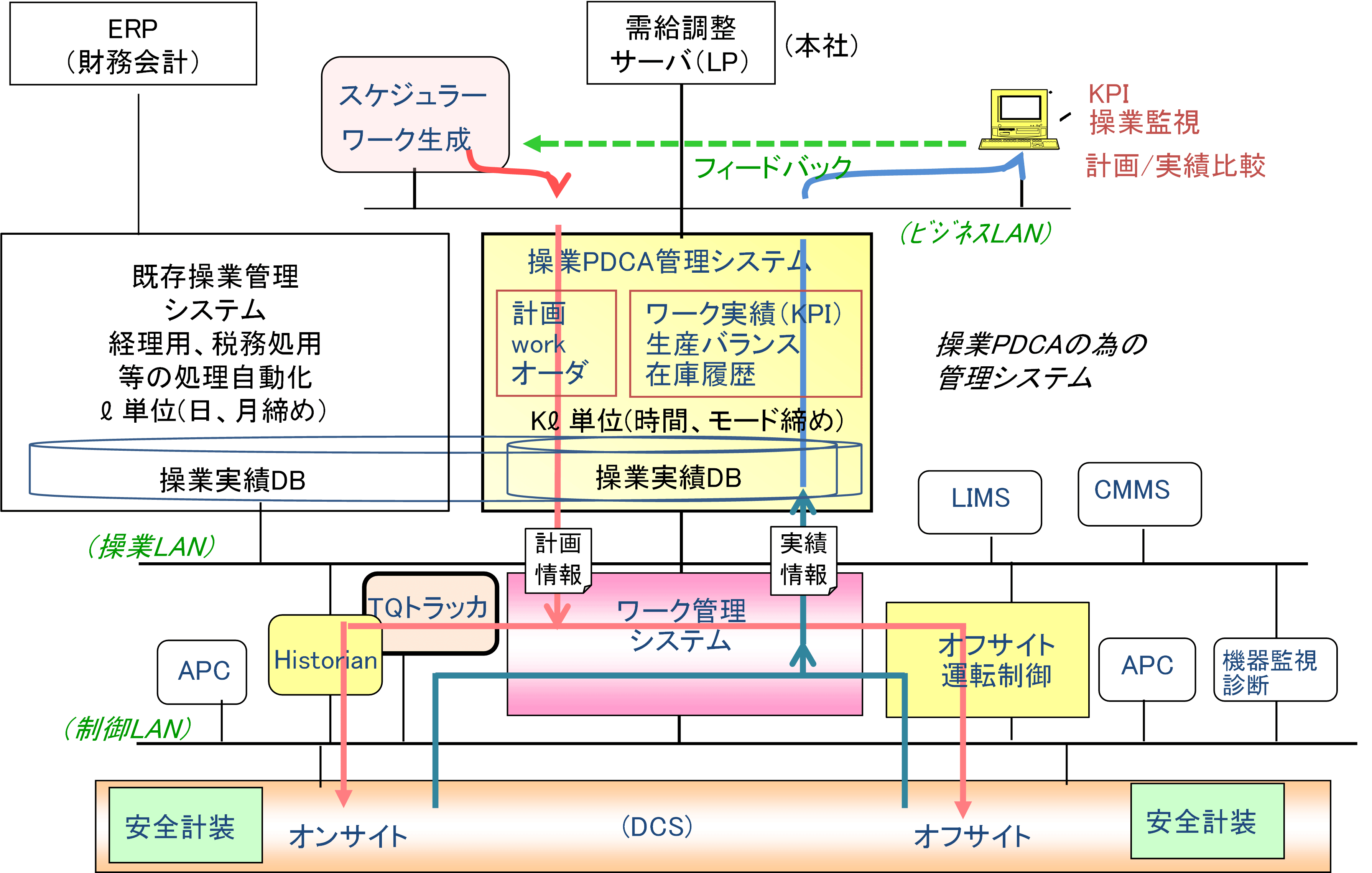
図5 操業PDCAのための実績管理システムの構成と情報連携フロー
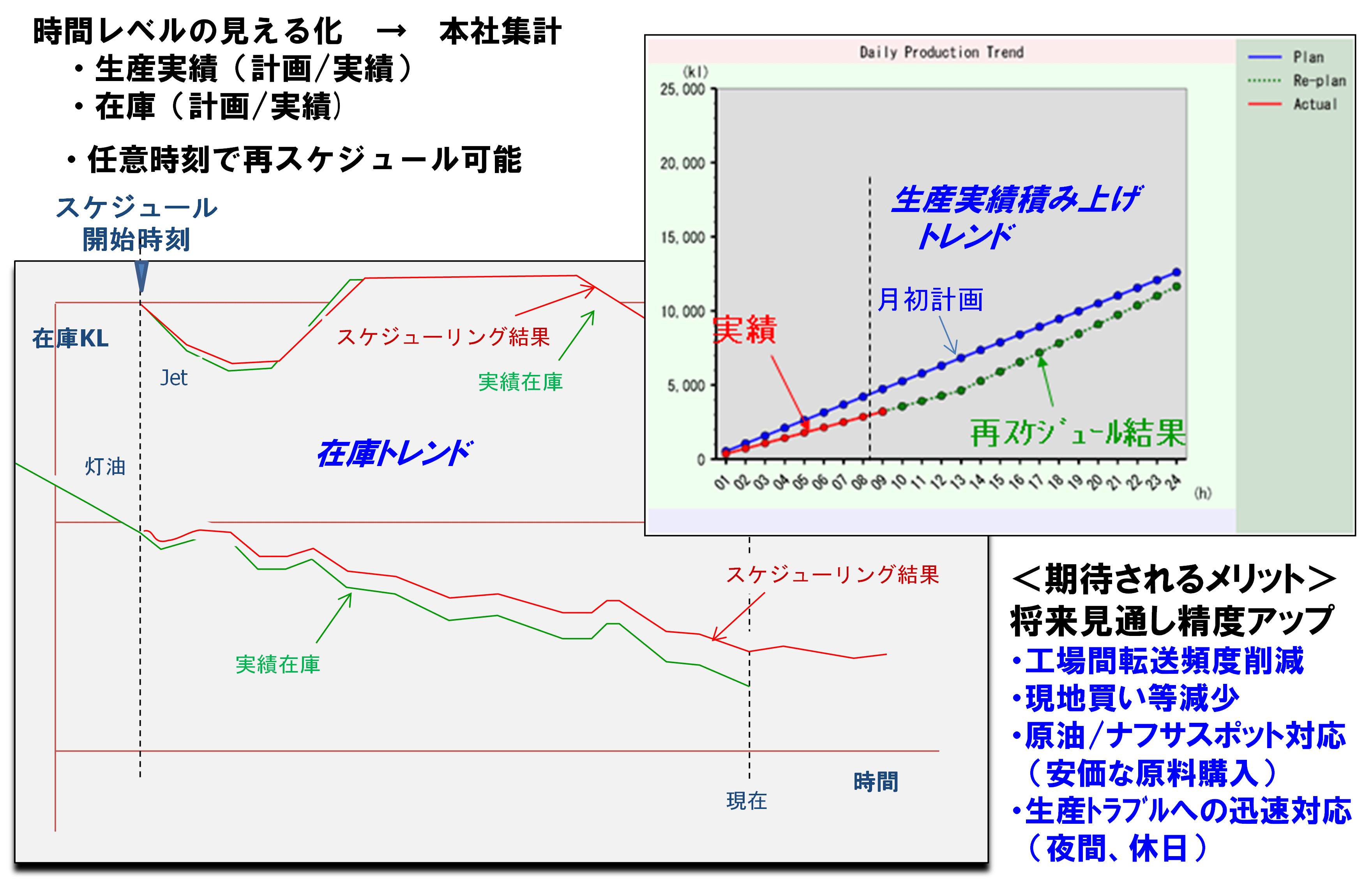
図6 リアルタムな操業PDCAのための管理画面例と期待されるメリット
ポータルサイトへ