

連載 パンデミックに対応可能な安定操業
-石油・化学工場での自動化の課題と解決策-
第2回 オンサイト連続プラントでの自動化項目の整理と次の自動化課題
1.はじめに
前回はプラントの自動化について,過去の歴史と自動化が果たしてきた経営貢献という視点からの効果について述べました。
今回は,オンサイトプラント(連続プラント)の自動化の現状をボードオペレータとフィールド業務を含めて整理し,それらについて考察を加え,主な課題は何かについて述べます。
2.連続プラントでの自動化の現状全容
図1に,一般的な連続プラントにおける装置の運転形態を示しました。表1に,それぞれの運転モードにおける自動化の現状と今後の課題方向について,石油プラントを例にその全容詳細を示しました1)。 項目ごとに分類をして,どの部分の自動化についてのことかを示すことで理解を得やすくしました。
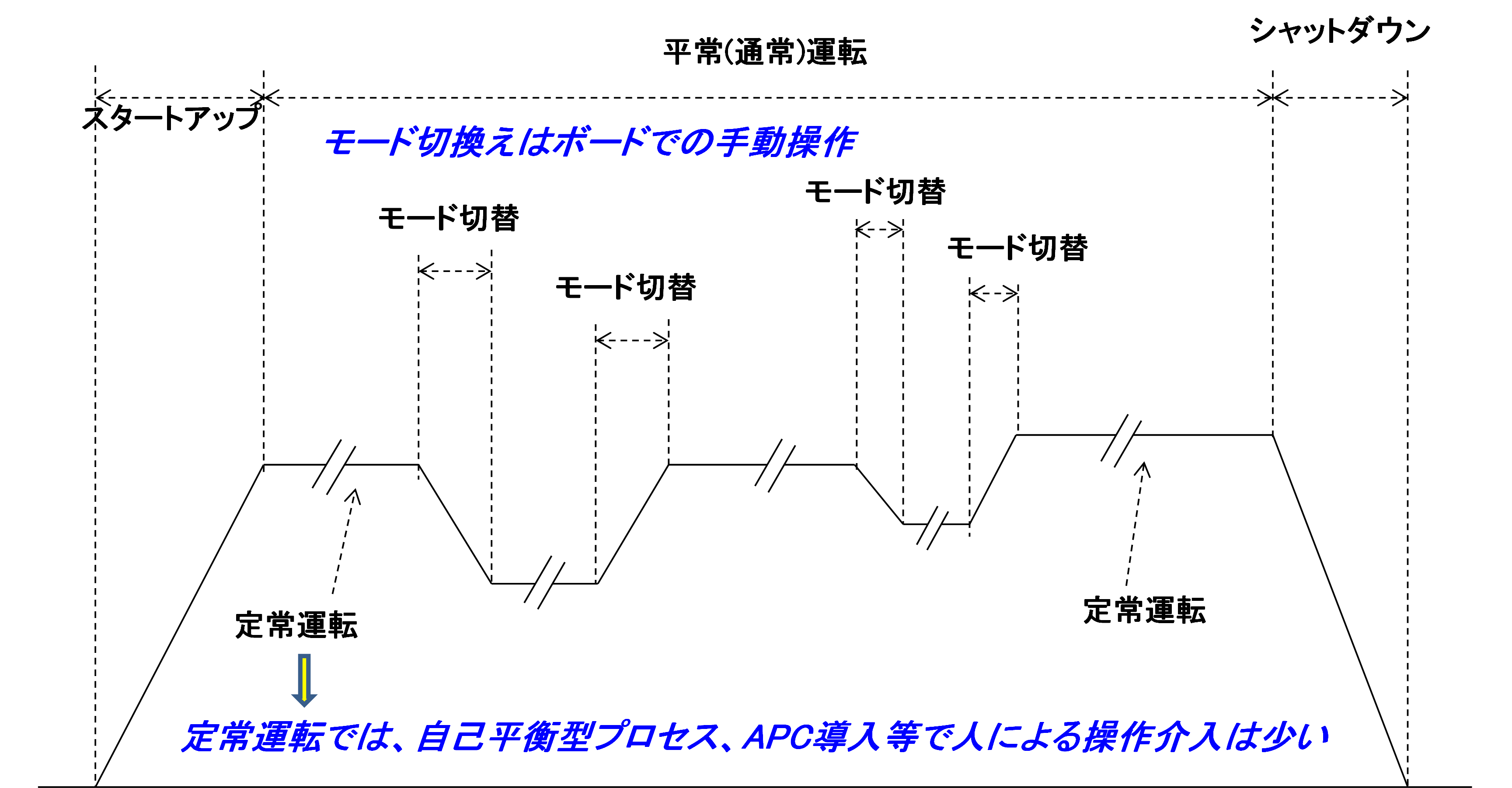
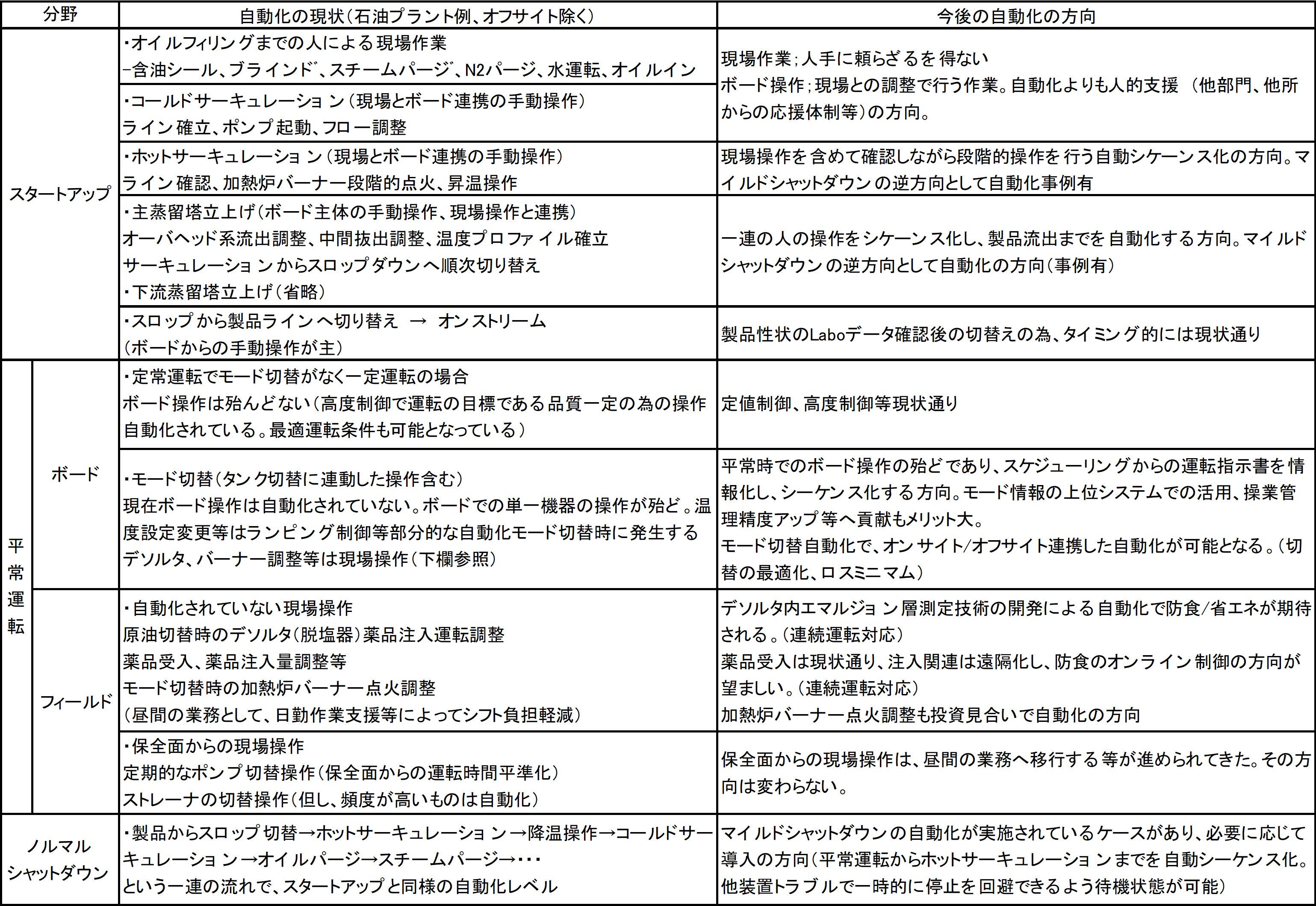
3.平常時ボード操作での自動化の現状
3.1 定常運転でのボード操作における自動化の現状
ボード操作で,定常運転においては,モード切替えを除く一定条件での定常運転では,過去には品質を目標値に維持するためにボード操作が頻繁に行われていた時期がありました。しかし,高度制御(APC)が導入されて以降,自動的に品質を維持することが可能となり,ボード操作が大幅に削減され,現状ではほとんど操作介入することなく自動運転が実現しているのが実情です。
3.2 モード切替えの自動化の現状
オンサイトオペレーションでのモード切替えという操作は,生産計画でのスケジューリング結果である運転指示書(生産工程)に示された操作となります。フィードタンク/ランダウンタンク切替え,フィード量増減指示,反応塔温度変更等がこの中で指示されます。
残念ながらこのモード切替え操作は,図2に示すようにボードオペレータの単一機器の操作(DCS画面から流量や温度設定値の変更)により行われており,一部昇温操作でのランピング操作等が自動化されているものの,それ以外はほとんどが手動というのが現状となっています。
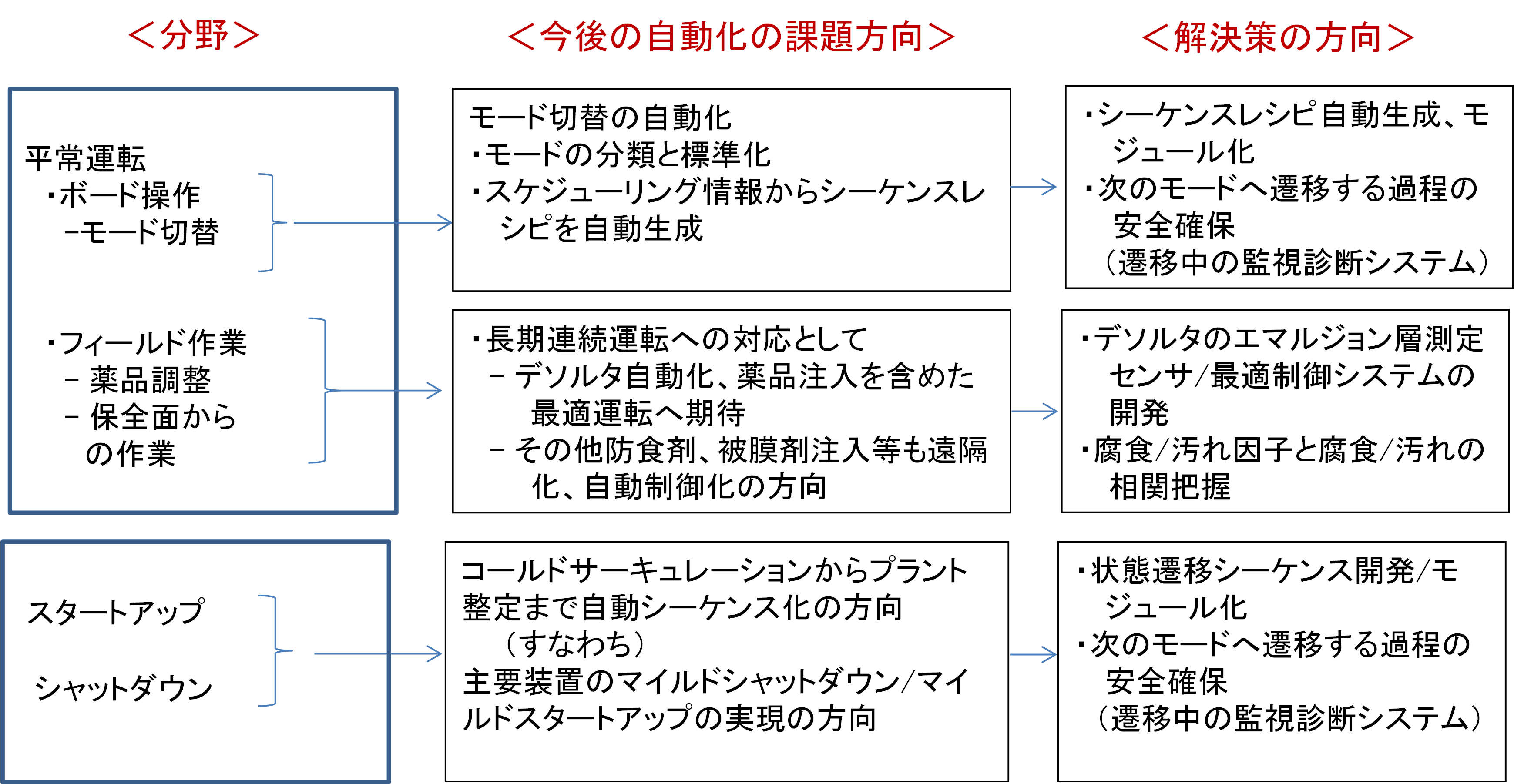
タンク切替え時はオフサイト部門(タンク管理,入出荷部門)のボードオペレータと電話連絡しながら切替えタイミングを図っています。
また,石油プラントでの原油タンク切替えでは,タンク品質の変化が大きいので,切替え直後のプラントの品質変動調整では,APCをオフにしてボードオペレータによる手動調整になるケースも多々あります。
4.フィールド業務における自動化の現状
4.1 防食剤等の薬品注入操作
(1)石油プラントでの脱塩器操作
石油の場合,原油切替え時のデソルタ運転調整で現場での調整操作の頻度が増加します。デソルタ内部のエマルジョン層等が見えないため,トライコックからサンプリングした液の色等を見るといった経験を積み重ねながら水注入量,薬品注入量等調整する現場操作が多いのが実情です。
(2)防食剤等の薬品や添加剤の注入操作
プラントへの薬品注入は現場のインジェクションポンプのストローク調整で行われますが,ほとんどが現場手動となっています。中和剤,被膜剤等の注入もそうなっています。
4.2 加熱炉バーナ調整作業
接触改質装置(リフォーマ装置)等の運転モード変更では,加熱炉のバーナ調整が発生するケースが多くあります。バーナ点火,消火等の自動化は,電力関連のボイラ立上げ/立下げの自動化が行われており,技術的なハードルは少ないものの,石油,化学プラントにおいては,投資対効果等の要因で,これまで見送られてきた経緯があるのが実情です。
4.3 フィールド業務における保全面からの手動操作
装置に設置されているポンプ(回転機類)のほとんどは運転時間管理されており,使用頻度時間の平準化を図るため, 適切な周期でスペアと切替えが行われています。ストレーナも詰まり具合で定期的にスペアと切替え操作等が行われています。 これらの切替え操作は,頻度が高ければ自動化されているし,そうでないものはフィールド業務として現場での手動切替え操作が行われているのが実情です。 5.スタートアップ,シャットダウンの自動化の現状と今後の方向 5.1 スタートアップの自動化の現状と今後の方向 プラントの事故の中でスタートアップ時に発生したものの割合が大きく,文献2)にも記載があり,その対策として自動化が期待されているのは事実です。合せて,オペレータの負荷を削減していく方向はパンデミック対策としても望ましいことと考えられます。 スタートアップでの作業は多岐にわたっていて,表1に示すように整理するとわかりやすくなります。我々が自動化の対象とするのは,コールドサーキュレーション以降であると考えられます。 過去に石油では二次装置(脱硫装置)等を対象に,DCSの上位システムとしてバッチ操作用ツールを使って,オペレータと会話しながらシーケンスを進めるスタートアップ自動化システムが構築された実績もあります。スタートアップからプラント整定までに多くの現場操作確認と連絡があり,その過程を含めてシステムに組み込み,画面上で確認しながら次の操作に移るというものです。こうしたシステムが横展開で多くの装置,引いては工場全体に活用されていかなかったのは,操作頻度が比較的少ないこと,システム依存への信頼性の面,ベテランによる人の技量に依存してしまった実情等があると推測されます。 5.2 シャットダウンの自動化の現状と今後の方向 緊急停止の自動化は従前から確立したものがあり,リレーから安全計装システム(Safety Instrumentation System)へ移行しつつあるのはご承知の通りです。 ノーマルシャットダウン操作については,スタートアップの自動化と同様の位置づけとなりますが,国内で自動化の事例を見ることは難しい状況です。 しかし海外では「マイルドシャットダウン」と称するものを見ることができます(平成2年当時仏某製油所)。これは,シーケンシャルに自動操作しながら平常運転からホットサーキュレーションまでもっていくシステムです。これは当時の安全計装システム(三重PLC方式)に類似したもので構築され,平常運転まで立ち上げるスタートアップ操作も自動化されていました。 上流の装置がトラブルで一時的に生産停止した際,原料供給が途絶え,二次装置も完全シャットダウンしなければならなくなるのを防止し,ホットサーキュレーションを維持して,安全な再スタートに備えるためのものです。ホットサーキュレーションから再立ち上げすることは,ホットボルティング等が不要となるなど,一旦火を消してから再立ち上げするのとでは比べものにならないくらい安全で効率的と言えます。 6.おわりに 今回は連載の第2回として,石油・化学プラント(連続プロセス)において,自動化の経緯,現状と今後の解決策の方向について解説しました。それらを要約すると図2のようになります。 本連載では次回から,図2に示したボード操作の自動化に関して,今後の課題と解決策について,新しい視点と具体的な内容について解説していくことにします。 2021年の石油学会の経営情報部会ワーキンググループにおいて,連続プラントの自動化に関する国際規格の調査検討が行われており,これはパンデミック対策につながるものとして参考にすべきものがあります2,3)。そこでは,プラント自動化関連の国際規格の動向がわかることから,次回からはそこからのヒントについても触れることにします。また,自動化による企業への貢献,経済性についてもできるだけ定量的に示していく予定です。 〈参考文献〉 1)本田達穂:「特別記事;石油/石化プラントでの残された自動化の課題と今後の方向」,『計装』,Vol.64,No.7(2021) 2)渕野哲郎:「プロセス産業におけるオートメーション化への期待と要件」,セッション;連続プロセス
のオートメーション,『石油学会第50 回石油・石 油化学討論会要旨集』(2021) 3)北島禎二:「ISA標準を中心としたプロセス産業の自動化に関する考察」セッション;連続プロセスのオートメーション,『石油学会第50回石油・石油化学討論会要旨集』(2021)
ポータルサイトへ