

連載 パンデミックに対応可能な安定操業
-石油・化学工場での自動化の課題と解決策-
第1回 石油・化学工場での自動化の経緯と経営貢献
1.はじめに~<連載開始にあたって>
このところ国内はもちろん,世界的にコロナ感染による社会活動への支障が問題となっています。石油・化学工場においても,運転をはじめ操業を維持するために必要な人員という視点からは,感染症等のパンデミックの事態に対応できるようにしていくことが求められています。
感染症等でのパンデミック対策の柱は,プラントでの操業可能な最小人員を把握しておき,一時的に少人数での操業を行うということです。言い換えれば,ある期間限定という制限はつくものの,対象プラントが最低何人で運転操業を維持することが可能かについて対応策を含めて検討することになります。
本連載では,最初に,これまでのプラント自動化(プロセスオートメーション)の歴史,経緯について述べ,現在残されている自動化の課題について述べます。また,そこで自動化が果たしてきた経営貢献についても合わせて解説します。
次に,オペレーションの自動化の中でボードとフィールドに分けて,残された課題の自動化とその経営効果について述べていくことにします。そこには,工場内の情報をさらに水平/垂直連携させていくことによる高度なオペレーションの自動化,操業管理についての解説も含まれます。
また,スタートアップ/シャットダウンの自動化についても言及することとします。
オペレーションの必要人員に関する考え方,指標についても述べることにし,本連載が今後のパンデミック対策の一助となれば幸いです。
第1回は,「石油・化学工場での自動化の経緯と経営貢献」について記します。
2.プラント操業での自動化の経緯
2.1 計装制御システム技術とプラント制御監視システムのトレンド
計装制御システム技術がプラント制御監視システムに与えた影響については,経済産業省特許庁が編集した「プラント制御監視技術の技術概要」に適切な記載があります1)。すなわち,情報通信技術の進展がプラント制御監視システムの技術的進歩の背景としてあり,その変遷を図1に示します。
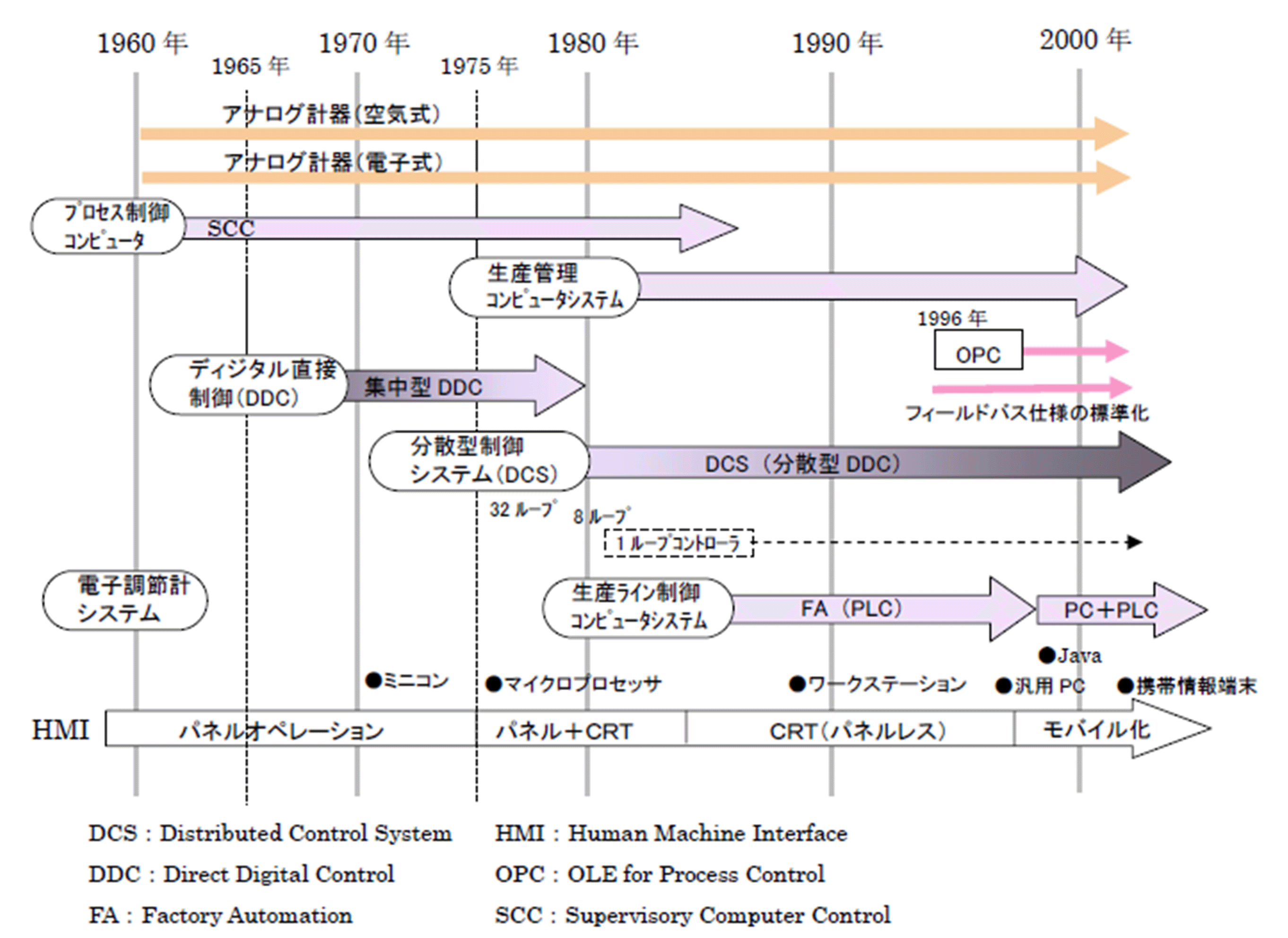
また,図2に示すように,コンビナートに立地する石油・石油化学・化学プロセス産業の自動化(オートメーション)において,計装制御技術・情報システム技術の進展と活用は,プラントの操業の効率化,少人数化および安全操業の確保・向上に大きく貢献してきました。
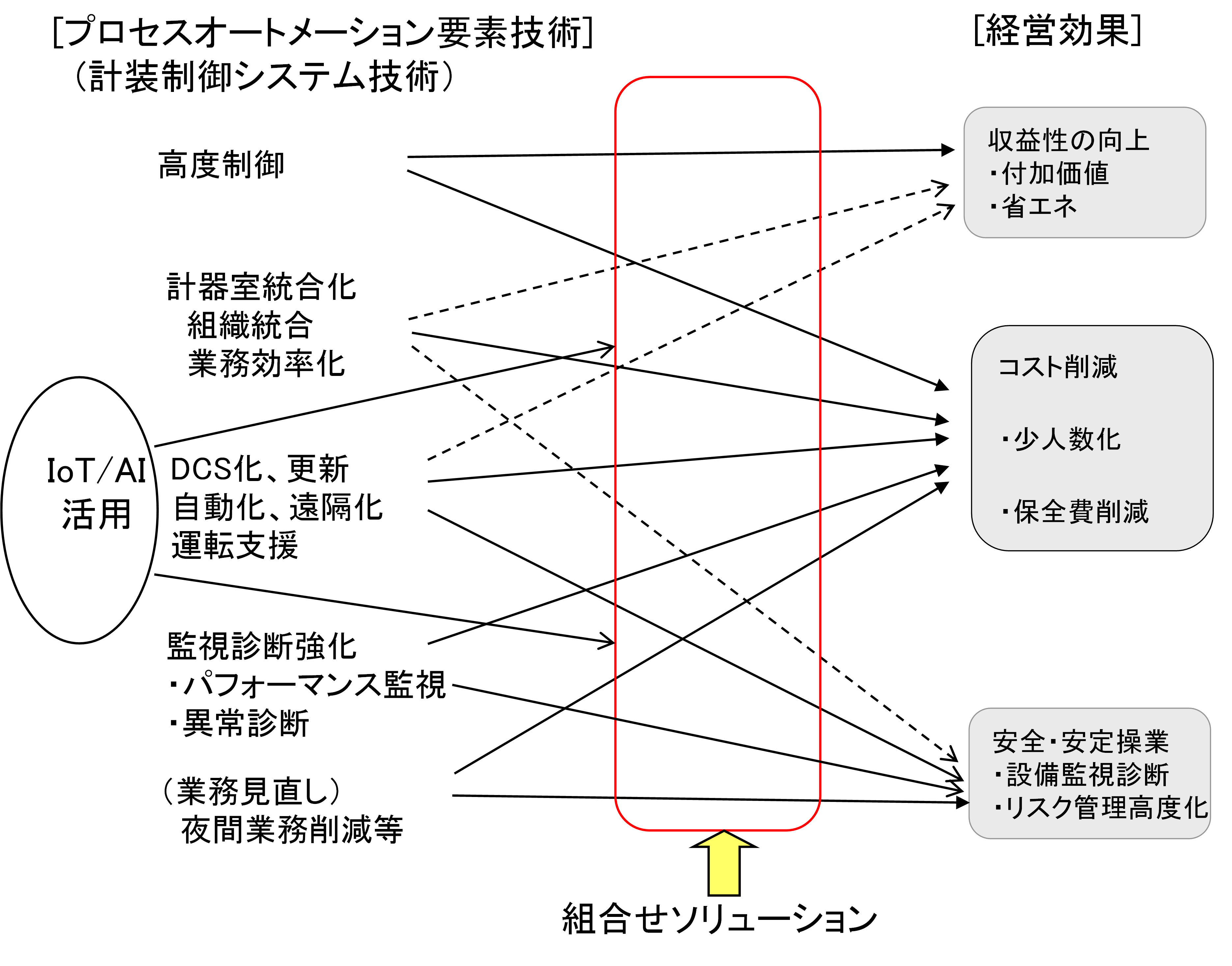
2.2 プラント自動化等により得られた経営効果
(1)少人数化効果
図3は計装制御システム技術変遷に伴う操業効率化,安全性向上の歴史,変遷を示しています。
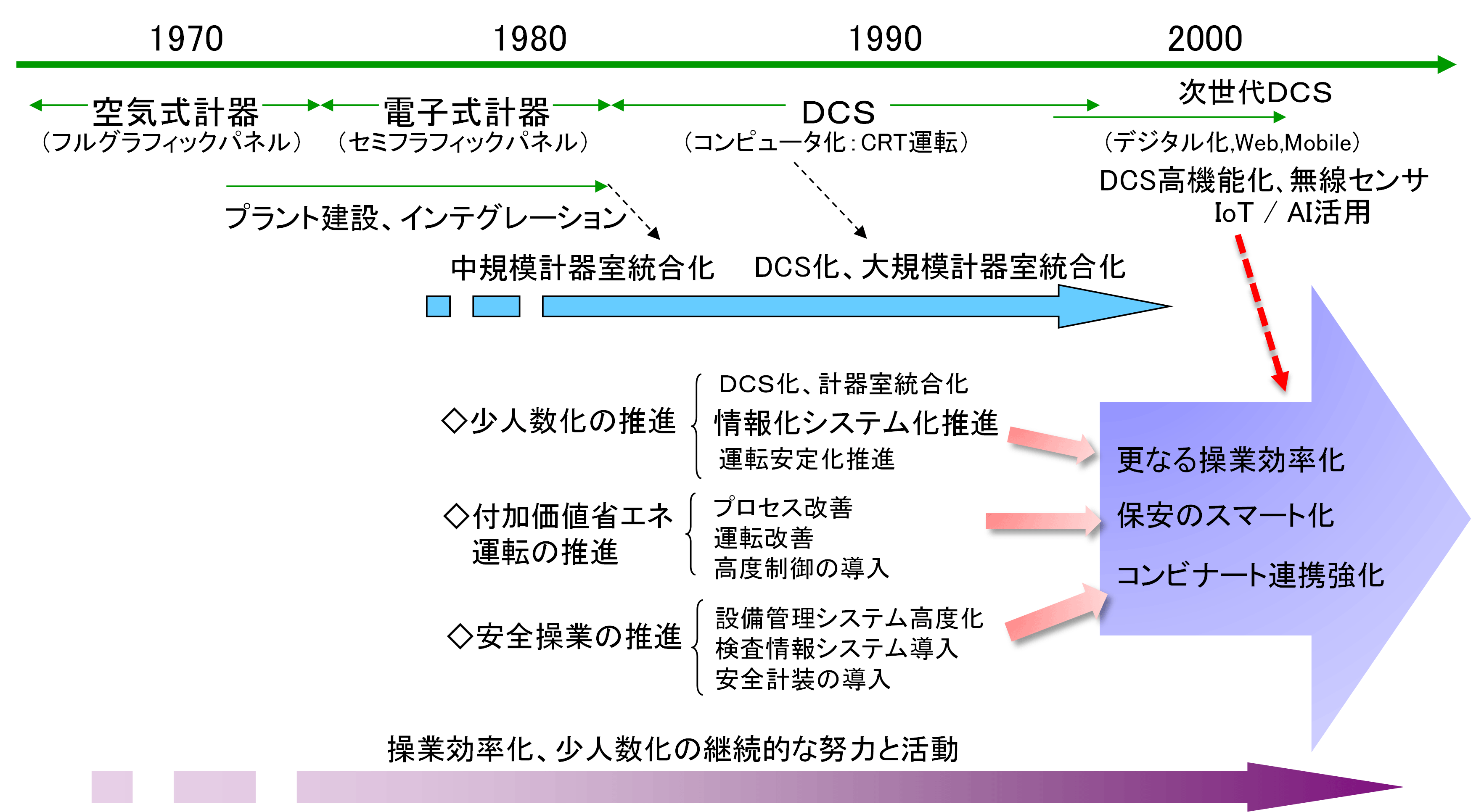
そのような経緯に伴って,図4に示すようなオペレーションの少人数化を実現してきました。国内において,プラント規模が500出力数(単一制御ループ数=調節弁の数)の範囲をカバーするボードオペレータ,フィールドオペレータの人員の推移を見てみると,自動化技術による少人数効果の大きさには計り知れないものがあり,競争力強化に大きく貢献してきたことがわかります3)。
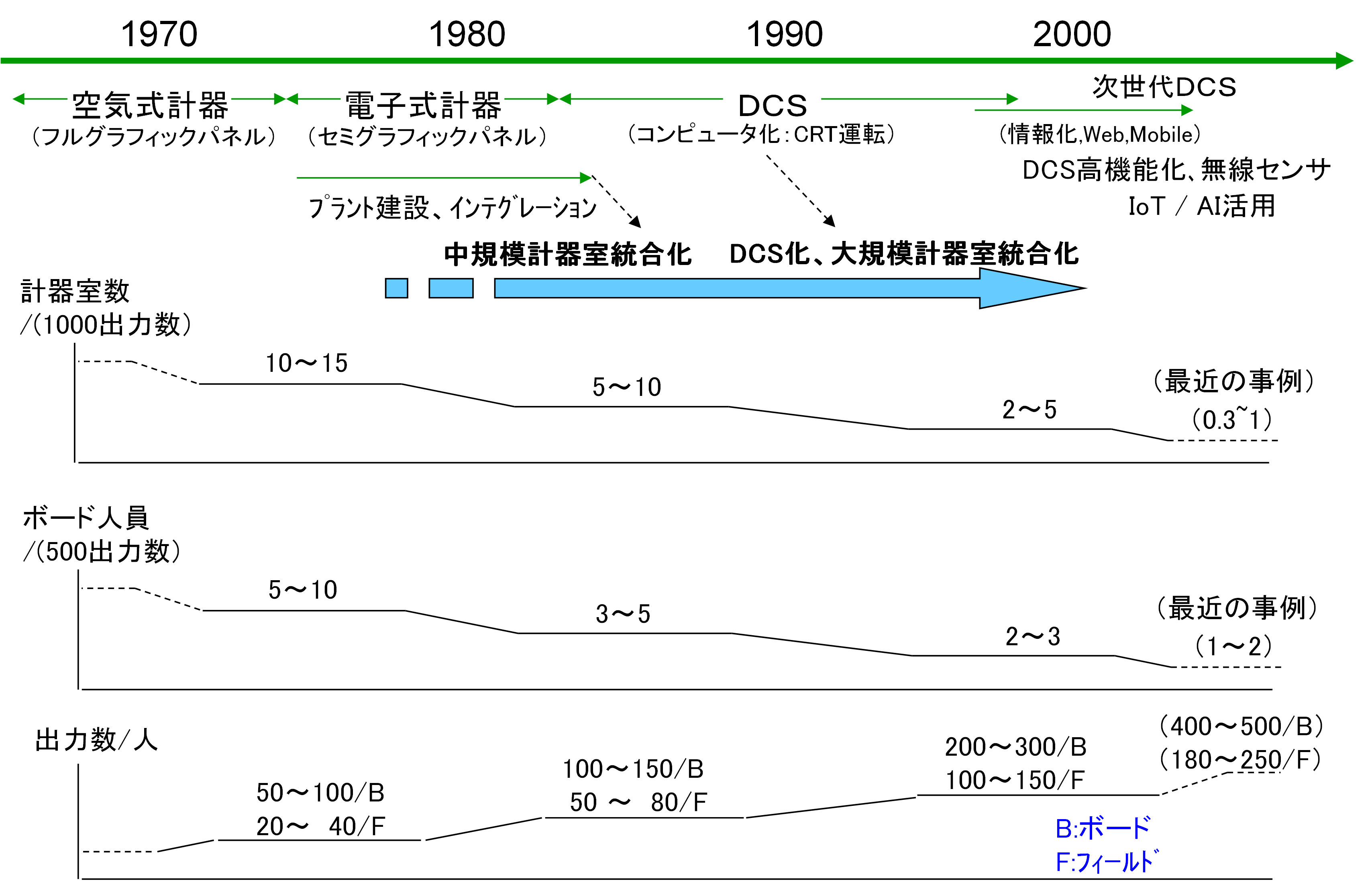
(2)付加価値アップ,ロス削減,省エネルギー
ご承知のように自動化が果たしてきた経営への貢献で,付加価値アップ,品質ロスの削減,省エネルギーがあり,その事例には枚挙にいとまがありません。それがどのくらいのインパクトなのかを石油精製での例で推定してみます。
筆者は海外の東欧諸国の製油所の近代化コンサルティングにおいて品質ロス(性状で規格値との差が生む価格ロス=ギブアウェイ)の実情をデータで算定したことがあります。その結果は原油処理キャパシティ10万バーレル/日当り約30~40億円/年分のロスというものでした。この状態は国内での19870年から80年代にかけての自動化レベルに匹敵すると考えられます。
一方,筆者が近年経験した国内での最近(2010~15年)の近代化FSの中で評価した製油所での品質ロスの規模は10万バーレル/日当り5~7億円/年の品質ロスを評価することができました。これは高度制御を含む自動化で実現できるギリギリのところまでロス改善がなされている状況と言えます。
すなわち,過去から製油所で自動化が果たしてきた経営効果は,品質ロス削減だけで,原油処理キャパシティ10万バーレル/日当り25~30億円/年という効果があって,現在もその効果を維持しつつあると言えます。
(3)安全性,信頼性の向上
もう一つ自動化(計装制御)技術が果たしてきた重要な役割として,プラントの安全性,信頼性の向上があります。
センサの電子化/小型化,自己診断機能等で,プラントの状態がより繊細に見える化されてきました。そのことが,プラントオペレーションでの安全性に大きく貢献してきたことは言うまでもありません。
近年に至り,センサの無線化が進展しつつあり,導入事例が増えてきています。これまで現場指示型であったものが無線センサの出現で計器室での監視を可能にし,今後無線導入は進展していくものと思われます。
以上から計装制御システム技術と経営効果の関係を示すと図2のようになります。経営効果を得るには要素技術を組み合わせてソリューション(たとえば,「プラントの安定度指標とボード人員」等)にすることが求められます。
3.この10年でのプラント自動化の進展は(他産業と比較して)
石油,化学工場での自動化の進展と比較して,他産業の自動化の進展具合はどうかという視点で見てみます。
3.1 この10年での食品,自動車産業での自動化の長足の進歩
他産業の自動化が進んでいる例として食品と自動車関連では,この10年で長足の進歩を遂げてきました。図5には,両産業での工場自動化の動画URLを示しました。
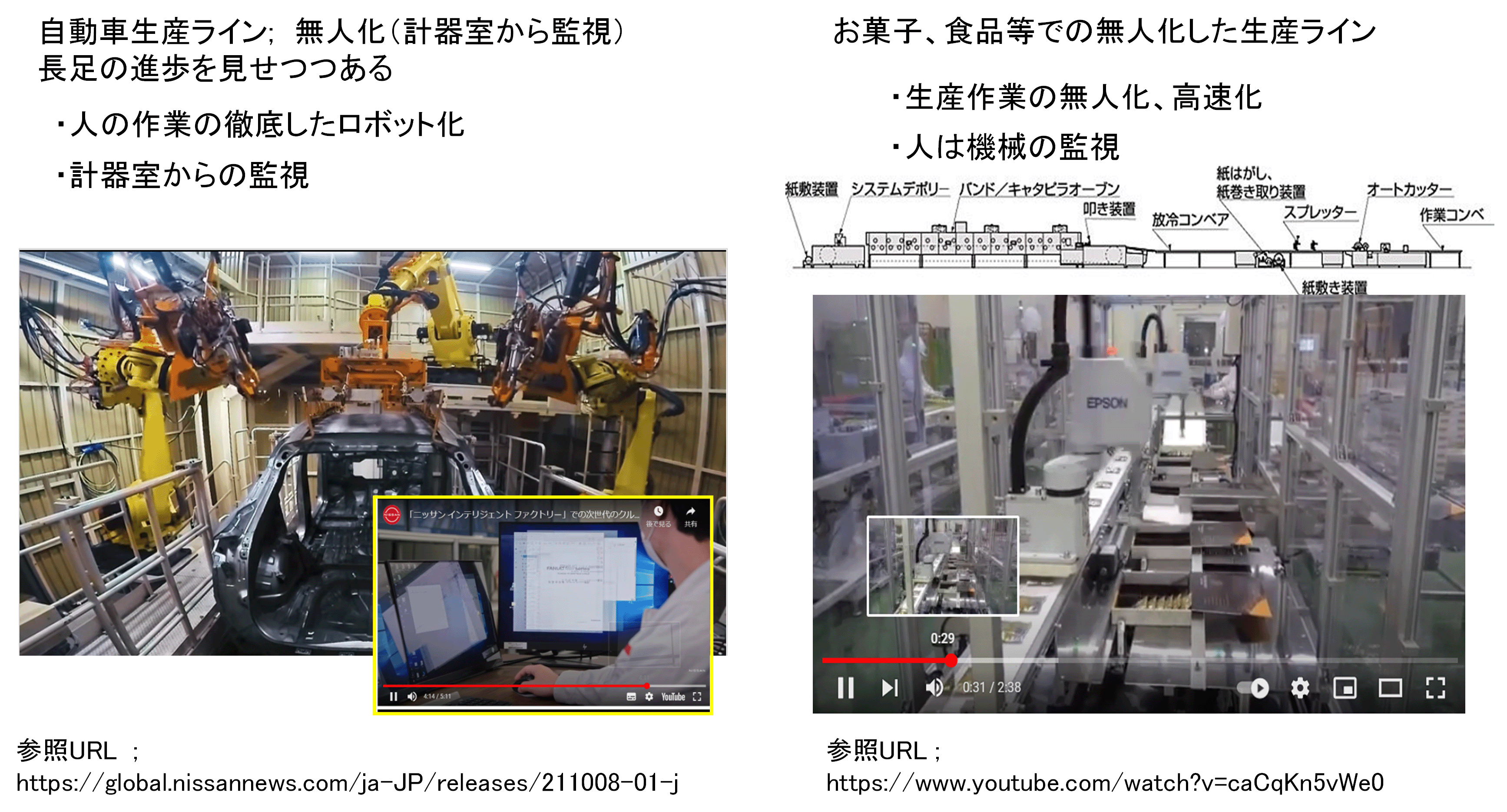
食品産業では工場の作業は全て機械が行い,人はトラブル等機械の状態を監視する形となっています。これらの自動化には多くの工夫と汗が払われたと推察されます。
また,最新の自動車生産工場の完全自動化の例があります。通常はコンベア上を流しながら人が組み立てや溶接といった細かい作業を行う形ですが,この工場では,全てそれらの組み立てや溶接作業をロボットが行います。人は計器室でコンベアに沿って配置されたロボットの監視を遠隔で行う形となっており,機械の状態監視とトラブル対応を担う役割となります。
このように他産業での自動化はこの10年で長足の進歩を遂げつつあることが伺えます。
3.2 この10年での石油,石油化学工場での自動化の進展状況は
一方,プロセス産業でのプラントオペレーションの自動化において,この10年の進展はどうであったかというと,基本的な自動化のレベルはほとんど10年前と変わっていないのが正直なところです。しかし,自動化機器,システムを構成する一つひとつの要素機器では進展がありました。オンサイトシステム(連続プロセス分野)では,DCSの性能アップ,アラームの高度管理システム,緊急シャットダウン用のシステムのリレーからSIS(安全計装システム)への置き換え,高度制御システムの拡充,オンラインプロセスデータ管理システムの普及活用,センサのディジタル化・自己診断機能の高度化,リモートタブレットの導入活用,無線センサ等々があることはご承知の通りです。(図6)
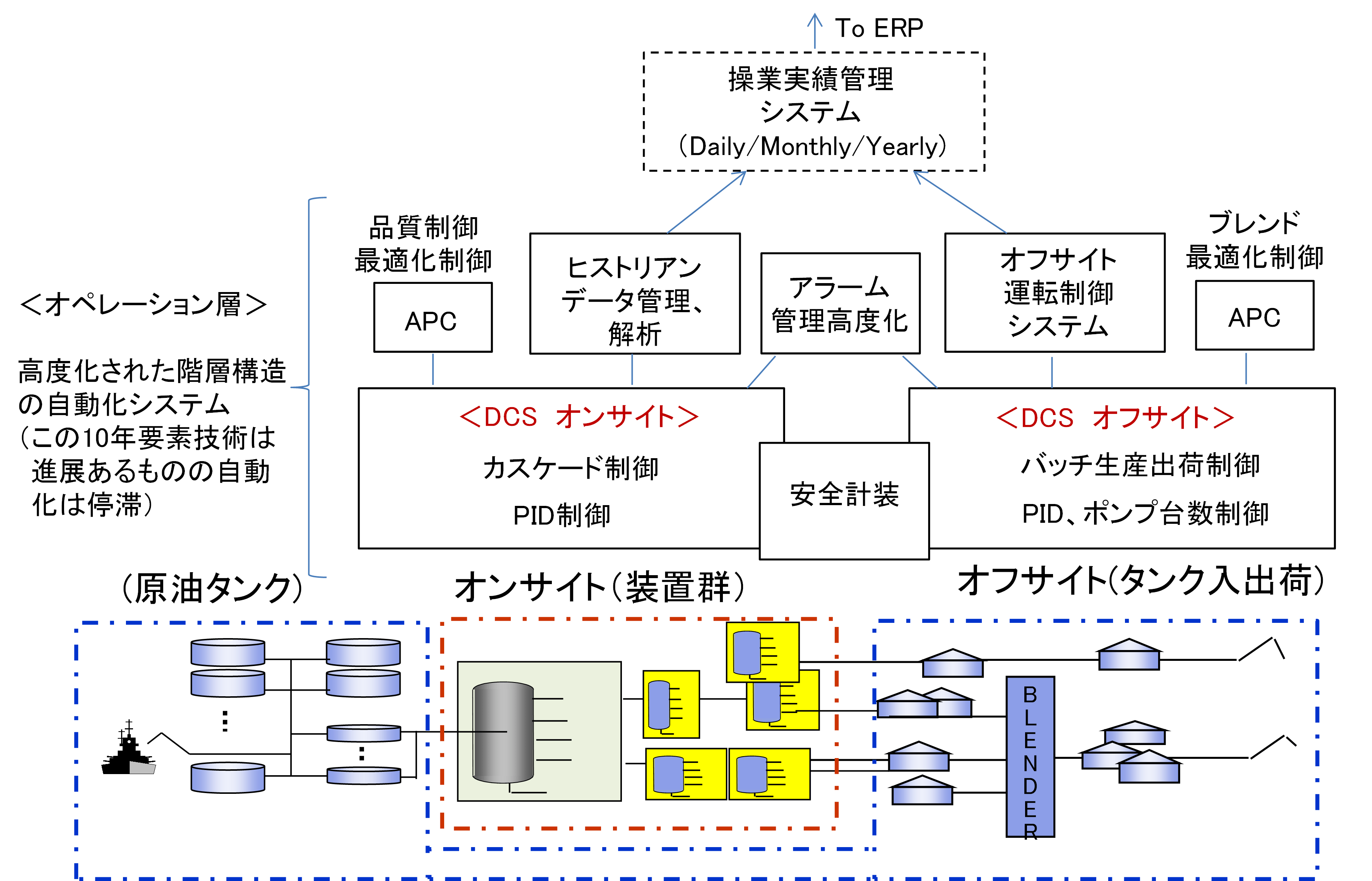
また,オフサイトシステム(タンク,入出荷分野)では,構成要素の高度化の点ではオンサイトに同じで,かつ現場の弁がほとんど遠隔自動化され,計器室からのオペレーションはジョブをキーとしたバッチ作業(タンク切替,シフト,ブレンド,入出荷等)が完全に自動化されている状況と言ってよく,国内のオフサイトは世界に誇れる自動化レベルとなっています。
元々流体を扱う産業ですので10年以上前には既に自動化はほぼ完了の域に達してしているというのが主な理由だと考えられます。
しかし,本当にそうでしょうか。いくつかのことが理由で,次のステップの自動化が進まなかったということはないかもう一度考えてみることで,課題が見つかってきます。
4.この10年の自動化の停滞をブレイクスルーする課題抽出の視点
確かに,オペレーションでの現場操作等ではほとんど自動化がなされており,残っているものは投資対効果が得られないもの,それほど作業に負担がなく,お金をかける必要性が認められず,放置されているもの等があります。これらの課題が存在することを認識しながら次の課題を見つけるといったことを含めて,以下に示す視点は重要と考えます。
すなわち,それほど負担がなく放置された手動操作でも自動化することで,関連分野すなわち上位システムで新たに必要な情報が得られることにより,別の効果が生じるといった視点が重要になります。特にこれまで欠けていると思われる視点としては,他分野との連携(情報連携と自動化)があります。
たとえば,次のような視点があります。
・垂直連携として,操業管理分野からオペレーション指示とオペレーションの実行,およびオペレーション実績の管理
・水平連携として,オンサイト分野とオフサイト分野のオペレーションの自動連携
また,オペレーションの自動化に関する国際規格の動向からも新しいヒントが期待できます。
5.おわりに
今回は連載の第1回として,石油・化学プラントでの自動化の経緯とこの10年での自動化の進展状況について,他産業との違いを含めて解説しました。また,残された自動化の課題について,どのような視点で見直せばいいのかについて解説しました。
本連載は,それらの視点から課題を抽出し,パンデミックにおいても,運転操業継続が可能な状態を作ると同時に,自動化投資に対する見返りとしての経営効果が得られることが狙いです。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
次回は,オンサイトプラントの自動化項目の現状について具体的な項目の整理と考察を行います。そこで,本稿で述べた課題抽出の視点から次の残された自動化の課題の洗い出しを行います。
〈参考文献〉
1)経済産業省特許庁監修:『「プラントの制御・監視技術の技術概要』(2016/7)
2)本田達穂:「残された自動化の課題と今後の対応策」,『2020計装制御技術会議資料』(日本能率協会主催)
3)本田達穂:「連載 少人数化によるプラント操業の革新を目指して(1)」,『計装』