

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第12回(最終回) 操作端 その2:遮断弁
今回は,最終回です。1年間にわたって計装設備に関するいろいろなトラブル事例を紹介してきました。流量計,液面計,圧力計,温度計,分析計,調節弁と一連の計装設備についてトラブル事例を紹介しました。最後は,操作端の一つである遮断弁のトラブル事例について紹介します。
■遮断弁■
遮断弁は,安全設備として使われている重要設備です。普段は使われることのない弁ですが,いざという時には大変重要な計装設備です。必要なときに正常に動かなければ事故につながってしまいます。
作動したときに,きちんと遮断できなければトラブルにつながります。遮断するに当たって,作動時間も重要な要素となることがあります。求められる作動時間内に動いてくれないと事故になることもあるからです。誤作動にも配慮が必要です。遮断弁が突然開いてしまうこともドラブルにつながります。
重要設備であるがゆえに,多くのトラブル事例を学んでおくことが大切です。
【事例①】
緊急遮断弁を作動させる電磁弁の空気配管に漏れが見つかった。修理をするまでに,緊急遮断弁の誤作動防止のため,電磁弁が動かないように固定ピンを電磁弁に取り付けた。ところが,大きな地震が発生したため緊急遮断弁を遠隔操作で閉めようとしたが,電磁弁に固定ピンを挿入していたので緊急遮断弁が閉まらず大事故になった。
【事例②】
冬場プラントの運転が乱れ,緊急遮断弁を作動させプラントを停止しようとした。しかし,外気温が低かったことにより,弁の摺動部(動く部分)の動きが悪かった。規定の時間内に遮断弁が全閉とならず事故になってしまった。温度条件の一番悪い時期に作動テストをして作動時間を検査しておくべきだった。
【事例③】
工事のため遮断弁で高温の液体の縁切りをした。
空気で動く遮断弁だったが,誤作動を防ぐために重要な空気の元弁を閉止することはしていなかった。
工事が終わり緊急遮断弁の下流側で作業を始めたところ,誤って遮断弁の開閉操作ボタンに触れ突然弁が開いて事故になってしまった。
事例①は,2011年の東北大震災の時に起こった球形タンクの爆発事故の要因の一つです。球形タンクの配管には,万一の漏洩事故に備えて緊急遮断弁が取り付けられていました。
地震が起こる前に,図1に示すような緊急遮断弁を動かすための計装空気用電磁弁の空気配管に漏れが見つかりました。修理するまでの間に誤作動が起こることを防ぐため,電磁弁が誤って動かないように動きを固定するピンを取り付けていました。
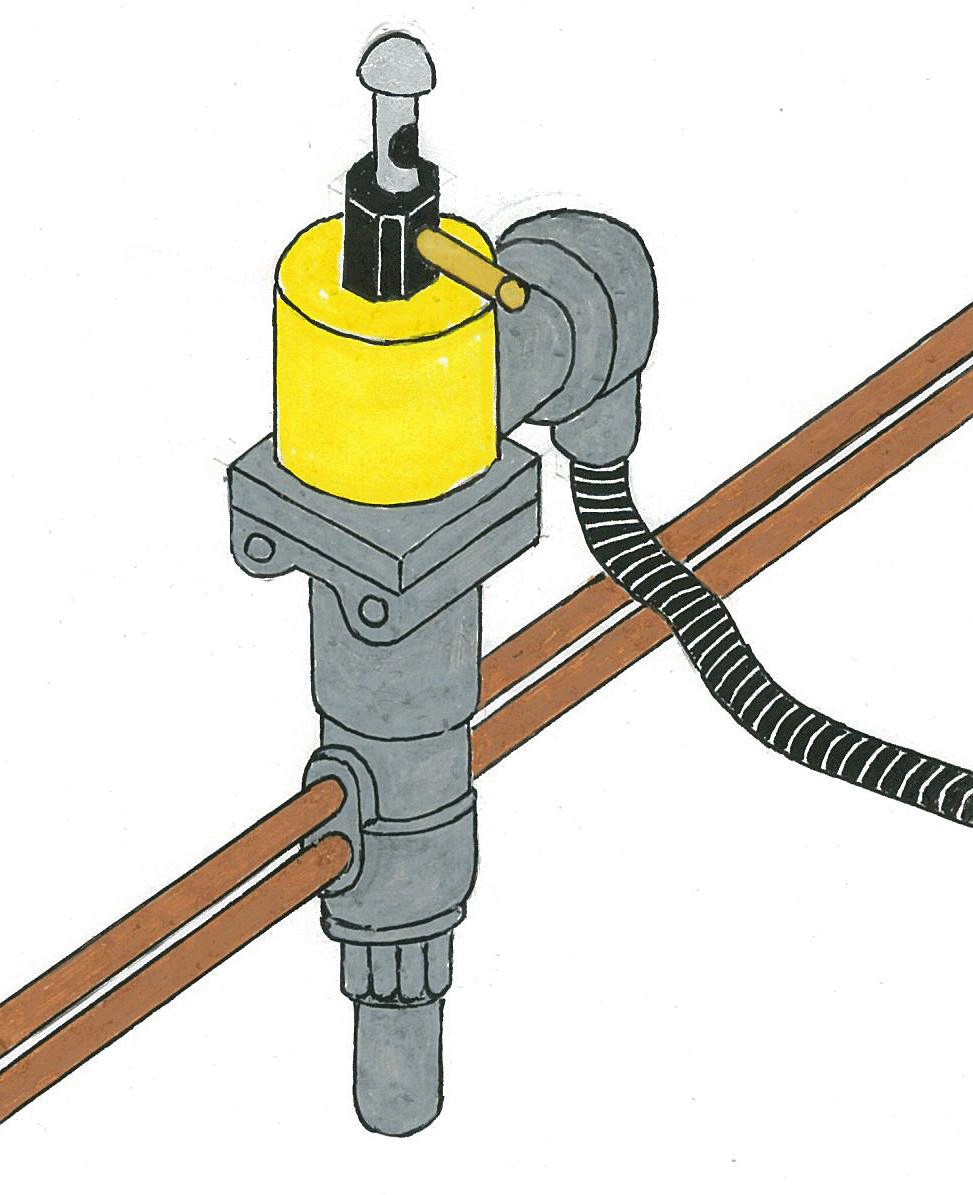
しばらくして,地震が起こり遠隔操作で緊急遮断弁を急いで作動させようとしたものの,電磁弁を固定して動かせないようにしていたことから弁を動かせなかったのです。
重要保安装置の一つである緊急遮断弁は,いついかなる時にも作動しなければなりません。修理の都合とはいえ,緊急遮断弁という安全装置を長期間作動できない状況に放置しておくことは望ましくないのです。重要設備の補修に当たっては,最短の時間で復旧することが求められています。
計装設備で不具合が起こったとき,故障を長期間放置しないことです。最短の期間で故障を修理して正常の状態に戻す必要があります。いついかなる時にも安全装置が作動できるように,計装設備の維持管理を担当する者は努力する必要があります。計装エンジニアは安全に関しても大きな責任を負っているからです。
事例②は,緊急遮断弁の動きが遅かったことによるトラブル事例です。弁類はグランドと呼ばれるシール機構があります。弁は弁棒と呼ばれる軸の部分を上下に動かしたり回転させたりして弁を動かして開閉します。この弁棒が動く箇所の漏れを防ぐのがシール機構と呼ばれる部分です。グランド部と呼ばれることもあります。
シール材を巻き付けて締め付けることにより,液などが外に漏れなくなります¡締め付けることで隙間が減るからです。きつく締め付けては固くなり弁が動かなくなります。緩すぎると液が漏れてきます。微妙な調整が必要な部分です。特に冬場のような寒い時期にはグランド部が固くなることがあるからです。
緊急遮断弁は,開閉する作動時間も管理する必要があります。検査確認の項目から漏らさないで下さい。
事例③は,遮断弁を使って縁切りをしたことによるトラブルです。化学プラントでは,配管の途中で遮断することを縁切りと言います。通常は,誤作動の可能性の少ない手動弁を使って縁切りをします。
しかし,大口径の配管では手動で弁を操作することはかなりの労力を使うため,空気や油の力を使って動かします。弁本体を動かすのに使われる駆動部分に空気などのエネルギーを使うのです。弁の開閉操作は簡単になるのですが,誤って開閉操作をすると簡単に弁が開いてしまうという問題点もあります。
この誤作動によるトラブルを防止するためには,空気や油圧などのエネルギー源を停止しておく必要があります。誤って操作SWなどを動かしても遮断弁が動かないようにするためです。
このトラブルは,図2に示すように遮断弁の周りでチェーンブロックを操作して作業をしていたときにチェーンが遮断弁の操作SWに触れてしまったのです。弁を開にするSWボタンに触れたことにより弁が勝手に開き,高温の液体が周囲に吹き出し多くの人に被害を与えたというトラブルでした。
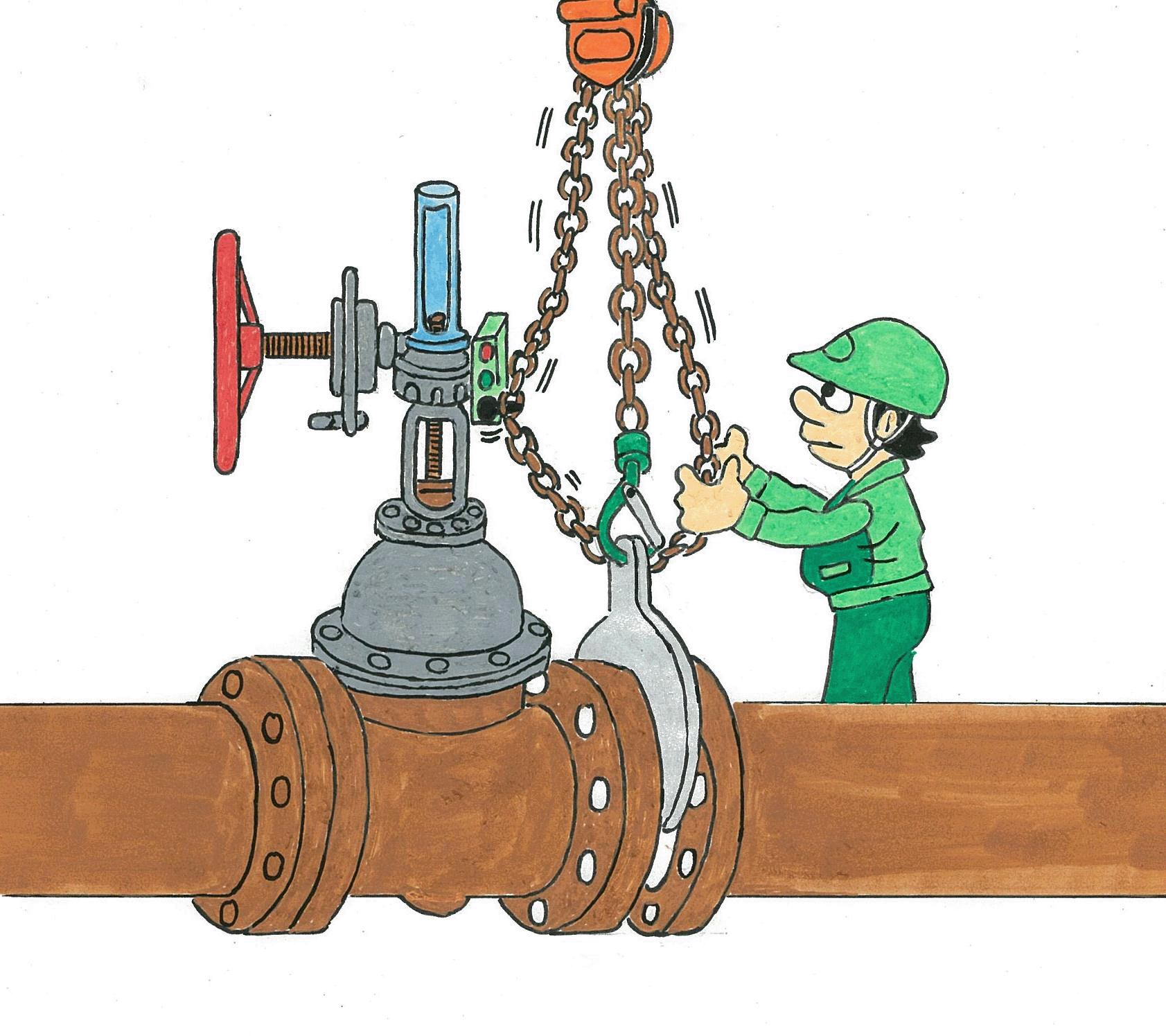
遮断弁は調節弁と同様重要な操作端です。要求どおり確実に動く設計も必要です。また,動いて欲しくないときには誤って動かないような設計上の配慮も必要です。人に優しい設計を心がけ,点検など保全にも手を抜かないでください。
■最後に■
まだまだ伝えたいことはいっぱいあったのですが,あっという間に1年間が過ぎてしまいました。少しでもお役に立てたならば幸いです。今後も折に触れ,計装関係のトラブルなども私のホームページで紹介していきます。1年間ありがとうございました。