

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第11回 操作端 その1:調節弁
検出端で流量,液面,圧力,温度や組成などの成分値をうまく測定できたとしても,その結果を利用して制御に結びつけなければ自動化という重要な課題を達成することは難しい。計測・制御というものは,調節弁などの操作端があって始めて成り立つものなのです。今回は,操作端と呼ばれる調節弁に関するトラブル事例を紹介します。
■調節弁■
調節弁は,制御に使われる計装設備であることから正常に作動しなければすぐに事故に直結してしまう可能性があります。また,配管に直接挿入されているインライン計器であることからトラブルがあれば,流体が漏れて火災や爆発事故になることもあります。
【事例①】
調節弁のポジショナが故障した。制御ができなくなったことにより,運転が乱れた。運転員は,なんとか回復しようと試みたもののうまくいかず爆発事故につながってしまった。
【事例②】
運転中調節弁のポジショナのフィードバックレバーが突然はすれた。プロセス制御ができなくなり事故となってしまった。
【事例③】
調節弁のグランドからわずかに液が漏れているのを,運転員がパトロール中に発見した。グランドの増し締めをすれば,漏れは停まるだろうと安易に思い強く増し締めをした。液が漏れなくなったのを確認して現場を離れたところ,しばらくして運転が乱れ事故になった。安易にきつく増し締めをし,調節弁が正常に動かなくなったことにより起こったトラブルだ。
【事例④】
プロセス変更により,定修中に内弁のサイズ変更をした。定修後に運転を始めたところ,配管が異常振動を始めた。内弁サイズを小さくしたことにより,液がフラッシュ(気化)するようになってしまったことによる異常振動トラブルだ。
事例①は,調節弁のポジショナに関するトラブルです。英語で「位置」という意味を示すのはポジション(POSITION)です。位置を制御する機械という意味から,英語ではポジショナ(POSIONER)という表現が使われます。つまり,ポジショナとは弁の開度を制御するために必要な重要な部品です。
調節弁の開度を正確に制御するにはこのポジショナという設備が必要です。ポジショナに送られてきた開度信号と弁の開度位置を比較してずれがあれば修正する優れものの装置です。
つまり,このポジショナという設備が故障してしまうと調節弁の開度を制御する機能が全て失われてしまうのです。制御そのものができなくなってしまいます。
ポジショナは空気で駆動する空気式と電気信号で動く電気式があります。ポジショナの故障原因は,空気式ポジショナであれば,空気信号が流れる部分でゴミなどの詰まりでトラブルを起こすことがあります。空気を使って微妙に制御する装置であることから,わずかなゴミの付着や詰まりでもトラブルを起こします。ゴミを取り除くフィルタ類の定期的な清掃交換が必要です。
電気式ポジショナは,フィードバックコイルと呼ばれる電磁石が組み込まれています。細い電線を巻いたコイル状の部品です。電磁石の磁力を使って弁の開度位置を制御するためこのフィードバックコイルが壊れると制御不能となります。高温環境や雰囲気の悪いところで弁を長期間使用していると,コイルの電線が切れて故障することがあります。
ポジショナという部品は,定期的な分解点検と清掃が不可欠です。しっかりと点検計画を立ててトラブルの防止を図って下さい。
事例②はポジショナと弁本体を接続しているフィードバックレバーと呼ばれる部品のトラブルです。ポジショナと弁をつないでいるフィードバックレバーが外れてしまえば,弁の開度状況はポジショナへ正常に伝達されなくなってしまいます。事例①と同様に全く弁の制御がきかなくなってしまいます。
トラブルの原因は,フィードバックレバーと弁本体を接続するナットの「ゆるみ」です。最初から締め付けが緩かったり,弁の振動で緩んでしまうことが原因です。
ポジショナそのものの点検と同様に,このフィードバックレバーを接続するナットのゆるみがないかの点検を怠らないようにしてください。
事例③は,図1に示すような調節弁のグランドの締め付けすぎによるトラブル事例です。調節弁はステムと呼ばれる弁棒が上下に動いて弁の開閉を行っています。ステムが円滑に動くことが必要ですが,動くときにガスや液がステムの周りから漏れてしまっては困るのでグランドパッキンと呼ばれるシール材が用いられています。
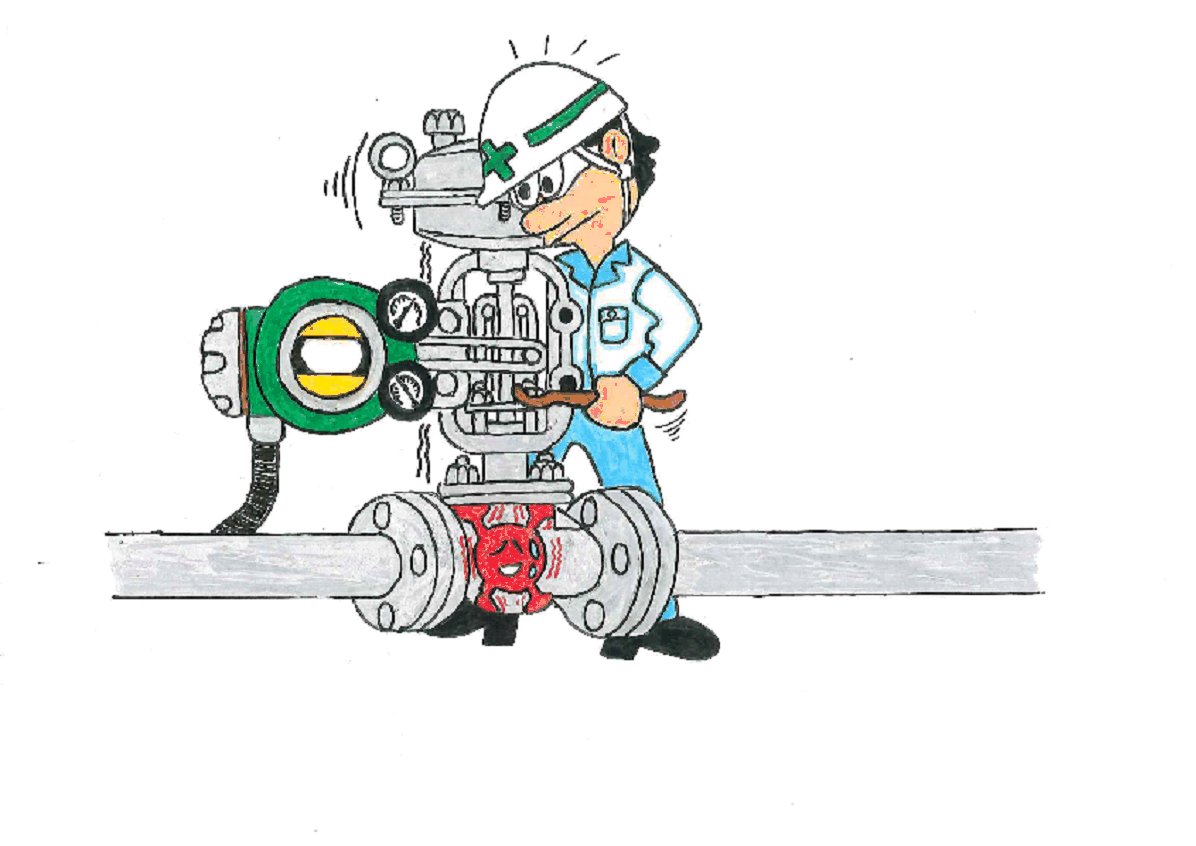
グランドパッキンは,一般的にボルトで締め付けることにより隙間を減らし,漏れにくくする構造になっています。しかし,締め付けすぎるとステムと呼ばれる弁棒が強く締め付けられて動きにくくなってしまうという問題点もあります。
ほどほどに,ボルトを増し締めする必要があるのです。このように,安易にグランドパッキンを強く締め付けすぎたことで過去に多くのトラブルが起こっています。
運転中に,グランドパッキン部の増し締めをしたらバルブを少し動かして作動がスムーズであるか必ず確認してください。漏れが停まって一安心では困ります。グランドを締め付ければ,動きが悪くなるはずです。増し締めをしたら必ず調節弁の動きまで確認してください。
事例④は内弁変更時のトラブルです。調節弁は,内弁で量を絞り込むことから必ず差圧が発生します。
流体によっては,調節弁内で圧力が急激に下がることにより液体の一部が気化する現象が起きます。液体が気化すると,気体の体積は数百倍にも増えるので図2に示すように調節弁内で振動が発生したり,異常音を発生することがあります。流体の温度が沸点に近い場合にはよく起こる現象です。
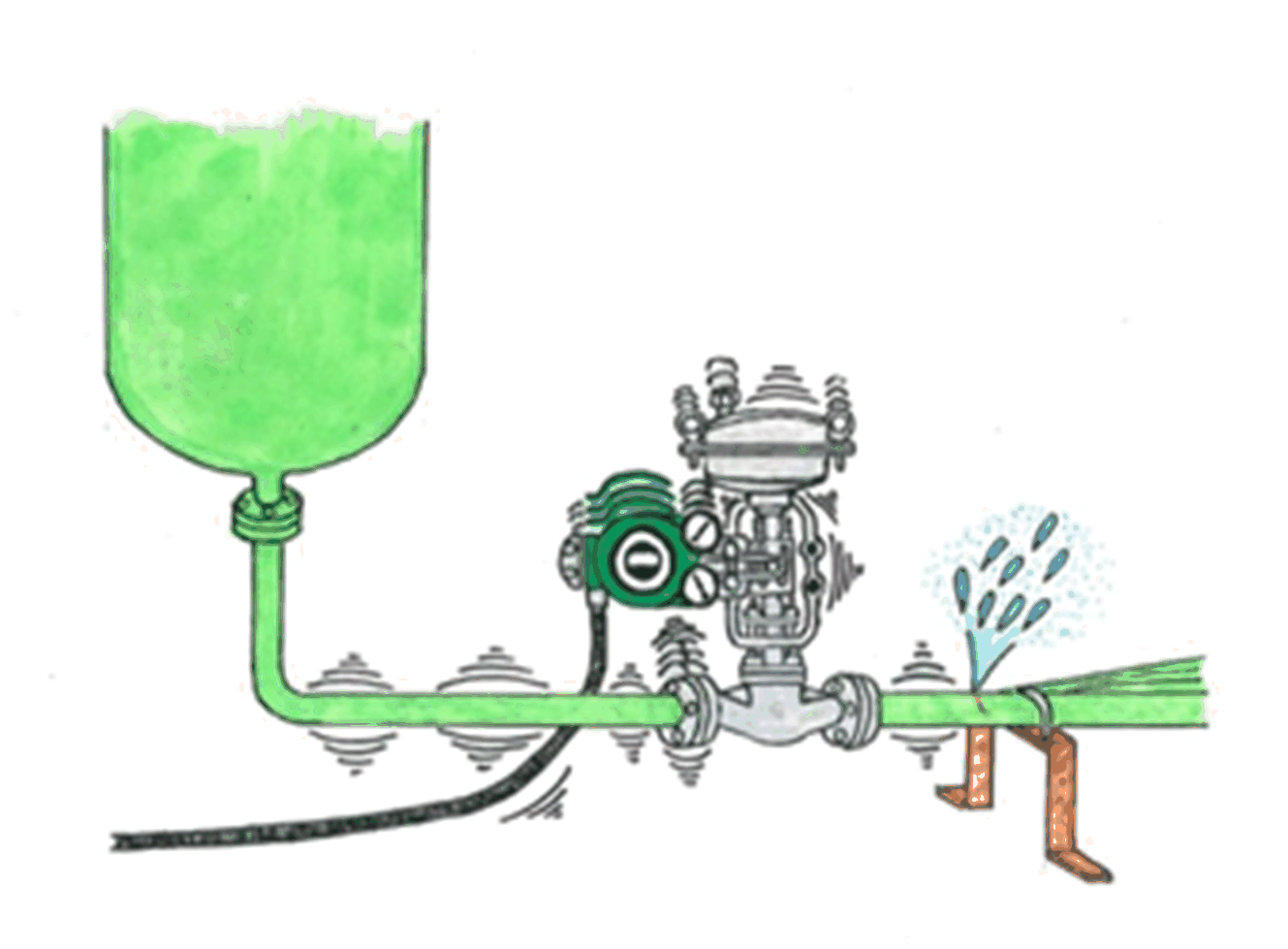
計装エンジニアは,単に計装知識のみを身につけていれば良いわけではありません。物質を取り扱うからには,物理化学的現象に関する知識も会得しておく必要があります。また,金属材料など機械工学的な知識も必要です。計装エンジニアには幅広い知識が求められているのです。