

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第 10回 分析計 その 2 : 排ガス・排水分析計,ガスクロマトグラフ
前回に引き続き分析計のトラブル事例を紹介します。
■排ガス・排水分析計■
【事例①】
ボイラの煙道排ガス測定にNOx,SOx分析計が設置されていた。赤外線式でコンクリート製分析室の中に分析計を設置していた。計器校正のため標準ガスボンベを使って校正作業を行っていたところ作業員が建屋の中で気分が悪くなった。
【事例②】
化学プラントの燃焼排ガスを処理するダクトにジルコニア式酸素分析計が設置されていた。通常は,排ガスの成分は窒素と微量の酸素だった。ある時,化学プラントの運転が乱れた時,酸素分析計を設置していた排ガスダクトが爆発した。
【事例③】
アルミニュームの入った工場排水を処理する廃液中和槽にpH計を設置して管理していた。あるとき大量の廃液が流れ込み,廃液中和能力を超えてしまった。長期間 pH計を点検していなかったため,pH値は正常な指示を出していなかった。しばらくして,廃液中和槽で爆発が起こった。
事例①は,計器の指示値を標準ガスで校正している時に起こったトラブルです。NOxやSOxは人間に健康被害を及ぼします。冬の時期の校正作業だったため,作業員は分析室の扉を閉めた状態で,しかも標準ガスを室内において校正作業を進めていました。
分析室には換気扇も用意されていましたが,風が入ると寒いので換気扇は停止させていました。
閉め切った分析室内で,毒性のあるガスを分析計に配管接続するたびに室内にガスが漏れていたのです。何度も濃度の違うボンベを切り替えたことにより,室内は汚染され作業員は気分が悪くなってしまったのです。
化学物質は毒性のあるものもあります。万一のことを考え換気は絶対止めてはいけません。標準ガスボンベも屋外に置いて配管で分析計に引き込む方式を採用してください。たかが標準ガスボンベと思わないでください。たかが換気と思わないでください。排ガス測定分析計の点検時は毒性に注意してください。
事例②は,プラントの運転が乱れた時に排ガス成分の組成が変わり,多量の可燃性ガスが含まれ図1のような爆発事故が起こってしまったのです。ジルコニア式酸素分析計は高温の排ガスを測定するのに適した分析計です。煙道に直接挿入できることからサンプリングシステムも不要で,経済性の面でも有利です。分析計のセンサ部には酸素濃度を検出するための高温の電気炉のような検出器が使われています。
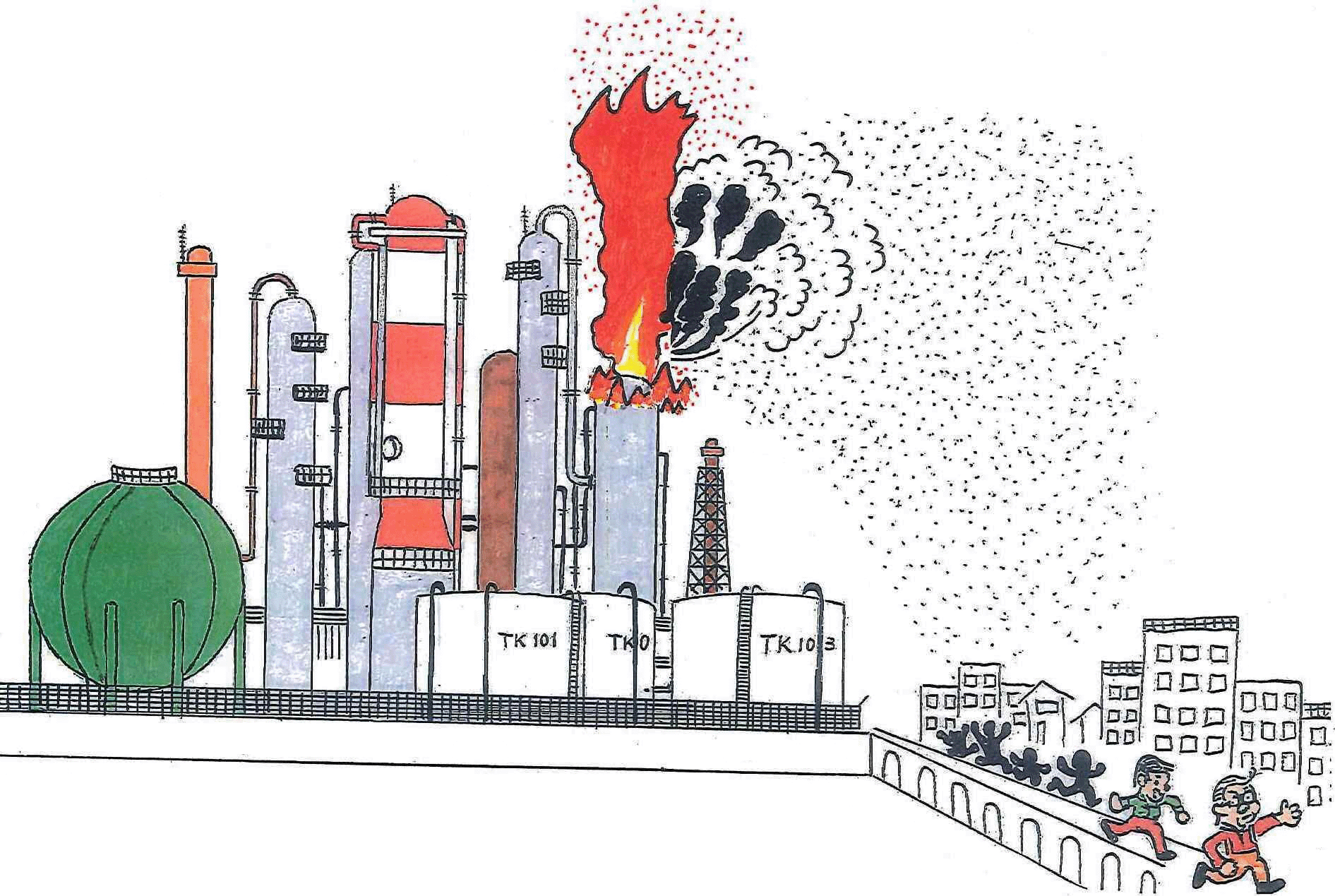
このため,可燃性のガスが含まれている排ガスでは燃焼着火するので使用には適しません。
今回の計器選定に当たっては,通常時は,可燃性のガスは含まれていないことから計装エンジニアはジルコニア式酸素計を選定してしまいました。しかし,異常時には可燃性ガスが混入したわけですからこの選定は間違っていたのです。事故が起きた後,異常時でも安全な磁気式酸素分析計に変更されています。
計器の選定に当たっては,通常時のプロセス条件だけではなく,異常時などの組成なども考慮して安全な計器を選定することが大切です。そのためには,計装エンジニアは単に計器の知識を持っているだけではなく,製造プロセスに関する知識を常に持つようにしてください。
事例③は,廃液の中和処理槽で起きたトラブルです。
廃液は一般的に,中和の程度を見るためにpH計を設置して管理します。このトラブル事例では,pH計を長期間点検していなかったため,pH値が強酸領域に入っていたのに指示値はpH7付近を示していました。
廃液にはアルミニウムが含まれていました。アルミニウムは金属の一種です。酸性物質は,金属と接触すると水素を発生する性質があります。硫酸タンクなどでは,水素が発生しているのに気づかずにタンクの溶接補修をしていて爆発する事故事例が多く起きています。
この事故も,アルミニウムという金属と酸との接触により水素が発生したことにより起きた事故です。
中和作業では,多くの現場でこのように水素が発生していることもあります。pH計の故障で水素が発生すればこのような事故が起きてしまいます。
設計に当たっては,分析計も故障することもあるという前提で安全対策を行ってください。水素が発生する恐れがあるなら,ガス検知機器を併設してください。万が一,pH計が故障することがあっても,構造原理の異なる計器を設置していれば同時に故障する確率は極端に減ります。
分析計は計装計器の中でも比較的高価です。他の安価な計器を併用して安全性の確保を図ってください。
■ガスクロマトグラフ分析計■
化学プラントの中では,比較的高価な分析計です。
単一成分だけではなく多成分を同時に分析できる利点があります。カラムと呼ばれる細い管の中に,測定成分を流します。物質ごとに異なる時間で出口に到達する性質を利用して,成分を分析して濃度も計測することができます。
成分と濃度があらかじめわかっている,標準ガスという物質をガスクロマトグラフに流します。図2の上部で表されるように,A,Bというような成分ピークが表れたとします。
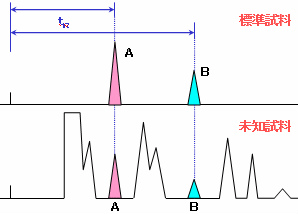
次に未知の成分を流すと,図2の下部に示されるようなA,Bと同じ時間帯にピークが現れます。三角形のようなピークの面積は濃度と相関があり,面積値を割り出すことによりその物質の濃度までわかるという優れものです。
【事例①】
長期間,標準ガスを使ってガスクロマトグラフの校正を行っていなかった。あるとき,スタートアップ後,ある成分の指示値が少なめに出るので研究分析部門にサンプリングしてもらい成分の分析を依頼した。手分析の結果と,ガスクロマトグラフ分析計の指示値を比較したら誤差が生じていることがわかった。
長期間標準ガスで校正していなかったことにより,リテンションタイムと呼ばれる成分が現れる時間がずれていることにより起こったトラブルです。このため,指定されていた測定時間帯ではピークの全体を捉えることができず,ピークの一部分しか検出することができませんでした。この結果,成分濃度を表すピーク面積が減少したことにより低めの指示を出していたのです。
ガスクロマトグラフは,時間が経つとカラムト呼ばれる細い管の中の充填物が劣化してきます。検出時間も変化します。定期的に,標準ガスを使って校正してください。
〈参考文献〉
1)出典引用:https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/
internet-seminar/hplc/hplc5.html