

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第8回 温度計
化学プラントには多くの温度計が使われています。
流量計や液面計のように多くの種類があるわけではありませんが,温度計のトラブル事例を紹介します。
■温度検出端■
温度計の検出端だけを使って温度を測ることは可能です。しかし,化学プラントなどでは温度や圧力も高かったり,腐食性のある物質も取り扱うため保護管というもので温度計の検出端を保護する方式を採用しています。この保護管にまつわるトラブル事例も過去多く起きているので紹介します。
【事例①】
温度計の指示が不良になり,温度計の検出端のみを取り外す作業をしていた。ネジ込み式保護管であったため,パイプレンチを使って温度計の検出端を外していた。誤って,保護管まで一緒に外れてしまい大量の液が噴き出した。
【事例②】
反応器の温度調節制御用に温度計が取り付けられていた。温度計の保護管が短く,反応器内の温度を正確に測ることができず異常反応を起こし爆発した。
【事例③】
高温高圧の蒸気を測定する温度計保護管が異常振動で破損した。
温度計の保護管の接続方式には,「溶接型」,「フランジ型」,「ネジ込み型」の3種類が使われています。
事例①はネジ接続型の保護管で起きたトラブル事例です。図1に示すように,ドラムに取り付けられている温度計が故障したので温度計の検出端のみを取り外そうとしていました。パイプレンチという工具を使って検出端を回していたつもりが,温度計の保護管まで一緒に外れてしまい液が噴き出したという事故事例です。
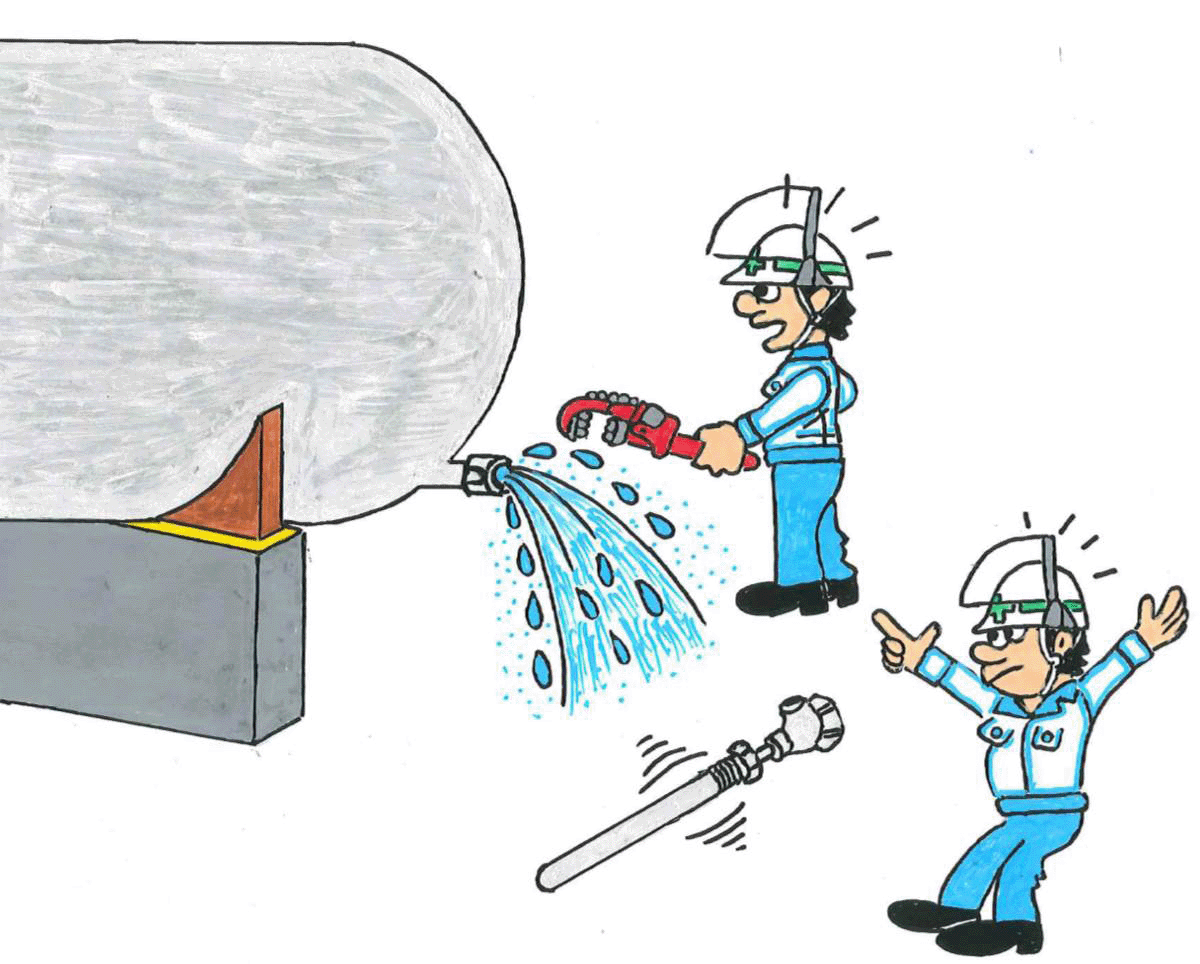
保護管は,ネジ込み形式であったため,ネジが共回りして保護管が外れてしまったのです。ドラムの中に入っていた液体は,有毒な物質だったことから,噴き出した液体で作業員が中毒になってしまいました。
このように保護管が外れてしまえば,流出する液を止めるのは容易なことではありません。このトラブル事例では,防毒マスクを被った別の運転員が事故現場に近づき木栓を流出部に打ち込んで漏洩を止めことなきを得たということです。
ネジ込み式の保護管を誤って外すトラブルは,繰り返し起こっています。安易にネジ込み式保護管を使うとこのような事故が起こります。危険物や毒性物質など,漏れたら困る流体を測定する場合,ネジ込み式は使わず溶接型など安全な形式の保護管を使用して下さい。
事例②は,温度計の保護管の長さに関係するトラブル事例です。写真1に示すように反応器やドラムなどの容器内温度を正確に測定するには,保護管は適当な長さのものを選定して内部の温度を正確に測る必要があります。短すぎると,容器の外からの外気温などの影響を受けてしまうからです。このトラブル事例では,保護管長さは40cmの長さが必要なのにその半分の20cmだったため反応器内の温度を正確に測れなかったのです。保護管の長さを決めるに当たってはプロセスエンジニアとよく相談して決めて下さい。

事例③は保護管が振動で破損しでしまった事例です。配管などに保護管を挿入すれば流れに乱れを生じます。その結果,保護管の周りには渦が発生します。
繰り返して発生する渦により保護管は振動を続け最後は破断してしまうのです。
流れのある流体で発生する現象で,「カルマン渦」と呼ばれます。渦は一定の周波数で発生します。保護管の長さによっては渦の発生する振動で共振が起こることがあります。共振とは,揺れが激しくなる現象です。
温度計の保護管長さを決めるときには必ずカルマン渦の影響を検討して下さい。
■温度調節・変換部■
【事例①】
研究所の加熱実験用設備で温度計が故障した。温度調節計の電源供給部が故障して,加熱ヒータ出力が100%振り切れ状態になって異常に加熱されてしまった。過熱防止用の安全装置も作動しなかったため小火になった。
【事例②】
反応器の温度調節制御用に温度計が取り付けられていた。あるとき検出端の熱電対が断線し温度の指示がゼロとなり,温度調節計の出力は 100%に振り切れた。このため,加熱用蒸気の調節弁は全開となり温度が異常上昇した。反応器は異常反応を始めて爆発した。
上記の事例①は老朽化が原因です。化学プラントなどでは,事故や災害を防止するために計装設備も定期的に点検が行われます。しかし,研究設備などでは保全コストを勘案して壊れたら修理するという考え方が一般的です。予防保全という考え方は取り入れられていないというのが現実ではないでしょうか。
この実験設備は,購入してから20年を経過していました。その間,一度も温度計の点検は行われていませんでした。そのため,電源部に使われている電解コンデンサが劣化してこのような事故になってしまったのです。過熱防止用の安全装置で事故は防げるはずでした。しかし,安全装置を20年も点検していなかったため故障していて正常に作動しなかったのです。
研究所を担当される計装エンジニアは,計器点検の重要性を訴え続けて下さい。事故が起きてからでは遅いのです。
事例②は,検出端の故障で温度調節計からの出力信号が振り切れたことにより起こった事故です。検出端である熱電対や測温抵抗体の断線は起こることがあります。現場にある配線接続箱で接触不良が起こり正しい指示を出せないこともあります。検出端が断線したり,接触不良を起こせば指示はゼロとなるか低めになります。
このような温度計検出端や配線系統でトラブルが起きた時に安全を確保する必要があります。入力部の異常を検出すると出力信号を安全方向に振り切らせるのです。「バーンアウト」という概念が温度計にはあります。入力信号に異常があれば,出力信号を安全方向に変化させるのです。「+」方向であれば,バーンアップ。「-」方向であればバーンダウンと呼んでいます。この事故事例では,バーンアウトという安全対策を怠ったことにより起きています。
重要な温度計には。「バーンアウト」機能を使って安全を確保して下さい。