

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第7回 圧力計 その2 :禁油・禁水処理と圧力制御
化学プラントには多くの圧力計が使われています。
前回は,ブルドン管圧力などを中心にトラブル事例を紹介しました。今回は引き続き,圧力計に関わるトラブル事例を紹介します。
■禁油・禁水処理■
化学物質には「混触危険性」という注意すべき危険性があります。混ぜると反応を始めたり,着火するなど危険なことが起こるからです。計器に油や水などが付着していれば,このような現象が起こることがあります。油や水を十分取り除いて,トラブルを防止する処理をすることを「禁油・禁水処理」と言います。
この,禁油や禁水処理を理解していなかったり,処理を怠ったことによりトラブルが起きているので紹介しておきます。
【事例①】
酸素ガス容器に充填中,充填圧力をみるために,圧力計のバルブを開いたところ,圧力計取付口が溶融し,火が噴き出し立合者2名が火傷を負った。圧力計に付着していた油が原因で激しく燃焼した。
【事例②】
塩素を取り扱う配管の圧力を測定する計器の導圧管が腐食して穴が開いた。導圧配管内に残っていた水が塩素と反応して塩酸ができたため急速に腐食が進んだのが原因だった。
事例①は,計器の中に残っていた油と酸素が反応したトラブルです。酸素は,油と激しく反応する物質です。計器の点検や校正時には,油を使うのが一般的です。しかし,禁油指定された計器であれば,油を使わない方法で計器の校正をします。ところが,禁油仕様ということを伝えずに点検依頼をしたために,油を使いその後油の除去も行いませんでした。その結果,このようなトラブルが起こってしまいました。
禁油や禁水仕様の計器は,計器の見やすい箇所に「禁油」,「禁水」という文字の入った注意表示を取り付けてこの種のトラブルを防止して下さい。
事例②は,禁水が必要なのに計器を取り外して点検した際に,安易に水洗して水分を完全に除去せず取り付けたことにより起こったトラブルです。塩素は水分があると塩酸という酸を生成します。酸は,金属を犯すため腐食の原因となります。
水分を嫌う箇所では,計器の取り外し点検をしたときには水分を完全に乾燥させておく必要があります。安易に水洗してしまうとこのようなトラブルを起こします。
禁油計器と同様に,計器には「禁水」の表示をしておくことがトラブル防止の基本です。
■圧力制御■
タンクやドラムなどの容器の圧力管理に圧力制御が行われています。しかし,圧力制御がうまくいかなければ容器の破壊という形で事故になってしまいます。検出端の故障や圧力調節弁という操作端の故障が原因です。圧力の制御に失敗して起こったトラブル事例を紹介します。
【事例①】
可燃物を貯蔵したタンクに設置されていた窒素シール用圧力調節計が正常に機能しなかった。そのため,タンクに供給される窒素が過剰に供給されタンクの圧力が異常に高くなってしまった。本来なら,圧力を大気に逃がすブリーザ(放出)弁が作動して圧力は異常上昇しないはずなのにこの安全装置も作動せずタンクが破裂した。
【事例②】
運転中に8Bの圧力調節弁に大きな振動が発生し,調節弁まわりの圧力計取出部と安全弁の取出部の配管が折れて液が吹き出した。振動対策でサポートは強化したものの,しばらくして再び激しい振動で調節弁上流側の熱交換器フランジ部から突然液が吹き出した。
事例①は,図1に示すようなタンクの圧力調節計が故障してタンクが破裂したトラブルです。可燃物を貯蔵するコーンルーフタンクなどでは,爆発を防止するためタンク内に窒素を封入して爆発性の混合気を作らないようにしています。タンクは圧力を加え過ぎると破壊するので,数十mmH2Oという微圧で圧力制御が行われています。
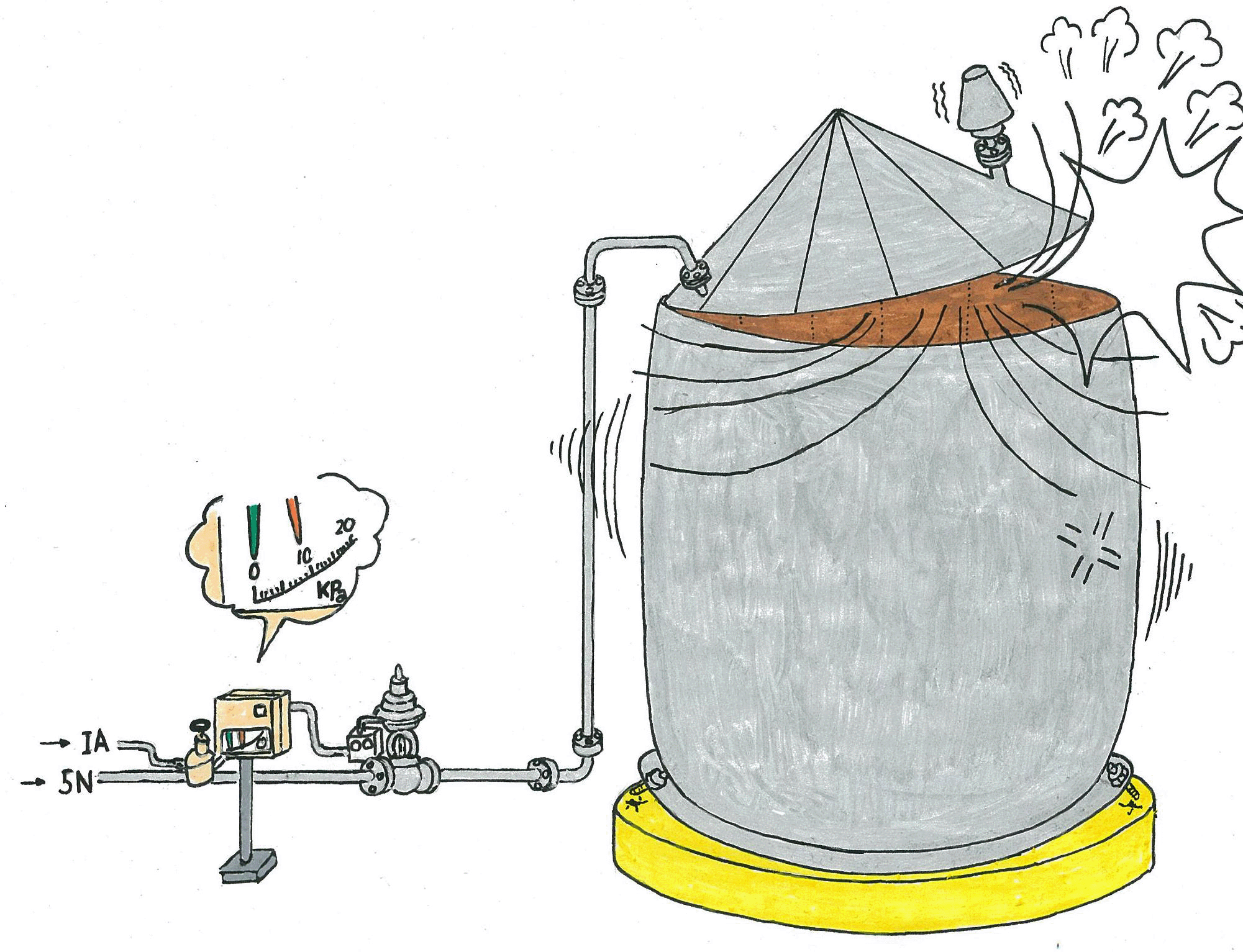
故障の発端となったのは,計装空気の供給に使われていた減圧弁です。長いこと点検も行われていなかったため,減圧弁フィルタ容器の腐食が進んでいました。あるとき,フィルタ容器が腐食で穴が開き正常な圧力の計装空気を供給できなくなってしまったのです。このため,圧力制御が正常に機能せず,タンクに送り込まれる窒素が過剰になり,タンク内の圧力が異常に上昇して破裂してしまったのです。
圧力調節計本体は定期的に点検が行われてはいたものの,補機である減圧弁は全く点検が行われていなかったことからこのトラブルが起きてしましまったのです。
計器類は本体の点検だけではなく,付属する計器補機も確認を行う必要があります。電気式計器なども,計器本体はしっかりと点検していたものの,電源を供給する電源装置の点検を長期間行ってなかったことからトラブルを起こしている事例もあります。
計装計器は,計器本体だけではなく空気や電気を供給する補機を含めしっかりと定期点検を行って下さい。
事例②は,圧力制御で起こった図2に示すような圧力調節弁の振動によるトラブルです。振動を起こした調節弁は,弁入口と出口の差圧が約2MPaもあり,出口側はフラッシュ(部分的に気化)して気液混層となる使われ方をしていました。調節弁サイズは8Bであったものの,調節弁の後方は配管口径が太くなっており,時々激しいフラッシュ現象を起こし,配管が激しく振動したのが原因でした。
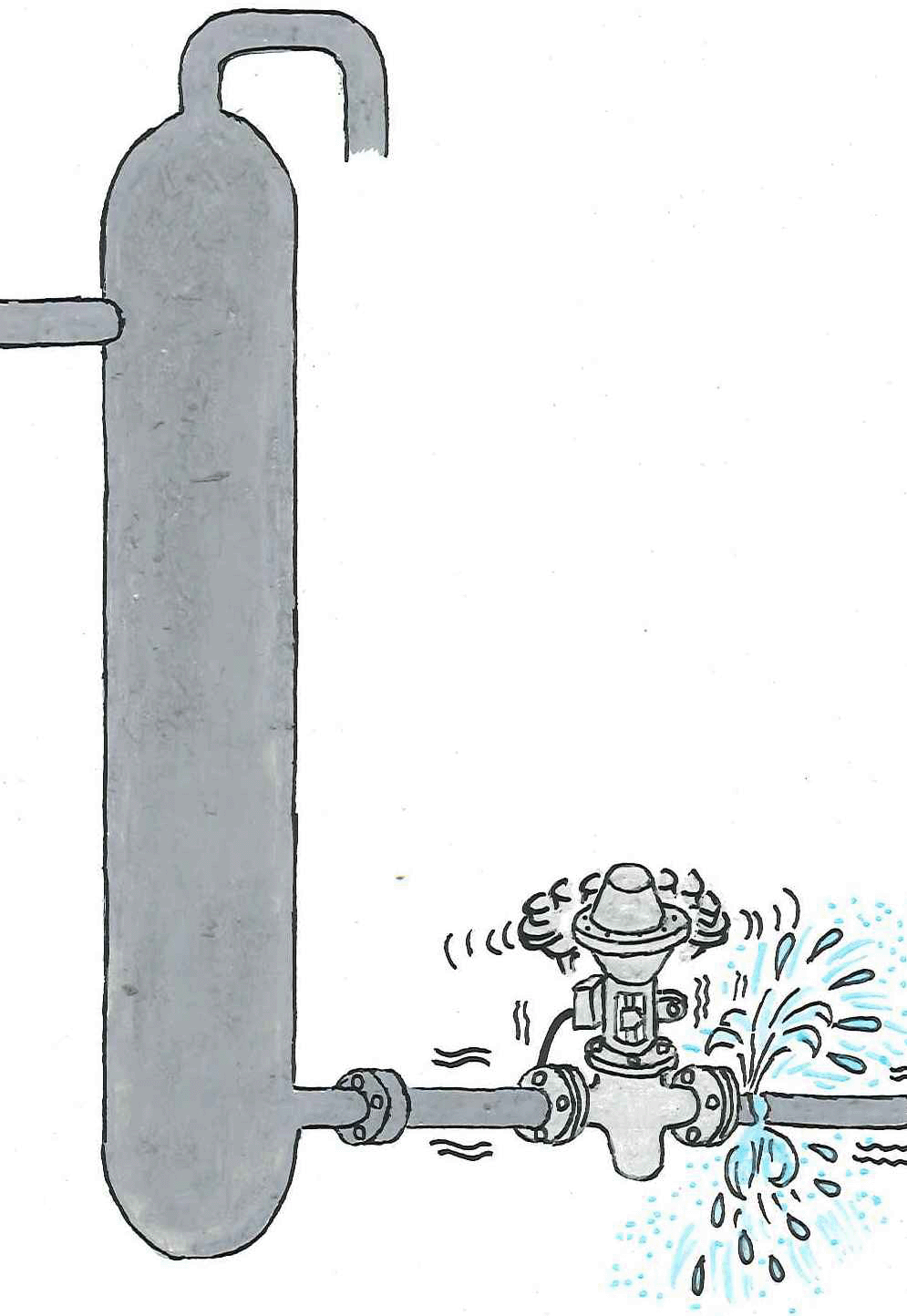
このように調節弁で急減圧をさせると,流体の一部が気化して急激にガスが増えることにより激しい振動が起こることがあります。
このトラブル事例では,配管にサポートを取り付け振動対策を施したものの再び上流側のフランジが振動で緩み漏洩トラブルを起こしたものです。 振動が起こった場合,無理にサポートで固定しても本質的に振動は収まることはありません。2段階で圧力を下げていくか,アングル弁などを選定して振動の起きにくい環境を作り出すことが必要です。