

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第6回 圧力計 その 1:ブルドン管式,発信器
化学プラントには,図1に示すように多くの場所に圧力計が使われています。圧力に関するトラブル事例を紹介していきます。
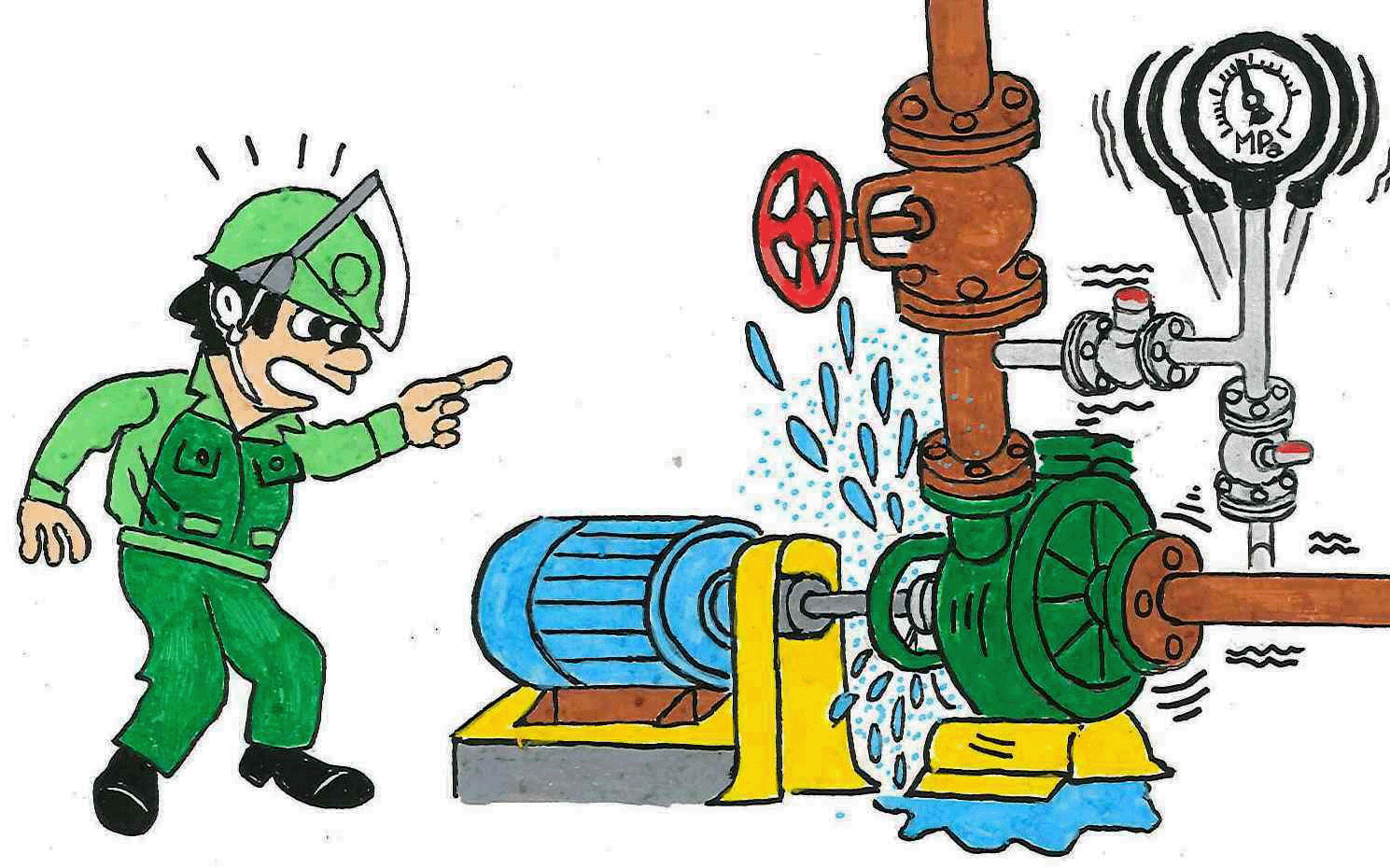
■ブルドン管式圧力計■
フランス人のブルドンという人が考え出した原理を利用したのがブルドン管式圧力計です。構造が簡単で電気や空気などのエネルギー源を必要としない自力式と呼ばれる計器です。つまり,流体などの圧力そのもののエネルギーを使って自ら指示を出す優れた計器なのです。さらに構造が簡単ゆえに,価格も安いことで多くの現場で使われています。
【事例①】
ポンプの吐出圧力を測るブルドン管圧力計を点検のため取り外すことになった。パイプレンチを使って外していたところ,ポンプからの取り出し配管部の根元が折れ大量の可燃物が噴き出した。しばらくして,漏れた可燃物で静電気が発生して着火し化学プラントが爆発を起こした。
【事例②】
ブルドン管圧力計が設置されていた場所のすぐ近くに,昇降用の猿はしごが設置されていた。工事のため作業員がはしごを下りていたところ,誤って圧力計に作業靴が当たり,衝撃でブルドン管圧力計の塩化ビニル配管が折れ大量の薬液が噴き出した。
【事例③】
ポンプのストレーナが詰まったため清掃することになった。脱液をしてブルドン管圧力計の指示を確認したところゼロを示していた。ストレーナの蓋を開放し始めたところ急に液が噴き出してきた。
事例①は,ブルドン管圧力計の取り外し時の事故です。ブルドン管圧力計は,精度確認などで定期的に取り外すことがあります。取り外しや取り付け作業ではいろいろなトラブルが起きています。危険な流体であれば,作業員が誤って液を被ってしまえば,薬傷などの労働災害が発生します。
可燃物の流体であれば,液が漏れればこの事例のように爆発や火災事故になります。取り付けや取り外し作業頻度が多い計器であることから,取り付け取り外し作業時に関わるトラブル事例が多く存在します。
ブルドン管圧力計の接続方式は,ネジ込み式やフランジ接続などが使われます。ネジで接続するタイプでは工具を使って力を入れて廻しながら取り外すことになります。ブルドン管圧力計に使われる導圧管は1/2Bや3/4インチの小口径配管が使われるため,工具を使って無理な力を加えればどうしても配管に無理な力が加わります。この事例では,本来はモンキースパナを使って外すことになっていたのに,大型のパイプレンチを使って取り外す作業をしていたことにより配管に無理な力が加わり折損してしまったのです。
ブルドン管圧力計の取り付け取り外しには,無理な力をかけないように配慮が必要です。必要に応じて配管にサポートを取り付けて強度面の補強をすることも災害防止には有効です。
事例②は,ブルドン管圧力計の導圧配管が折れてしまったトラブル事例です。測定流体は,腐食性物質であったことから導圧配管は塩化ビニル製の非金属材質が使われていました。塩化ビニルは鉄やステンレスなどに比べると強度がありませんので,本来なら導圧配管にはサポートを取り付けて強度面で補強をしておくべきでした。
さらにブルドン管圧力計が猿はしごのすぐ脇に位置するような場所にあったことにより,はしごを下りてきた人の作業靴が当たり強度の弱い塩化ビニル製導圧管が簡単に折れてしまったのです。
圧力計の取り出し配管に無理な力が加われば事故や災害になります。導圧管が,金属ではなく非金属の樹脂製配管であればこのような事故が起こるということです。化学工場では,導圧管に強度の弱い塩化ビニル樹脂製配管などが多く使われています。長期間使用した導圧管は劣化が進んでもろくなっています。配管が,白っぽくなっていれば劣化が進んでいると思って下さい。すぐに交換するなど対策を打たないと思わぬ事故になります。
ブルドン管圧力計を設置するに当たっては,設置場所も慎重に選んで下さい。物や人が当たれば導圧管に衝撃が加わります。さらに,振動などがある場合はしっかりとサポートによる補強がなされているかも確認してみてください。
事例③は,図2に示すような作業をしているときに起こった労災事例です。ブルドン管圧力計がゼロを示していれば本来圧力はなく,ストレーナから液は噴き出しては来ないはずです。
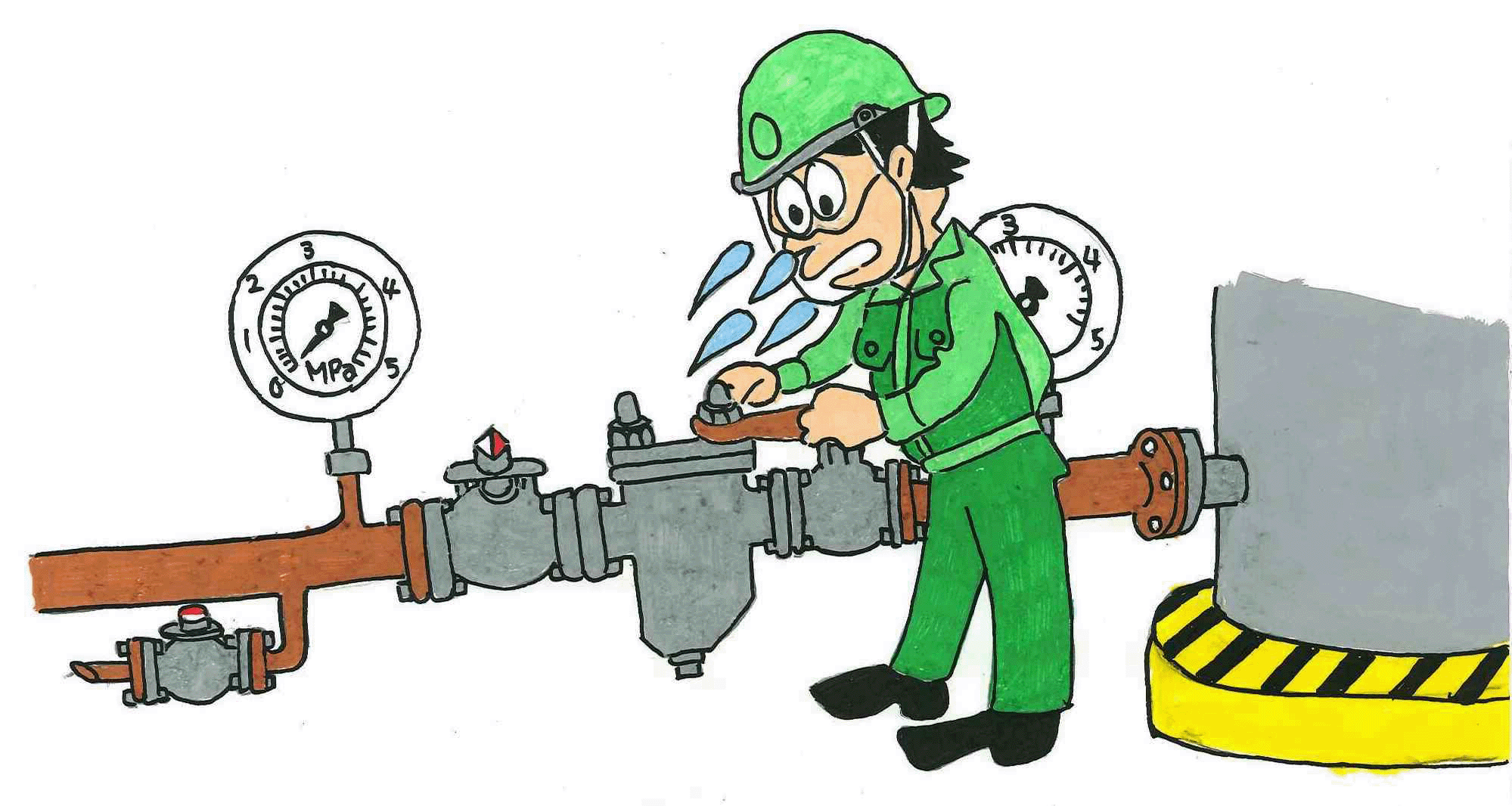
液が噴き出してきた原因は,ブルドン管圧力計のゼロ点がわずかに狂っていたため実際にはわずかに圧力が残っていたのです。振動のある場所に使われているブルドン管は長期間使うと内部のギヤ部分などが摩耗してゼロ点が狂うことがあります。
計器の故障は思わぬ災害を引き起こすこともあるのでしっかりと保全作業を行っていきましょう。
■圧力発信器■
【事例①】
冬になって気温が下がり始めた頃,化学工場のガスの圧力を測定する圧力発信器の指示が時々ばらつくようなトラブルが起こった。導圧管に保温を施工したところ正常に戻った。
発信器を使って圧力を測定する場合,測定する装置や配管などから導圧管という管を使って圧力を導いてきます。測定対象が気体であるか液体であるかによって導圧管の取り出し方法が異なります。ガスなどの気体であれば上側に立ち上げ,液体では下側に導圧管を引き出すのが一般的です。
今回のトラブルでは,上側に導圧管を立ち上げていなかったことにより,冬場になって外気温が下がり,ガス中の沸点が高い成分が液化して導圧管内に溜まり発信器まで行ってしまったために指示の乱れが生じたのです。
保温を施工したことにより,導圧管の温度が上がり液化しにくい状態になったことで解決することができました。その後,導圧管の取り出し方法も本来の上側取り出しに改善して抜本的な対策も行いました。
導圧管の取り出し方法は計器の測定上重要な要素です。設計時点での配慮だけではなく,実際に工事の段階で施工状況の確認を怠らないようにして下さい。