

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第5回 液面計 その2:ディスプレーサ式,他
前回に引き続き,液面計のトラブル事例を紹介していきます。
■ディスプレーサ式液面計■
筒状のフロートを使った液面計です。タンク,タワーやドラムなど数メートルの液レベルを測定するのに使われている液面計です。油と水が混在する液密度の違う界面を測ることもできる液面計です。
【事例①】
プラントのスタートアップ時,ディスプレーサ式液面計とガラス式液面計の指示が合わない状況が発生した。製造側は計器の故障だと譲らなかったが,その後スタートアップ時は液面計の設計密度とは違う条件で運転されていたことがわかった。
【事例②】
ディスプレーサ式液面計のフロートチャンバ底部にあるドレン弁から液を抜いていた。突然,ドレン弁がチャンバ底部から外れてしまい液が噴き出した。
事例①は,液密度が原因となったトラブル事例です。写真1に示すようなディスプレーサ式液面計は,フロートの浮力を利用した液面計です。浮力は押しのけた体積と液密度で決まります。このため,計器を新設するときは,製造部門と打ち合わせて通常使用する状態の液体の密度を使って設計します。
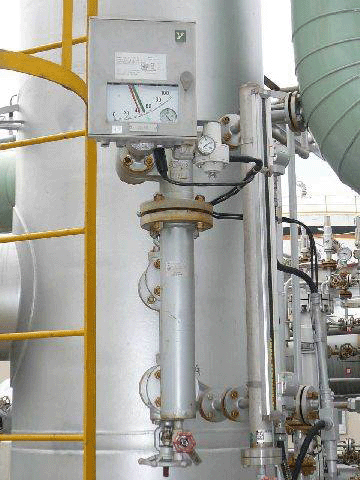
スタートアップのような,非定常状態では運転条件が必ずしも正常な状態ではありません。液体の密度も通常の状態ではないこともあります。水と油を混合するようなプロセスであれば,混合状態が安定化するまでは液の密度は絶えず変化しています。
つまり,液の密度が正常の値でなければ,計器は正しい値を示しません。設計値と呼ばれる液密度と異なれば必ず誤差となって現れます。プラントのスタートアップや停止作業時は,液体は通常の組成とは必ずしも同じとは限りません。液密度が違えば必ず誤差となって現れます。計装エンジニアは,このような現象が起こることをきちんと運転側に伝えておく必要があります。
計器は,設計条件と違う状況となれば誤差となって現れることを理解しておいてください。
事例②は,昔よく起こった事例です。ディスプレーサ式液面計は,フロート(浮き)はチャンバと呼ばれる筒の中に収納されています。チャンバの底部には,脱液用のドレン弁が設置されています。ドレン弁と接続される配管は,チャンバにネジ込み型で接続される形式がよく使われていました。
チャンバの材質が鉄であれば長期間の使用で,ねじの部分が腐食して弱くなっていることがあります。
それに気づかずドレン弁を触っていたときに突然ネジの部分が破損し,図1に示すように液が噴き出す事故が多発していました。
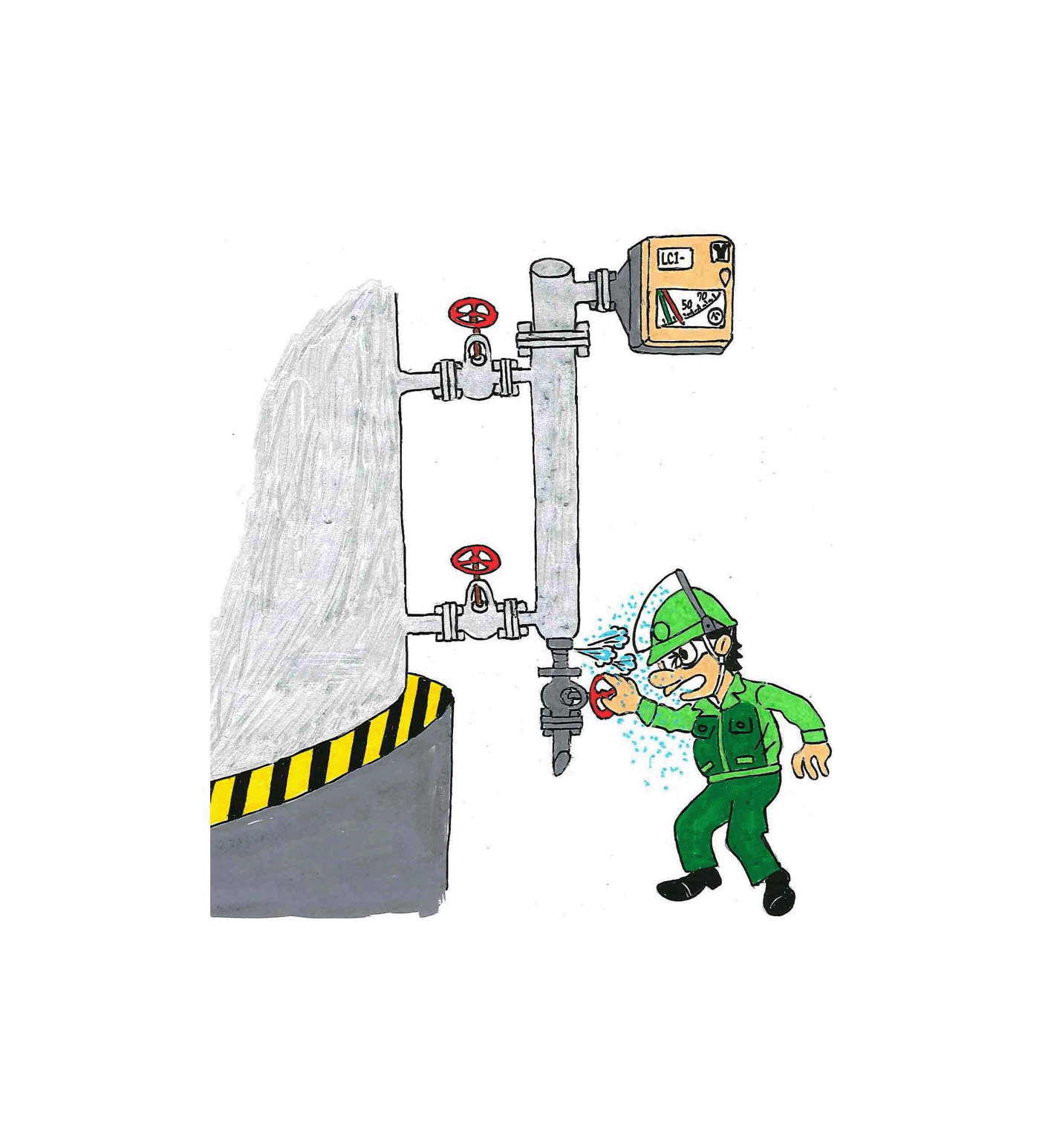
トラブル対策として,ネジを使わない溶接接続に改められ事故の再発を防いだことがあります。皆さんの工場でまだネジ接続のものが使われていないか一度点検してみてください。
■その他の液面計■
液面計が正常に作動しないと事故につながることがあります。液のオーバーフローなどは可燃物であれば火災などにもなります。計器の故障や調整不良によるトラブル事例もあるのでいくつか紹介します。
【事例①】
重油タンクに設置されていたパージ式液が実際より低めの値を示していることに運転員は気づかなかった。タンクに重油を受け入れていたところ,満液となりタンク上部から重油が噴き出した。
【事例②】
製品(球形ビーズのようなプラスチックの粒)を貯蔵する高さ10mほどのサイロ内には,放射線液面計が設置されていた。サイロ内の貯蔵量を検知して,一定量に達すると自動的に抜き出すシステムが組まれていた。定修時に,液面計を調整した際,計器のパラメータ(設定定数)を間違えてしまったため,スタートアップ後にサイロ内で爆発が起こった。
事例①はパージ式液面計のトラブルです。パージ式液面計は,タンクやドラムの上部より筒状のパイプで気体を送り込み,その背圧を測定して液レベルを間接的に測る方式です。液のレベルが変動すれば,それに比例して背圧が変化するという原理を用いた液面計です。排水ピットなど汚れのある液体でも測定できます。
今回のトラブルの原因は,背圧を導く導圧管の接続部分が緩んでいてパージ用の気体が漏れていたことが原因です。パージ流体がわずかに漏れたことから,背圧が実際よりは低めになってしまったのです。
パージ式液面計は,背圧を測定する配管部分などでわずかでも漏洩が起これば誤差になってしまいます。
事例②の放射線液面計の事故は,計器の点検の際に設定値を誤って作業員が入力したことにより起きた事故です。放射線式液面計は,粉体や粒体,高粘度物質など一般的な液面計では測れないものを測定するのに使われています。放射線が物質内を透過するとき放射線が一定量吸収量される原理を利用した計器です。サイロのような装置では,貯蔵している製品量に応じて放射線の吸収量が変化することから間接的に貯蔵量を推測することができます。間接測定方式であることから,いろいろなパラメータ(設定常数)を調整してレベルを計算します。このパラメータの設定を間違えてしまうと,正しい指示を示さなくなってしまいます。
今回のトラブルは,10%指示が低めに出ていたことに気づかず運転を続けていたところ,サイロ内に可燃性ガスが溜まりやすくなり静電気で爆発した事故です。
最近は,コンピュータを使った機器も増え,いろいろなパラメータの設定を必要とする計器が増えています。パラメータの設定は,慎重に確認しながら行ってください。