

連載【トラブル事例解説】現場計器に何が起きたのか
第2回 流量計 その1:オリフィス流量計
化学プラントには多くの流量計が使われています。その中でも,数多く使われているのがオリフィス式流量計ではないでしょうか。今回は,このオリフィス流量計についてトラブル事例を紹介します。
■オリフィスプレート■
第1回ではオリフィスプレートの下流側で渦が発生して事故になった下記事例を簡単に紹介しました。
2004年8月9日に原子力発電所で起こったこの事故について,少し詳細に説明します。
オリフィスプレートの下流側の配管に穴が開き高温の液が噴き出し,近くにいた5人が死亡,6人が負傷しました。下流側にできる渦の発生によりエロージョン・コロージョンが起こる可能性があるのに,約30年間という長期間点検もしていなかったのです。
温度は約140度,圧力は約1MPa,流量は約1700m3/h,配管外形は約60cmとかなり太い配管です。オリフィスプレートの下流側が60cmほどめくれるように破れていたという状況です。このため図1のように大量の高温水が,近くにいた作業員に吹きかかり大災害となってしまいました。鉄板の薄いところでは0.4mmと薄い紙のような状況だったようです。
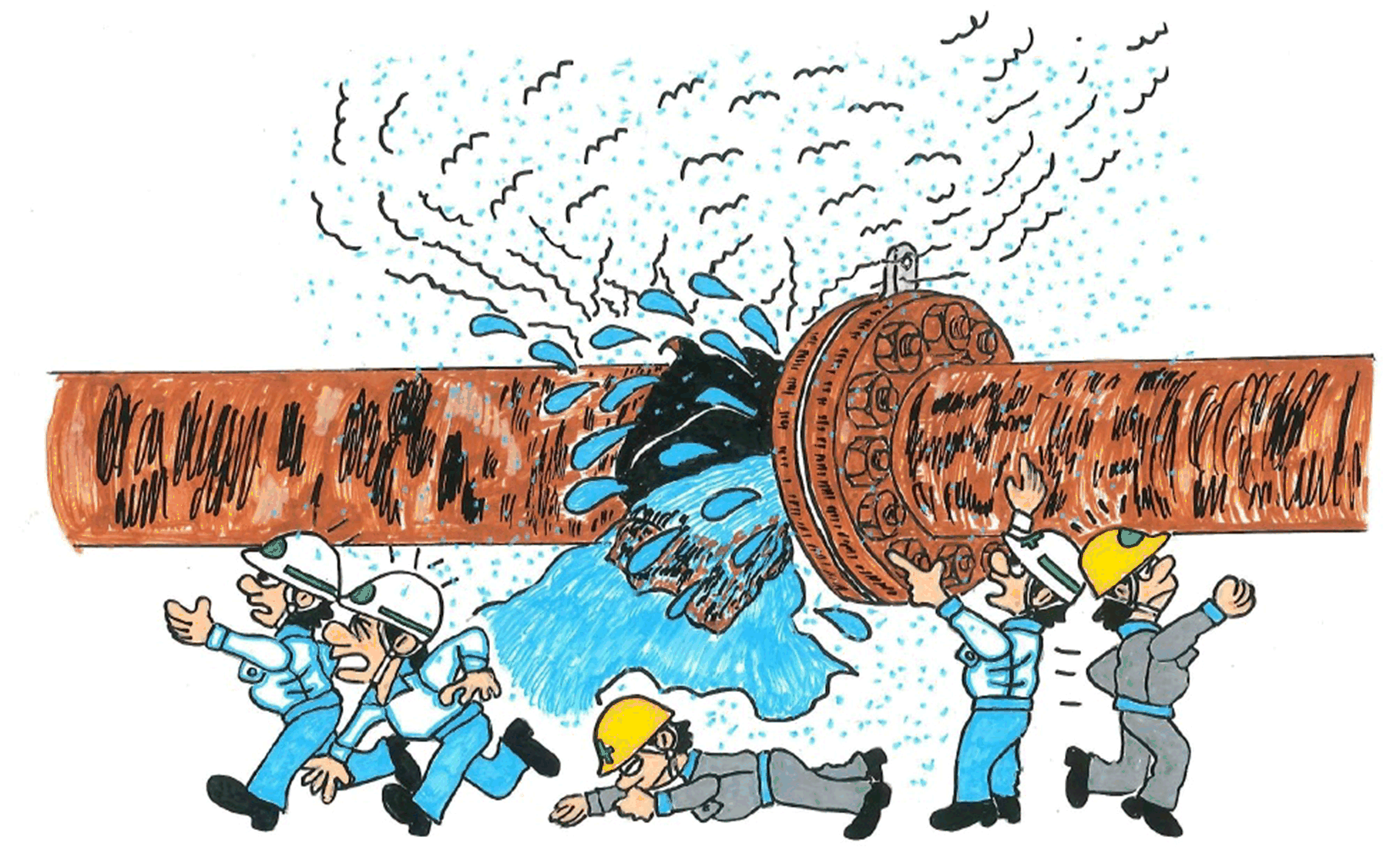
図2に示すような渦のエネルギーが,原因です。流体の持つエネルギ-を甘く見ないことです。金属とて,時間がたてば削れていくのです。さらに,水は腐食という現象も引き起こします。機械的に削られるエロージョンという現象と,腐食などのコロージョンという化学的現象の両方が原因で起こった事故です。
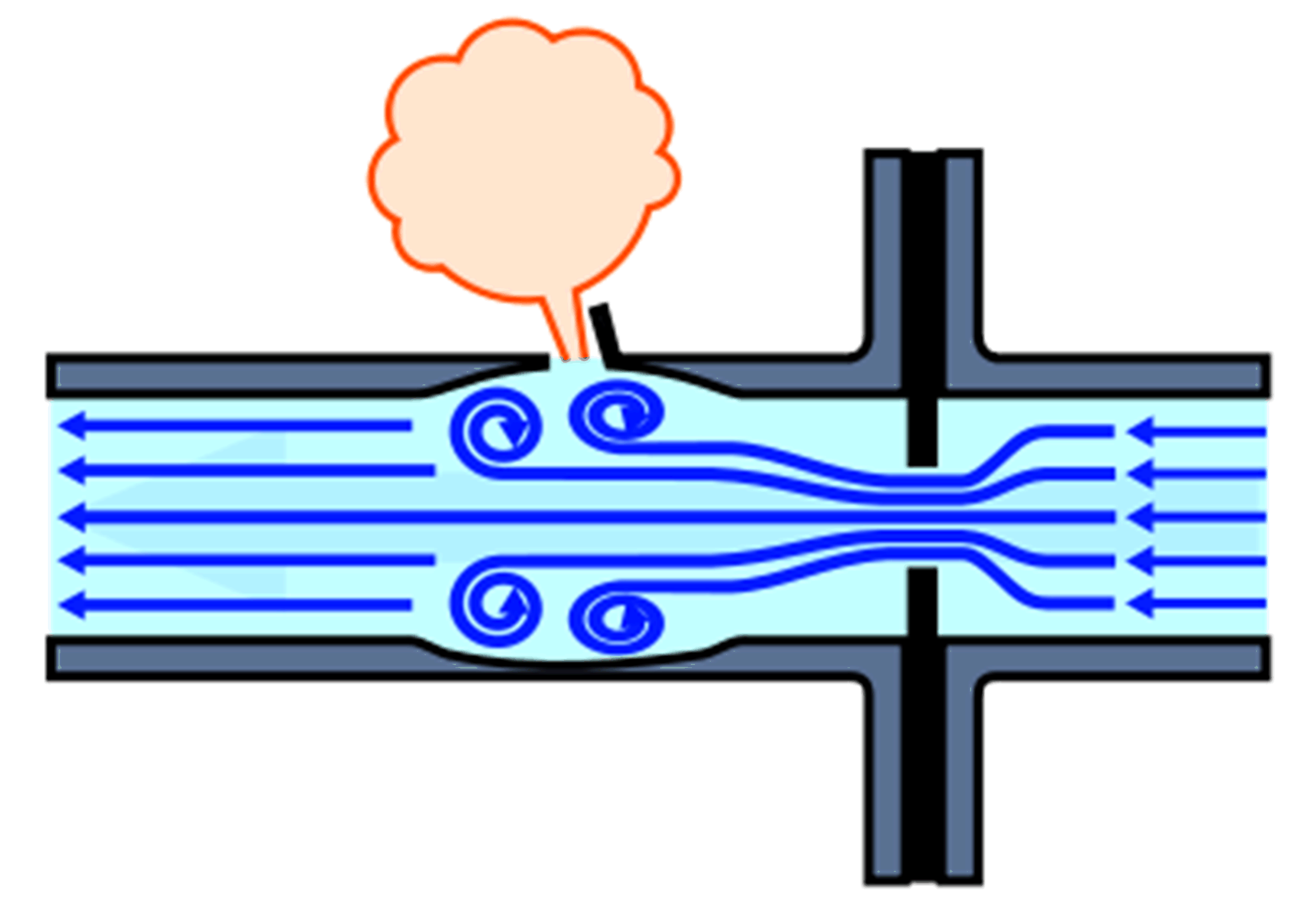
計器の選定についても考えさせられる事例でした。配管にオリフィスを挿入する方式は一般的ですが,大口径配管では配管が破れれば大きな事故になります。超音波流量計など,外部に検出器を設置する方式であれば,事故は起こらなかったかも知れません。
計器の選定には経済性も大切だが,プロセスによっては事故が起きたことを考え本質的に安全な計器を選定して欲しいということです。
■レンジ変更■
オリフィスプレートを使った流量計は,検出端であるプレート(板)さえ交換すれば簡単にレンジ変更ができます。プレートも安価なため,レンジ変更が想定されるプロセスには経済的です。しかし,簡単であるがゆえに,過去多くのトラブル事例が存在しています。
レンジ変更に係わるトラブル事例を2件紹介します。
① レンジ変更の依頼を受け,プレートを製作した。定修時にプレートを差し替えた。運転開始後,指示がおかしいとの連絡を受け設計データを確認したところ設計条件の数値を間違えていた。
② レンジ変更の依頼を受け,プレートを差し替えた。運転を始めたところ指示がおかしいと言われ調べたところ,発信器側の差圧変更を忘れていた。
①は,設計データを間違えた事例です。数値を一桁間違えたのです。連続プロセスであったため,運転を一度止め復旧したというトラブルです。うっかりが,多大な経済的損失を生む事例です。
②は,肝心の発信器のレンジ変更を忘れた事例です。レンジ変更で,検出側のプレートを作り替えて新作する場合は発信器側の差圧を変えないで製作することも可能です。この事例は,遊休品のプレートを転用した例です。プレートを転用するときなどは注意が必要なのです。
類似の事例で,計器室側の記録計のレンジを変更するのを忘れたという事例もあります。たかがレンジ変更と侮ることなかれです。
■計装導圧管■
オリフィスプレートで検出した差圧は,導圧管という細いパイプを通って発信器に伝えられます。導圧管に関連するトラブル事例を紹介します。
①導圧管が詰まって指示が出ないトラブルが起こった。検出端の計器元弁を閉め水圧ポンプで詰まりを取り除く作業をした。確認をしようと,高圧側の元弁を開けたところ,発信器下部のドレンプラグから液が噴き出した。
②凝固点が常温より低く,常時スチームトレースを活かす導圧管だった。あるときスチームトラップにゴミが詰まりうまく作動せず温度が下がった。発信器内部で固まり,ダイヤフラムが損傷した。
①は図3で示すような導圧管が交差するような形で工事施工がなされていたのが原因の一つです。導圧管が平行な形で工事施工がなされていれば,高圧側と低圧側は間違えなかったはずです。現場は,ほかにもいろいろな配管が障害になり見えにくかったということです。

設計の段階から,人がミスをしにくい施工方法を考えておくべきです。設計のミスは,後になって保全のミスという形で現れるからです。
もう一つのミスは,ドレンプラグを外したままで元弁を開けたというミスです。類似の事例で,シールポットのプラグを開けたまま,元弁を開けてしまったという事例もあります。完全に復旧してから元弁は開けるのが基本です。幸い着火しなかったから火災にはなりませんでしたが,可燃物が外に出れば燃焼の3要素が成立してしまいます。着火源は静電気という形で多くの事故が起きています。運転中の計装保全作業は,ひとつ間違えば事故になるのです。
②は,保温に関するトラブル事例です。凝固点の低いものは,スチームトレースの設計に注意が必要です。スチームトラップを付ければ,省エネにはなります。しかし,鉄さびなどが詰まればトラップが故障することもあります。安易に省エネ設計をすると,このようなトラブルが起こります。重要な計器であれば,指示不良はプラントの安全を脅かしかねません。トラップの二重化や型式の選定まで考慮しておくことが大切なのです。
たかが,スチームトレースと甘く見ないことです。
〈参考・引用文献〉
1)美浜発電所,Wikipediaより引用