

【ケーススタディ】
化学プラントの高度保安技術と計装
1.はじめに
安全や技術はいきなり作り出されたものではない。人が多くの失敗を経験して,そこから編み出した知恵が活かされて今が成り立っている。安全を支えるには技術の進歩も必要だ。計装技術を見ても,10年ごとに技術の変革がある。計装技術の変革は,省人化,高度化,自動化,信頼性の向上,保全コストの低減など多くの産業界からの課題に答えた結果だ。
本稿では,高度保安技術の意味するところを考えてみたい。時代が何を求めているかを知る必要があるからだ。次に,事故を防ぐ仕組みに計装技術がどう関わっているかを紹介する。
最後は,産業界からのニーズに応じて計装技術がどのように変革してきたかを振り返りながら,高度保安技術を支える計装について考えてみたい。
2.高度保安技術とは
高度保安技術とは,2010年代の後半から使われ始めた言葉だろう。
化学プラントでは,2017年から高圧ガスのスーパー認定制度1)というものが運用され始めている。最新技術や高度な人材を育成して安全・安定運転ができる能力を持った企業を認定する新制度だ。この認定を受ければ,企業は次のようなメリット得ることができる。 ①最大8年という長期連続運転が可能 ②設備の検査方法を自ら設定が可能 ③許可を得ず自主的に行える範囲が拡大 ④認定更新が5年から7年へと長期化 長期連続運転が可能になるということは,修繕費が大幅に削減でき企業にとって大きなメリットになる。 検査についても独自のものが可能となればコスト面でも有益だ。許可を得る範囲が減るということは申請業務量が減り,人的コストが節約となる。さらに7年間もその利点を利用できるメリットは大きい。 そうはいっても,この制度を利用するには企業として「高度な保安技術」を持っていることを証明しなければならない。企業はソフト,ハードの両面で国の要求条件を満たす必要がある。 2.1 ソフトウェア面 人という切り口では,高度な人材の確保と育成を要求している。つまり安全面では,潜在する危険源を確実に抽出し高度にリスク評価できる人材が求められている。HAZOP(Hazard and Operability Study)などの安全性評価手法を使いこなせる人材だ。事故情報のデータベース化などによる蓄積情報の充実で過去の教訓を使いこなすことも必要だ。 変更管理体制の充実も求めている。事故は何か「変更」したときに起きやすいという考え方からだ。 運転面では,定常時のみならず非定常時においても異常に対応できる高度な人材を育成し配置することを求めている。事故は,緊急時,運転開始時,停止時や試運転時などいわゆる非定常時に起こりやすいからだ。 技術管理面では,長期連続運転を可能にする管理基盤を体系的に構築し,管理するシステムを作り上げてPDCAを回すことを求めている。高圧ガス保安法ではこの仕組みを保安管理システムと呼んでいる。 検査管理面では,検査データを高度に評価する人材を要求している。技術士,電気主任技術者などの有資格者を入れて検査体制を充実することを求めている。長期連続運転には,高度な余寿命を推定する技術が必要だからだ。膨大な検査データをビッグデータ化し,高度に活用し評価できる人材が求められてきている。 教育訓練では,緊急時対応能力の向上,体感型の教育訓練設備の活用やベテランOBを活用した技術伝承が要求される。 2.2 ハードウェア面 ハード面では,最先端の高度な技術導入と情報の活用を要求している。ドローン技術の活用,IOT(Internet of Things)やビッグデータなどの先端技術などが例に挙げられているが,最新の設備診断機器やセンサ技術も含めてのことだ。ドローン技術は図1に示すような高所での機器異常点検が試行されている。 機器点検分野では,超音波などを使った非接触型設備診断器具の活用,3Dレーザスキャンによる腐食箇所の早期検知などだ。 計装分野での先進技術としては,アラームマネジメント,AIなどを活用した運転支援システム,モバイル端末利用によるデータ収集と解析,赤外線カメラと組み合わせた高度ガス検,自己診断機能を持つスマートバルブの活用などが既に始まっている。安全計装システムの導入も高度な技術と言えよう。 3.事故を防ぐ仕組み 事故が起きないようにするためには一つだけの対策では不十分だ。いくつかの防護壁という仕組みで事故の未然防止を図る必要がある。たとえば,防護壁とは図2のような考え方だ。 3.1 "事故を防ぐ最初の防護壁は「設計」だ" 計装設計段階でいかに事故を起こさない環境を作れるかは重要だ。本質的に事故が起きないようにフェイルセーフの設計が求められている。たとえば,電気や計装空気の供給が停まった時の調節弁の安全方向である。 次は,フールプルーフ設計をすることだ。間違っても事故にならない仕掛けだ。インターロックを設けることも有効な手段である。二重化するなど冗長化で信頼性を上げることも必要だ。 コストとの兼ね合いはあるが,設計段階で安全な状態を造り出す努力を惜しまないことである。 3.2 "「制御システム」は事故を防ぐ第2の砦だ" 化学プラントは運転していれば,いろいろなトラブルが起こる。流量の変化,温度も変化することがある。人間が計器の指示を常時監視して見ていれば良いのだが,それでは人に負担がかかりすぎる。制御システムの警報監視機能などを活用して,上手に人の負担を減らして行くことが安全の確保にもつながる。 1970年代までは,図3のような制御盤を用いた運転方式だった。この時代は,多くの運転員を計器盤の前に配置して運転する方式だった。高度な自動化は導入されておらず,いわゆるPID制御を基本とする制御システムだった。計器盤という運転方式は,調節計や指示計などの前まで人が行かないと情報が得られないという問題点があった。人が常時計器盤の前を歩き回って情報を集める必要があり,計器室には多くの運転員を必要とした。 1980年代に入ると,写真1のようなDCSが本格的に使われ始めた。コンピュータを活用した制御システムだ。DCSの登場により,情報表示端末の前に運転員は座っているだけで,あらゆる情報を入手できるようになった。さらに,シーケンス制御機能を活用することで自動化の範囲が急速に広がっていった。自動制御の世界が急速に進み始めた時代だ。警報機能も充実し,コストを掛けずに警報を追加できる時代になっていった。異常に早く気づくことができる時代が到来した。しかし,高度化によるブラックボックス化やアラームパニックという新たな問題も生じさせた。 3.3 "第3の砦は「人」だ" 制御システムは,あくまで機械だ。情報を提供し,警報は出すが,全てを判断して対応してくれるわけではない。異常が起きたら,人が歯止めを掛けてやる必要がある。 制御システムから出る情報を総合的に判断して,安全に運転する役割を果たすのが「運転員」と呼ばれる人だ。トラブルに対応できるためには,十分な教育が必要だ。緊急事態を想定しての訓練も必要となる。 2010年代に入っての重大事故2)の要因の一つに,DCSの警報が大量に鳴って対応がうまくいかなかったというものがある。いわゆる大量の警報で人がパニックになってしまったという問題点も発生している。設計の段階から,アラームマネジメントを考えておく必要がある。 もう一つの問題点は,DCSの画面設計だ。通常運転時に必要なDCS画面は用意されていたが,緊急時に必要なデータを集める画面設計が不足していたという問題点である。図4のようなDCSという制御システムは,画面設計の善し悪しも関係する。制御システムは「機械」と「人」がうまく会話できるような設計が必要だ。 3.4 "最後の砦は「安全装置」だ" 「設計」,「制御システム」,「人」による対応が全て破られてしまったときは,安全装置による対処が事故への歯止めとなる。計装設備であれば,自動停止インターロックや緊急停止装置を予め備えておくことが事故防止に有効だ。万一を考えて安全装置を設けておくことは事故防止に対する保険のようなものだ。わずかの投資が,甚大な被害を防止してくれる。 4.計装技術の時代変革 計装の視点で技術進歩を見てみると,1950年代までは空気式が主流だ。フィールド機器も空気式である。計器盤の機器も写真2のごとく空気式が主体だった3)。空気式計器の伝送距離は最大300m程度に限られることから,大規模工場への導入には限界があった。 1960年代頃から時代は電子式へと変化する。アナログ電子式計器へと変わり始めた。とはいえ当時使われていた電子部品は,まだトランジスタの時代であり故障も多かった。さらに電気を溜めるコンデンサも,寿命の短い電解コンデンサが多く使われており計器故障に悩まされた時代であった。 1970年代に入ると,電気部品はICが採用されるようになり故障率が大幅に低下した。1971年にマイクロプロセッサ(以下CPUとする)という画期的な電子部品が登場した。4bitの演算処理装置だ。最初は電卓から利用され,あっという間に計装の世界へと入ってきた。 1975年にはDCSが登場した。当時は1つのCPUで8~32ループを処理していた。CPUの故障は運転に大きな影響を与えることが不安のタネだった。1980年代になると様子を見ていたユーザもDCSの採用に踏み切っていった。新設もアナログからの更新もDCSに代わっていった。 1990年代になると第三世代の信号技術であるフィールドバスが登場した。DCSの機能向上により計器室の統合化が始まった時代でもある。 000年代に入ると,通信の高速化とフィールド機器までを含めたオープン化が進んだ。つまり,DCSによる情報制御の統合化が進んだ時代と言えよう。大量の団塊の世代が退職する2007年問題を境に,運転支援機能の充実も始まった。 2010年代に入ると,オープン化が加速し,広範囲の機器や情報の接続が求められる社会へと変革した。一方でセキュリテイの確保などの課題も生じてきた。 2020年代は,高度保安技術を支える形で計装技術はさらに進化していくのだろう。 では,フィールド計器の技術変革を見てみよう。 (1)流量計 昔から使われているのはオリフィス式流量計だ。最大の問題点は,絞り機構は圧損を発生するというエネルギーロスが大きいことだ。精度に関しては,容積式流計が優れるが,機械的構造が複雑がゆえにトラブルも多かった。この問題を一気に解決してくれたのはコリオリの原理を活用した質量流量計だ。その後,非接触の電磁流量計の登場などにより流量計の信頼性は向上してきている。 (2)液面計 古くから使われてきたのは,浮力を利用したフロート式流量計だ。フロート式と言えば,ディスプレッサ式液面計という設備が化学工場ではよく使われる。私が現役の頃のトラブル事例を紹介する。 当時は,フロートを収納するチャンバ(筒)の下部にある脱液用ノズルがネジ込み式だった。鉄製のチャンバはネジの部分が腐食により外れることが多かった。図5のごとく突然ネジ部が外れて液が漏洩する事故を多く経験した。 事故の頻発を受け,ネジ接続をやめてフランジ型接続に標準仕様が変わりトラブル頻度は激減した。 トラブルに対し仕様を変えたことが計器の信頼性を向上してくれたのだ。ユーザニーズを計器メーカが確実に汲み上げてこそ技術の進歩につながる。 (3)圧力計 ブルドン管圧力計など歪みを利用した原理が基本だ。電気式圧力発信器は,1970年代までは力平行式だったが,1980年代には半導体センサを用いた発信器へ変革した。このことが,精度や信頼性を大きく向上させた。 (4)温度計 熱電対や測温抵抗体が検出端の主流であることは変わりない。アナログの電子式変換器が使われ始めたころ,検出端の断線を検知してバーンアップ・ダウンの機能が登場した。これにより,断線時にも安全方向に作動させることができるようになった。バーンアップ・ダウンというフェイルセーフの機能は,安全性向上に大きく寄与している。 (5)ガス検知器 センサの発展が信頼性の向上に大きく寄与してきていると感じる。1970年当時は,高濃度のガスを検知すると瞬く間にセンサが駄目になった。その後,半導体センサの登場により大きく信頼性が上がった。 その後もガス検知器は高機能化を続けている。 (6)調節弁 国産品による調節弁が現れたのは1930年代後半だ。当初は,復座のグローブ弁だ。単座だと駆動部がかなり大型のものを必要とする。ゆえに復座のグローブ弁が最初に使われたのだろう。 その後,弁を駆動する推力の小さいケージ弁が使われるようになり,小型の駆動部で制御ができるようになった。弁構造の変革という技術革新が自動制御の世界を広めていったと言える。 弁構造の進化もさることながら,弁の位置を制御するポジショナという装置の進化も見逃すことはできないだろう。昔は図6のように調節弁のポジショナが動かないことが頻発した。ポジショナのフィードバック信号を受ける軸が固着してトラブルを起こすことも多かったからだ。しかし,その後潤滑性に優れた部品が開発され,軸受け部の固着トラブルも起きなくなった。部品材料ベースの進歩が,計装設備の信頼性を上げてくれたのだ。 (7)発信器 1970年代までは力平衡式の発信器だ。機械的原理を使う方式でよく故障した。大型で,重量も十数キロあった。検出部のダイヤフラムも故障しやすく信頼性は今より劣っていた。その後ダイヤフラムの加工精度も向上し信頼性も向上していった。 1980年代になり,半導体センサが使われる発信器が登場したことから信頼性も大きく変化した。画期的な技術革新だ。精度のみならず,信頼性も確実に向上した。その後圧力温度などを一括して検出できる複合型半導体も登場した。この変革が,発信器の信頼性に大きく寄与してきたのではないだろうか。半導体という技術の成果だ。 5.おわりに 石油精製や化学プラントは高度化し,しかも少ない人数で長期間にわたる安全安定運転が求められてきている。これを支えるためには,計装機器のさらなる高信頼化や高寿命化が不可欠だ。 事故の未然防止には,異常を早期に検知することが重要になる。人の機能を代替する高度な機能を持ったフィールド機器が求められる。フィールド機器の信頼性を上げるには,自己診断機能や自己修復機能の充実が求められていくはずだ。高寿命化の課題を解決するには,部品レベルの技術進歩も不可欠である。 とはいえ,機械だけが進歩すればいいわけではない。人も組織も進化していく必要がある。計装エンジニアだけが進化すればいいわけでもない。計装という分野は多様化,複雑化してきている。 計器メーカの保守管理センタとの連携がますます重要になる。インターネットを使った24時間監視が不可欠になるからだ。 化学プラントの運転員も進化していく必要がある。高度な計装機器を使いこなしていく必要があるからだ。 高度保安技術を使いこなしていくには,人と設備がうまく調和している必要があるだろう。人に過度に負担をかけないことが大切だ。フィールド機器,制御システム,操作端が総合的に機能する高い信頼性が計装システムには求められている。
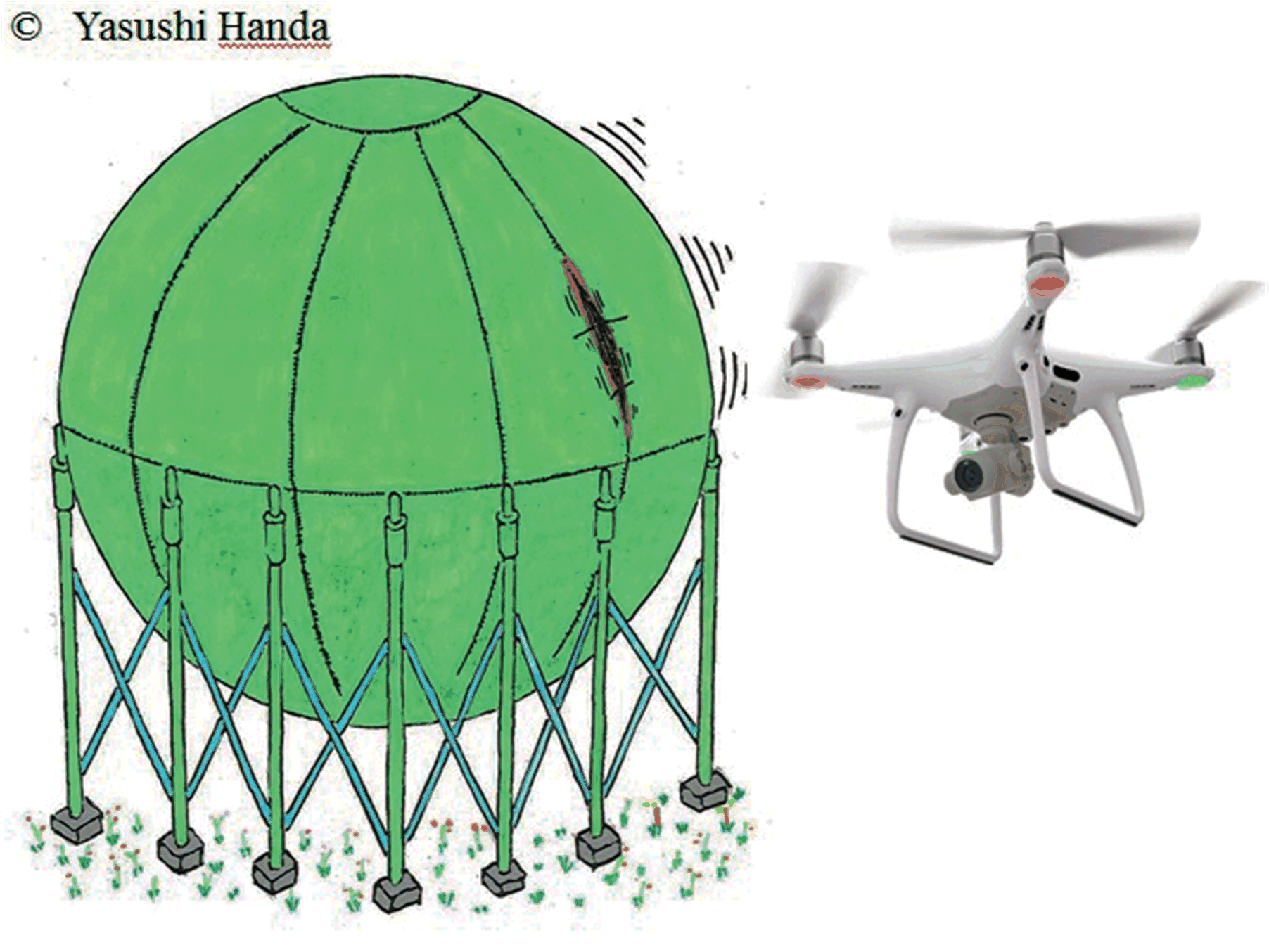
図1 ドローンの活用による高所異常箇所の点検
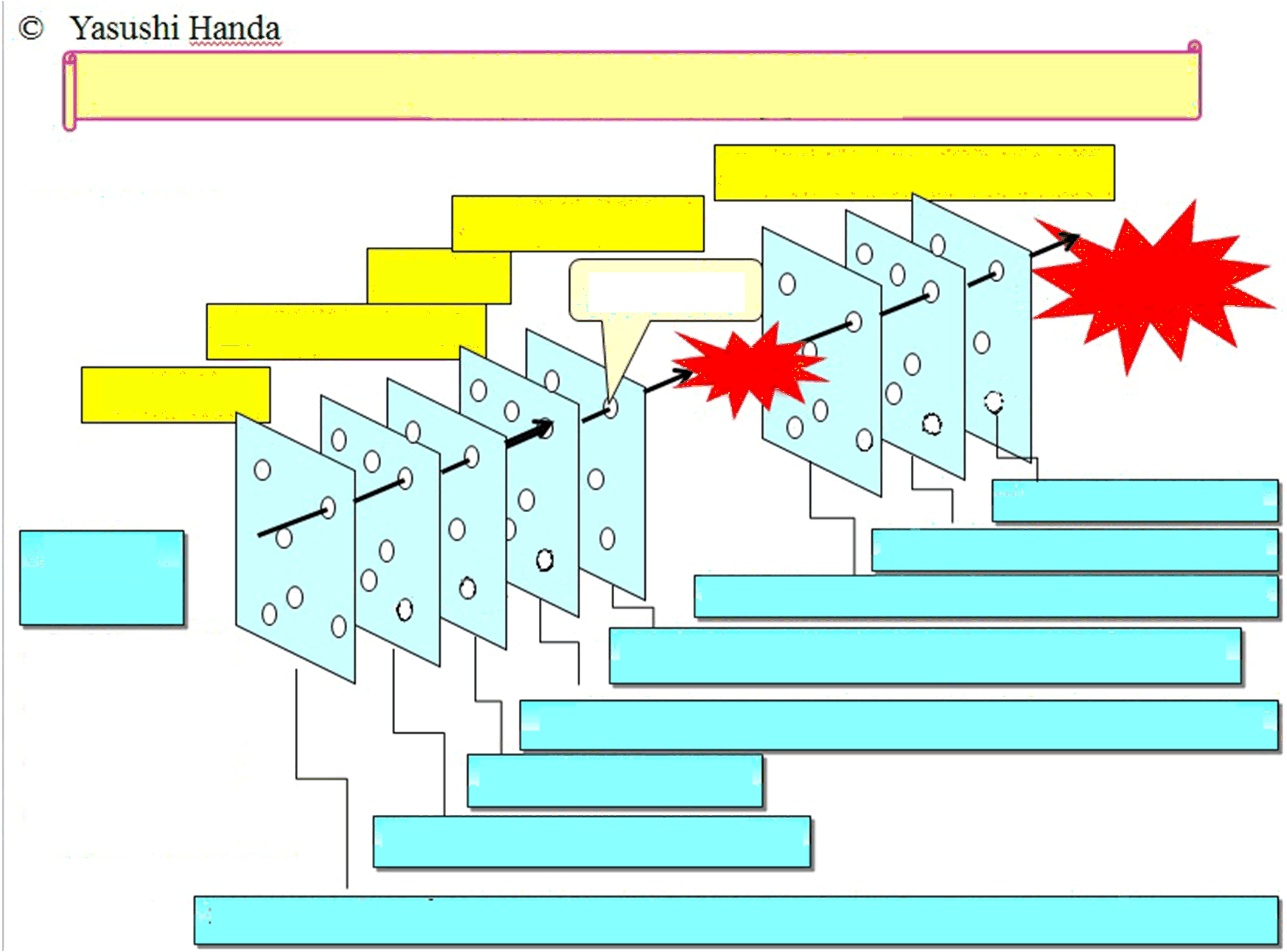
図2 事故を防ぐ防護壁
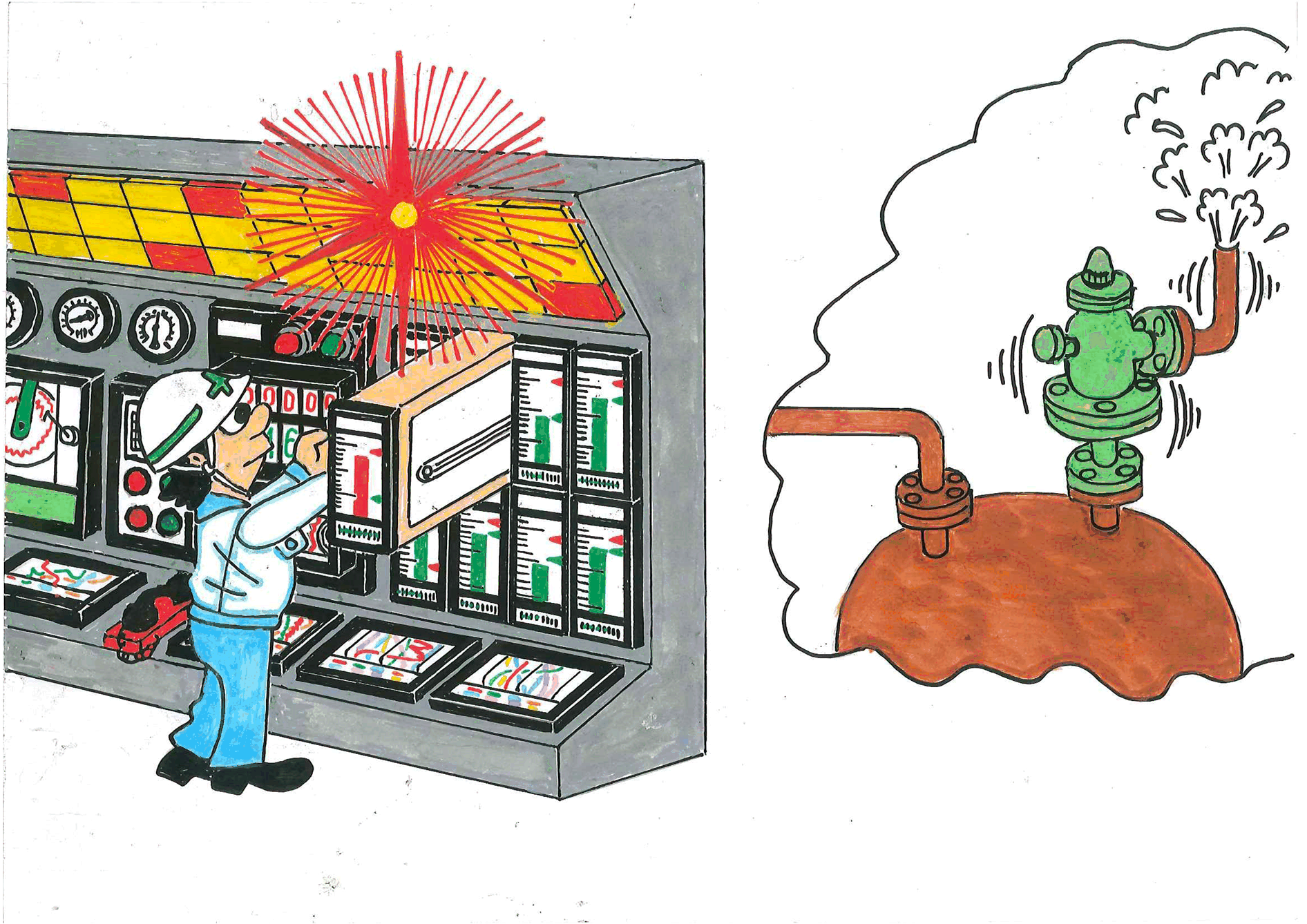
図3 計器盤運転方式

写真1 1980年当時のDCS
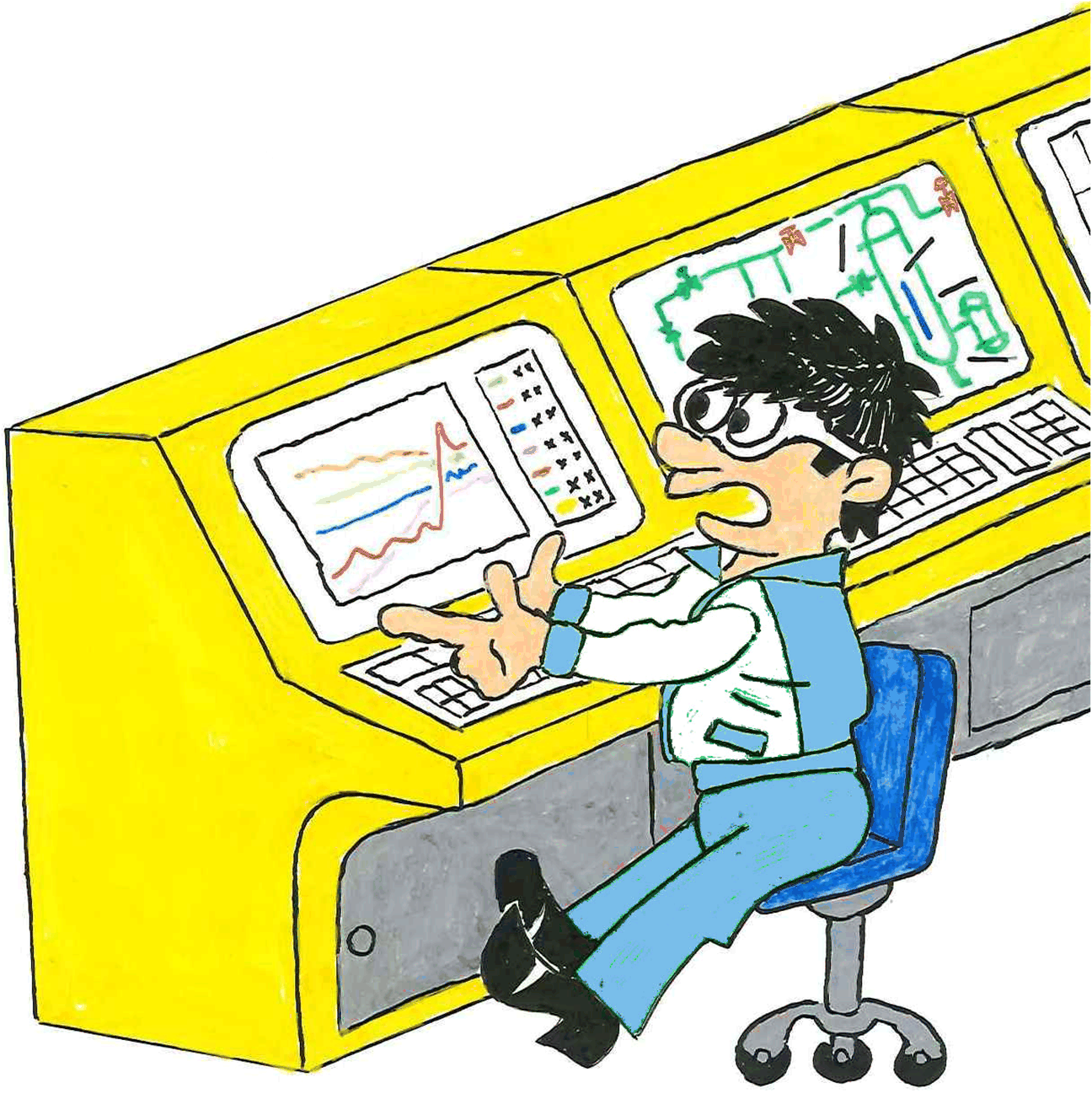
図4 DCSの画面設計
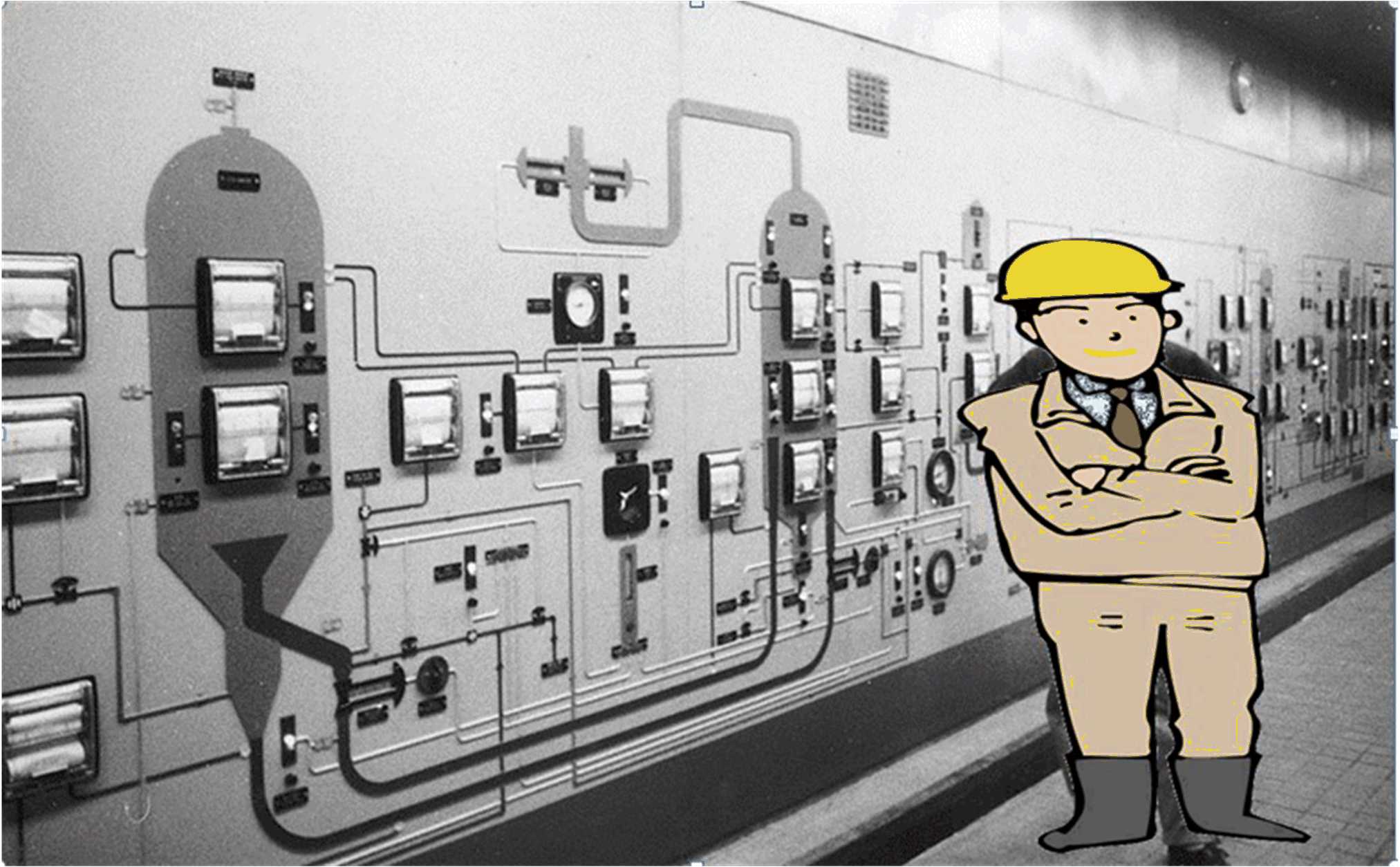
写真2 1950年代計器室
2
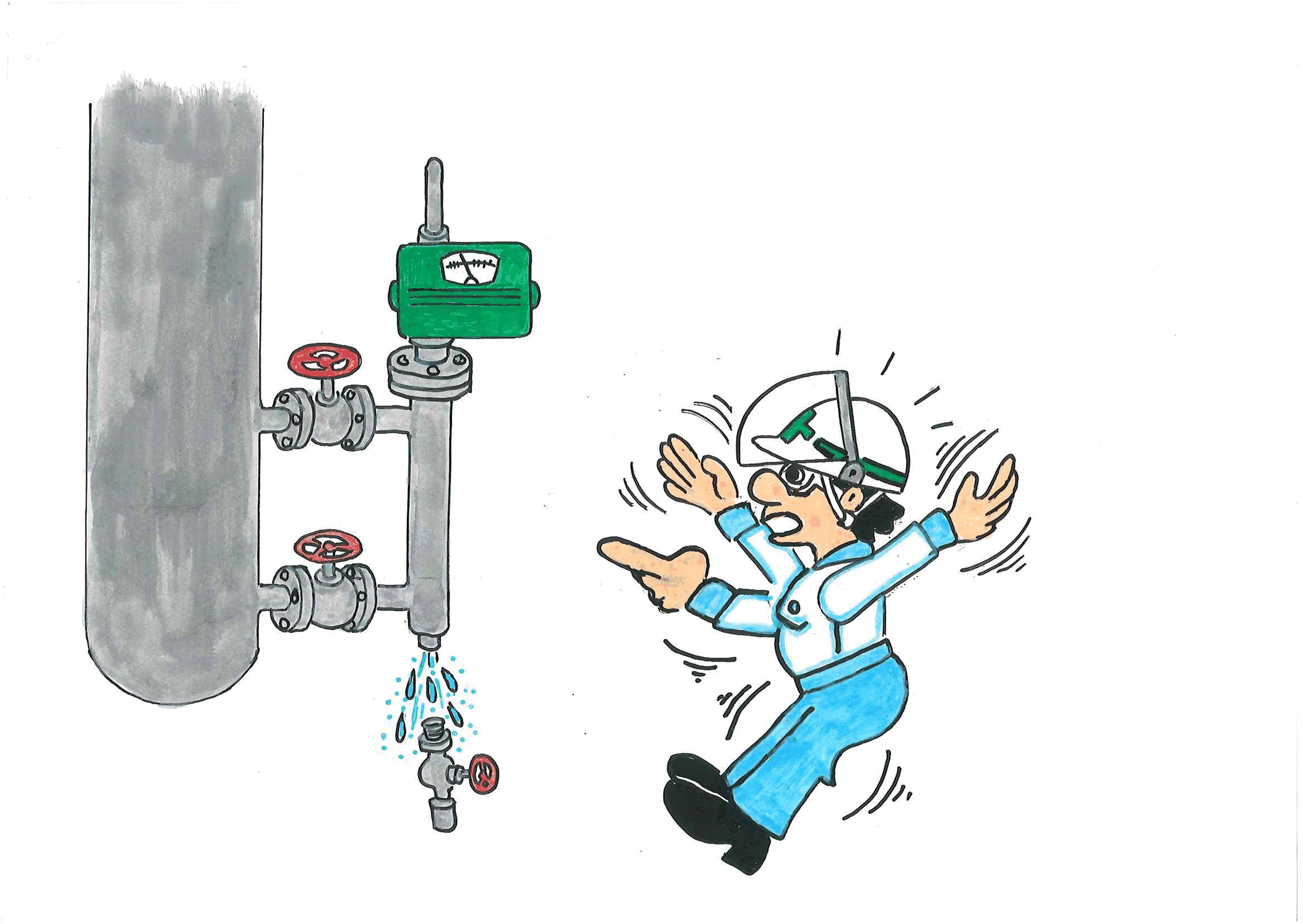
図5 液面計ドレン弁が腐食で脱落
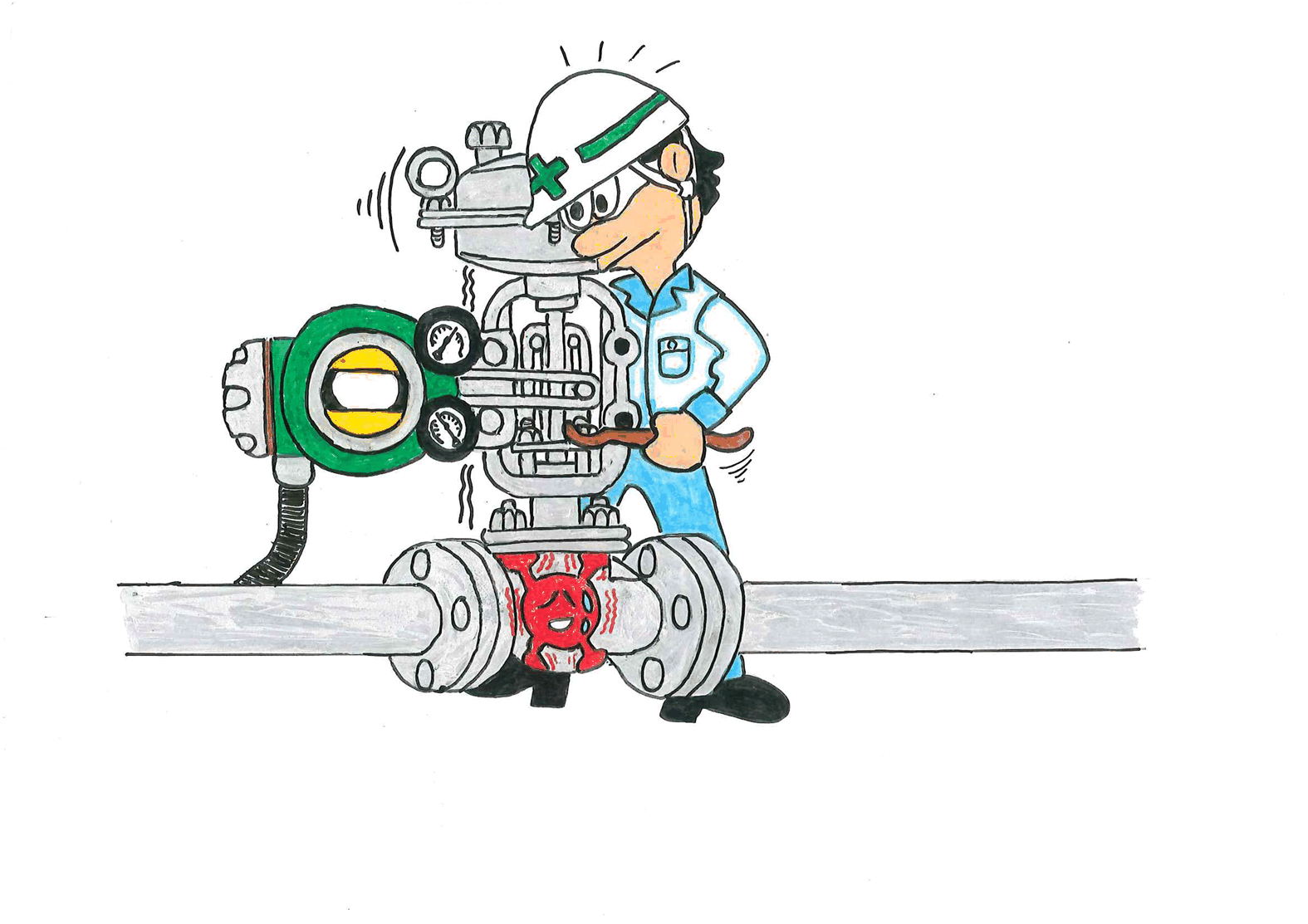
図6 調節弁ポジショナトラブル
ポータルサイトへ