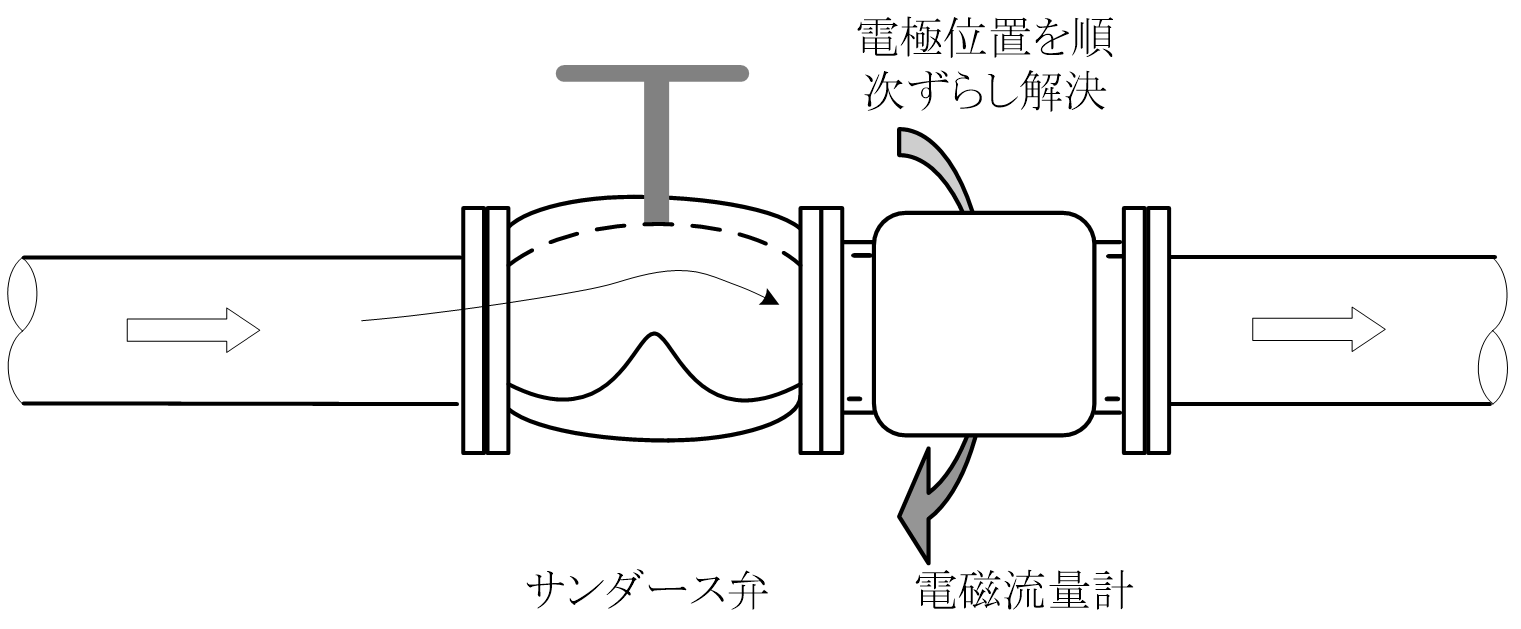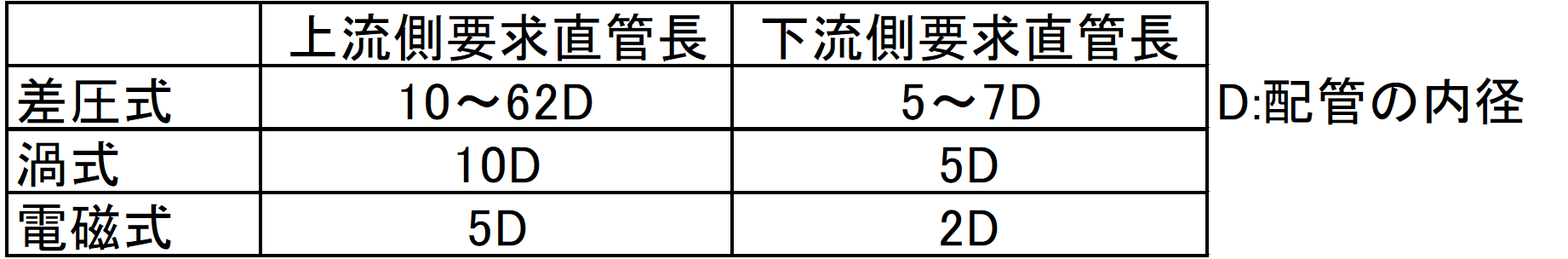
なぜ流量計の上流に直管長が必要なのか
流量計の流速分布の整定に要求される直管長は、およそ下表のようになっています。
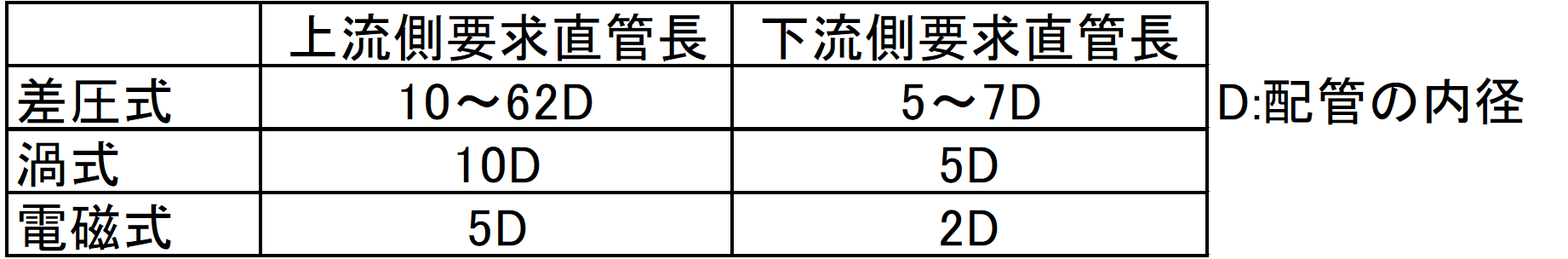
差圧式の要求直管長が10~62Dと幅が広いのは、オリフィスプレートの開口比(配管内径Dに対する絞り穴径dの比d/D)により要求直管長が異なるためです。開口比が大きいほど要求直管長が長く、開口比が小さいと短くなります。現実には、配管スペースの制限から要求直管長を満たせない場合もあり、そんな時どうなるのかも知りたいところです。
例えば上流側にベント部(曲管)がある場合を考えて見ましょう。
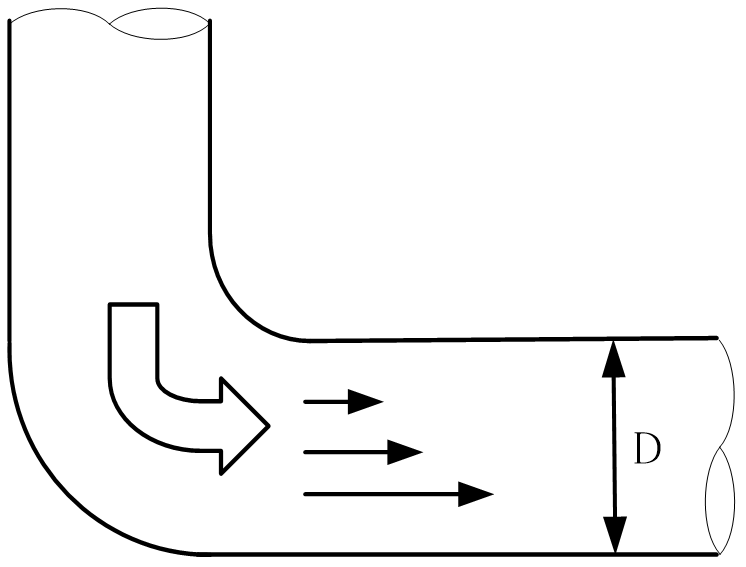
上図の場合、ベント部で流体が方向転換すると外周部が増速し、逆に内周部の流速が減速します。一方、差圧式は、差圧取出し位置に方向性を持ち、この流速分布の不均一が誤差の原因になります。渦流量計では、渦発生体の向き、電磁式では、電極位置なども同様です。
また、制御弁やストップ弁による流速分布の乱れや渦巻きポンプや複雑な配管の曲がりによる旋回流も誤差の原因になりますが、直管部はこれらの乱れを整定し安定させます。取引用や性能評価用流量計には精度が要求されますので充分な直管長が必要です。
電磁流量計は、比較的上流側直管長の影響が少ない流量計ですが、下図のように直前に設置したサンダース弁の影響を改善した例を紹介します。
サンダース弁を常時全開で使用しているにもかかわらず、流速分布の不均一の影響で電磁流量計に数%の誤差が出ました。電磁流量計を弁の上流に移したいのですが、プロセス運転の都合上できないため、電磁流量計の取付けボルト穴を利用し電磁流量計本体を回転し電極位置を順次ずらし、理論値にもっとも近い流量値になる位置(下図では電極上下)を見つけ解決しました。