

【巻頭フォーカス】
バッチプラントのスマート製造と関連規格 ―視点および論点
1.はじめに
Digital Transformation(DX)という用語は,IECのスマート製造に関する用語及び定義に関する技術報告書(TR)1),IIC Vocabulary Technical Report2),およびPlatform-i40 Glossary3)のいずれにもエントリがない。しかし, Digitaization/Digitalizationとも異なるカタカナの「デジタル化」ではないことは明らかであろう。「Digitaization/Digitalization を通じて『スマートに』Operational Excellenceを実現すること」とでも解せばよいだろうか。
いずれにせよ,ここでDigitalは単なる便法であり,関心事は業務オペレーション(モデル的な言い方をすれば,業務プロセスモデル)である。昨今のAIブームもあってかData Centricが持て囃される向きもあるが,業務において利活用すべきは単なる「データ」ではなく,意図や意味,文脈(コンテキスト)を含んだ「情報」であるはずである。 また,この関心事はData Centricと相性のよろしい自然科学的な現象ではなく,Simon4)が言うところのArtificialなものである。Data Centricがまったくダメというわけではないが,やはり明示的な情報モデル,それも概念モデルについて議論するほうがより健全であるようにも思われる。
そこでここでは,バッチ製造の種々の情報を,できればスマートに,取り扱うための標準モデルについて論じたい。筆者が標準化国内委員会に参加しているものを中心にそれらの動向を紹介しながら,視点や論点の私見を述べる。
2.スマート製造のための統一リファレンスモデル
2.1 動向
スマート製造に関するISOとIECのジョイント・ワーキンググループJWG 21にて審議されていた統一リファレンスモデルに関する標準規格IEC63339, Unified reference model for smart manufacturing5)(URMSM)が2024年10月に発行された。既存のRAMI 4.06)やIIRA7)といったスマート製造リファレンスモデル(SMRM)を参考にしながら8),それらが満たすべき要件を規定している(図1)。

URMSMはリファレンスモデルのメタモデルという性質上,抽象度の高い概念的なモデルを複数種類用いている。そのためURMSM規格は残念ながら,情報学的なモデリング論に慣れていなければ,実際に利用者が理解,活用するのが難しい面のある規格となっている。そのことはJWG 21でも認識されており,現在,いわゆるクックブックに相当するURMSM適用に関する技術報告書(TR)10)を準備中である。
2.2 視点・論点
URMSMの利用者としては,まずSM標準の開発者が挙げられる。SM実務者も様々なSMRMに基づく実装(または実装モデル,Smart Manufacturing Implementation Model;SMIM)間のインタオペラビリティ/インタコネクティビティを確保する場面では,URMSMに立ち戻って各SMRMの階層がどのように対応するのかを判断する必要が生じることも考えられる。 現在,どのSMRMもいわゆる「業務プロセスモデル」が構成要素として前提となっている。上位のBusiness層と下位の Asset/Implementation層をつなぐ中間の業務機能に関する層である。合目的的に規定しやすい面のある上位層や具体性の高い下位層と比べてこの層はモデル化が難しい。業務の具体的なインスタンスは描けたとしても,そのプロセスをボトムアップ的に汎化したモデルとして表すことは不可能である。その逆の方向に,まず明示的な業務プロセスモデルを規定し,それに従って具体的な業務インスタンスを発生させるようにしなければならない。そのような時にこそ,URMSMは業務の見方や考え方に関する指針を与えてくれるものであると考える。 3.バッチコントロール 3.1 動向 バッチ製造およびそのコントロールのモデル化であるISA-88 Part1は,改訂版が2010年に発行されたが11),対応する国際標準規格IEC61512は長らくED2が発行されないままであった。数年前にIEC61512のメンテナンスを担当するSC 65A/MT 61512が設立され,現在,ED212)の最終国際規格案(FDIS)が審議中となっている。 IEC61512 ED2ドラフトは,大枠はISA-88改訂版を踏襲しながら,“standard of standards13)”との適合性(ISA-9514)/IEC 6226415)機能階層モデル)を考慮してか,根幹となる階層モデルのひとつISA-88のPhysical Modelに相当するモデルがRole Based Equipment Modelという呼称となり,Process Cellより下の階層(Unit,Equipment Module,Control Module)がPhysical Equipmentとしてひとまとめにされている。 また,ISA-88の特徴的な3つの階層モデル(Process Model,Procedural Control Model,Physical Model)の関係を表す図では,Physical Modelの代わりにISA-88にもあったEquipment Entity Model(こちらはISA-88同様,Unit以下の階層も展開)が使われている。これらの違いは,実用上は形式的に単なる読み換えで済むものなのかも知れないが,概念上は大きな変更である。 ISA-88では従前のトピックに加えて,以下に関する文書化がワーキンググループで議論されている。 ・Abnormal Situation Management(ASM) ・Design, Interface ・(広義の)Operation なお,後述のNAMUR Module Type Packages(MTP)もトピックとしてあがっているものの,具体的な議論はこれからとのことである。 また,バッチではなく連続プロセスを対象とするが,TRとして発行されていたプロシージャ・オートメーションに関するISA-10616,17)が,2023年に正式な規格として発行された18)。ISA-106は,ISA-18.219)やISA-10120)等のプロセスオートメーション(PA)関連規格で採用されているライフサイクル・アプローチを採っていたり,階層的なBasic Process Control System(BPCS)コンポーネントがFisherのBatch Control Systems第1版21)でも参照されているPurdue Reference Model for CIM22)を思わせる構造をしていたりと,ある意味においてISA-88を補完する側面も持ちあわせている。 3.2 視点・論点 最近のPA関連規格群は,個々の独立した規格というよりも,相互に密接にかかわり合う,一緒にあわせて考慮すべきものであると認識することが重要である。特にスマート製造という文脈において,この認識がより重要となり,スマート製造システムのIntegrityを確保するために統合的な視点が不可欠となる。 IEC61512 改訂に際して加筆されることを期待したが,ISA-88ではスコープ内のコントロール・アクティビティであるとされながらも,ISA-95 Lv.3:Manufacturing Operations Management(MOM)に相当するアクティビティに関する記述が足りていない。 Lv.3機能ではあるが,バッチ間の順序関係を決定するバッチ・スケジューリングがCoordination Controlのためには欠かせないが,ISA-88は1つのバッチ内のコントロールを主眼としており,複数のバッチ間の関係に関しては基本的に言及していない。この辺りが,ISA-95とISA-88とのギャップにもなっている。 時代的にオブジェクト指向の影響を色濃く受けたISA-88は,本質的にモジュール化と相性が良い。この点に関しては後述のMTPにて再度議論する。 4.Module Type Packages(MTP) 4.1 動向 NAMURの提唱するMTP23)は,モジュラシステムのエンジニアリング概念を定義するものであり,国際標準化審議がIEC/SC65E/WG14にて提案されている。基となると思われるVDI/VDE/NAMUR 2658の部構成(表1)を見ると,その対象範囲はプロセスオートメーション全般に関した多岐にわたるものとなっている。現在のところはIEC規格でもその部構成を踏襲した提案となっている。 MTPでは,個々の機器モジュール(Process Equipment Assembly;PEA)を組み合わせ,PEA間にまたがるProcess Orchestration Layer(POL)が全体の協調を図ることによって,柔軟な生産システムを迅速に構築可能とする。MTPはIndustrie 4.0のPlug&Produceコンセプトを実現するソリューションのひとつと目されている(図2)。 現在は,業界団体PROFIBUS & PROFINET International(PI)がホストとなって,MTPに関する仕様書作成や認証テストを主導している26)。 4.2 視点・論点 概念実証(PoC)27,28)では,モジュールパッケージの構成単位が設備機器に寄ったものという印象であった。しかしながらMTPのモジュール(PEA)は,化学工学という学問分野の体系において根幹となっている「単位操作(Unit Operation)」をスマート製造の文脈で実装したものとみなすこともできる。1900年代初頭に提唱された単位操作も,スマート製造という文脈に沿ってそろそろ捉え直してもよい頃合いであろう。 MTPの考え方はバッチプロセスばかりでなく,連続プロセスに対しても有用である。特にISA-106が対象としているようなスタートアップ/シャットダウン時等におけるブロック運転を考える上では,MTP的なモジュール化の概念が重要となっていくものと考える。さらに,MTPモジュールはPEAという名称が表すように,アセンブリ系の離散型製造とも親和性が高い。モジュラという概念は,ISA-95 Lv.2の各コントロール(連続,バッチ,離散)を包括的に扱うための仕組みとなり得るポテンシャルを有している。 MTPのモジュール化は,プロセス/プラントのみならず,必然的にそれらのエンジニアリング・アクティビティ自体をも対象とすることに留意しなければならない。すなわちMTPの方法論は,これまである意味でアート的な側面のあった業としてのエンジニアリングを,技術としてパッケージングすることにつながる。 一方で,まだまだ議論を要する点もある。前述のように,モジュール間の協調はPOLにて行う。ISA-88のバッチ内/バッチ間と同様に,MTPにおいてモジュール間のCoordination Controlをどのように実現すべきか,少なくとも現時点では定かとなっていない。スケジューリングに関しては,ここでも問題となるであろう。 ところで,MTP以前の2000年前後,自律分散システムによる次世代Intelligent Manufacturing System(IMS)に関する議論があった。スマート製造に関するキーワードの一つに「自律性(Autonomy)」があるが,IMSで議論された方法論がMTPに応用できないだろうか? 手前味噌となり恐縮ではあるが,筆者は当時バッチプロセスを対象とした自律分散型スケジューリング29)を研究テーマとしていたこともあり,IMSでの議論はMTPにかなり良く適合すると考えている。 5.今後必要となる視点・論点 ISA-88の源流のひとつはNAMURであり30),NAMUR MTPはISA-88,ISA-95, ISA-106をベースとしている27)。 〈参考文献〉 1)IEC TR 63283-1:2022,Industrial-process measurement,control and automation-Smart manufacturing-Part 1: Terms and definitions 2)IIC, Industry Internet of Things Vocabulary, Ver.3.00, 2022. 3)https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Industrie40/ Glossary/glossary.html 4)ハーバード・A・サイモン:『システムの科学(The Sciences of the Artificial』,第3版,パーソナルメディア(1999) 5)IEC 63339 Ed. 1.0:2024, Unified reference model for smart manufacturing. 6)https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/ Publikation/rami40-an-introduction.html 7)https://www.iiconsortium.org/iira/ 8)IEC TR 63319, A meta-modelling analysis approach to smart manufacturing reference models(ドラフト). 9)Richard Martin, IEC 63339 Unified smart manufacturing reference model, INCOSE, 2022. 10)IEC TR 63597, Application of IEC 63339 to Smart Manufacturing Reference Models(ドラフト). 11)ANSI/ISA-88.00.01-2010, Batch Control - Part 1: Models and Terminology. 12)IEC 61512-1 ED2, Batch control - Part 1: Models and terminology(ドラフト) 13)Dave Emerson, The Open Process Automation Standard takes flight, ISA InTech, May/June 2019. 14)ANSI/ISA-95.00.01-2010(IEC 62264-1 Mod),Enterprise-Control System Integration-Part 1: Models and Terminology. 15)IEC 62264-1:2013,Enterprise-control system integration. 16)ISA-TR106.00.01-2013, Procedure Automation for Continuous Process Operations-Models and Terminology. 17)ISA-TR106.00.02-2017, Procedure Automation for Continuous Process Operations-Work Processes. 18)ANSI/ISA-106.00.01-2023,Procedure Automation for Continuous Process Operations. 19)ANSI/ISA-18.2-2016,Management of Alarm Systems for the Process Industries. 20)ANSI/ISA-101.01-2015, Human Machine Interfaces for Process Automation Systems. 21)Thomas G. Fisher, Batch Control Systems: Design, Application, and Implementation, ISA, 1991. 22)https://www.pera.net/Pera/PurdueReferenceModel/ ReferenceModel.html 23) https://www.namur.net/en/focus-topics/automation-modular-plants.html 24)PI,Module Type Package,Plug and Operate for Process Industries-Status and Roadmap, 2024. 25)ZVEI Status Report, Process INDUSTRIE 4.0: The Age of Modular Production, 2019. 26) https://www.profibus.com/newsroom/press-news/mtp-activities-have-picked-up-speed
27)ZVEI White Paper, Module-Based Production in the Process Industry-Effects on Automation in the “Industrie 4.0” Environment, 2015. 28)ProcessNet White Paper, Modular Plants: Flexible chemical production by modularization and standardization-status quo and future trends, 2016. 29)北島禎二ら:「メッセージ交換を用いた分散型スケジューリングシステムの並行実行性能評価」,『計測自動制御学会論文集』,Vol.35,No.4,546-553(1999) 30)NAMUR NE 33, Requirements to be met by Systems for Recipe-Based Operations, 1992.
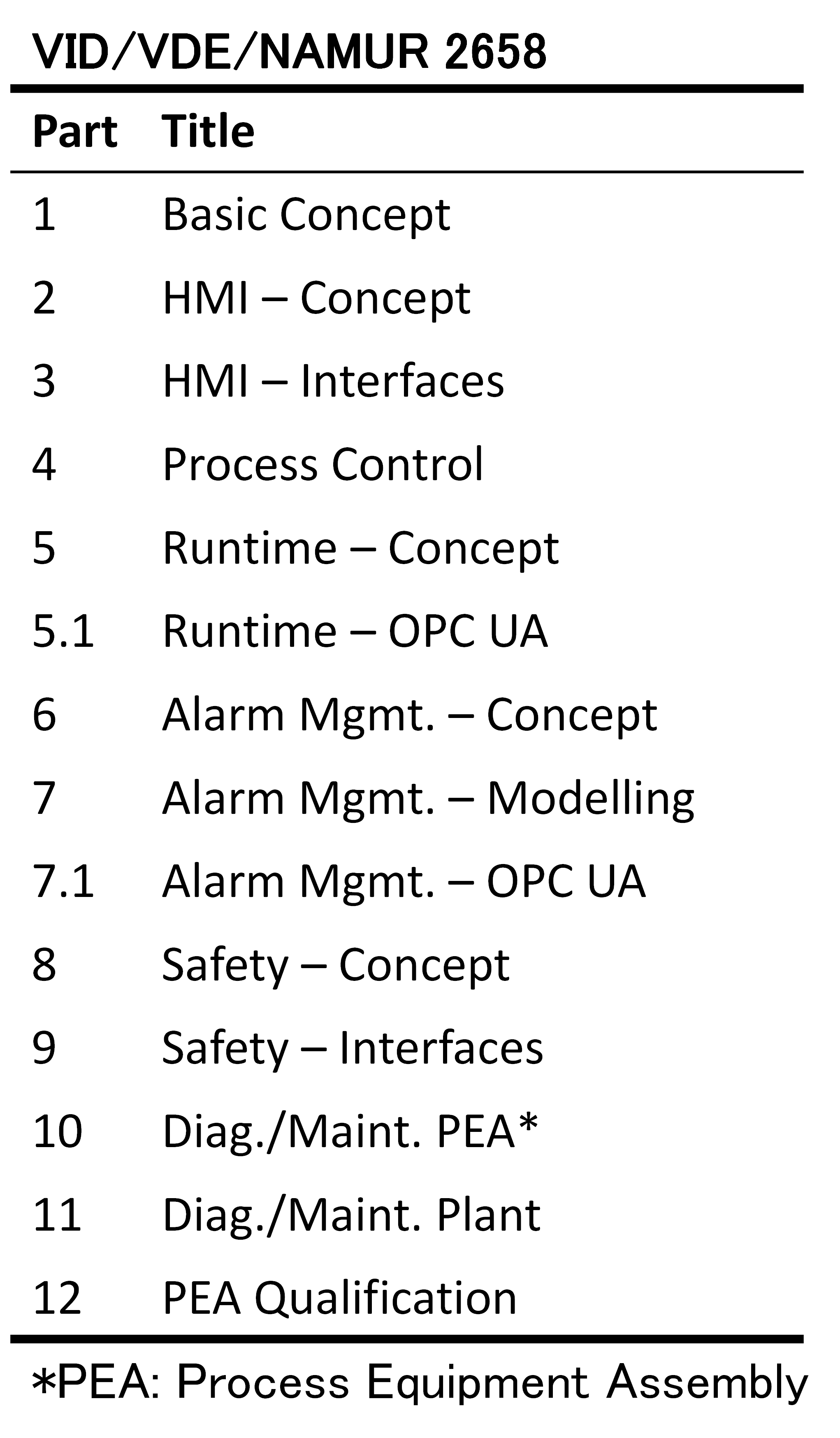
表1 MTP規格の部構成24)

図2 モジュラ・プラント・エンジニアリング25)
ポータルサイトへ