

【トレンド】
統合情報サーバによる 設備統合監視・リモートオペレーションの実践適応法
1.はじめに
プラントは,必ずしも1箇所に集中して所在しているわけではなく,離れた各拠点サイトに点在するケースも多くある。また,サイト内でも複数のプラントが存在し,そのプラント自身も様々な設備・機器から構成されており,それらを複数のシステムでそれぞれの目的に合わせた管理・操業を行っている。そして,多くの産業では原材料やオペレーションの複雑化の課題や,オペレータの高齢化が進み熟練者が減少することによるブラックボックス化などの問題が顕在化してきている。
そのような中で利益を意識した操業を実現していくには,単体のプラント内のみでの個別最適ではなく,プラント間・サイト間を超えた全体最適での設備統合監視操作および管理を効率的に行う必要がある。また,近年の技術動向としてビックデータ,AIやロボットなどをプラント操業に活用する動きが加速している。これらを実現するためには,プラントのデータを包括的に一元管理して,必要時には迅速にアクセスできる必要がある。
本稿では各プラントの生産・操業に関わる様々なデータ・情報の統合管理や各プラントを構成する多様なシステム(DCSや設備管理システムなど)の統合操作監視を通して,単一プラント内のシステム統合はもちろん,各サイトに広域にまたがった複数プラント全体を通したシステム・設備・機器の統合を実現できるシステム,統合情報サーバ(「CIサーバ」:Collaborative Information Server)について紹介する。
2.統合情報サーバ開発の狙い
CIサーバにはデータ統合,アプリケーション連携,リモートオペレーション,の3つの特長がある。以下ではそれぞれの特長について説明する(図1)。
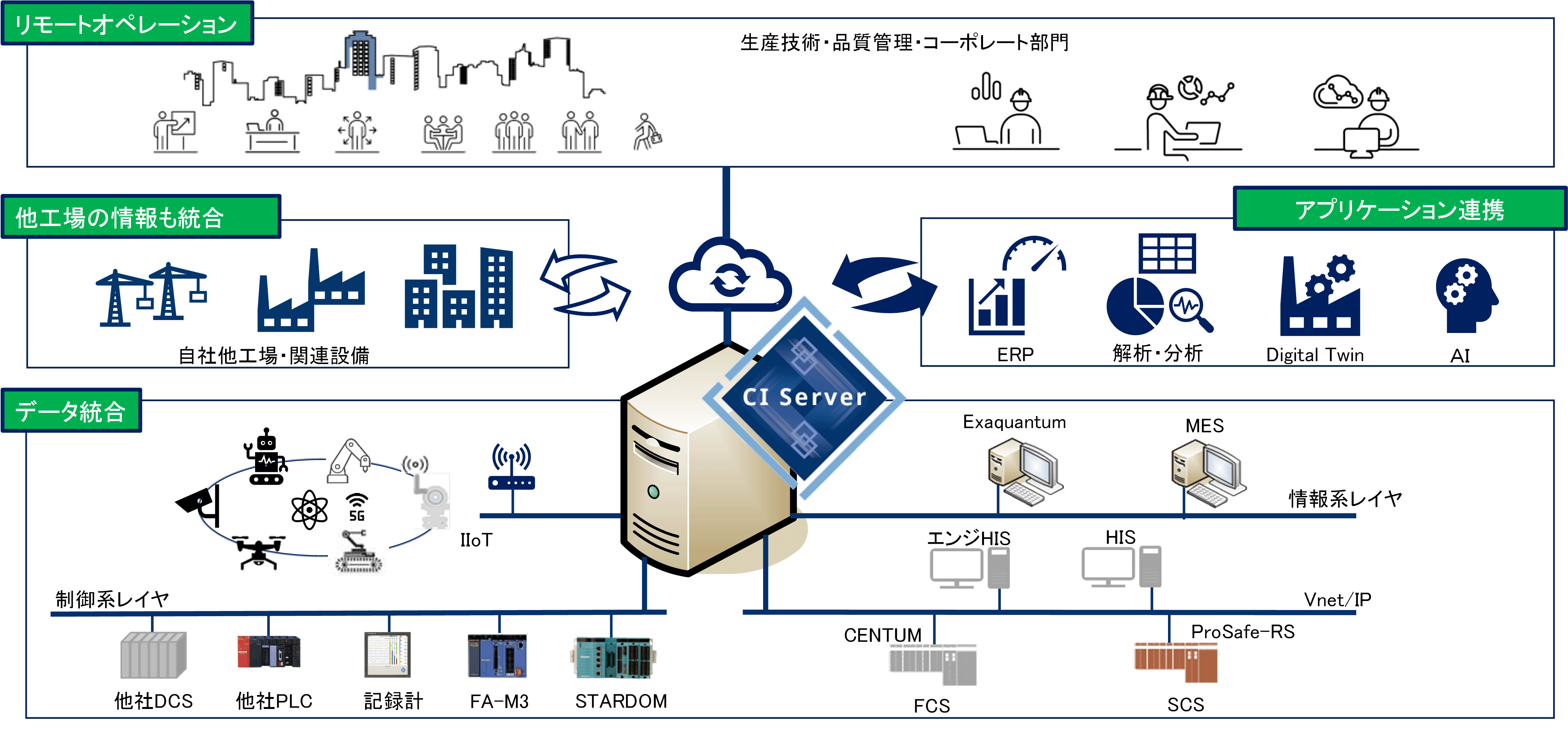
2.1 データ統合
CIサーバは最新の通信プロトコルから従来から活用されている通信プロトコルまで幅広くサポートしているため,これまで制御システムに接続されていなかった工場内の装置や各種センサやロボット,IIoT(Industrial Internet of Things)の最新センサ情報も一元管理し,操業改善の可能性を飛躍的に高められる製品である。
このようにCIサーバの特徴はデータ統合することにあるが,各サイト・プラント間にまたがる膨大な量のデータを統合することにより,これらをプラント操業に活用可能な付加価値のある情報へと変化させることが可能となる。
各サイト・プラント間により導入しているシステムが異なる場合,異なるシステム間のデータを利用するときには負荷が高い作業が伴う(他システムで必要なデータを集める,データを移動させる,自システムで使えるように変換する)。あらゆるデータが統合されることで,手作業で行っていた作業に伴うヒューマンエラーの削減,統合データのグラフ化やダッシュボードを用いた可視化など,データを都度変換することなく日々の作業がスムーズに進めることができるようになる。
2.2 アプリケーション連携
製造現場においては,現場オペレータが設備巡視作業などの定常業務を行っているが,作業範囲が広域であることから時間を要する。また高所や足場の悪い場所,粉塵が舞うなどの危険エリアがあることから安全性の点で作業員に大きな負荷がかかっている。そこで,プラントを自走し,人の代わりにデータ収集などの定常業務を行うロボットによる安全で効率的なプラント操業や保守を行い,人の作業を代行するだけではなく,人ができないことを実現する,ロボット管理コア(Robot Management Core:RMC)とのアプリケーション連携も可能になった。
また,データ分析やAIが急速に成長し,多くの業界でデータ活用が重要視されてきている。収集したデータを元に分析を行う場合,プラントのシステムや設備の一部からのデータを元に分析したとしても比較検討できるパターンは限定的になってしまう。統合されたプラントのあらゆるデータを取り込むことで,より正確で高度な分析を行うことができ,新たな対策や改善方法がわかる可能性がある(図2)。
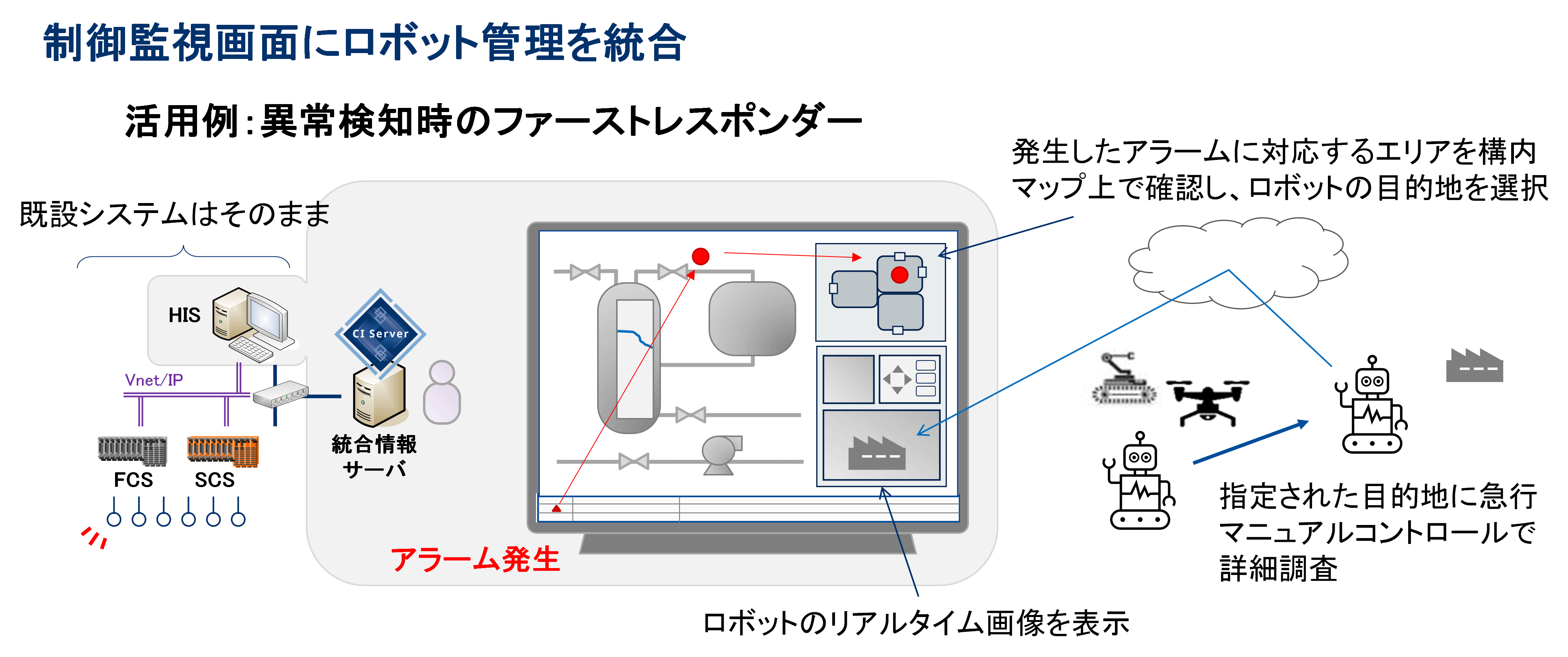
2.3 リモートオペレーション
システム・設備・機器の統合によってデータの集約を行うことで,中央監視室で一元管理されたデータを監視できようになる。加えて,CIサーバは遠隔監視操作(リモートオペレーション)を行うことも可能にする。リモートオペレーションのシステムを構築することにより,本社や他工場から設備の稼働状況の見える化が可能となり,遠隔地から生産状況のモニタリングや設備の操作,現場にいない意思決定者との円滑な連携を行うことで,生産性の向上と品質の強化を実現することができる。
離れた場所からリアルタイムな運転・操業が可能となることで,プラントの様々な役割を持った関係者がデータにアクセスすることになるが,その役割に応じて必要な情報が変わってくる。CIサーバでは現場オペレータ,設備保全,品質管理,コーポレートなど様々な担当に応じて閲覧や操作権限に制限をかけることで,意図しない操作や秘密情報漏洩を防ぐことができる。これらのことにより各関係者が同じデータベースの情報を共有し,その中から各々がデータを取得することで,必要な時に必要なデータにアクセスしてリアルタイムの情報共有を行い,プラント全体を通した統合オペレーションが実現できる。
次項ではリモートオペレーションを構築する方法について説明する。
(1)リモート監視システムの構築
CIサーバによって収集されたデータを遠隔地から監視できようにする。たとえば,他工場の運用状況を確認する,テレワーク中の自宅から現場の進捗状況を確認する,遠隔地の熟練者が監視画面を共有しながら作業を支援する,本社から各工場の生産状況を比較する,のような使い方が挙げられる。
また,遠隔地から監視できることは,監視業務の負担軽減につながり,設備間の移動時間も削減できる。CIサーバによる監視には,監視用アプリケーションをインストールしたPCを使用して行う方法のほかに,モバイル端末や業務PCの専用アプリケーションをインストールしていない端末を利用し,WEBブラウザ(GoogleChrome)経由で監視することもできる。これにより,現場にいなくても生産現場の状態や品質,生産性などをリアルタイムで確認できる。
(2)リモート監視操作システムの構築
CIサーバでは遠隔地からプラントの操作を行うことができる。遠隔地と現場をVPN接続やビジネスイーサネットなどでつなぎセキュリティ対策を行い,プラントの稼働状況や品質,生産状況などを遠隔 地から確認しながら,プラントの設定値変更や機器の操作を行うことができる。 ただし,遠隔からの操作の留意すべき点として,セキュリティ対策やリスクマネジメントを十分に検討することが必要となる。また,予期せぬ事態が発生した場合には,迅速かつ適切に対処する方法も検討しておく必要がある。 たとえば,リモート監視操作システムのみを構築するのではなく,リモートとの通信が切れた場合には現地でオペレーションができるように,現地でも監視操作できるシステムを構築しておくことは有効な対策と言える(図3)。 3.課題と進展方向 CIサーバには,以下のような課題がある。 (1)リアルタイム性への要求の高まり プラントの様々なデータを統合できるため,収集するデータ点数が膨大になる。具体的には,10万点のデータを扱う場合に全ての信号をリアルタイムな1秒周期で収集することはPCおよびアプリケーションの処理能力を超えてしまうため,たとえばデータは10秒周期で収集するように設定にするなどのシステム設計が必要になってくる。また,データの収集を速やかに行うための高速なネットワーク環境の準備が必要になる。 (2)セキュリティへのリスク サイバー攻撃の脅威は年々増加してきていて,国内外の様々な企業が被害にあう事例が発生している。しかも,日々進化して高度化している。CIサーバはデータ・情報を一元管理し,リモートオペレーションによるアクセスがあることから,CIサーバ単体だけでなく,ネットワークや通信機器も含めた全体のセキュリティに十分配慮が必要となる。通信の暗号化や,一般的なユーザ認証,アクセス制限などのセキュリティ機能と,当社が提供するセキュリティ対策サービスと組み合わせることで,今後ますます拡大していく脅威に対して,継続的な対応を行っていく必要がある。 (3)様々なデータソースの統合 CIサーバは様々なメーカの機器や通信プロトコルに対応できる特長があるが,近年多様化が進んでいるIoT機器やセンサの技術に追従していく必要がある。様々な通信による収集を一元的に実現するために,よりオープンなデータ連携を追求していく。 なお,今後の進展方向として,CIサーバをプラットフォームとした制御システムの自律(Autonomy)を目指していく。 4.制御システムの“自律化”へ向けて 現在,多くの製造業ではAIなどの先端技術の導入といった大掛かりな変革には至っていない。システムの多くは高度に構造化された一連の作業を自動的に実行している状態であり,人間が監視し,必要に応じて人間が指示を出すことで成り立っている。AIやロボットの飛躍的な進化を踏まえると,将来,工場の設備や操業システム自体が学習能力や適応能力を持ち,人間の監視や指示がなくても自律的に操業できるようになると考えられる。 この状態を自律(Autonomy)と考える。横河電機では,この「自律」状態を,制御システムの将来のあるべき姿と考え,「自動化から自律化へ (IA2IA:Industrial Automation to Industrial Autonomy)」と称して,制御システムの自律化を目指していく(図4)。 CIサーバは,プラント内の様々なデータを統合して,アプリケーション(AIやロボット)と連携して情報を提供し情報を受け取る,離れた場所から設備の状況を確認する,これらの機能を用いて将来のあるべき姿を実現するプラットフォームの役割を担っていくシステムである。 IA2IAによる「自律」の実現は,現在の制御システムから見れば革命的とも言える。しかしその歩みは,決して一足飛びで実現されるものではない。横河電機は,「革新と,安全・安心の両立」を実現することが必要であると考えている。これまでのシステムと現場の努力で獲得してきた安全・安心はそのまま維持し,それに対して「外付け」で新しい機能を追加することで,革新とリスク回避を両立させ,かつ経済的にも優れた進化を実現できると考える。 〈参考文献〉
1)佐藤邦明,塩野敏泰,棚村崇史,中村江里:「次世代制御システムのビジョンと取り組み~自律化の実現に向けて~」,『第164回制御技術部会大会資料』,(一社)日本鉄鋼協会 生産技術部門,2021年6月
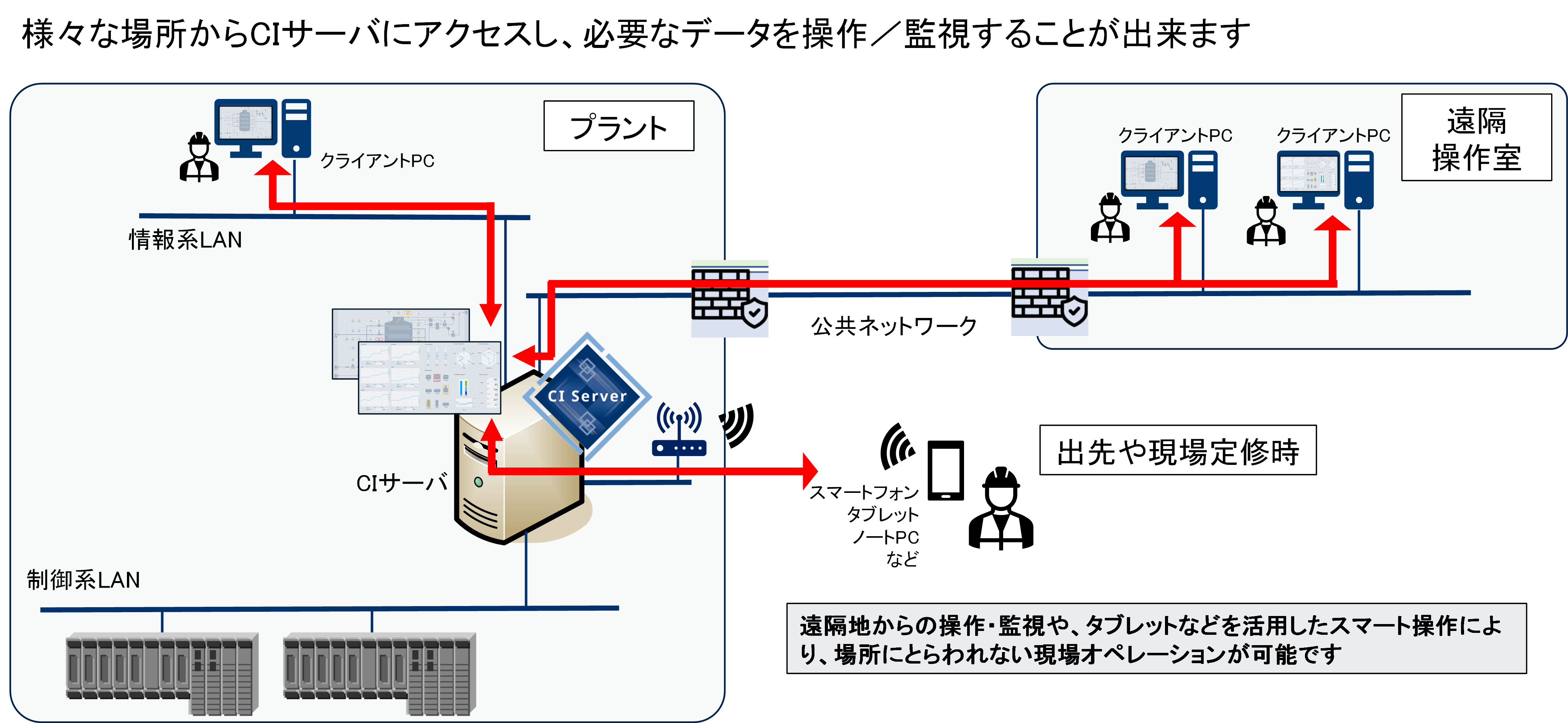
図3 リモートオペレーション

図4 自動化から自立化へ「IA2IA」
ポータルサイトへ