

【トレンド】
グラフィックな可視化技術が拓く リモートオペレーション
1.はじめに
1980年代,UNIXワークステーションとともに対話的でグラフィックなユーザインタフェース(GUI/HMI)を実装したオペレーション卓が標準的になった制御システム(DCS/SCADA)は,その後,LinuxとWindowsへ,開発フレームワークもC/C++からActiveX,Java,.NETへと展開されてきた。
米国SL(Sherrill-Lubinski)は,1983年の創立以来40年以上にわたって,監視データのグラフィックな可視化とエディタ技術で,制御システムの開発とシステム更改を長年支えてきた専門メーカである。
SLユーザにおいて開発されてきた制御システムのライフサイクルは10年前後に及び,欧米では1980年代より,日本国内では創業した1991年以降,当時はX端末やActiveX,Javaを使って遠隔監視が実現され,その後,.NET,リモートデスクトップサービス,そして近年ではHTML5によるクラウド運用のオペレーションも展開されてきた。
本稿では,監視制御システムのダイナミックGUI/HMIならびに専用カスタムエディタの開発ツールである「SL-GMS(米国SL社製グラフィカルモデリングシステム)」の突出したグラフィックな可視化技術が,いかに柔軟なリモートオペレーションを拓いてきたかを,国内ユーザ事例の数々からまとめる(図1)。
2.制御室を越えてリモートオペレーションへ
近年の市町村合弁(公共)やサービス管轄拠点の統廃合(企業)などを背景に,より少人数で広域を運転管理するプラントのオペレーション環境は複雑化している。その最適化と制御システムの維持継続が求められる中,Web化ならびにリモートデスクトップ運用による遠隔監視が進行し,さらにはクラウド運用の監視を目的としたHTML5へのニーズが高まっている。そして,安全で安定したプラント操業における運用面コストや要員不足が,コロナ禍をきっかけに,一段とリモートオペレーションを加速化しているようだ。
SLユーザシステムで観られるリモートオペレーションの適用例は,以下の通りである。
1)プラントや工場における制御室内の制御システムと同じグラフィック操作画面で,場内における情報系部門のほか,場外に点在する関連部門,サービスセンタ,管理・委託会社,在宅勤務などから,昼夜を問わずWeb運用またはリモートデスクトップ運用されているサーバにアクセスして閲覧操作可能。
2)広域に分散した変電所や浄水場などの施設設備,遠制局,遠隔制御装置,情報伝送制御装置,電流計・水圧計や各種センサなどの様々な機器装置から,リモートにある中央管理センタやO&M(運転・保守) サービスセンタの二重化されたサーバへ24時間ノンストップでIPネットワークによって監視制御データを収集;
-リモートにあるバックアップ管理センタのサーバと連動し,それぞれの管理センタにおける制御システムの操作卓と同じグラフィック監視制御画面をWebサーバで配信し,リモートにある関連部署や関連事務所からも閲覧操作できる。
3)プラント現場で産業用サーバに収集される測定データを,別の場所にあるグラフィックな操作卓を使って構内ネットワークで監視制御;
-1対1の場合もあり,旧ターミナルサービス (LinuxではX端末),現在のリモートデスクトップサービス(Linuxの場合にはVNCサーバ)が使用されることが多く,イントラネットでWeb運用されることも少なくない。
4)近年HTML5で実現されるようになったのが,複数のプラントや建屋などの設備を管理する中央監視制御システムを,クラウドサービスとして提供するものだ。施設内における設備機器の稼働状態は,測定データを定期的に収集してクラウドに蓄積することで,インターネット上のダッシュボード画面を使って常時監視できる。そして,遠隔操作で設備機器のオンオフ制御や運転計画を行える。
クラウドサービス化により,常駐管理者が不在でも遠隔から監視や制御ができ,複数のプラントや建屋の一元管理や休日夜間対応などが可能になる。
3.リモートオペレーションを拓いてきた,SLのグラフィック可視化技術
リモートオペレーションにおける制御システムの開発では,多種多様の要求仕様に応じた高機能で高性能なグラフィック操作画面を短時間で開発し,さらに現場における設備変更や増設,機能拡張,マシン入替えなどに伴うグラフィック操作画面の更新にかかる保守費用を最小限に留めることが要求される。
そして,デスクトップ運用で開発された制御室のコンテンツリッチで高対話性のグラフィック操作画面を,そのまま変更することなくWebまたはリモート運用できることが必然だ。柔軟な適用が問われる監視制御システムの可視化においては,その都度スクラッチでグラフィック操作画面をつくり直すことでは,対応できない。
C/C++,ActiveX,Java,.NET Framework,HTML5,そして.NET 8(.NET 6)のそれぞれで対応してきた「SL-GMS」各製品では,共通の「SL-GMSDraw」ダイナミックグラフィックエディタを提供している(図2)。
とえば,圧力計や流量計,バルブや配管などの相互関連性を持った多数の機器装置で構成されるグラフィック系統図画面の開発では,しきい値で警報色が変わる,機器のオンオフ,バルブの開閉など,様々な動的属性を持ったグラフィックモデルを,アプリケーションから独立して対話的に作成する。そして,次々とコピーしてそれらの形状,動的属性,接続データ変数を変更しながら多数展開し,それらの動的振る舞いをすぐSL-GMSDrawエディタ内でプレビューして確認できる。同様に複数の画面へと展開可能だ。
これにより,GUIの開発ならびに保守コスト増加の2大要因である仕様変更と,データモデル/API変更にも容易に対応可能で,つくり直し工数を大幅に削減できるようになっている。さらに,SL-GMSでは制御システム固有のカスタムエディタを簡単に構築できるツールを提供しており,現場における設備変更や増設にもポイント&クリック操作による編集環境で簡単に対応でき,案件ごとやエンドユーザ顧客ごと,またシステム更新における画面の作成・変更・保守でコストを一層削減し,すぐにリモート/Web運用に展開できる。
そして,SL-GMSDrawエディタで作成したグラフィックモデルとSL-GMSのAPIは,40年にわたって旧バージョンから上位互換性を保持し,ライフサイクルが10年以上に及ぶ制御システムの最も容易な移行を長年支え続けている。
4.リモートオペレーションにおける可視化技術の変遷
これまで,リモートオペレーションにおけるSL-GMSユーザシステムのWeb化は,ActiveXからJava(アプレット,JavaWebStart),Microsoft .NET (XBAPとWPFによるリッチクライアント,ClickOnceによるWebでアプリケーション起動),Windows ServerによるリモートデスクトップWebアクセス,実行中の表示画面を周期的にイメージとして生成するSL-GMSのAPIによる画像Web配信,そしてHTML5へと展開されてきた。比類なくコンパクトで高速なSL-GMSでは,一貫してデスクトップ用に開発した同じ高対話性のグラフィック画面をそのまま,かつローカル運用と同等の高い性能でWeb/リモート運用展開できることを保持し,リモートオペレーションのニーズに応えてきた。
これによって,アプリケーション開発とその保守で約6~7割が影響受けるHMI工数を削減し,遠隔監視におけるネットワークやセキュリティなどに注力することが可能になる。
5.HTML5版「SL-GMS Web/Developer」でクラウド運用へ
SL-GMSは,1983年以来,真のオブジェクト指向技術アーキテクチャを持ったパイオニアツールとして,その後の新機能,拡張,新しいOSやフレームワークへの対応,さらには新製品の開発において,絶対的な優位性を実証してきた。
そして近年,クラウド運用を目的としたWeb運用選択肢として,幅広いブラウザと端末を使用できるHTML5への要求が増え,2020年9月にHTML5版「SL-GMS Web/Developer」新製品をリリースした。
従来のSL-GMS製品(C++,ActiveX,Java,Microsoft .NET)で提供されてきた同じSL-GMSDrawエディタで作成したグラフィック操作画面を,HTML5ならびにJavaScriptを使ったWebブラウザでクラウド運用することを目的に開発された新製品である(写真1)。
SL-GMSDrawエディタで様々な動的属性を持ったグラフィックモデルを対話的に作成し,エディタ内ですぐにその動的振舞いを確認した操作画面は,SL-GMSのHTML5コードジェネレータを使って,比類なくコンパクトで高速なHTML5コードに生成される。
これは,25数年以上前の1998年に,SL-GMS J/Developer(Java)のコードジェネレータによって生成される桁違いにコンパクトで高速なJavaアプレットと同様に,SLが長年培ってきた描画技術とグラフィックコード生成技術により,高対話性で高性能な監視画面のHTML5によるWebブラウザ運用を実現している。
SL-GMSDrawエディタで作成して保存したm1形式のモデルを,SL-GMS Web/DeveloperのHTML5コードジェネレータを起動してHTML5ファイルに変換する。そして,変換したHTML形式のモデルファイルを読み込んで表示実行するためのJavaScriptランタイムライブラリ(API)と,カスタム機能(画面初期化,データ変数の定義,変数データ値の更新など)を含む,ブラウザアクセス用の「HTMLサンプルファイル」を提供している。これらのファイルを変換したHTMLモデルファイルとともに,サーバに配置し,ブラウザでアクセスするだけでWeb運用できるようになっている。
その後,2021年にリリースしたV2.0a,V3.0aでは,JavaScript(HTML5)の組み込みグラフ(棒グラフ,トレンドグラフ,円グラフ)とテーブルを追加し,詳細画面へのドリルダウンや複数レイヤによるオーバレイ機能などを追加。これらにより,複数現場における制御システムからのIoTデータを集約して一元監視するリモートオペレーションダッシュボードの開発も支援強化している。
さらに,2022年にリリースしたV4.0aでは,オーバービュー小窓やブリンク機能など,従来の SL-GMS製品(C++,Java,.NET)による開発でよく実装されてきた多彩なグラフィック機能を HTML5版に追加し,制御システム(DCS/SCADA) のブラウザ運用を一層強固にした。そして,2023年にリリースした最新V4.1a では,テーブル列に SL-GMSモデルを表示,テキストとオブジェクトの輪郭をグロー表示で強調する属性,Webフォントのサポート,パネルのコンテンツを印刷できるメソッドなど,細部に至って小回りが利く新しい機能の数々が追加され,制御システム(DCS/SCADA)の Web化とクラウド運用監視ダッシュボードの開発をより強化し,リモートオペレーションを促進している(図3)。
6.おわりに
国内においても1991年来,主要なDCS/SCADA製品やソリューションにSLの可視化とエディタ技術が組み込まれ,浄水場・焼却炉,発電所・変電所,空港・鉄道・道路,宇宙・防衛,工場・ビルなどにおける様々な監視制御システムで稼働し,日本の社会インフラを支えるシステム構築の一端を担ってきた。そして,SLユーザの制御システムは1990年代より多種の技法によってWeb/リモート化され,SLの可視化技術は,リモートオペレーションを拓いてきた。
本稿でまとめている内容の国内ユーザ事例とデモンストレーションについては,弊社のホームページから参照できるほか,Webセミナで実際の画面とともに紹介している。
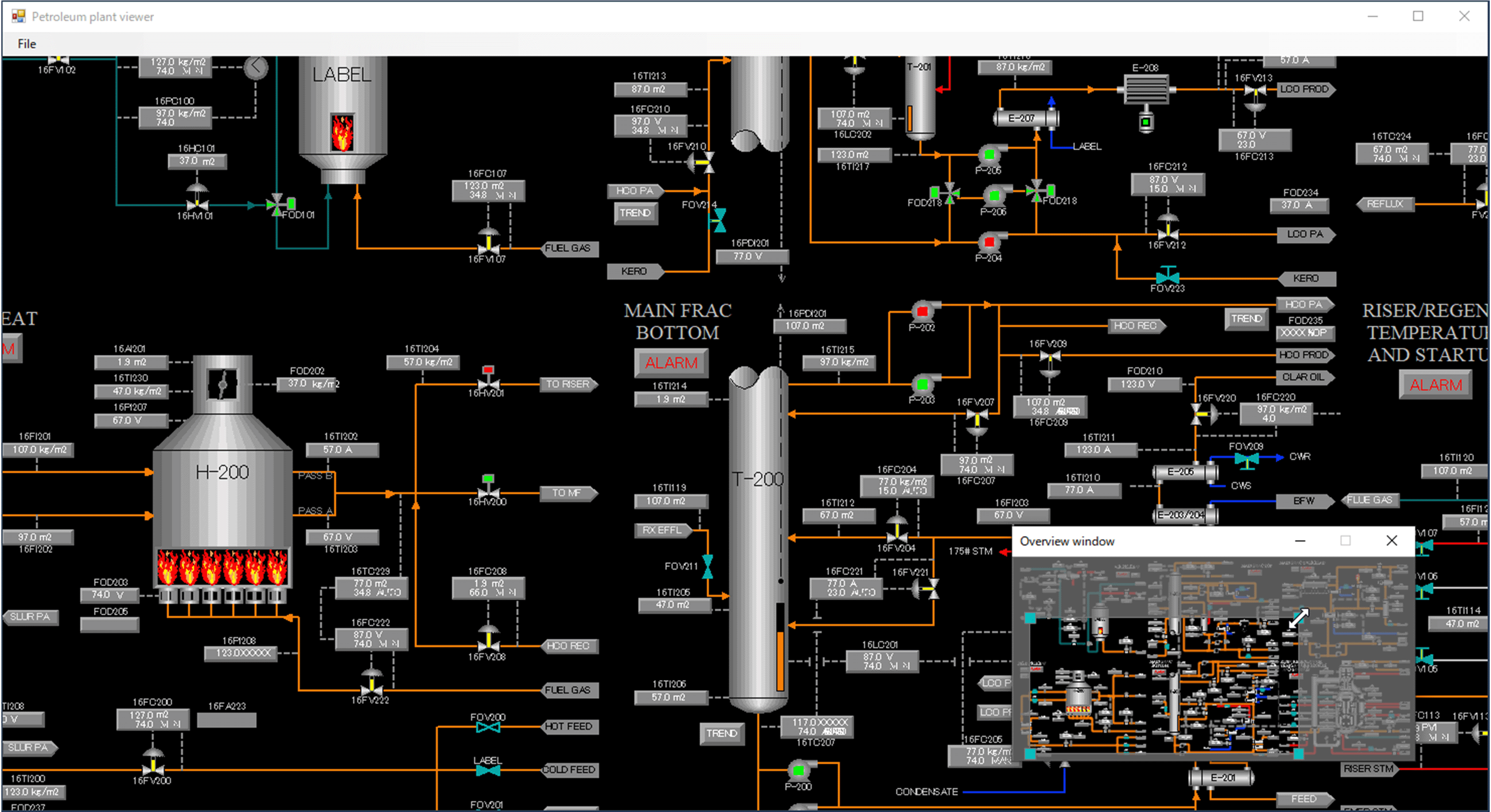
図1 リモート/Web運用されるグラフィック系統図をオーバービュー小窓で高速にズーム/パン
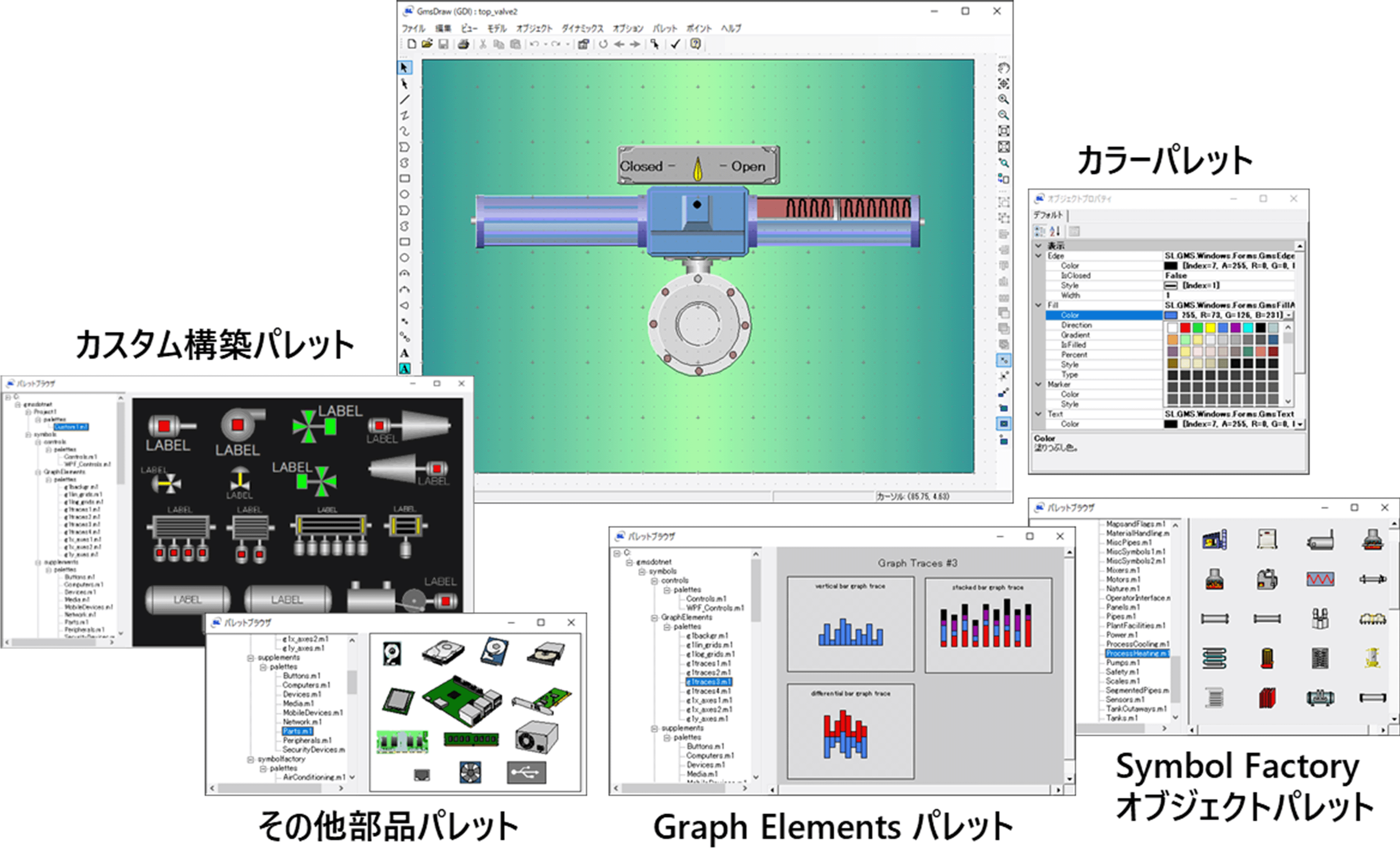
図2 C++,Java,.NET,HTML5各製品で共通の 「SL-GMSDraw」ダイナミックグラフィックエディタ
た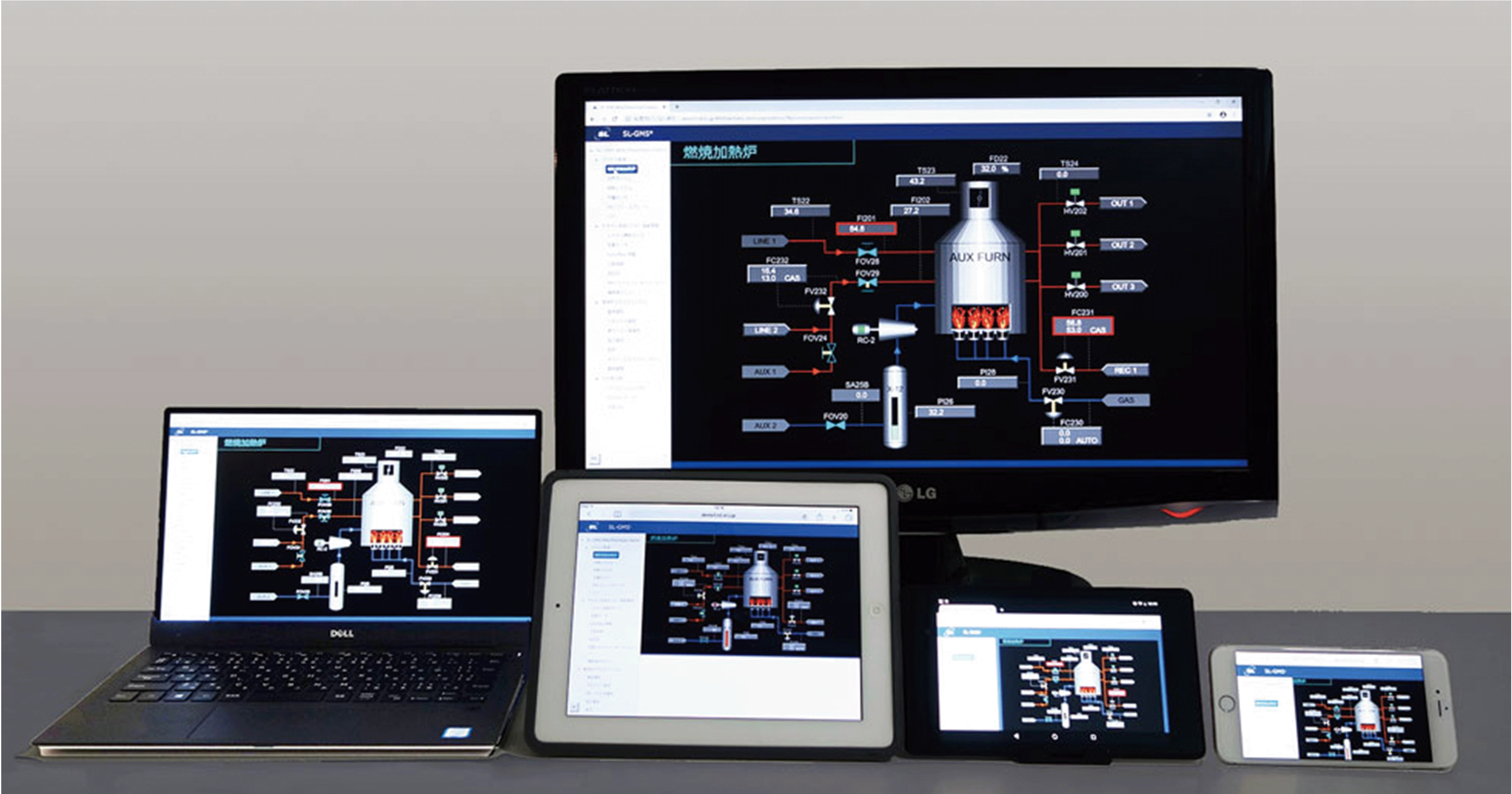
写真1 制御室と同じグラフィック操作画面を,コンパクトで高速なHTML5に変換してブラウザ運用
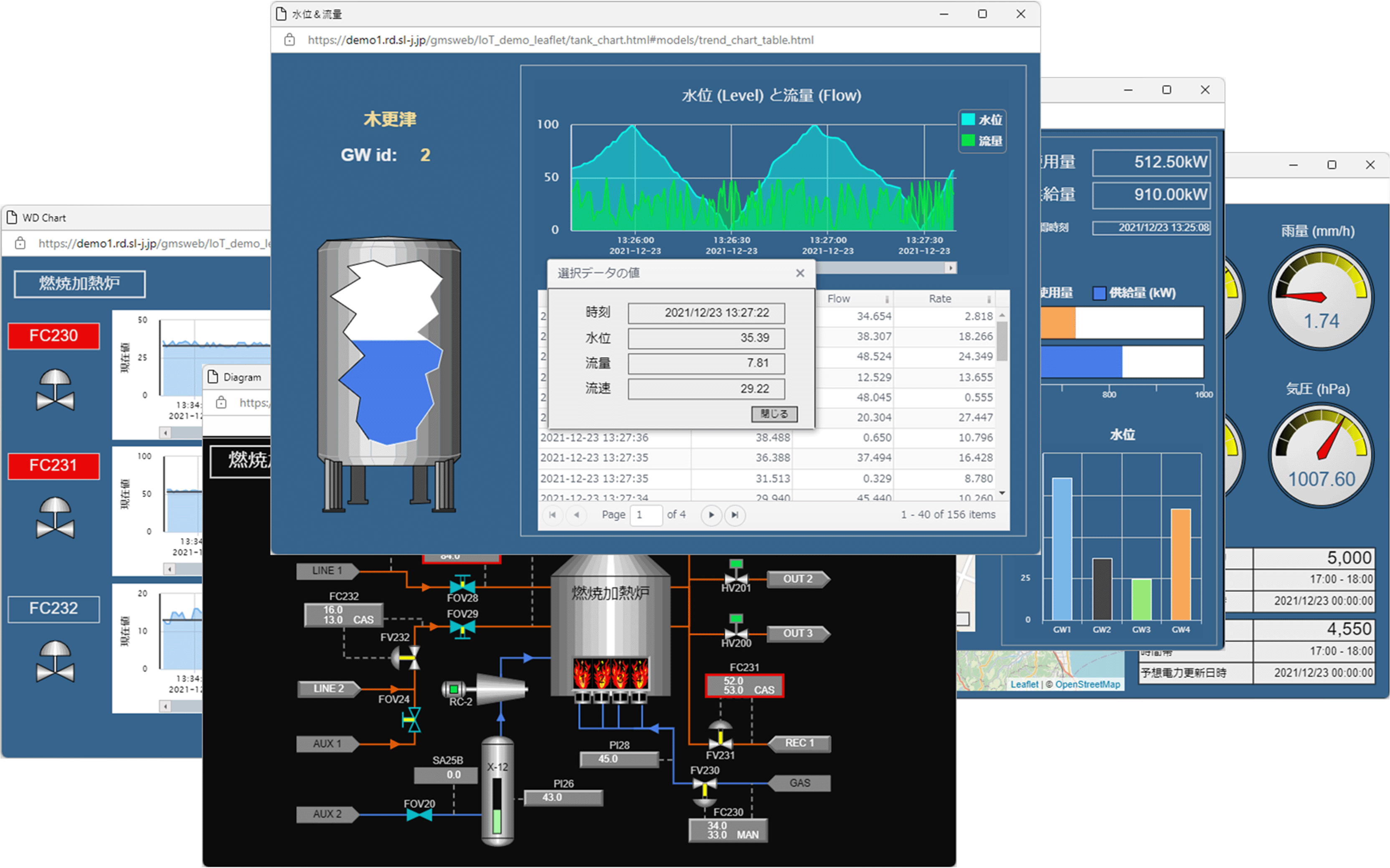
図3 リモートオペレーションにおけるクラウド運用の監視ダッシュボード
ポータルサイトへ