

【New Products】
高放射率を有する平面黒体炉が実現する 非接触温度計の正確な校正
1.はじめに
産業界における非接触温度計測のツールとして,放射温度計やサーモグラフィが利用されており,生産ラインでの移動体の温度計測や,設備の監視,建築物の診断など,様々な用途に用いられている。ここ数年はコロナ禍の影響もあり,非接触かつ短時間で体温を測る需要が増し,サーモグラフィによるスクリーニングのほか,ハンディ形の額式体温計やタブレットタイプの体温計が広く普及することで非接触の温度計測が身近になった。
このような温度計は,測定対象物から放射される赤外線を内部の素子で検出して温度に換算しており,これらの温度計に目盛付けする際の基準放射源として黒体炉が使用される。黒体炉の性能を示すパラメータの一つに,“放射率” がある。一般的に,光を透過しない物体では,以下の関係が成り立つ。
ε(放射率)+γ(反射率)= 1
入射光を全く反射しない,放射率1の物体は黒体と呼ばれ,黒体温度と放射エネルギーの関係はプランクの放射則で示されている。弊社は放射温度計やサーモグラフィといった温度計を製造・販売しており,出荷調整する際は任意の温度に加熱した黒体をこれらの温度計で視定して目盛を付けている。
放射率が完全に1である理想的な黒体は現実には存在しないが,黒体炉にとって放射率は1に限りなく近い方が望ましい。黒体の放射率が低い場合の問題点として,温度計を校正する際に温度誤差が大きくなるほか,周囲の熱源(温度計自身も含む)や周囲温度が背景放射となって黒体面で反射し,温度計に入射することで誤差となることがある。
産業技術総合研究所(以降,産総研と言う)と共同で,このような問題を解決する高放射率の平面黒体炉を開発したので紹介させて頂く。
2.製品概要
2.1 外観
開発した高放射率平面黒体炉「IR-R40」は,小形・軽量で,可搬性に優れている(写真1)。底面のネジ穴(1/4-20UNC)を使用して三脚に取り付けるか,卓上置きで使用する。外形寸法等の仕様は表1を参照頂きたい。

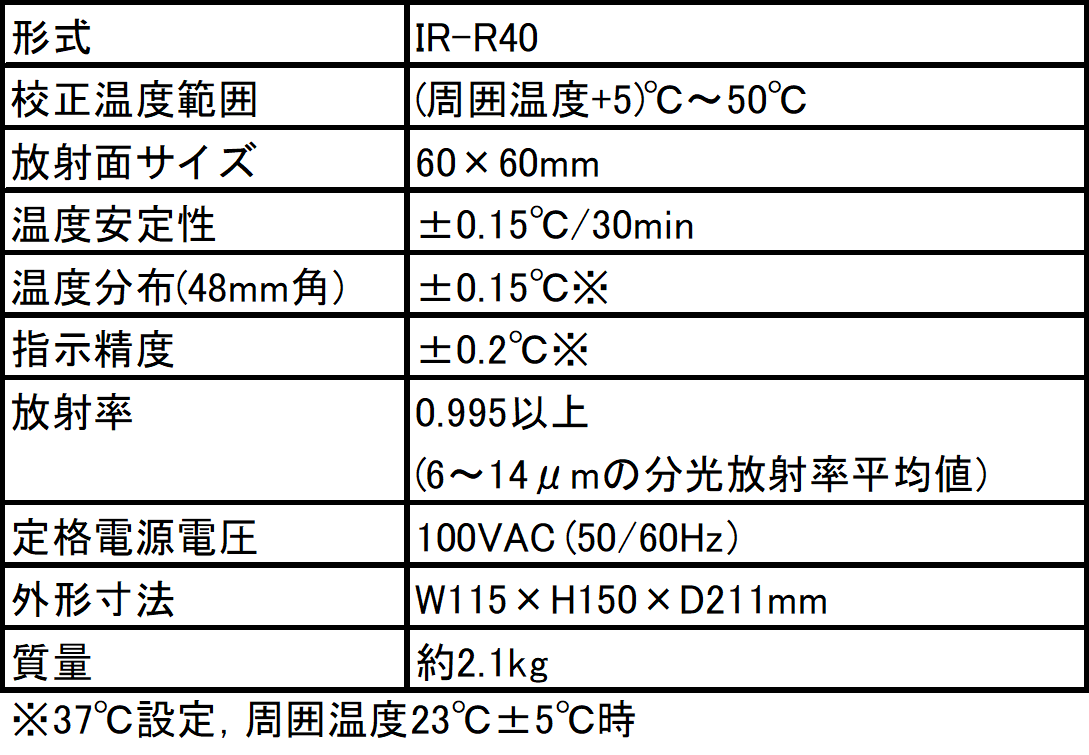
2.2 高放射率
IR-R40の性能面での一番の特長は放射率の高さにあり,一般的な平面黒体炉が0.96~0.98の放射率であるのに対し,平均で0.995以上の放射率を有する(図1)。
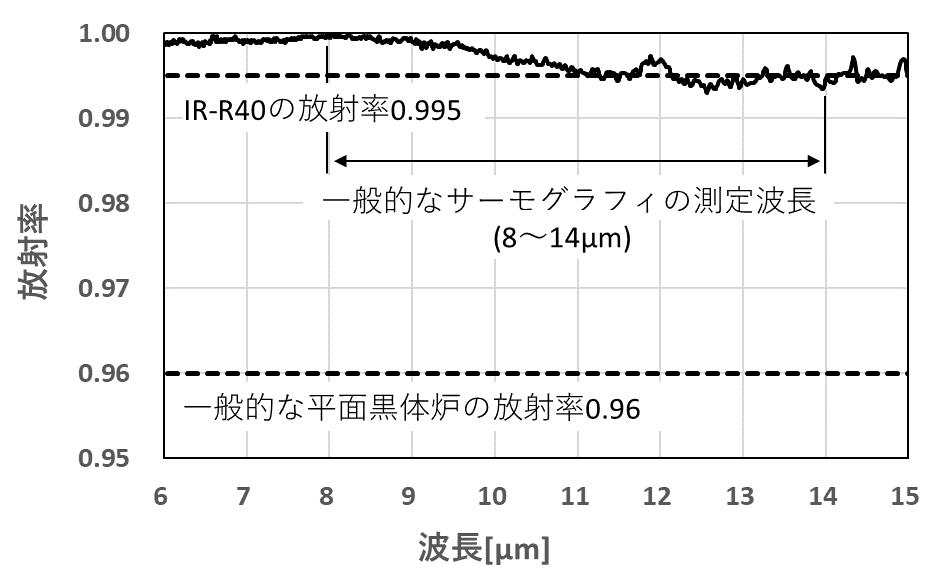
黒体炉は黒体の形状によって空洞形と平面形に分類される(図2)。空洞形は黒体部を円筒形状,底部を円錐にし,入射光を内部で多重反射させて外部に出にくくすることで放射率を高めている。奥行きLに対する開口径Dの比(D/L)が小さいほど放射率を高められるが,高放射率と必要な開口径を両立させようとすると装置の外形が大きくなる傾向がある。
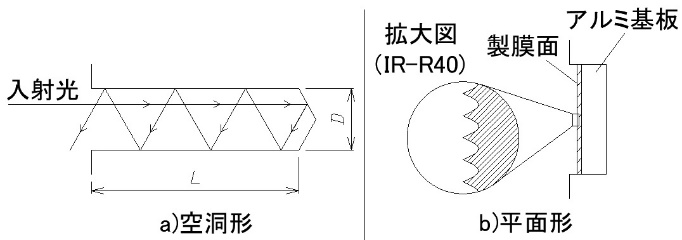
一方,平面形は構造上,開口サイズを大きくしやすいが,空洞形のように黒体形状で放射率を高めることができないため一般的に放射率が低い。8μm~14μm付近を測定波長とする一般的な放射温度計やサーモグラフィは測定視野が広いことから,平面黒体炉との相性が良いが,放射率の低さがネックになっていた。
IR-R40は平面形であるが,産総研で開発された黒体の技術を用いることで高放射率を実現した。放射面となるアルミ基板の表面に転写によって黒体となる樹脂を製膜することで,形成されたミクロンサイズの凹凸が入射光の反射を抑え,放射率向上に寄与している。
高放射率であることの効果を示すため,黒体の放射率εが温度計指示値に及ぼす影響について試算した(図3)。周囲温度を23℃と仮定して,黒体温度に対して温度計指示値がどの程度変化するかを示している。黒体温度が37℃の場合,放射率1の黒体に対して,放射率0.96の黒体は0.53℃低く測定されるが,放射率が0.995では0.07℃の低下で収まる。
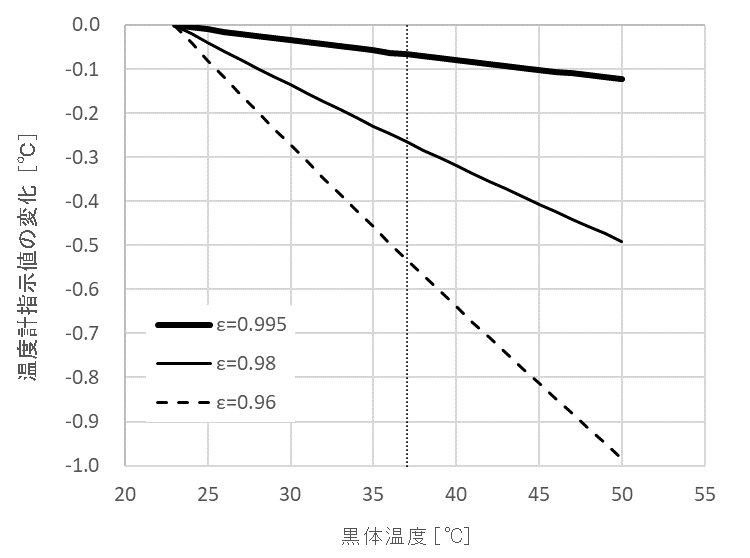
2.3 信頼性
生産ラインでは,測定器で得られた測定結果が製品の品質に大きく関係し,高い品質や安全性が求められる製品では,測定器の導入時だけでなく,その後の運用において定期的に校正できるか否かが重要になる。IR-R40は出荷時に検査結果を1台ずつ添付するほか,国家標準にトレーサブルであることを示すトレーサビリティ証明書を発行可能である(証明書は別途有料)。
一方,性能面における配慮として,出荷時は校正済放射温度計で検査するが,黒体の表面温度と背面に取り付けた温度調節計の指示値が正確に一致するよう,調節計に補正をかけている。そうすることで温度制御用に組み込んでいる測温抵抗体や調節計の個体差,組立等で生じる1台ごとの指示値のばらつきをトータルで小さく抑えている。また,使用中に電源電圧変動で黒体温度が変化することがないよう,内蔵の直流電源からヒータに電圧を印加している。
3.現場適用法
3.1 用途
主な用途として,各種非接触温度計(放射温度計,サーモグラフィ)の目盛校正,保守点検を想定している。
3.2 使用方法
使用方法はいたってシンプルで,温度調節計の上下矢印キーで目的の温度に設定した後,ENTERキーを押すと確定される。電源投入から50℃で安定するまでの待ち時間は約10分で,温度が安定すると温度調節計の“EV4”のランプが点灯する。装置背面に設けた端子台からRS-485通信で設定温度や現在温度を集録ソフトで取得することも可能である。データ集録ソフト「TRAMS」は弊社HPから無償でダウンロードできる。
3.3 使用上の注意点
注意点として,手の油脂が付着するため黒体部に触れるのは厳禁であり,仮に埃などが付着した場合はエアダスタ等で除去頂く。使用していない時に黒体を保護するためにアクリルカバーを前面に取り付けている。黒体炉使用時はカバーを外すが,外したカバーが邪魔になったり紛失したりしないよう,装置上面に固定できるようになっている。
また,エアコンの風が直接当たるような環境では黒体の表面温度が変化するため,場所を移動するか,仕切り等で風を遮る必要がある。
なお,IR-R40に限った話ではないが,額などを測る非接触式体温計で黒体を測定すると,黒体温度に対して多くの機種で指示値が2~3℃高めに表示される。人間の体温は中心部から離れるに従い低下し,体表面では腋下温度や舌下温度と比べて数℃低くなる。体温計メーカは各社独自のアルゴリズムで,体表面温度から腋下あるいは舌下温度を推測して体温として表示しているためである。中にはそれらしい温度を表示しているだけで,実際の温度変化を反映していない温度計も出回っているため,信頼できるメーカの製品を購入することをお勧めする。
製品によっては体温を測定するモードと物体の表面温度を測定するモードを切り替え可能なものがあり,後者のモードで黒体を測定すると黒体と近い温度が表示される。
4.今後の開発
現在,IR-R40と同じ製膜方法の黒体を用いて,温度範囲を拡大した平面黒体炉の開発を進めている。温度範囲は-15℃~120℃(暫定)で,黒体面サイズは100mm×100mmである。ペルチェ素子で加熱・冷却しており,20分ほどで室温から120℃,あるいは室温から-15℃に昇降温する。温度調節計等の電装部品を搭載した制御ユニットと,黒体面がある黒体ユニットが分離した構造になっており,ユニット間を専用ケーブルで接続して使用する。
黒体ユニット単体で見ると小形な分,設置の自由度が高い。外形寸法は制御ユニットがW184×H200×D300mm,黒体ユニットはW184×H200×D200mmで,質量はそれぞれ約5kgである。外形サイズや質量はIR-R40より大きくなるが,温度範囲が広く,食品関連や赤外線センサ開発など, IR-R40ではカバーできない需要に応えられるものとして期待している。