

【製品動向:ベンダ・プレゼン】
スマート化に貢献する無線式流量計
1.はじめに
昨今の急速なIT技術の進歩,無線技術の発達と成熟により,あらゆるモノがネットワークにつながるIoT(モノのインターネット)の時代になっている。計装分野でもセンサのネットワーク化,無線化が進み,無線を使った計測管理が行われている。
無線は「通信の信頼性」を100%担保することは困難であり,欠測のリスクが常につきまとう。しかし,省力化や省エネ,障害の予兆検知などセンサからの信号を監視・管理する,つまり「見える化」が目的であれば計装分野での無線活用のハードルは低くなる。
本稿では,この点に注目した無線式流量計の製品紹介とその特長を紹介する。
2.無線のメリットとデメリット
無線は,その目的に応じて規格が多数あり,十把一絡げに捉えてメリット/デメリットを論じることは好ましくないが,一般的に有線通信もしくは有線信号伝送と比較すると,メリット,デメリットは次のようにまとめることができる。
①メリット
・配線せず遠隔地から計測値を確認・記録できる。
・複数箇所のセンサ計測値収集に配線コストがかからない。
・計測値を伝送する過程においてノイズ混入等によるアナログ的誤差が生じない。
②デメリット
・配線がない代わりに親機と子機の両方を設置する必要がある。
・現場の環境によっては通信できない(使えない)ことがある。
・電池駆動が求められることが多く,大量のデータ伝送,頻回な通信は難しい。
無線を活用していく場合,これらの点をよく理解したうえで,目的に応じた使い方を十分に事前検討しておく必要がある。たとえば,既に電源や信号などの配線が整備されている場合,既設インフラを有効活用すべきである。しかし,既設インフラが整っていない,新たにセンサを設置したい場所が分散している,電源が確保できない場所に多数設置したい等,メリットが十分に活きるケースにおいて,無線は非常に有効である。
3.無線式流量計システム「Link920」
3.1 開発の経緯
民間においては,2016年4月に開始された電力小売自由化に伴いスマートメータ(無線通信機能を搭載した電力計)が普及し,その後,ガスメータや水道メータについても無線の搭載が進められている。2021年9月の資源エネルギー庁資料によれば,電力スマートメータは東京電力管内では100%の設置が完了し,全国でも2024年度までに設置が完了する予定と示されており,普及が進んでいる。
一方,産業界では,日本に限らず海外でも現状の運用で特に大きな問題はなく,各種計器のスマート化には投資の優先順位が低くなっていた。しかし,気候変動対策としての脱炭素社会への転換,そして労働人口減少への対応として,無線活用の注目が高まっている。また,意外にも流量計と無線の組み合わせは,適切な製品やパッケージがほとんどない状況でもあったことから,当社では遠隔・自動データ収集管理を簡単,安価に導入することに特化した製品として「Link920」を開発した。
3.2 Link920の構成
Link920は次の(1)~(3)が全てパッケージ化されており,ユーザが購入後に煩雑な設定をしたり,上位システムを開発したりする必要がない極めてシンプルな無線ネットワークシステムである。図1に全体のシステム図を示す。
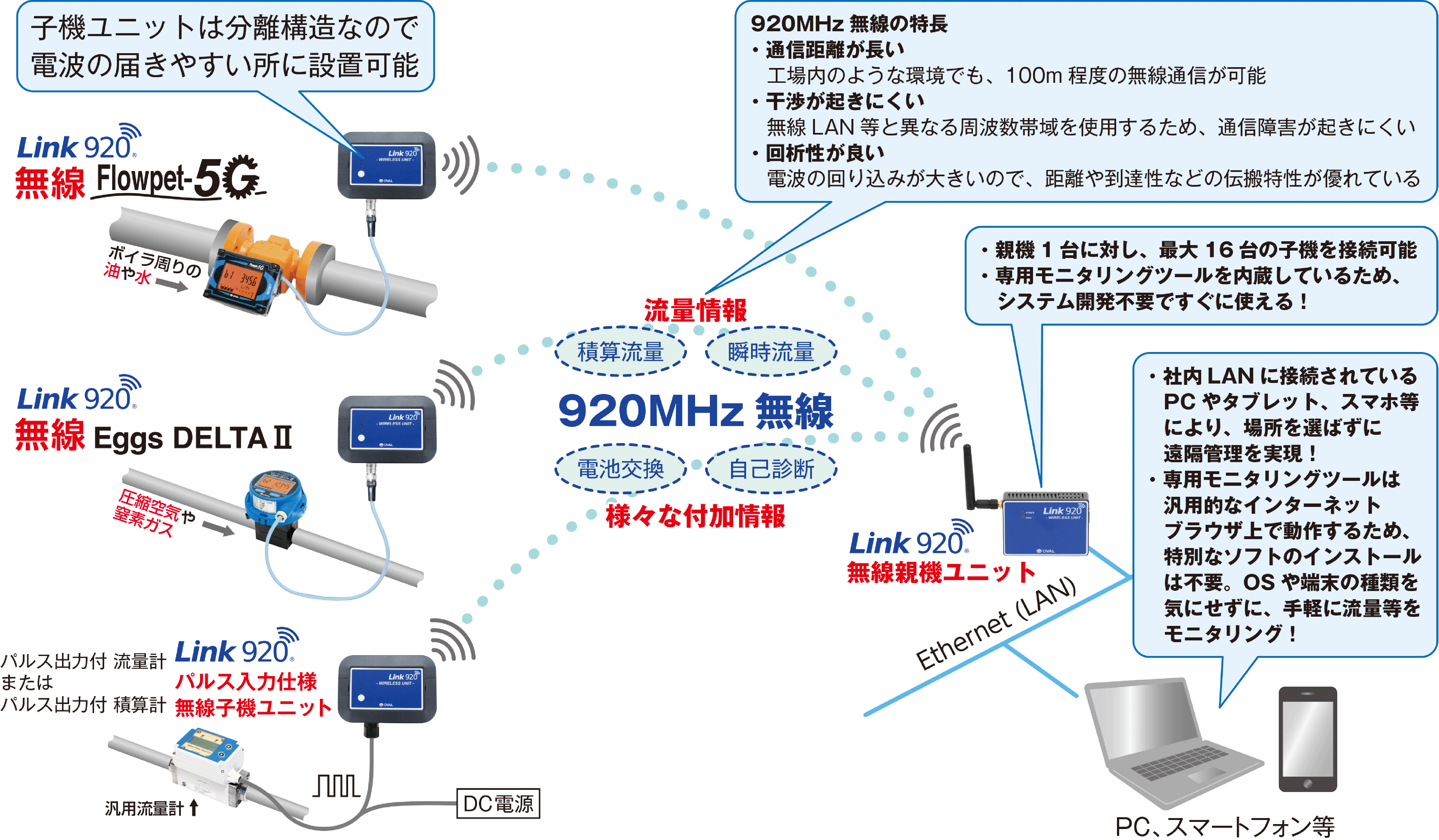
(1)子機(流量計)
子機ユニットは流量計とセットになっており,コネクタで接続して子機を電波の飛びやすいところに取り付けるだけで済むように設計されている。
適用できる流量計は,多数の実績を持つ容積流量計「フローペット-5G」,渦流量計「Eggs DELTAⅡ」の2機種を用意している(写真1,写真2)。また,パルス出力付きの流量計やパネル計器を容易に無線化するためのパルス入力用子機ユニットも用意している(写真3)。
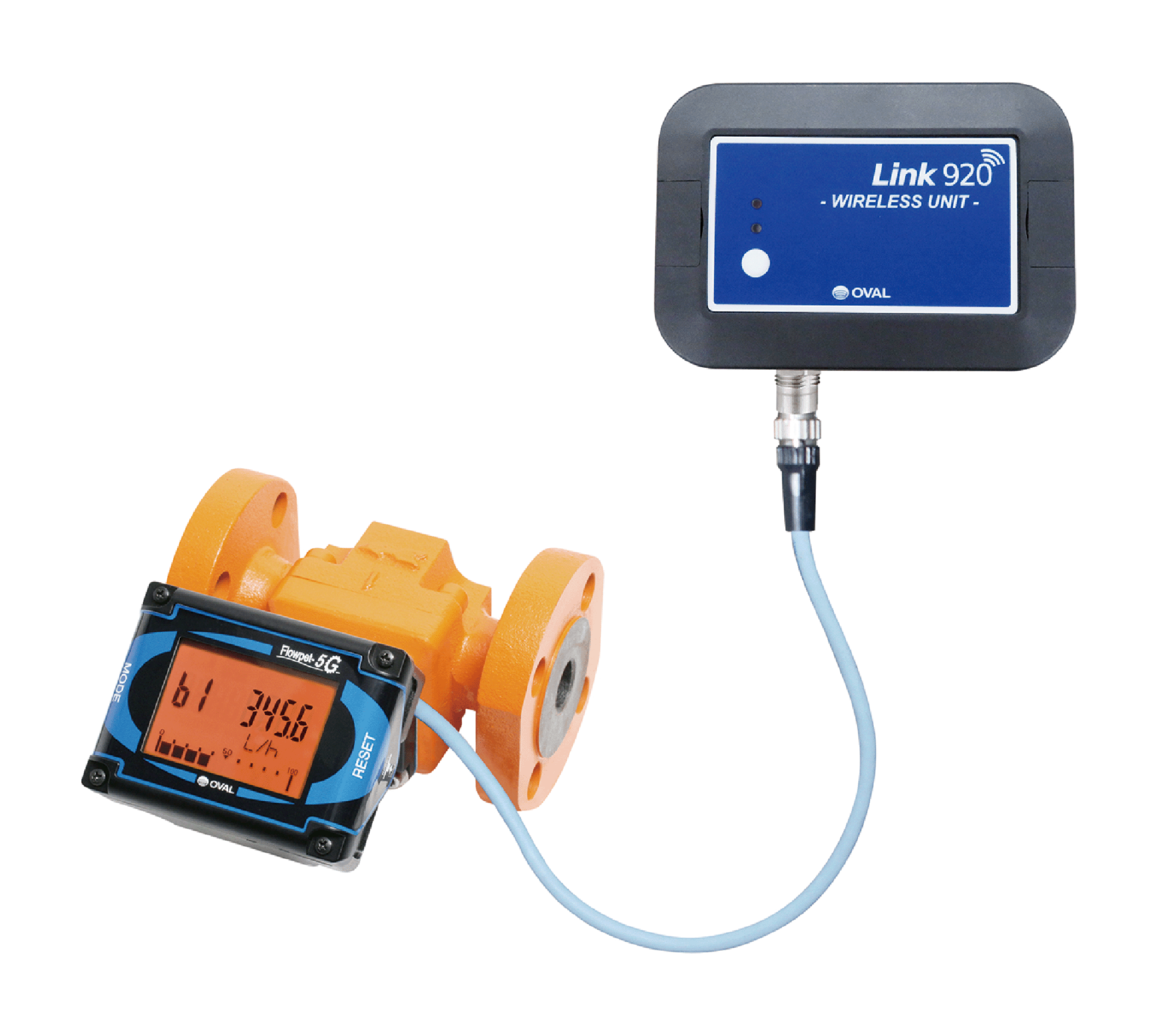
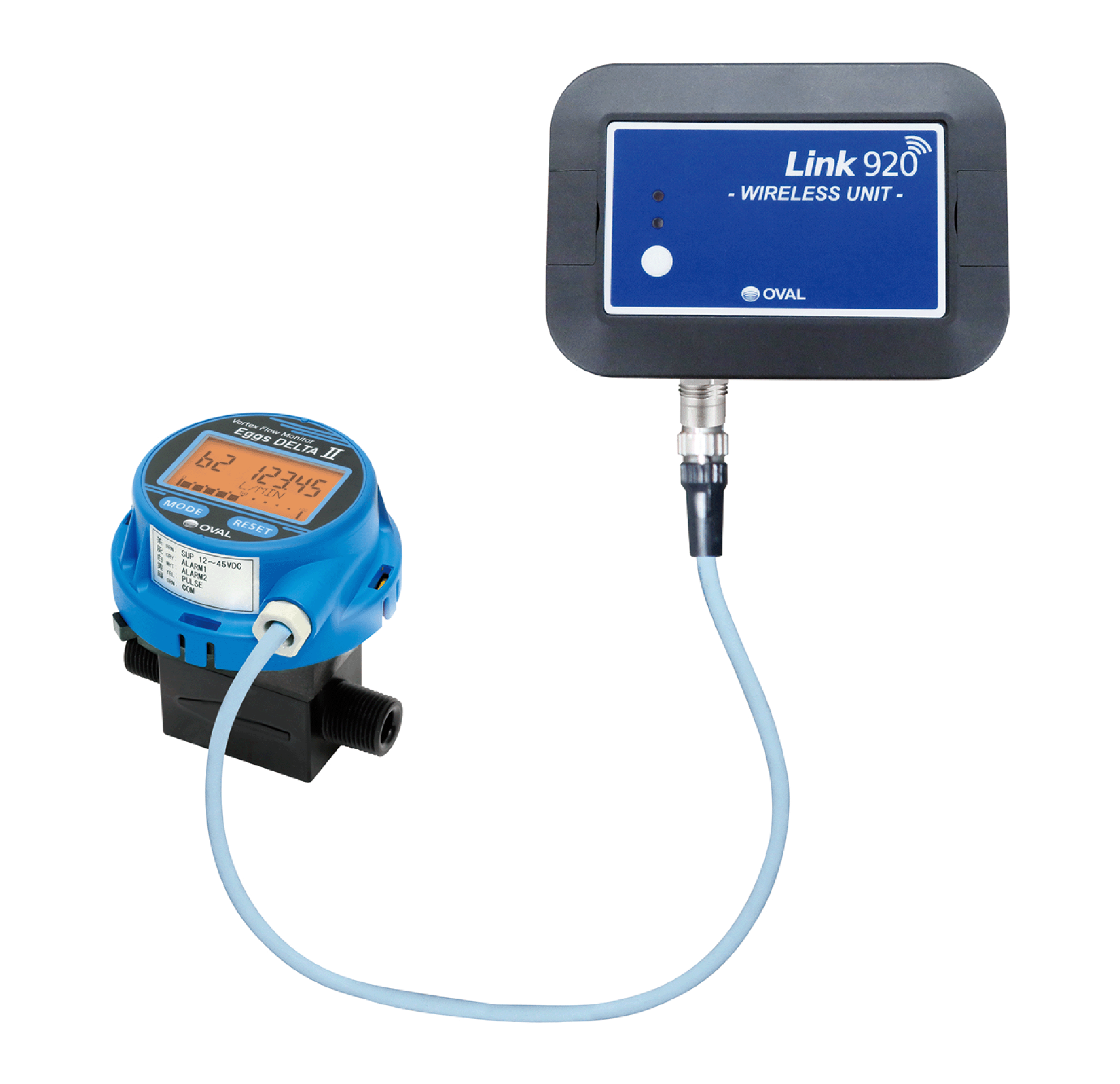

(2)親機
親機は全てのLink920子機に対して共通で使用でき,1台の親機で最大16台までの子機を接続することができる(写真4)。中継機能は有していないが,親機を複数台設置することによって接続できる子機を増やしたり,広いエリアをカバーしたりすることが可能なよう,お求めやすい価格としている。
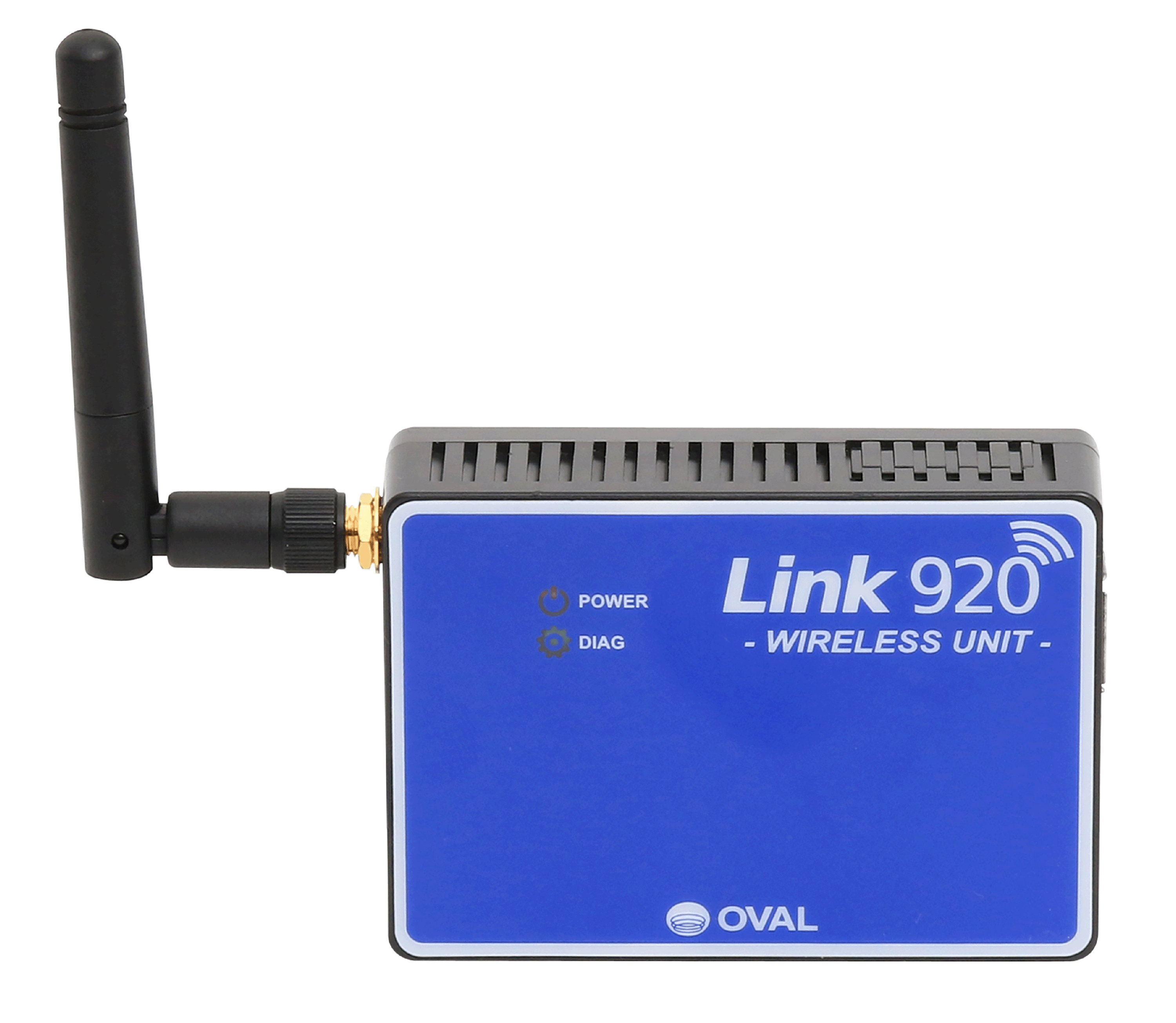
(3)データ収集ツール
子機側の流量計から収集したデータの蓄積,計測値やグラフの表示,簡単な解析などのツールは親機に予め内蔵されたモニタリングツールを使用することができるため,上位システムを開発する必要がない。モニタリングツールは直感的に使用できるインタフェースを備えており,汎用的なブラウザ上で動作するため,ソフトウェアのインストールや保守も不要である。ブラウザベースのため,PCだけでなくタブレットやスマートフォンにも対応している(図2)。
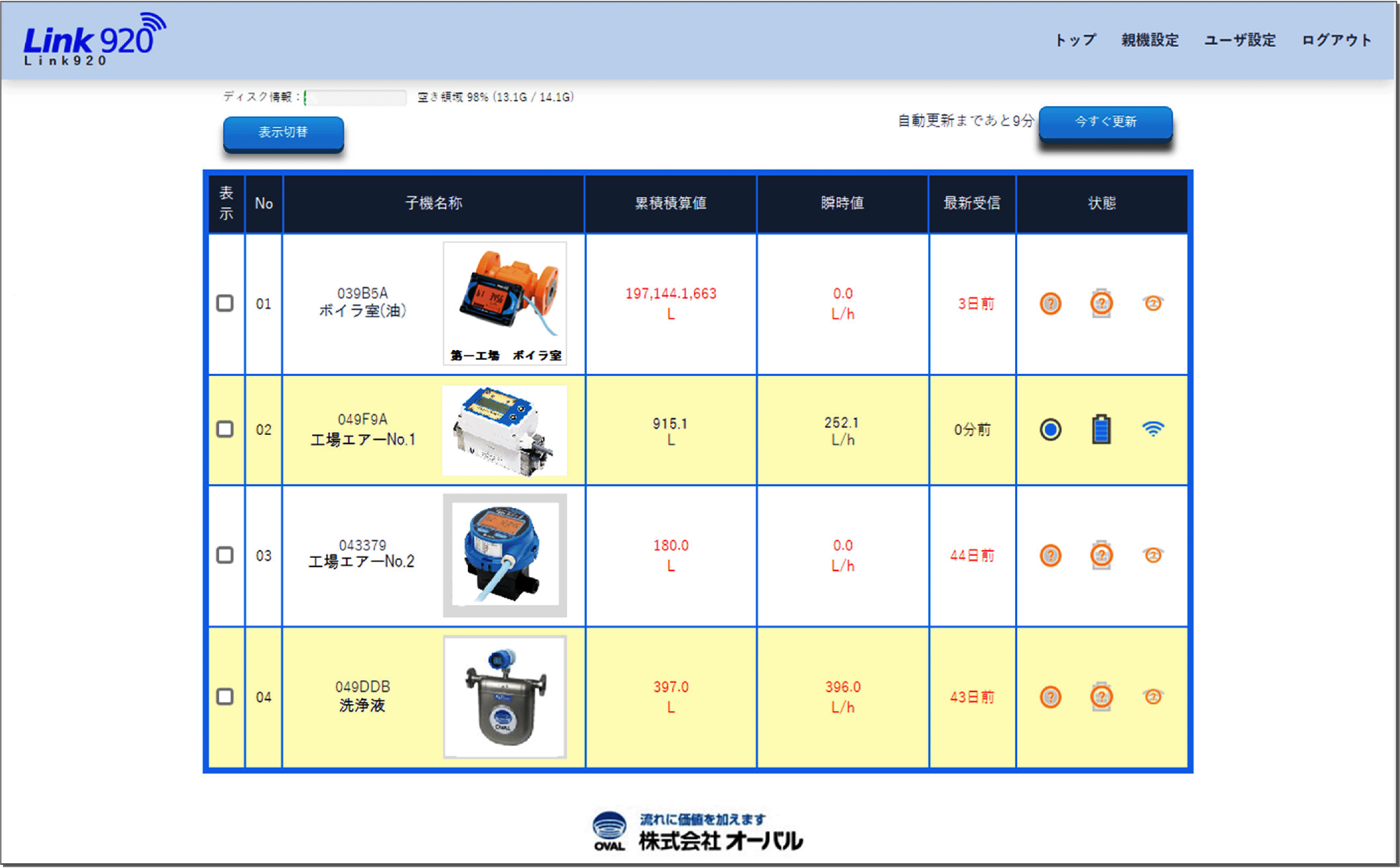
また,蓄積しているデータをCSV形式で取り出し,詳細な分析やデータのグラフ化など表計算ソフトによるデータの二次的活用も可能である。
3.3 Link920の特長
1)Link920シリーズの無線機能付専用流量計およびパルス入力無線子機は内蔵電池のみで動作するため,現場は外部電源設備や外部電源用配線が不要。
2)従来の工業用無線で多く使用されている2.4GHz無線ではなく,近年IoT用途で注目される920MHzのLPWA(Low Power Wide Area:低消費広範囲)無線を採用。これにより,工場内のような遮蔽物がある環境でも100m程度の無線通信が可能で,電波干渉が起きにくく通信距離や伝搬特性が優れている。 3)無線親機内にモニタリングツールが内蔵されているため,上位システムが不要。モニタリングツールは直観的に操作しやすく,また汎用的なブラウザ(ChromeやFirefox等)で動作するため,特別なソフトウェアをインストールする必要がなく,ソフトウェアの保守も不要。ブラウザベースのため,LANに接続されている機器であればOSを問わず手軽にモニタリングできる。 4)システム一式をパッケージで提供するため「親機と子機のペアリング設定」や「親機のネットワーク設定」等の面倒な各種ネットワーク設定作業は完了した状態で出荷することが可能(初期セットアップサービス使用時)。 5)容積流量計フローペットシリーズの旧製品を使用されているユーザは,電子計数部(変換器)の交換だけで無線化が可能。 6)データ収集の上位システム開発や維持,ネットワーク工事,付帯設備など様々なイニシャルコストが不要。子機(流量計)を現場に設置し,親機をLANに接続するだけで,即時使用開始できる。 7)当社もしくは代理店担当者が,現地での事前通信テストを必ず実施し,通信可否を確認することにより,購入後に通信できなかった,使えなかった…といったトラブルを防止。 3.4 アプリケーション例 工場内の各現場に流量計は取り付けられているものの,現場表示のみを利用しており,監視員が工場内を巡回して水や油,空気の使用量を記録しているような場合(図3),工場内を巡回する要員の確保,記録ミスや記録漏れ,端末への入力間違いの防止への対応など,手間がかかる割に効率が悪い。
このようなケースを無線化すると,自動的に定められた間隔で流量を正確に記録することができる上,人の巡回に比べると記録頻度を増やすことが可能であり,瞬時流量のモニタリングが可能となる。瞬時流量のモニタリングができると,単なる使用量管理でなくトレンド分析による高度な省エネへの活用や,設備等の監視による運転状態,異常の早期発見にもつながる。 このような例では,効率化,省力化とともに保全の高度化も期待できる。 3.5 流量可視化のポイント 流量計が他のプロセス計測器(圧力計,温度計,レベル計)と大きく異なる点として,「積算値」がある(他の計器では瞬時値しかない)。積算値と瞬時値を区別するには,自動車のメータに置き換えるとわかりやすい。現時点の走行速度(km/h)は瞬時値,現在までの総走行距離(km)は積算値である。 これを流量に当てはめると,単位時間当たりに流れる量(m3/hなど)が瞬時値,現在までの流れた総量(m3など)が積算値である。前項でも述べたような巡回監視で行う使用量管理であれば人の巡回による積算値を見ることになる。 一方,無線化すると流量計からは瞬時値と積算値,両方のデータを得ることができる。瞬時値のデータを得られると,たとえば「休み時間で工場が止まっているはずなのに水が流れている」とか「特定の時間帯だけ空気がたくさん流れている」といった普段とは異なる事象,想定とは異なる事象を確認できることがある。こうした事象から,「見えない場所で水が漏れていた」とか「特定の時間に稼働する機械に不具合があった」といった要改善事項を早く知ることができ,省エネや異常の早期発見につながる。 これに加え,使用量管理の積算値であれば,巡回監視の手間を省きたいという目的だけでも無線を導入する意義はあり,加えて積算値の曜日変動や季節変動などを捉えて,省エネなどの活用につなげることも可能である。流量を可視化したら,積算値と瞬時値の両方を目的に応じてうまく管理していくことが肝要である。 4.おわりに 省力化や省エネ,障害の予兆検知などを目的として現場データの収集を検討する場合,規模感はユーザにより様々である。大は小を兼ねるとは言うものの,大規模なシステムをいきなり導入するのはハードルが高くリスクもある。Link920 は,中小規模を想定し,必要な機器一式をパッケージで提供するワンストップ・ソリューションとした。これによりスモールスタートや部分的な活用などが可能となる。 また,意外と工場のユーティリティ関連(水や空気,油など工場を稼働させるために必要な流体)の管理を緻密に行っているケースは少ない。ユーティリティ関連であっても,これらの使用量が合理的なのか,むだがないのかを把握し,削減していくことは省エネ,コストダウン,環境負荷の低減に資する。 加えて,アプリケーションで紹介した事例のように,人を介在させることなくデータの収集ができ,省力化のツールにもなることから,Link920はユーザの業務効率化の一助になれると考えている。
図3 アプリケーション例(現場巡回監視の自動化)
ポータルサイトへ