

【トレンド】①水質監視分析
水質監視に役立つ液体分析計 -現場ニーズに適応する濁度計・残留塩素計
1.はじめに
世界において1,2を争う生活用水使用量を支える日本の水道事業では,水質基準を満たした安全でおいしい水を安定供給するために各種の液体分析計が使用されている。これらの液体分析計の中で,濁度および遊離(残留)塩素の測定は原水,ろ過池管理,また微生物学的安全性の確保のために欠かせないものである。
日本の水質管理,測定機器の技術は世界においてトップレベルであり,常に注目されている。
当社では,pH計・濁度計・残留塩素計・アルカリ度計など,水道事業の発展に欠かすことができない定置型液体分析計を,1950年代から長年にわたり製造・販売を行っている。 今回,従来からあるセンサ技術を基礎とし,近年特に日本社会の変化により顕在化してきた課題に対し,貢献できる新技術を搭載した濁度計・残留塩素計の開発を実施した。本稿では,その開発の狙い,強化技術等について説明するとともに,導入運用状況や液体分析計の今後の方向性などについて紹介する(写真1)。 2.開発の狙いと現場ニーズ 進国における人口の減少に伴い,ノウハウを持った技術者の減少およびメンテナンスなどを行う作業員の削減など,それに関わる人材の減少という世界共通の課題が出てきている。このため,操作が簡単でメンテナンスが容易で,最少人数で効率的に施設の管理や運営をサポートできるような機器が求められている。 今回,デジタルセンサ,各種通信手段を搭載した濁度計,および残留塩素計を開発し,現在の機器の状態等を現場や計器室で確認できるようになった。これによりさらに効率的な管理,運営をサポートできると考えている。 3.開発ポイント 3.1 自己診断機能の拡充による予防保全機能向上 液体分析計を含めた工業計器において,定期的なメンテナンスは安定した測定を行うために必須の作業である。 液体分析計の場合,メンテナンス機器の洗浄,測定値の確認,校正および定期的な消耗部品の交換などのメンテナンスが必要である。メンテナンスの周期や消耗部品の交換周期についてはアプリケーションの状態や稼働時間により変わるものの,メーカが示した推奨周期でのメンテナンスや部品交換を行うことが一般的である。 今回開発した濁度計は,光源の状態や機器内の乾燥状態が画面上で確認できることから光源や乾燥剤の交換時期などが推測できる。また,新しい残留塩素計では稼働日数が表示できることから,消耗部品の適切な交換時期を推測できるようになっている(図1)。 洗浄や校正などのメンテナンスに関しては,推奨周期での実施をまずは推奨するが,アプリケーションや時期によりその周期は異なるため,最終的にはユーザが運用実績をもとにメンテナンス周期を判断,決定する必要がある。新しく開発した濁度計や残留塩素計は共通変換器「FLEXAシリーズ」を使用しているので,メンテナンスの負担の軽減につながるような多彩な機能が搭載されている。
メイン表示であるホーム画面(図1)には測定値だけでなく,様々な必要な情報が示されている。たとえば,日常多く実施する校正については,ショートカットキーとしてCALボタンが用意されている。ここを押すだけで簡単に校正モードに入れる。また,各種機器情報や設定についてはMENUキーを押すだけで展開できる。さらに,各種自己診断機能を搭載しており,異常時にはその重要度に応じたアイコンで表示され,異常の内容や対処方法も表示できる。 3.2 メンテナンス性を向上させた交換部品 前項で述べたように,消耗部品の定期的な交換は分析計の安定した測定のために必要な作業となる。このため濁度計や残留塩素計では消耗部品の交換周期の延長や交換工数の削減など,メンテナンス作業の効率化を考えて設計している。 たとえば,濁度計は光源の定期的な交換が必須であるが,その光源を従来のランプからLEDに変えた。これにより寿命を3倍に延ばし,1年に1回の交換が必要だったものを3年に1回の交換で済むようにした。また,交換作業も今まではランプ交換後に光軸調整等の作業が必要であったが,光源交換のみで光軸調整は不要とし,作業工数の削減を実現した。 残留塩素計では測定に重要な回転電極との電気的コンタクト部の部品交換において,回転電極の駆動用ベルトの張りの調整,接触面の調整作業が必要であった。また,これまでは電気的コンタクト部がむき出しだったため,ベルトの粉や埃などが付着し指示に影響を与える可能性から定期的清掃が必要であった。 今回開発した新しいコンタクト部は一体化構造となり蓋をされていることから,交換は容易で,粉や埃の付着がないためメンテナンス作業が大幅に削減される。回転電極とモータを直結した構造としギアヘッドやベルトを不要としたためモータ交換も簡単になっている。 このような新しい濁度計や残留塩素計は消耗部品の交換作業時間が削減され,現場での作業効率化により役立つ製品となっている。 4.既設の液体分析計と共にトータルソリューションの提供 一般的な浄水設備の工程を図2に示す。河川より取水された水は,各工程を経由し最終的に配水池から市街地,各家庭へと供給される。工程ごとに,多くの液体分析計が用いられ,常時測定がなされている。 濁度計,残留塩素計のみならず,弊社の水質計器の共通変換器であるFLEXAシリーズは,リモート環境での運用を想定したデジタル通信機能が搭載されている。そのため測定値に何らかの不具合が生じたとき,デジタル通信を用い遠隔地から接続された機器の自己診断情報や内部ログ情報を入手することが可能である。対象の分析計がどのような状況であるか,たとえば,汚れが検出部に付着している,あるいは消耗部品の交換が必要等,ある程度の判断が可能になり,現場に赴く以前に一次対応が可能になる。つまり,スキルを持った少人数の要員で複数の施設のメンテナンスをサポートすることが可能になる。 次に,pH検出器のデジタル化がメンテナンスに変革をもたらした事例について紹介する。
従来の変換器同等の機能を持ったスマートアダプタ(図3)を検出器に装着することで,校正データなどのデジタルデータを検出器側に保存でき,デジタル検出器として使用できるようになった。検出器とスマートアダプターを一体で現場から取り外し持ち運びできるので,浄水場のラボなど作業のしやすい安全な場所で校正等をすることが可能となった。 スマートアダプタを使用することで,従来の検出器で必須であった現場設置の変換器で行う校正・メンテナンス作業の時間を削減でき,また校正作業による測定中断時間を最短にできるなど,現場作業の効率向上に貢献している。 この分析計の遠隔操作による運用は,国土の広い海外からの要望も多く,国内での多くの実績により培った,汚れに強く安定性に優れた自動洗浄装置付き検出器(残留塩素計の回転電極ビーズ洗浄方式,濁度計の超音波洗浄)と組み合わせることにより,測定の安定性に優れ,不具合の際も効率の良い対応が可能な分析計として,グローバルで貢献できると考える。 5.これからの水質監視について 世界的に注目されている日本の水質管理技術は,今後より多くの国や地域でさらなる展開が期待される。 安全な水の供給のため液体分析計を使用した水質監視は重要で,分析計を長期間安定して稼働させることが求められる。グローバル化に伴い,使用方法,設置環境方法,管理方法は多種多様なものとなっているが,それぞれに適した運用方法を見極め,その作業を効率よく実施することが必要である。 長期間安定した稼働を実現するために,自己診断機能を強化し,メンテナンス性を考慮した設計としていることは前述の通りである。ここに最近急速に発展しているデジタル技術を活用することで,より適切な運用と作業の効率化が実現可能と考えている。 活用すべきデジタル技術として,まずはIoTがある。 近年,水道施設の大規模化,広域化に伴い,現場の機器情報を集中監視する設備が増えている。現場の様々な情報をインターネットなどの高速回線を使用して伝達することで,少人数でより多くの機器の管理が可能となる。 また,最新の水質計は測定値だけなく,現場にある機器の健康度,校正時期,校正データ,電極の交換時期,メンテナンス時期,など様々な情報を送ることができる。従来は巡回点検によって集めていた機器情報を遠隔で収集することで巡回点検の頻度を下げるとともに,必要な時に必要なメンテナンスをするCBMが実現する。何か問題が発生した際にも様々なデータを簡単に高速で有識者に共有することができ,早期解決が可能になる利点もある。 さらに,AI技術の活用も水質計の管理には有効と考える。従来はメンテナンス担当者の長年にわたる作業の中で積み重ねてきた経験値が機器の運用を支えており,これにより安定した運転を実現していた。しかし,近年では熟練のメンテナンス担当者の退職,メンテナンス担当者の若年齢化,また必要なトレーニングを受けぬまま作業を実施している事例もある。 結果として,機器の異常を示す兆しに気付かぬまま運用することになり,機器の不適合につながるケースもある。そこでAI技術を活用し,データを蓄積して学習し違和感を検出することができれば,従来と同様の運用が可能になると考える。 分析計の自己診断機能による機器異常の検出も可能だが,実際の設置環境や測定対象によって変わることがあり,機器側でそれぞれの現場に合うように膨大なデータベースを用意し適合させるのは困難である。そこで実際に使用するプロセスでデータを蓄積し,違和感を検出し,必要なメンテナンス時期を予測することは,運用上有効なものと思われる。これらデジタル技術の発展を分析計に積極的に取り入れ,さらなる効率化と安定した測定を実現することが可能と考えている。 6.終わりに これまでのプロセス分析技術は水質管理や安定操業に貢献してきた。近年その役割は新たな段階を迎えている。データを有効に活用することで少ない人員で適切な管理が可能になる。水質計器で管理された安全でおいしい水を安定供給する設備が世界中で普及し,人々の健康に貢献することを願い,これからも優れた製品開発に取り組んでいきたい。 〈参考文献〉 1)吉村誠司,服部晋也:「残留塩素管理の高度化に向けた測定機器の精度管理方法の検討」,『水道の国際比較に関する研究(国外の生活用水使用量)』,水道技術研究センター(2017)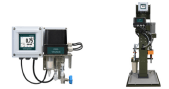
写真1 新残留塩素計(左)と新濁度計(右)
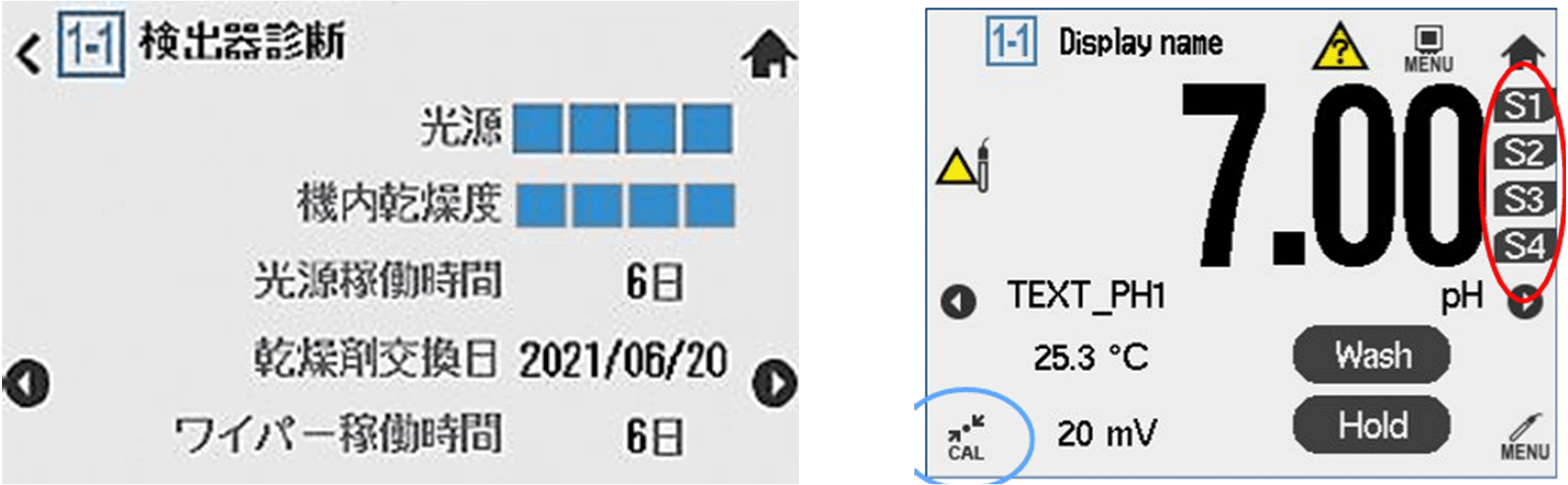
図1 変換器「FLEXAシリーズ」の診断画面とホーム画面
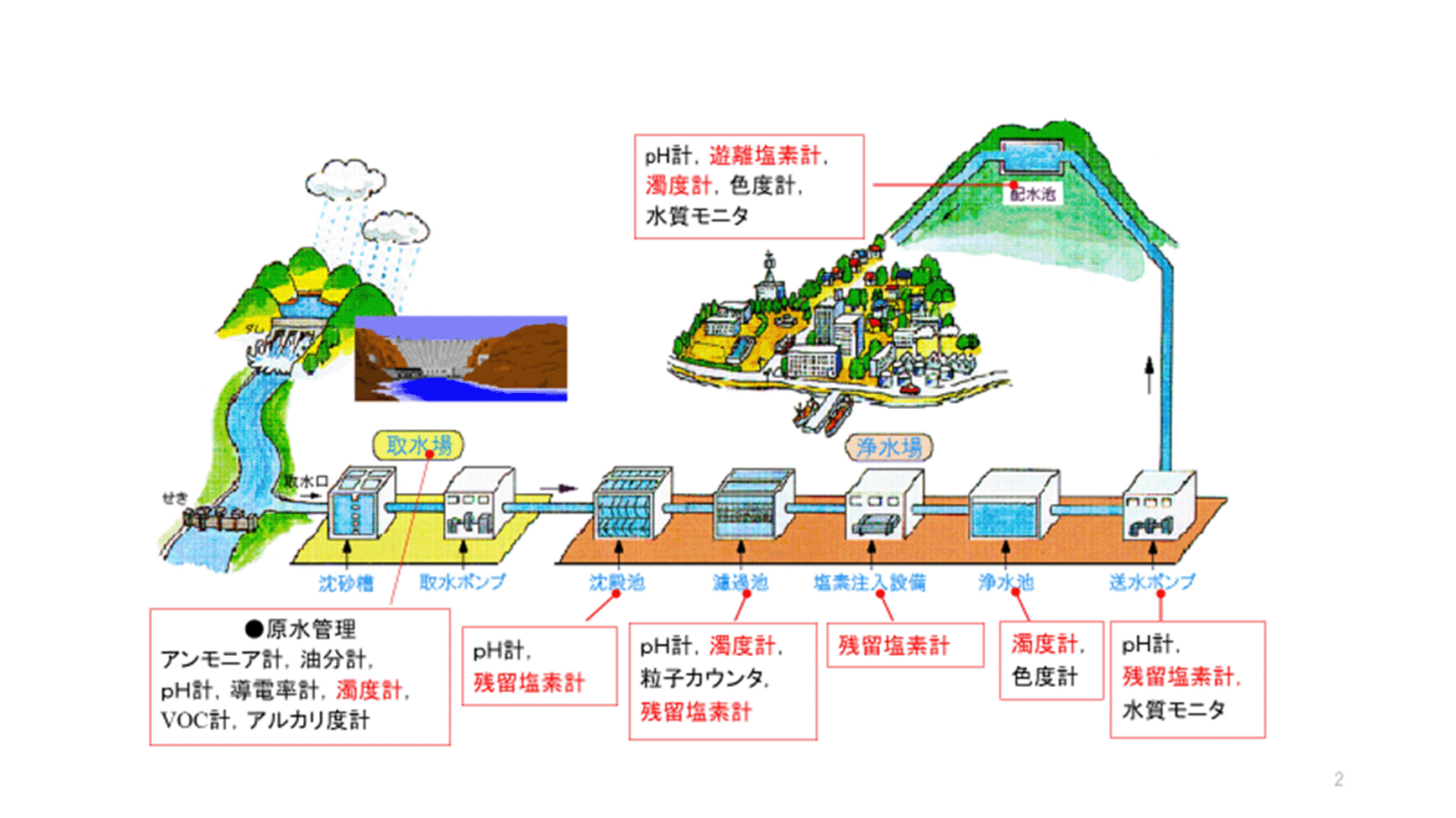
図2 浄水設備と分析計

図3 スマートアダプタ
ポータルサイトへ