

【トレンド】①水質監視分析
現場事例にみる 水質監視/溶液分析計の設置・運用法と注目技術
1.はじめに
水および溶液を対象としたプロセス分析計(以下,水質計と略す)において,特にここ数年は排水のCOVID-19病原体の監視が主要な議題となっている。欧州委員会は加盟国に対して,SARS-CoV-2(コロナウイルス)などの病原菌の有無を監視するために,2021年10月1日までに大都市での排水サンプリングおよび検査を実施するよう勧告した。そのためには,水質計およびソリューションを活用して,リアルタイムなPCR検査および殺菌状況の監視によって,病原菌による汚染を早期に検出し,ウイルスの発生を予防的に管理できるシステムが必要となった。すなわち,排水中のパンデミックウイルス株のデータを提供する排水監視システムを構築することが必要となった。
これらを実現するためには,水質計によるサンプリング, 分析室(ラボ)での検査, および殺菌状況の監視といった測定ソリューション一式を提供することにより,排水監視,水の抽出,処理,流通における高度な品質管理が促進されるとともに,付随する関連資料の管理,機器検証,メンテナンス戦略により最適なリスク管理と水の安全性維持が必要となった。さらに今後も地球の環境保全を推進するためには,有害物質を定量的に常時監視する水質計によるモニタリングシステムの構築が不可欠である。
水質計(イン/オンライン型)は,河川・湖沼・海域などの公共用水域の水質保全,上・下水や工場排水処理プラントなどの運転管理,処理水の水質監視などの目的で,広く活用されている。最近の水環境の保全・水質の保全に対する社会的関心の高まりとともに水質に関する基準も厳しくなり,水質計自体も開発・改良が進んだ。従来のpH計,濁度計などの一般的な水質計に加え,より多くの水質項目の連続計測,より微量の成分の計測,より低価格でメンテナンスフリーなどを実現する製品も現れてきた。
2.水質計の種類
水質計には様々な種類があるが,測定方法,測定対象の特徴,特性,およびその用途に基づいて広く分類できる。さらに,プロセスのサンプリングと監視の頻度に基づき,水質計は図1に示すようにインライン水質計,オンライン水質計,オフライン水質計に分類することができる。

●インライン水質計
インライン水質計とは,水質計が,測定対象の反応タンクや貯蔵タンク,あるいはその流路など,測定対象物に直接接触し,検出,分析,記録,送信,監視が連続的に実行される方法である。インライン水質計の重要な特徴は,連続したフィードバックループでタイムロスなく動作し,基本的にリアルタイムまたは高速でのパフォーマンス,非破壊測定,および高耐久性が必要だということである。これは,分析員がサンプリングを採取することを必要とせず,生産プロセスラインに水質計を配置できるため,プロセスを分析および監視するための最も望ましい方法である。
●オンライン水質計
オンライン水質計は,常に自動サンプリングと分析が実行される方法である。サンプリング機器,プロセス分析機器は,測定対象の近くに配置される。この方法は,化学組成のように,組成の急速な変更または継続的な監視を必要とする組成に使用される。
●オフライン水質計
オフライン水質計では,分析のためにサンプル(分析試料)が採取され,関連するプロセス分析機器が設置されている分析室(ラボ)や試験所などに運ばれる。そして,これらの輸送されたサンプルは,これらの機器によって分析される。この方式は,時間がかかる精密分析や,少量のサンプルから複数の成分を分析するために使用される。
これらの分析手法の違いによって,水質計の種類に対する優劣をつけるものではなく,特定の目的に応じて使用されているということに留意が必要である。
水質計は,物理量,化学量,または生物学的量を高精度で再現性に優れた測定をするために使用される。その信頼性により,ヘルスケアから社会インフラ,製造業に至るまで,様々な業界で幅広く使用されている。一般的に使用される水質計のうち最も多いセンサは次の化学センサである。
●化学センサ 化学センサは,組成,特定の元素やイオンの存在,濃度,化学活性などの化学情報を人間が読み取れる信号に変換して検出する。化学情報は,分析物の化学反応または調査したシステムの物理的特性に由来する場合がある。特定のコンポーネントに対して高い感度を持っているが,感度を持たないコンポーネントもある。通常,物質は複数の成分で構成されており,測定対象の標的成分のみの濃度と組成比を検出するために化学センサが使用される。化学センサには,物質成分に対する高感度と高選択性が必要である。 3.水質計の用途による種類 水質計を用途別に分類すると,概ね以下の4つのグループとなる。 3.1 一般用水質計 水処理プラントなどに一般的に使われている水質計5機種(残留塩素計・遊離塩素計,濁度計,pH計,アルカリ度計,電気伝導度計)の主な仕様を表1に示す。いずれの機種も自動洗浄・自動校正機能の付加により,長期間のノーメンテナンス運転が可能となっている。 また,上下水を効率良く処理するために,連続して測定することが要求される。しかし,連続した測定が要求される一方で,センサは劣化や汚れにより定期的な校正や交換が必要である。また,排水や上下水管理を行うためには,複数台の分析計の購入や維持が必要であり,資本支出,営業支出の両面で問題がある。 これらの課題解決のため,図2 に示すように複数のセンサ入力を持ち,保守効率を向上した水質計やセンサ部分のみを交換することを可能にしたスマートアダプタなども開発されている。 また,従来のスマートセンサは,センサと変換器一体型の構造をとっており,センサの寿命とともに変換器部分も含めてセンサを交換する必要があった。これらの問題を解決するために,校正アルゴリズムと機器診断機能を持たせ,センサと変換器を分離するためのコネクタを装備している。センサ側にも接続用コネクタを持たせ,変換器と分離できるようにしている。さらに,接続するセンサが固定ではないので,センサ個体を認識するためのシリアル番号や,校正情報を記録するためのID チップをセンサに内蔵しているものもある。 3.2 環境用水質計 湖沼や内湾などの閉鎖性水域の富栄養化が大きな社会問題となり,富栄養化の要因物質である窒素,リンの除去および自動計測の重要性が高まっている。 これらの水質計を代表して,アンモニア分析計,全窒素分析計の概要を以下に説明する。 (1)アンモニア分析計 水中のアンモニア性窒素(NH3-N)は,NH3およびNH4+であるが,pH >11ではNH3の割合が98%以上になる。試料がこの状態で攪拌されると,NH3は気液界面を通して移動しNH3濃度は気液間で平衡状態になる。本水質計はこの気相部のNH3濃度を隔膜電極で測定するものであり,また濃度の決定には標準添加法を採用している。 非接液式イオン電極法の採用により安定性が高く保守が容易,標準添加法の採用により校正が不要,サンプリングが容易などの特徴がある。 (2)全窒索分析計 水中に存在する窒素の形態は無機態ではアンモニア性窒素(NH3-N),亜硝酸性窒素(NO2-N),硝酸性窒素(NO3-N)が,有機態ではアミノ酸,タンパク質中の窒素などがある。全窒素(T-N)の測定はこれら各種形態の窒素をNO3-Nに変換する前処理と,NO3-Nを測定しT-N濃度を求める定量の2段階からなる。本分析計では,前処理に試料pH約12のアルカリ性にしてオゾンを通気するアルカリ性オゾン酸化法を,定量に公定法と同じ紫外線吸光光度法を採用している。このため,試料を希釈する必要がない,保守が容易などの特徴がある。 3.3 バイオ水質計 (1)水質安全モニタ ゴルフ場農薬の排水規制に見られるように,上水の取水水質の安全性が重要視されている。しかし,多種類の有害物質の連続計測は困難なため,取水の安全性監視の手段として,一般に浄水場では原水を導入した水槽に魚を飼育している。魚の行動や健康状態から水質の異常を検知する方法であるが,行動を監視するという曖昧性から客観性に欠ける,毒物混入の判定に時間がかかるなどの問題があった。そこで,魚の代わりに微生物を使って急性毒物の混入を監視しようとするのが,バイオセンサの原理による水質安全モニタである。 亜硝酸生成細菌を固定した微生物膜を溶存酸素電極に装着してセンサを構成する。このセンサに一定濃度のアンモニアを供給すると,膜内の亜硝酸生成細菌の呼吸により溶存酸素が消費されるため,一定のセンサ出力が得られる。ここで有害物質が混入すると呼吸活動が阻害されセンサの出力が低下する。この出力低下の程度を検出して有害物質の混入を検知する。 図3に水質安全モニタの原理を,図4に水質安全モニタの応答図を示す。連続的なモニタリングが可能で,急性毒性物質には低濃度(1mg/L以下)で短時間(20分以内)に応答する。 (2)BOD計 有機汚濁の重要な水質指標の1つであるBOD(生物化学的酸素要求量)は,水中の好気性微生物の呼吸作用によって消費される酸素量のことである。公定法*1)では測定に5日間を必要とし作業の熟練を要することから,短時間で簡便な自動計測器が望まれていた。バイオセンサによるBOD測定法が平成2年9月にJISで制定され,この方式によるBOD計が各種排水の計測に実用化されている。 図5にBODの測定原理を示す。雑食性の酵母(トリコスポロン)の入った固定化微生物膜を,溶存酸素電極が挟み込む形でセンサが構成されている。膜内を拡散してきた有機物を,微生物が資化するときに消費する溶存酸素量が有機物濃度に比例することを利用し,溶存酸素の減少量からBOD濃度を求めている。短時間(40分以内)で連続自動測定ができ,低濃度(2mg/L)から測定ができる。 (3)トリハロメタン計 上水道の原水中の腐食質と殺菌用塩素との結合により生成するトリハロメタンは発癌性物質といわれている。しかし,公定法であるガスクロマトグラフ法は操作が複雑で熟練を要する,連続分析ができないなどの問題があり,連続で迅速な膜分離・蛍光定量法によるトリハロメタン計はこれらの問題を解決した画期的な分析計である。 図6にトリハロメタン計の測定原理を示す。 試料水はポンプで分離部に送り込まれる。分離部では水中のトリハロメタンが分離膜を通して分離され,別系統からポンプで送り込まれるニコチン酸アミドと水酸化ナトリウムの混合溶液に移行する。 反応部ではトリハロメタンとニコチン酸アミドが反応し,蛍光縮合体を生成する。そして検出部で370nmの励起光を照射すると,トリハロメタン濃度に比例した458nmでの蛍光を発生する。この蛍光強度を測定してトリハロメタン濃度を求めている。前処理が不要で,個人差のない測定ができ,短時間(40分)で測定ができる。0~200μg/Lの広い測定範囲をもち,公定法のガスクロマトグラフ法と高い相関性がある。 3.4 上水用水質計 (1)溶存オゾン計 オゾン処理はトリハロメタンを生成しない上に脱色,脱臭,殺菌の効果をもっており,上水の高度処理の中心的なプロセスとなっている。水中の溶存オゾン計測に使われている従来の紫外線吸光度式,電極式は,測定セルや電極の汚れの影響を受けやすい欠点をもっている。半導体センサ応用の溶存オゾン計は溶液部がなく,長期間の安定性を実現している。 図7に溶存オゾン計の測定原理図を示す。試料水は一定流量で抽出槽に導かれる。抽出槽の上部(試料液の表面)に清浄空気を一定流量で流し,水中の溶存オゾンをキャリアガス中に移行させる。これと同量の乾燥空気を混合し,半導体センサに送り込むと,半導体センサはオゾン濃度に比例した抵抗変化を示す。この抵抗値を測定し,検量線より水中の溶存オゾン濃度を求める。 無試薬で連続測定ができ,測定範囲が0.01~ 5mg/Lと広く,手分析(ヨウ素滴定法)と高い相関性がある. (2)凝集センサ 浄水処理の凝集プロセスでは,原水に含まれている濁質を凝集し沈澱しやすくするため,原水に凝集剤を注入し急速に攪拌した後,フロック(細かいゴミ,泥,微生物などの不純物の固まり)形成池で緩やかに大きなフロックに成長させる。凝集剤の注入率は原水の流量・水質などのパラメータにより適正値が求められるが,従来はジャーテスト*2)結果に基づき経験式を用いて注入率を決める方法がとられてきた。しかし,このジャーテストは時間がかかるので1日に1~2回しか実施できず,降雨時の急激な濁度変化などには追従困難で,オペレータが経験と勘によって対処してきた。 図8に凝集センサの浄水池への適用例を示す。混和池から水を凝縮センサに採取して,フロックのゼータ電位による電場内の動きを画像処理により定量化する。凝集状態を視覚的に捉え,適切な注入剤注入信号をコントローラに演算出力する。リアルタイムで計測でき,専用の凝集コントローラとの組み合わせにより凝集剤注入制御の完全自動化が実現できる。 4.水質計のメンテナンス 水質計の信頼性向上と性能維持のためには水質計の性能と機能の向上だけでなく,日常のメンテナンスが欠かせない。特に環境分野の水質計は,連続で常時監視を求められるほかに,設置環境や測定試料の性状も水質計にとって過酷な条件の場合が多く,日常のメンテナンスは測定結果の信頼性を維持する上で大きな比重を占める。 環境水質計の対象分野は,大気,水,土壌という広大な世界である。測定対象となる物質や物性は多種多項目にわたっており,試料性状や測定対象により測定原理が異なる多種類の水質計が存在する。定性や定量を行うため,水質計は測定対象の様々な化学反応や物理反応を利用している。水質計にトラブルが発生した時,測定原理や製品の構造と特性に基づいて客観的な事実を集めて原因を探ったり,過去のトラブル事例を参考に原因を特定している。 しかし,複合的な要因や過去の事例にないトラブルでは,原因究明までに時間がかかることがある。また,現場でないとわからないトラブルも多く,技術者が直接現場で様々な調査をしなければならない場合も多い。 このため連続計測を使命とする環境水質計では,水質計のトラブルは測定データの欠測となることから,速やかに正常復帰させるように強く求められる。 濁度計では,洗浄のために使用しているワイパ方式は間違いを起こしやすく,メンテナンス作業が大変な作業となる。こうしたことから,センサを清浄に保つため超音波洗浄装置を組み込み,高周波の振動発生により光学面の汚れを明瞭に減少させ,または汚れが堆積していくことを完全に防止するなどの改良が図られている。 5.水質計の導入メリット 水質計の導入は,プロセスの最適制御・監視に加え,設備管理の面でも予防保全や予知保全をさらに向上させるといった複数のメリットをもたらす。測定データをより速く送信されることを保証するだけでなく,精度を高め,それによりプロセス制御を改善し,設備の健全性を向上させる。水質計により,プロセスや設備からリアルタイムの連続データフィードが提供され,収集した情報を分析モデルと組み合わせることにより,データを統一指標で可視化することが可能となる。 インライン水質計の主なメリットには,データ取得時の感度の向上,ほとんどタイムロスのない伝送・通信,および連続的なリアルタイム分析が含まれる。リアルタイムのフィードバックとデータ解析により,プロセスが能動的になり,最適に実行される。センシング技術の絶え間ない進化は,解析や情報処理の能力が付加されたインテリジェンスを持つスマートセンサを搭載した水質計を生み出した。 水質計に搭載されたインテリジェントセンサは,自己テスト,自己検証,自己適応,自己識別など,本質的にインテリジェントな機能を実行できる。これらはプロセスの水質要件を理解し,幅広い条件を管理し,リアルタイムの意思決定を支援するための水質条件を検出できる。 6.水質計のさらなる進化 センシング技術は,プロセス自動化の進歩に合わせて進化しており,より高性能でネットワーク化された水質計が展開されている。産業の進歩やデジタル化への移行が加速するにつれて,プロセスの自動化の強化,異常検出機能の強化,および予知保全機能の必要性が,水質計やセンシング技術のさらなる導入を促進している。 6.1 期待される水質計 小型化にもかかわらず,今日の水質計は非常に強力で高い応答性を備えている。故障率が低く,以前よりも消費電力が少なくなる。近い将来,プロセスは水質計からの電子機器の大幅な小型化とさらなる進歩に加え,低価格,消費電力の削減,応答性の向上,障害に対する高耐久性を実現する機能の向上を期待できる。多くのプロセスプラントでは,プロセス制御用の水質計とデジタル化された操作を既に導入しており,データを検出,報告,分析してプロセスの効率を高めている。 次なる進歩へ向けた水質計システムは,データを収集する単なる分析計ではなく,データに価値を付加する分析メイキングへシフトすることである。さらに性能性を向上させ,持続可能な操業を実現するには,これまで測定が困難であったプロセスの水質分析データのより広範囲な収集,あるいは過去に使われていなかった高精度なプラントの水質データの利活用が必要である。 6.2 IoT水質計 産業用IoT(IoT:Internet of Things)の急速な進化は,その用途と範囲をさらに拡大し,補完している。IoT水質計は各水質計から自動計測されたデータを通信回線やWi-Fiでクラウドへ蓄積し,Webブラウザから水質データをリアルタイムで参照することができる。水質データの計測推移がグラフや一覧で表示される。過去のデータを参照し水質異常時にアラート通知が可能となっている。さらに,インテリジェントセンシングと人工知能(AI)あるいは機械学習を組み合わせることにより,迅速な意思決定を支援し,プロセスや設備のパフォーマンス最適化を推進する。 スマート製品に対する需要の高まりと,プラントのデジタル化の加速に伴い,IoT水質計の役割と重要性は成長し続ける。そして,多数のIoT水質計を使用し,堅牢で信頼できるセンサシステムを構築するには,現在よりも安価で設置が簡単なことが鍵となる。 なお,センサと測定機能が一体化したスマートセンサを搭載したIoT水質計については, ・変換器を使用せずに,機器診断機能を使用したい。また,センサ部のみを交換したい。 ・センサの保守作業を改善したい。 ・DCS などの上位機器,レコーダ,指示計,タブレットなどに接続してデータ監視システムを搭載柔軟に構築したい。 これらの課題やニーズを解決する機能を組み込んだIoT水質計も開発されつつある。 6.3 カメラ画像監視水質計 工場などから流出した油類や化学物質が原因となる水質事故は,毎年多数発生している。排水処理施設や下水処理場では,これらの水質事故を防ぐため,技術員が定期的に水質状況を目視で確認している。 水質異常に関する分野での国内の民間企業や研究機関では,AIやIoTなどの最新技術を用いた,カメラ画像監視技術の研究開発が多数実施されている。リアルタイムに水質状態を判定し,色や粘度などを基に水質異常を判定する技術である。さらに,深層学習の一種であり,高度な画像解析能力を持つニューラルネットワークを用いて,カメラ画像から水質異常の発生を検知するモデルを構築し,水質監視の高度化・省力化を図るシステムも研究開発されている。 7.おわりに ナノレベルの超極小型センサが実用化されるほど,現在のセンサ技術の進化は目覚ましい。水質計に関する下記の項目を向上させるため,我々計装技術者は今後もさらに,センシング技術・情報技術・化学知識を磨かないといけない。 ・多種多様の試料を計測する水質計に対して,試薬による校正,メンテナンスの効率向上を考慮して水質をより正確に計測する。 ・分析に時間を要するオフライン水質計の効率向上とインライン化するための代替技術の開発。 ・近傍の配管振動などを利用したエネルギーハーベスト技術を活用して,水質計のエネルギーの消費を削減する。 <謝辞> 最後に,著者が担当した発電プラントの分析計,水質計・薬液注入装置などプラントの環境・水質向上のエンジニアリングにご助力いただいた,日機装㈱,㈱櫻製作所,東亜ディーケーケー㈱,横河電機㈱,㈱堀場製作所,㈱島津製作所,日本ガイシ㈱,ABB㈱の関係各位に感謝致します。 注) *1)公定法とは,分析化学・微生物培養の分野において成分の定性分析,定量分析,微生物の培養検出を行う際,国際機関,国家もしくはそれに準ずる公定試験機関,研究所において指定された方法をいう。 *2)ジャーテストは,日々変わる水質に対してどの程度の薬品(凝集剤)を入れると適正なのかを比較し調べる試験。 〈参考文献〉 1)竹内,黒岩:『実務の計装技術』,電気書院, pp.96-103,1999 2)石井,土井,日野:「環境保全に貢献する次世代液分析計FLXA402/SA11」,『横河技報』,Vol.62,No.1(2019) 3)『HORIBA Technical Report』,Readout No.31, pp.84-87,2005 4)宇都宮,小松,土性,他:「深層学習を用いた水質異常検知に関する研究-排水処理施設でのF/S の実施-」,『AI・データサイエンス論文集』,Vol.3,No.J2,pp.231-237,2022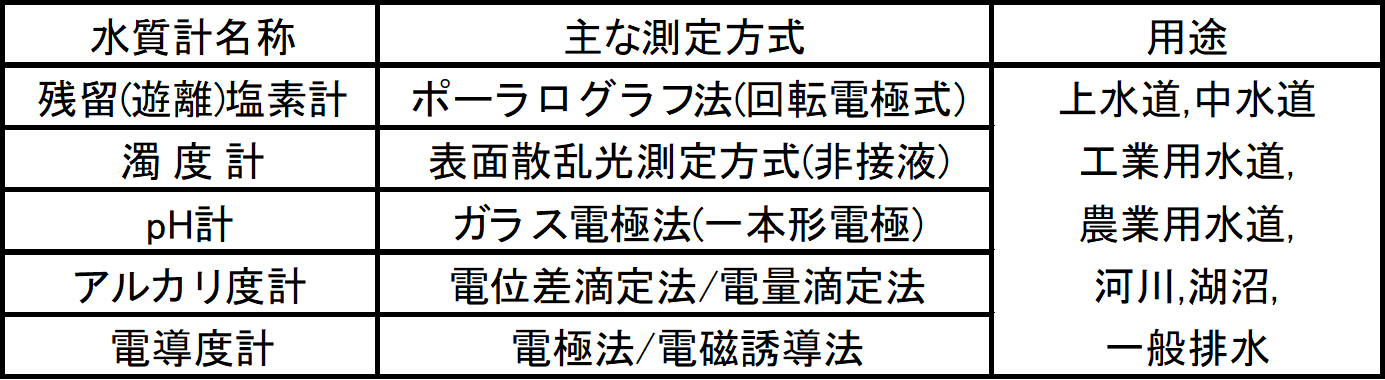
表1 一般用水質計一覧
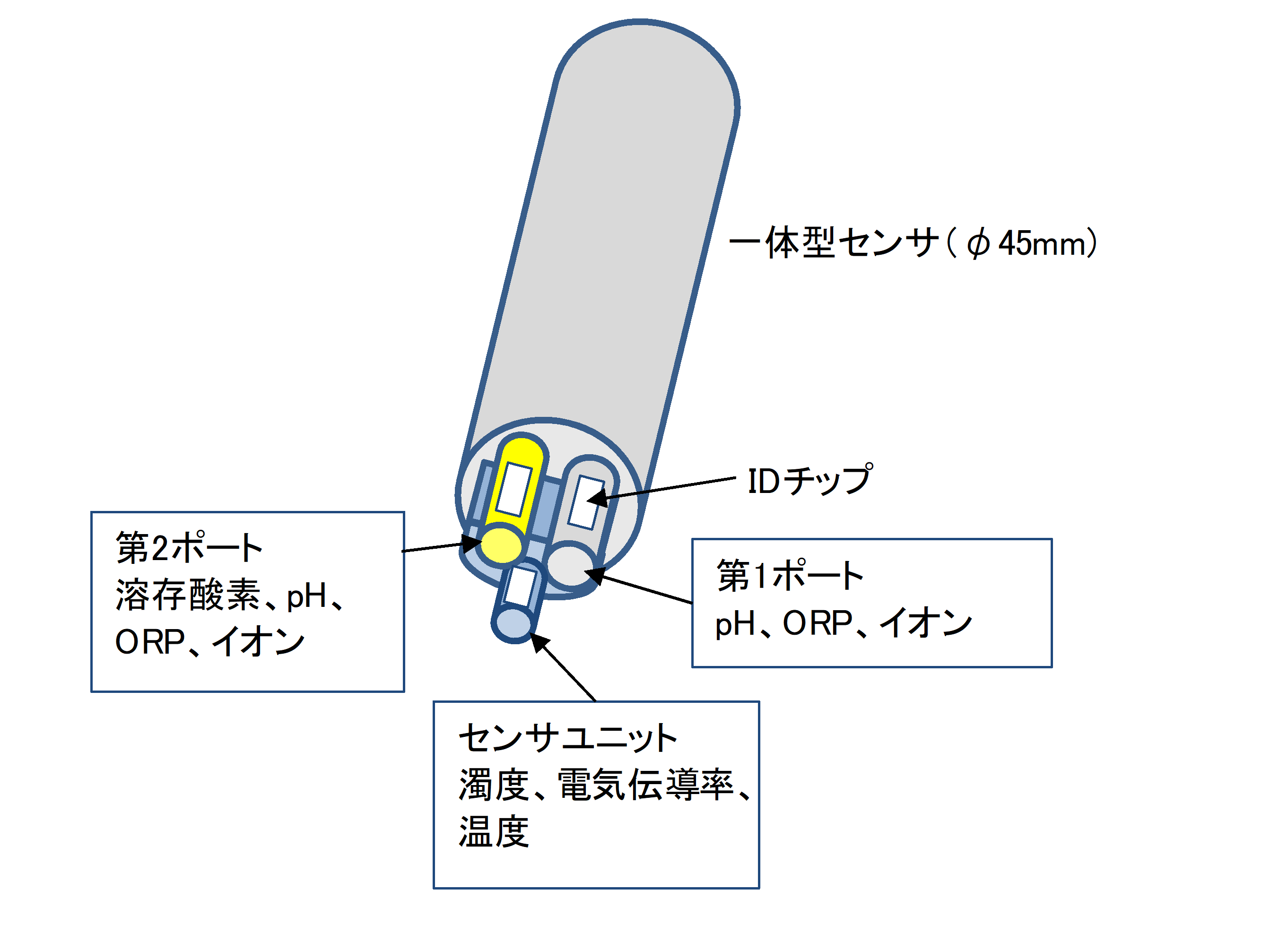
図2 多項目水質計の例
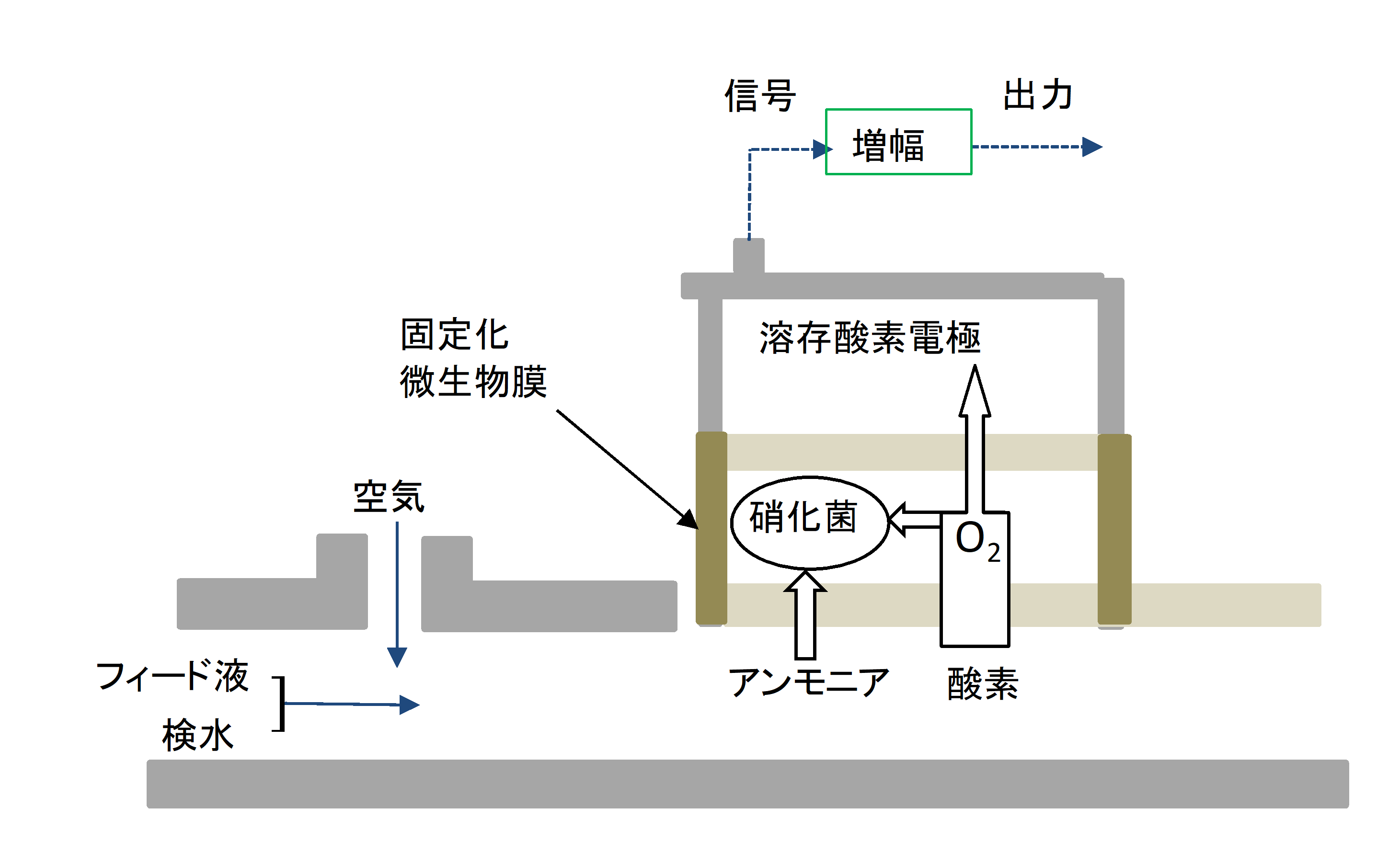
図3 水質安全モニタの原理図
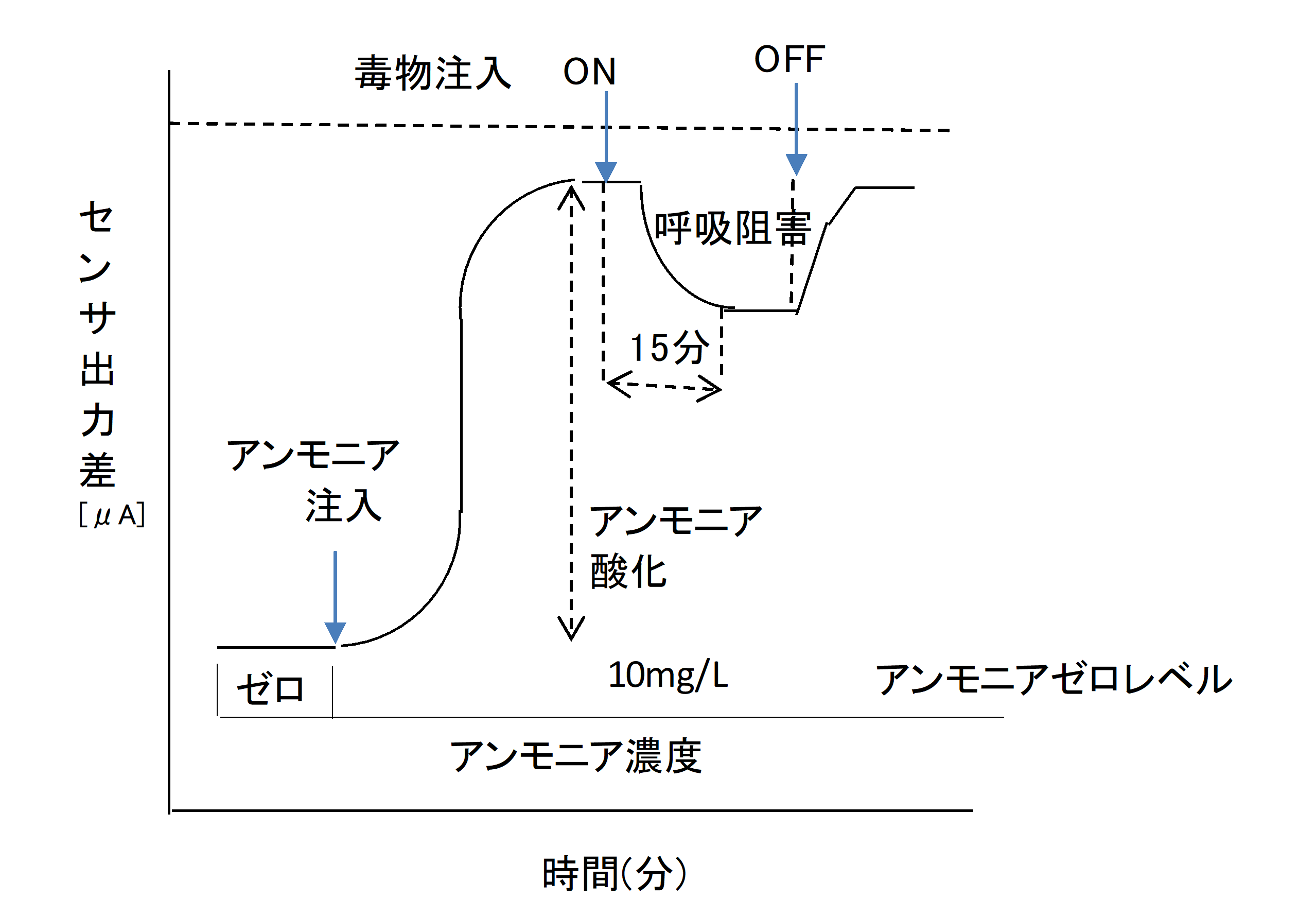
図4 水質安全モニタの応答図
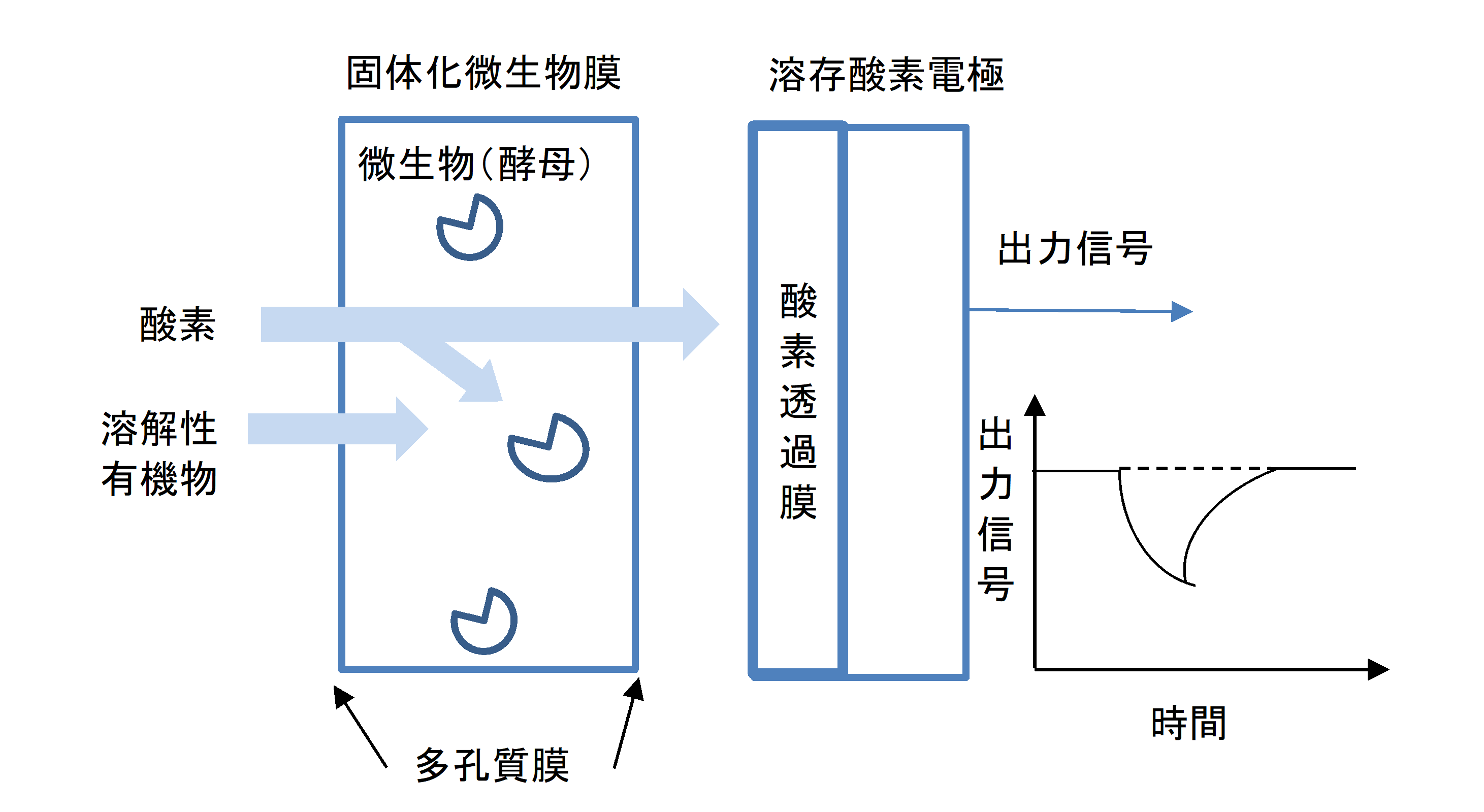
図5 BOD計の測定原理図
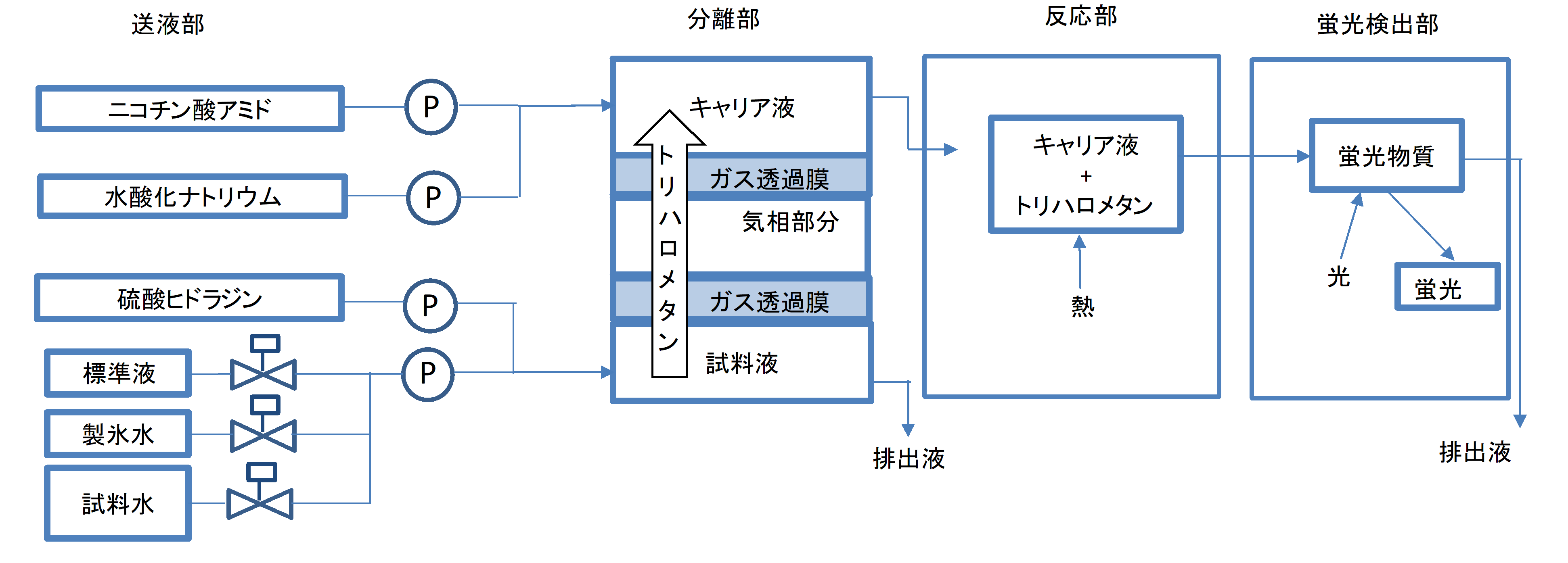
図6 トリハロメタン計の測定原理図
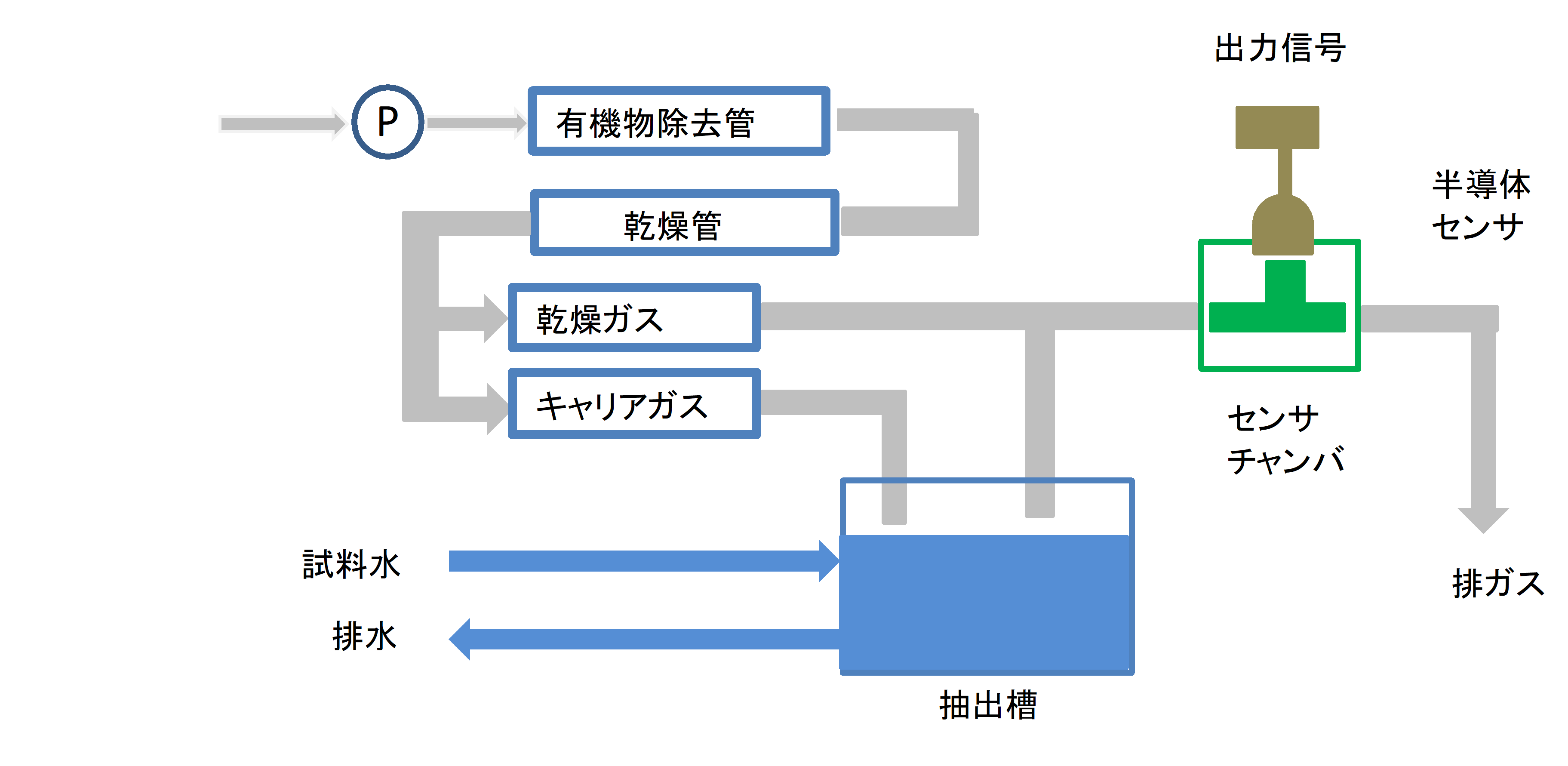
図7 溶存オゾン計の計測定原理図
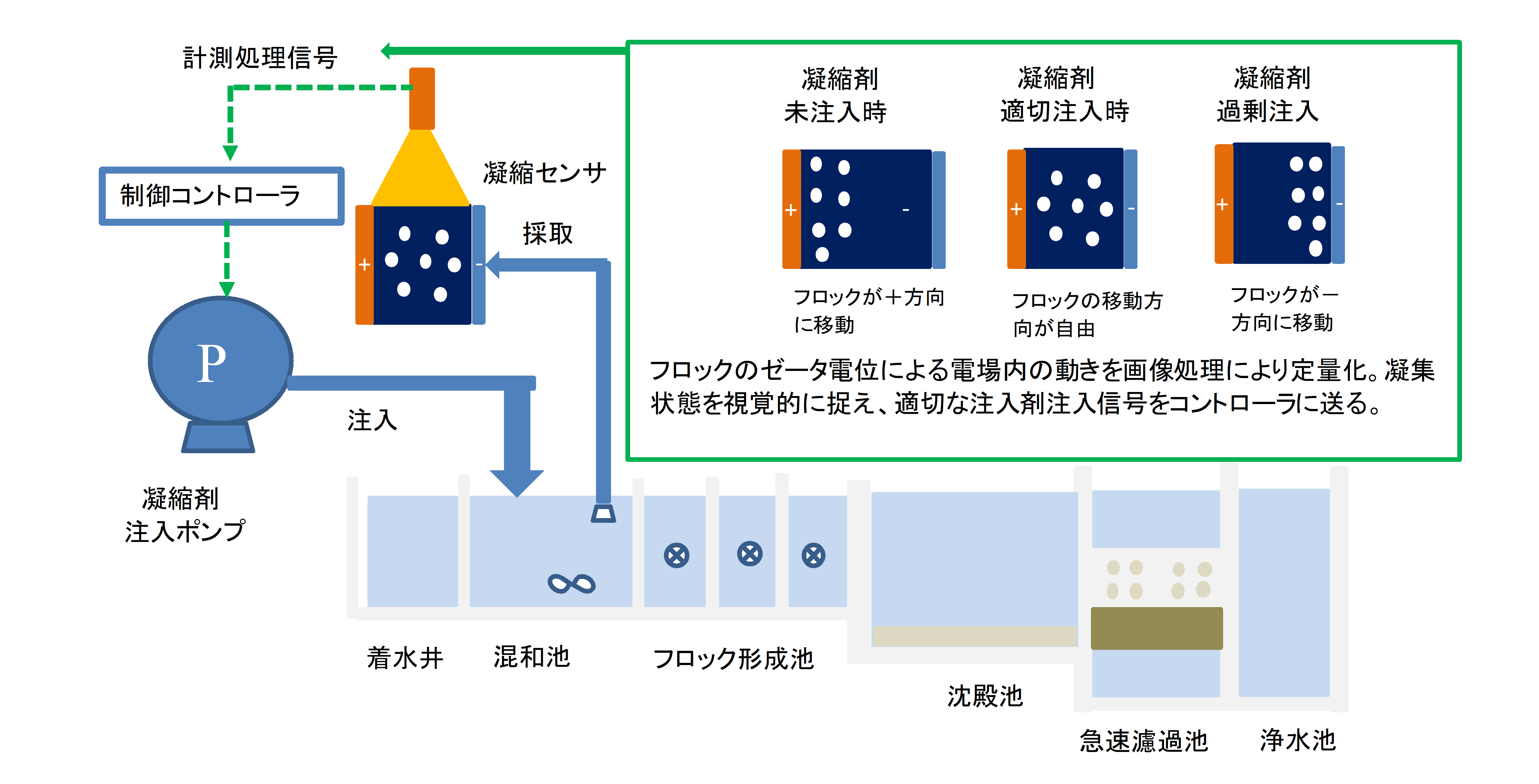
図8 凝集センサの浄水池への適用例
ポータルサイトへ