

【プレゼンテーション】
製造DXによる“変化に追従できる工場”の実現 ~生産システムの新たな役割~
1.はじめに
日本のモノづくりは,高い品質と性能で世界をリードしてきた。それを支えていたのは,現場の徹底したカイゼンや擦り合わせ活動を通じて,顧客ニーズに即した高品質なものを追求するという現場力の高さである。
しかし,最近日本のモノづくりを取り巻く環境は非常に厳しい。アジアを中心に新興国の追い上げ,国内では労働人口の減少,設備の老朽化,技術伝承の難しさなど早急に取り組まなくてはならない課題が山積みである。ところが,ここにきて世界的にはコロナ渦が沈静化傾向にあり,各国が経済優先に舵を切っている。その結果日本の経済も堅調さを取り戻しつつあり,受注が増加している。目の前の繁忙さが構造的な課題の解決を先送りにしてはいないだろうか?
政府は,国内経済は日本のモノづくりが支えていると認識しており,DXレポートなどを発行し,製造業に対し,デジタル技術を利用し山積みの課題を早急に解決するよう後押しをしている。
本稿では,これらの課題解決の一助となる弊社のソリューションを紹介する。
2.モノづくり現場の状況
設計通りに運転しているのに品質が悪くなることがある,その結果,歩留り悪化,収率が低下している。自動化システムが導入され管理ポイントを守って運転しており,アラームも出ていないのになぜ品質が悪くなるのだろう,原因が良くわからない。こんな声が10年位前から聞こえていた。
調査するとほとんどの原因は,4Mの変化に起因していた(図1)。たとえば,原料,コストダウンのために仕入先を切り替えたが,当然成分は基準範囲に入っている原料なのに,不純物など何かが微妙に違う。次に設備,保全部ががんばってメンテナンスをしているが,設備の性能は導入時に比べると少しずつ下がってきている。このように自動化システムで設計情報として制御してきたパラメータ以外に起因するものが多いことがわかってきた。そのため,従来通りの管理ポイントを制御し,管理幅を守っても品質が悪くなるといったことが時々生じている。
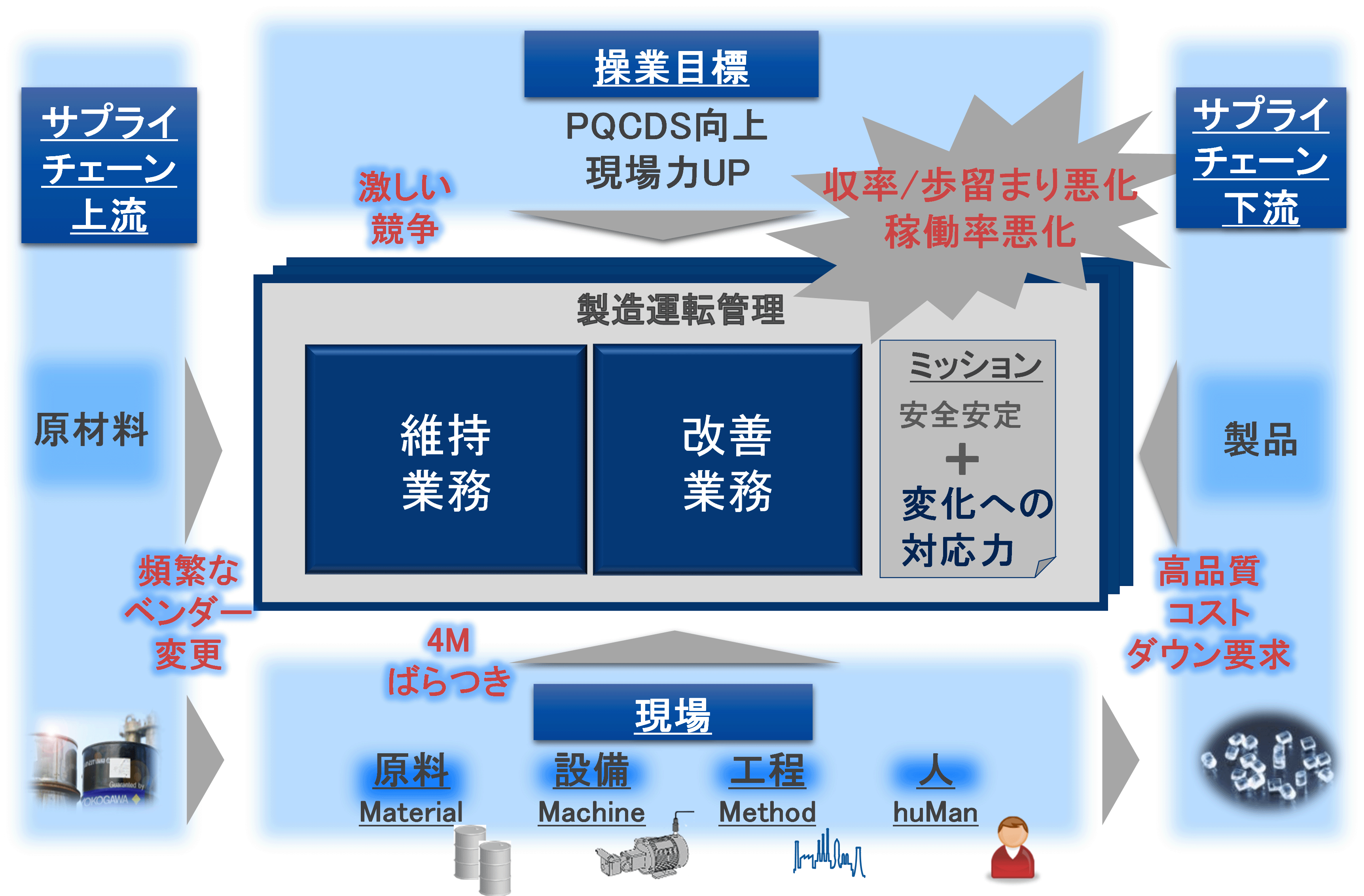
もちろん,現場ではこの状況を自動化システムだけに頼るのではなく,ベテランのカン,コツ,経験を現場ノウハウとして調整し品質を維持している。ただし,省人化で人が少なくなっているにもかかわらず,手間が増えて現場は大忙しになっている。さらに,この先もモノづくりを取り巻く環境はますます大きな変化が進んでいるため,現場の負担が大きくなっていくであろうと思われる。
3.国のDX推進の動き
経済産業省は早くからDXの重要性を認識し,2018年に「DXレポート初版」を発行し,2025年を目標にDXの実現を進めることが記されている。その後経済産業省が調査したところ9割の会社が何も取り組んでいないことがわかり,2021年に「DXレポート2.0」を発行した。
また直近では,活動を後押しするため,東京証券取引所および(独)情報処理推進機構と共同で「DX銘柄」を選定し,2022年6月に,「DX銘柄2022」選定企業33社と「DX注目企業2022」15社,DXセレクション16社,表彰DX認定業者30社を認定した。
このように,国は日本のモノづくりをより強くするためにDXを一層加速しようとしている。
4.制御性改善から,モノづくりの見直しへ
以前からYOKOGAWAには,制御性改善などの相談が寄せられていた。しかしこの3,4年は,制御性改善だけでは解決せず,モノづくりそのものを見直したいとの相談が多くなっている。相談を進めるとその裏には,必ず本社からの『DXを推進せよ』という命題をもっている顧客企業がほとんどである。
さらに,直近1年に絞ると,8割の顧客企業の相談は,DXのコンセプトを考えるフェーズから,DXの実装フェーズへと移ってきている。これは,前述の経済産業省のDXレポートにある2025年目標と連動していると考えられる。
しかし,実装フェーズに入っているユーザの多くが,中々思うように進んでいないのが実情である。その多くが,とにかく蓄積されたデータから何か新しいことを見つけようと,AIや機械学習という技術を利用して取り組まれているが,『思うような結果がでていない』,『結果に現場が納得してもらえない』,『現場と本社の意見が食い違い困っている』など,多くの不安や相談が寄せられている。
次章からは,これから製造DXに早急に取り組みたい,あるいは取り組んでいるがしっくり来ていない,こんなユーザに向けて現場も本社も両者が納得する製造DXを実現するためのヒントをお伝えする。
5.変化に追従できる工場
今まではいろいろなものが安定していたので,各部署が与えられたミッションをより効率的に実行することが重要であった。しかし,4Mが変化する状況においては,設計通りの製造は成立しない。(設計では考慮しきれない)効率だけを追いかけてもモノづくりが上手くいかなくなってきたからだ。これからは,設計情報とともに,いろいろなものが変化することを前提に各部署が壁を取り払い協力して“知恵を創出”する両輪での製造が重要である。
知恵の創出の手段は2つある。
・すでにある現場の知恵の定量化,ロジック化
・設計,実績のGAPの定量化と原理原則との考察
YOKOGAWAは,製造DXでやるべきことを,ビジネスアジリティを支える『変化に追従できる工場』への進化と定義した。
これを実現するソリューションとして,弊社のモノづくり変革ソリューション「Digital Plant Operation Intelligence」を紹介する(以下,DPI)。
6.モノづくり変革ソリューション「DPI」で実現する4つの要素
DPIでは,製造DXの実現=変化に追従できる工場の実現に向けて,ポイントを4つの要素に整理した(図2)。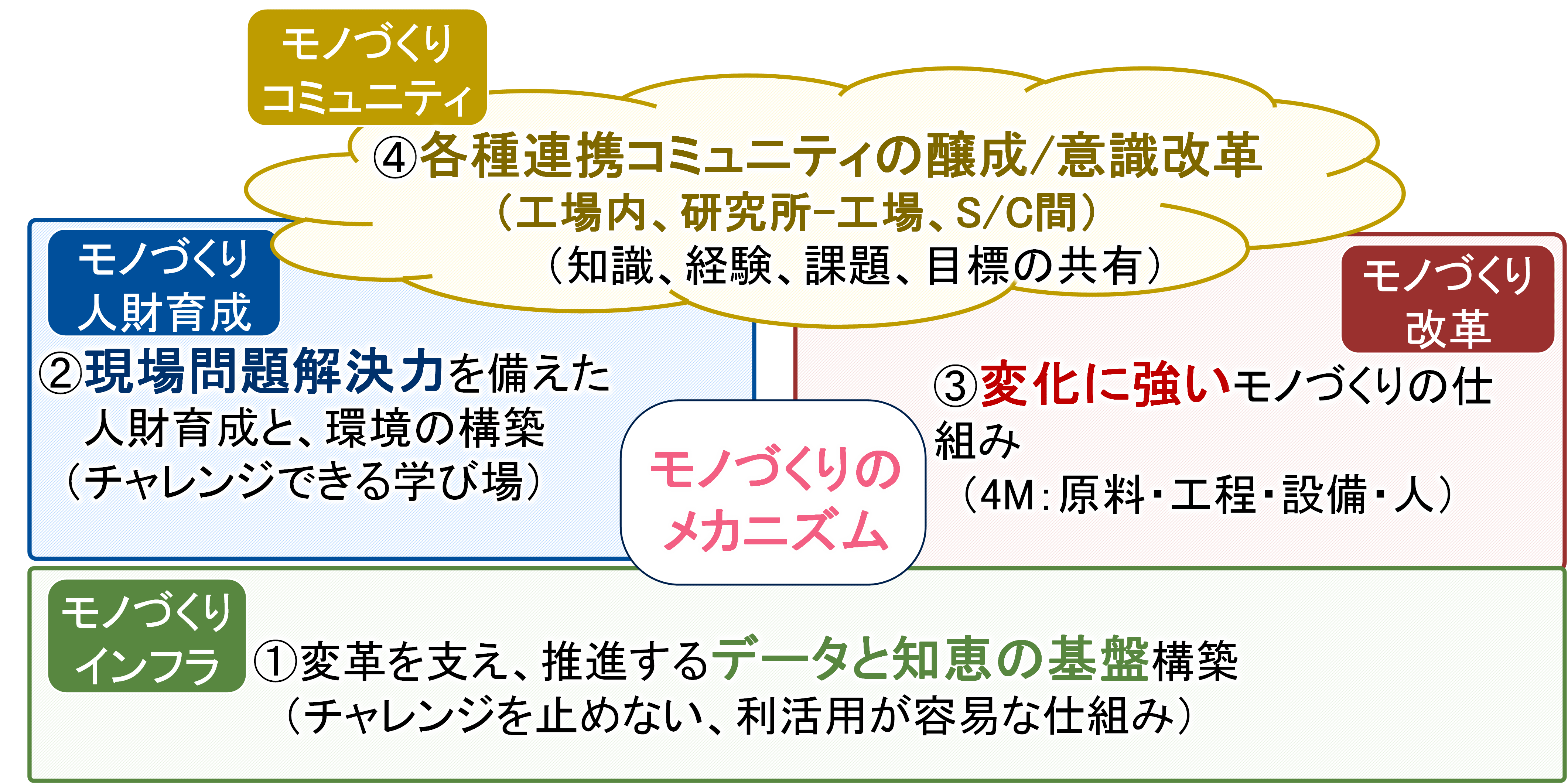
6.1 モノづくりインフラ
製造DX実現の大前提として,データ活用基盤の構築が挙げられる。データをデジタル化するところに課題の焦点が当たるが,多くの場合はデジタル化されたデータをモノづくりの観点で意味のある形に統合するところに難しさがある。
インフラ構築にあたっては,一般的にはOT領域とIT領域のデータ統合というテーマで検討が進められることが多い。しかし,OT領域のデータは,モノづくり設計情報をより正確に実行するために蓄積されているデータであり,IT領域のデータは,モノづくりの状態を管理するためのデータである。それぞれ目的が異なるため,単にデータベース同士をつないだだけで実用性のあるデータ統合を実現できるわけではない。
モノづくりの状況を正しく認識,評価し,本来の設計情報とのギャップを見つけ,対策を立案するために,モノづくりの情報として使いやすい形に変換して結合する必要がある。どのデータをどのように変換すべきか,これがまさにモノづくり現場の知恵であり,現場固有の事情を踏まえたデータ解析を行うことによって得られる競争力である。
6.2 モノづくり人財育成
4つの要素の中でも最も重要なポイントである。
オペレータ自身がスキルアップし,モノづくりのノウハウを見える形で表現する必要がある。近年流行しているAIや機械学習を活用することも視野に入れる必要はあるが,モノづくりに原理原則が存在することを考えると,AIや機械学習だけに頼るのではなく,実際に起きている事象とデータからモノづくりの本質を見抜ける手腕があるかどうかが,知恵の創出成功のカギとなる。
また,活動を進める中で部署間の連携・協力が必要となる。したがって,組織をまたがって活動全体を推し進められるリーダ的存在も必要である。
6.3 モノづくり改革
現場の知恵を見える形で表現できた後は,それを仕組み化する必要がある。たとえば,製造前,製造中,製造後というフェーズで区切った場合,
・製造前:4Mの状態に合わせたモード別製造
・製造中:いつものとの違いの検知と回復
・製造後:次の製造への新たな知恵の引継ぎ
といった具合にそれぞれのフェーズで必要な要件が異なる。各場面に応じた要件は,原理原則からの設計情報をベースに製造運転する従来の制御システムでは本来対応できない領域であり,設計情報と4M状況を考慮した知恵ベースの製造運転として変化に追従できるアクショナブルな意思決定支援システムが必要となる。
6.4 モノづくりコミュニティ
上記の3つの要素,“インフラ”,”人財育成”,”モノづくり改革”これらを揃えて一つの現場だけでやっていても,この活動は続かず,広がらない。現場の知恵は重要ではあるが,本来の設計に遡りながら本社,R&Dも巻き込み,組織を超えてベクトルを合わせて変化への対応を進めることが重要であり,そのためのコミュニティが必要となる。
7.DPIソリューション
以上の4つの要素に対応した,DPIのソリューションから『人財育成サービス』と,現場から創出された知恵を運転で利用する仕組み『アクショナブル意思決定支援システム』を紹介する。
7.1 人財育成サービス
4つの要素から“6.2人財育成”と“6.4コミュニティ”の活路を見出すために,近年注力しているワークショップについて過去事例を交えて概説する。
事例の舞台となるのは,ABC化学㈱(仮称)高機能ポリマ製造課である。ここの現場では,データを用いた製造改善をやるべきであるという雰囲気が高まっていた。担当者の中には自らテーマを考え,孤軍奮闘ながらも試行錯誤し活動を進めるメンバもいた。しかし,メンバの頑張りで本社上層部への活動報告をするものの,内容に自信や確信がないことから,上層部からの指摘に対応できず,モチベーションが下がってしまっていた。その結果,後続のメンバも現れず,活動は停滞状態であった。
この状況の中,YOKOGAWAのコンサルタントも参画してワークショップが始まった。このワークショップでは,扱うテーマは実課題とし,複数部署(製造,品質,設備,計装など)でチーム体制を構築,“ワイガヤ”によって多角的に仮説を洗い出した。その仮説をデータで検証し,チームでの議論を通して現場の知恵を集結させていくプロセスを踏んだ。
その結果,担当者だけではたどり着けなかった技術的な製造条件が判明した。さらに,ワークショップを進行する中で,各自がもつ知識やスキルは,他のメンバにとってはすぐに真似することができないモノづくりの知恵であることがわかり,チームメンバの個々のモチベーションが向上していった。現場が覚醒した瞬間とも言える。
ワークショップ終了後は4つの要素のうち,上層部のメンバも含めてインフラやモノづくり改革のあるべき姿について議論した。組織横断で,「変化に追従できるモノづくりを実現するんだ」という強い姿勢が見え,One Factoryになりつつあると実感した。
本事例では,データサイエンティストだけではなく,製造スタッフが今まさに反応がどのように行われているか,どのようなオペレーションがなされたかなどを想像しながら仮説を立て,これを実データで検証する,そこに弊社のコンサルタント(第三者視点)が入り“なぜなぜ”をくり返すことで,過去からの思い込みを排除できた。この成功例から学ぶことは,このようなプロセスを踏むことにより,現場の製造スタッフ全員が理解し納得する結果を導けたことである。
7.2 アクショナブル意思決定支援システム
4つの要素から,『インフラ』と『モノづくり改革』について,現場で運用される生産システムに求められる新たな3つの要件として説明する。
(1)IT/OTコンバージェンスとモノづくりのためのデータレイク
モノづくりDXがうまくいっていないユーザの多くは,モノづくりDXの第一歩であるIT/OTコンバージェンスでつまずいており,「モノづくりの見える化」「全体最適な意思決定支援」まで辿り着けていない。変化に対応するためにITシステムとOTシステムを繋ぐことにチャレンジするが,いざやろうとしてみると直接繋げるのは難しい。
モノづくりインフラで説明した通り,ITシステムとOTシステムは目的が全く異なるので,YOKOGAWAは,ここにモノづくりのためのデータレイクを含んだ新たなシステムを追加して,ITとOTをつなぐことを提案している(図3)。
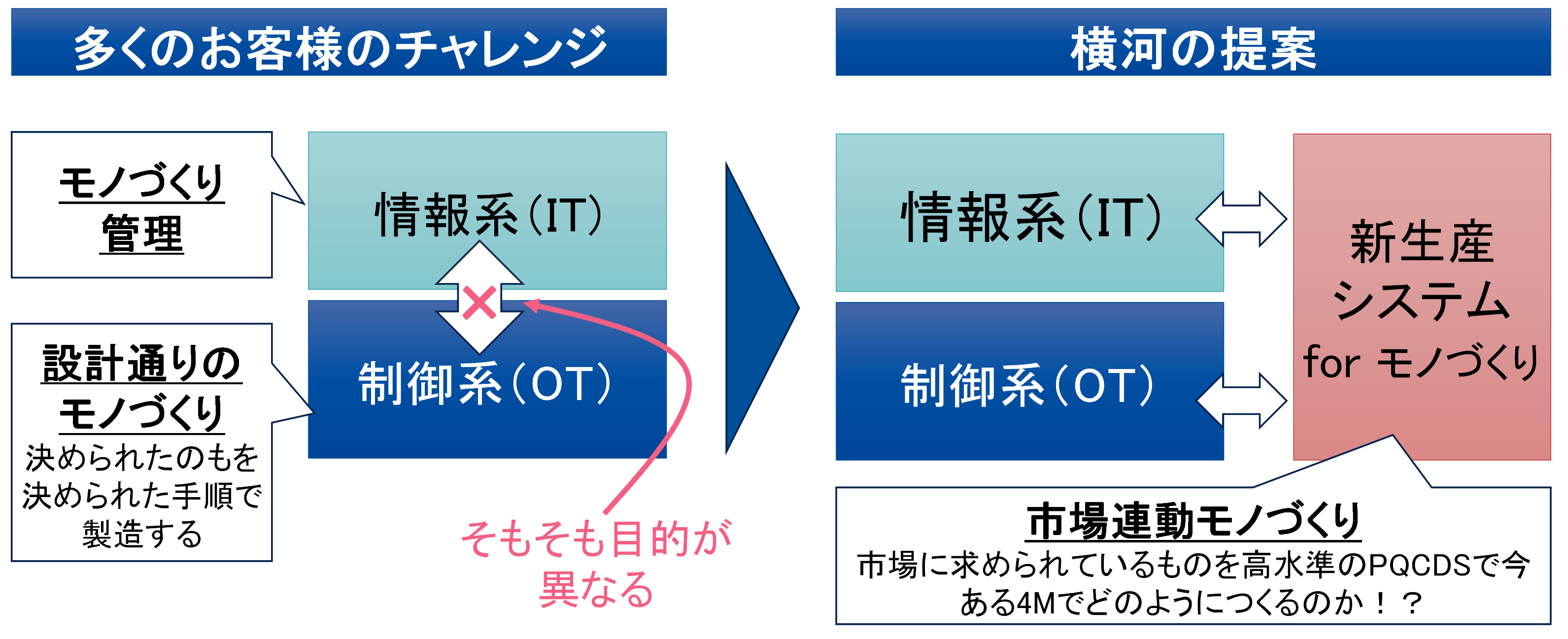
(2)知恵の創出・活性化・研鑽
現在,工場の熟練者は,高度な判断を既設システムからのデータと自身が持っている経験やノウハウを駆使して行っている(図4)。このような熟練者の判断を現場全員が同じように行うことは難しく,さらに,変化が激しい状況では,より迅速な判断が求められ,ますます難しくなっている。
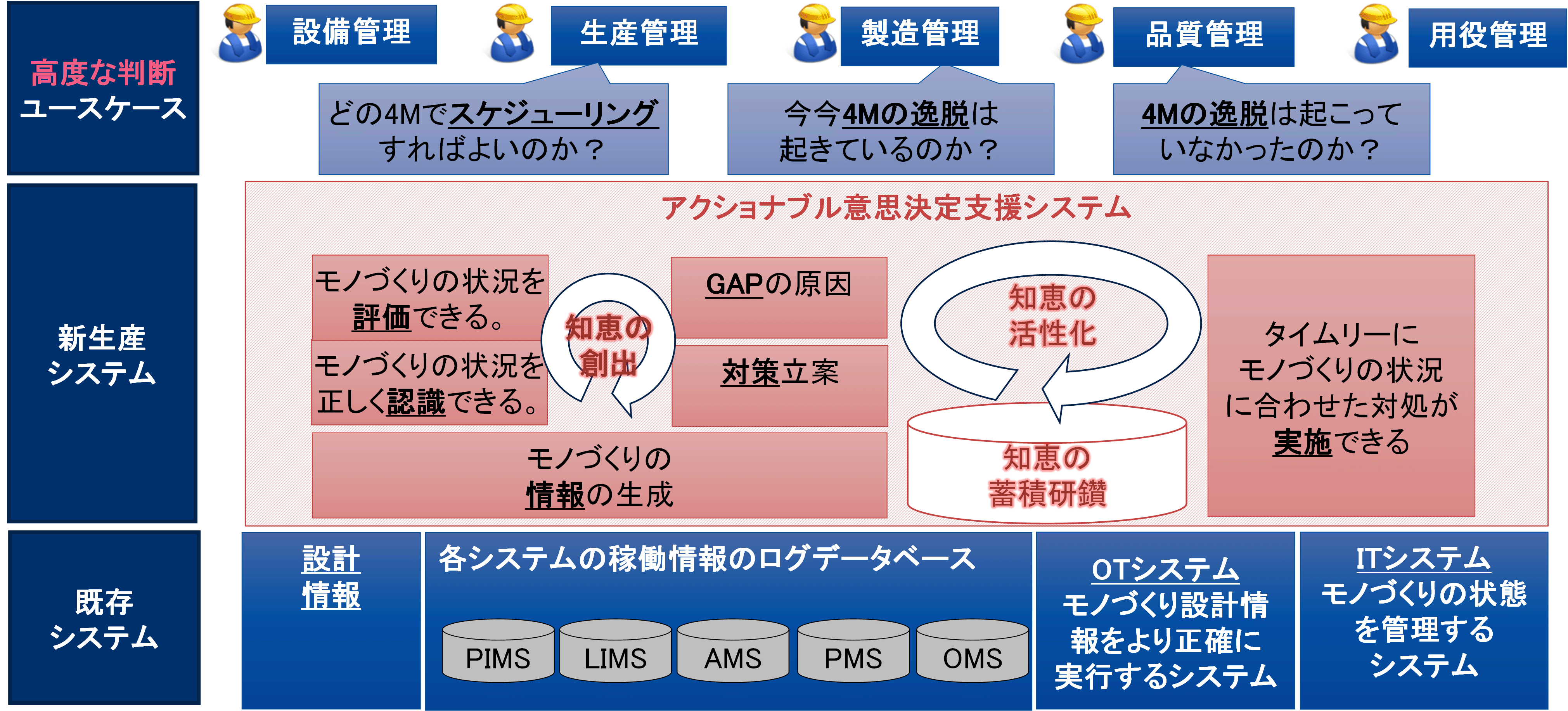
このような課題に対して,モノづくりに関わる人達の知恵を扱えるようにすること,それが,新生産システム,『アクショナブル意思決定支援システム』である(図5)。
新生産システムでは,既存システムのデータからモノづくり用の情報を生成し,その情報を使って,モノづくりの状況を正しく認識し,評価する。そして,設計情報とのギャップを発見すると,その原因を特定し,対策を立案する。この一連のサイクルが『知恵の創出』である。 そして,創出された知恵をモノづくりの状況に合わせてタイムリに利活用することにより,どの担当者でも同じように高度な判断が素早く行えるようになる。これが『知恵の活性化』である。 また,知恵は蓄積され,使いこまれることでブラッシュアップされていく。これが『知恵の研鑽』である。 (3)制御からモノづくりへ アクショナブル意思決定支援システムは,既設の制御システムに追加される形で導入される(図6)。 設計ベース,つまり決められた管理幅に入るように制御を行う制御システム(DCS)と,知恵ベース,つまり4Mの変化に対して知恵を使ってオペレータを支援するアクショナブル意思決定支援システム,この2つのシステムが互いに補完することで,変化に追従できるモノづくりが実現されると考えている。 8.おわりに 変化に追従する工場を実現するための製造DXの4つの要素を概説した。 モノづくり現場で長年培ったカン,コツ,経験をデータで検証し,現場の知恵のデジタル化を実現し,誰もが使えるように,既存システムに補完する形でシステムを導入することで,労働人口の減少,技術伝承の課題に対応しつつ,変化に追従する工場が実現できるようになる。 この結果,日本のモノづくりが今までも,そしてこの先も世界をリードすることができると考える。YOKOGAWAは引き続き,製造DX実現にチャレンジする製造現場を支援していく。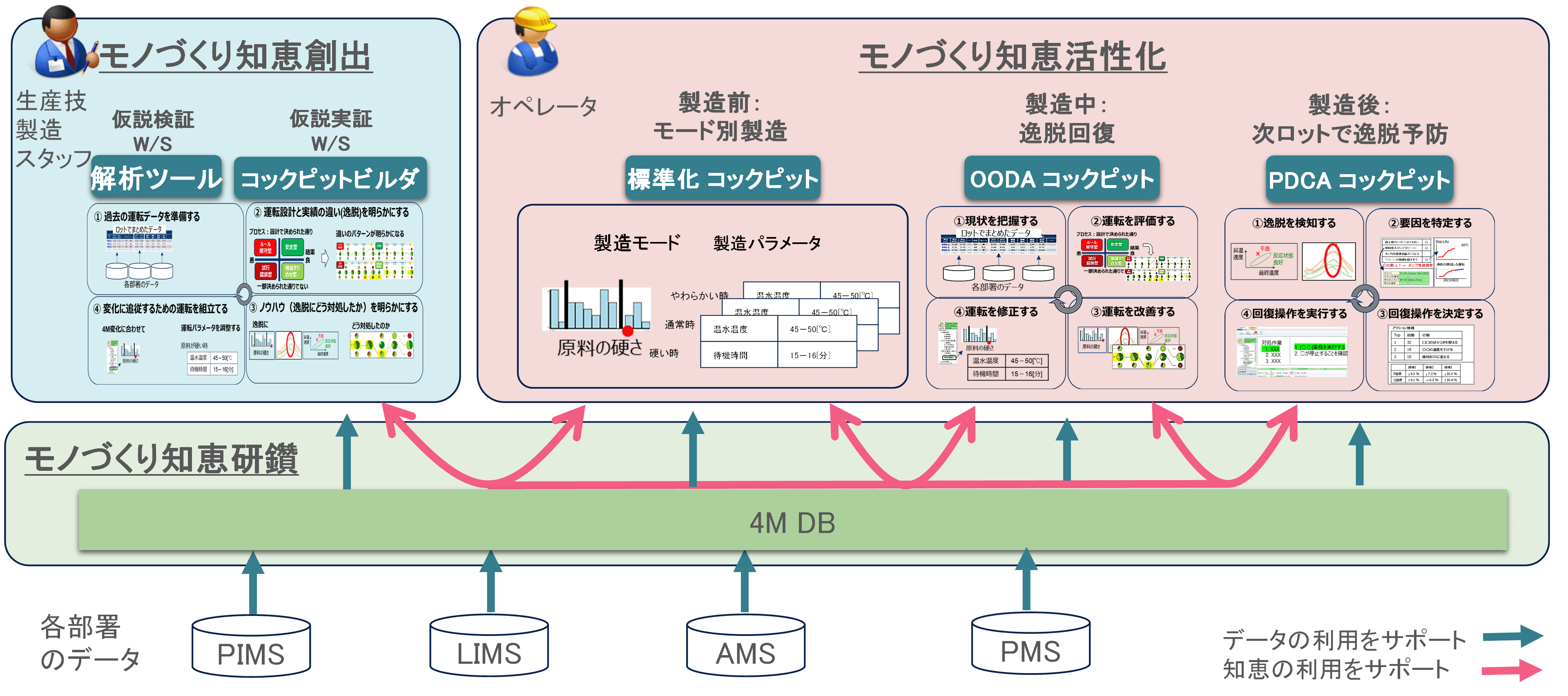
図5 新生産システム「アクショナブル意思決定支援システム」
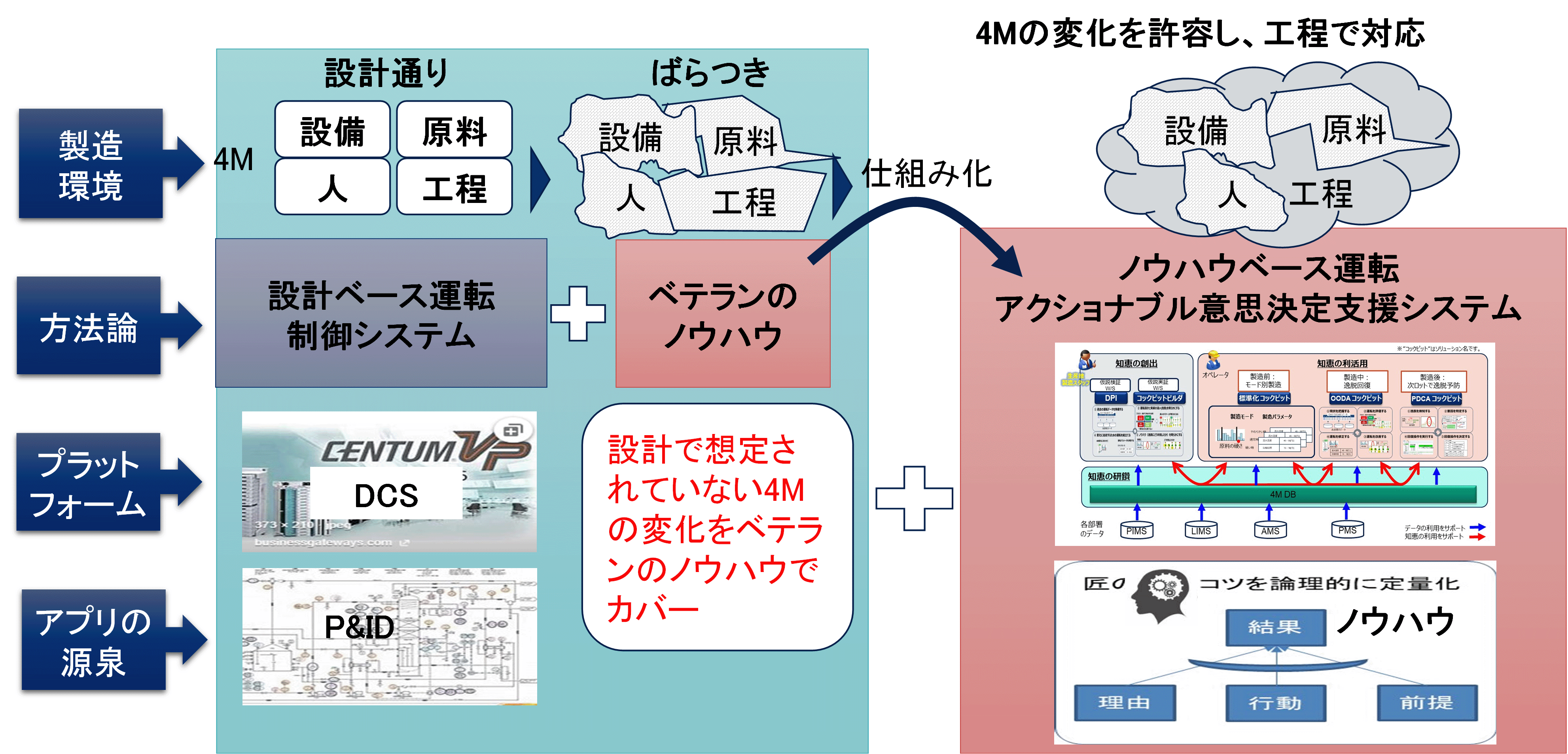
図6 生産システムの新たな役割
ポータルサイトへ