

【巻頭フォーカス】
スマート保安と予兆監視・予知保全
1.はじめに
軍事侵攻や震災,気候変動,新型コロナウイルスによるパンデミックなど,少し前には想定していなかった出来事が次々と起こっている。一方では,AIやバイオテクノロジーなどの技術が急速に進歩し,次々と常識を覆している。今までの常識が非常識となり,変化が起こる前の姿には戻ることのできないニューノーマルである。
ニューノーマル時代においては,不透明かつ予測できない様々なリスクに対応した従来とは異なる事業継続計画が必要であり,その実現のためにはデジタル技術の活用が不可欠となる。「ものづくり白書」1)によると,ものづくりのニューノーマルでは,レジリエンス,グリーン,デジタルの3つの視点が重要であると述べられている(図1)。
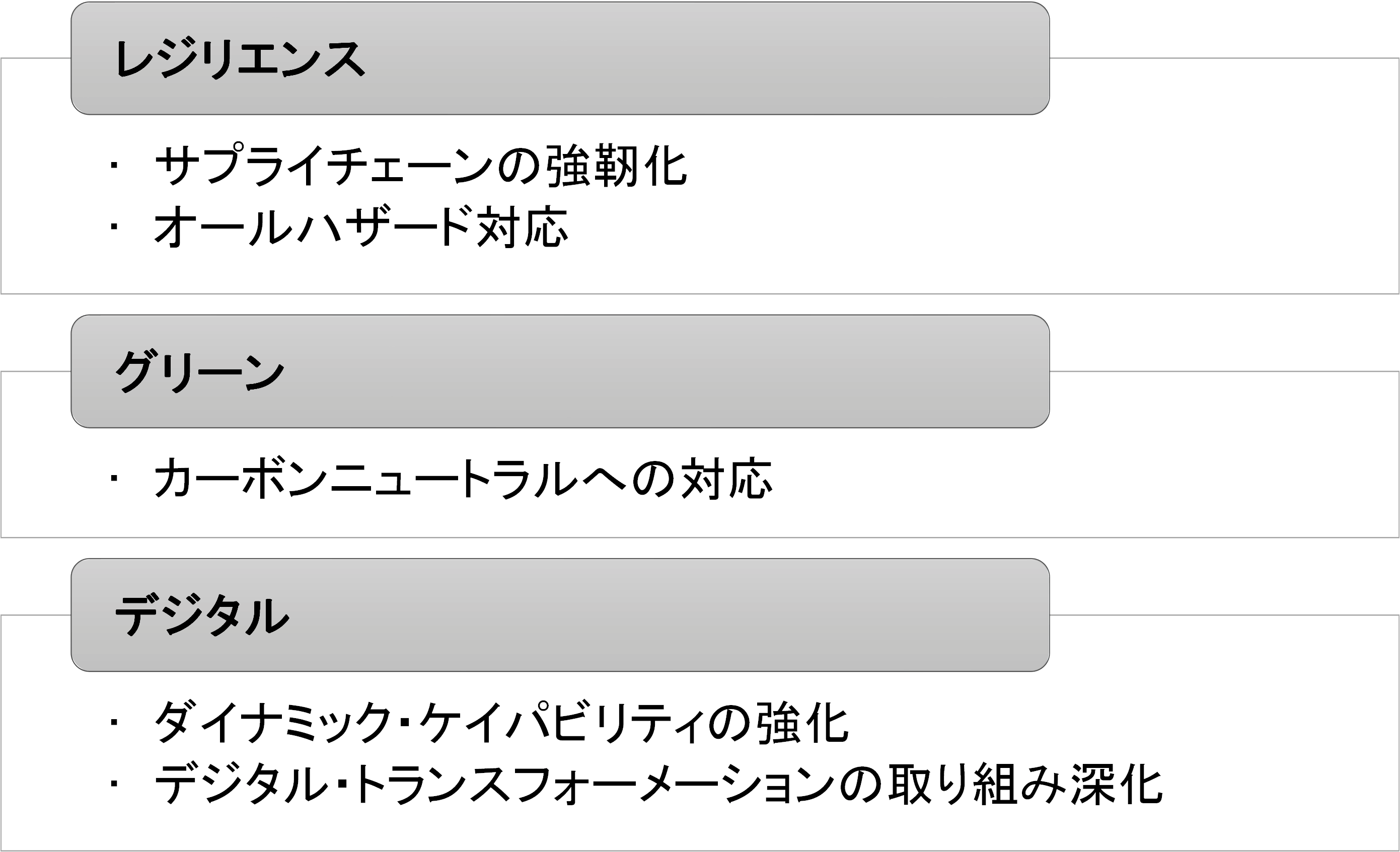
中でも特に重要な要素はデジタルであり,レジリエンスやグリーンへ対応するためにもデジタルなしではあり得ない世界となっている。ものづくりのデジタル化は,スマート化やデジタルトランスフォーメーションなどとも呼ばれ,IoTやAIを活用したスマート工場を目指して,現在,急速に進められつつある。
2.スマート保安
経済産業省では,産業保安力を強化する方策として,保安業務にIoTやAI等を活用する新技術の実証や,こうした技術の活用を促す規制改革を進めており「スマート保安」と呼んでいる。
「スマート保安」とは,技術革新やデジタル化,様々な環境変化に対応した産業保安に関する主体的・挑戦的な取り組みであり,具体的には,IoTやAI等の新技術の導入によって事業・現場における自主保安力の強化と生産性の向上を持続的に推進するとともに,規制・制度を不断に見直すことであると述べられている5)。たとえば,設備の状態をオンライン・リアルタイムに把握・監視できる新技術を活用することによって,安全性の向上のみならず労働負荷の低減や効率性の向上,競争力の強化につなげることが可能となる。
2020年6月には官民のトップによるスマート保安官民協議会が設置され,スマート保安の重要性を認識し,その推進のための基本方針を策定した2)。その下に高圧ガス保安分野や電力安全分野などの分野別の部会も設置され,スマート保安の実践に向けた具体的なアクションプランが検討されている。2020年7月には初版が公開され,その後も毎年プランの進捗がフォローアップされている状況である。
図2に,高圧ガス保安分野のアクションプランで述べられている項目の一覧を示した。①企業組織の変革,②情報のデジタル化,③現場作業の効率化,④意思決定の高度化の大項目の下で,それぞれ個別の中項目が複数設定されており,アクションプランでは,その下にさらに具体的なアクションが配置され,喫緊から短期・中期・長期の時間軸の下に進捗状況を管理しているところである。
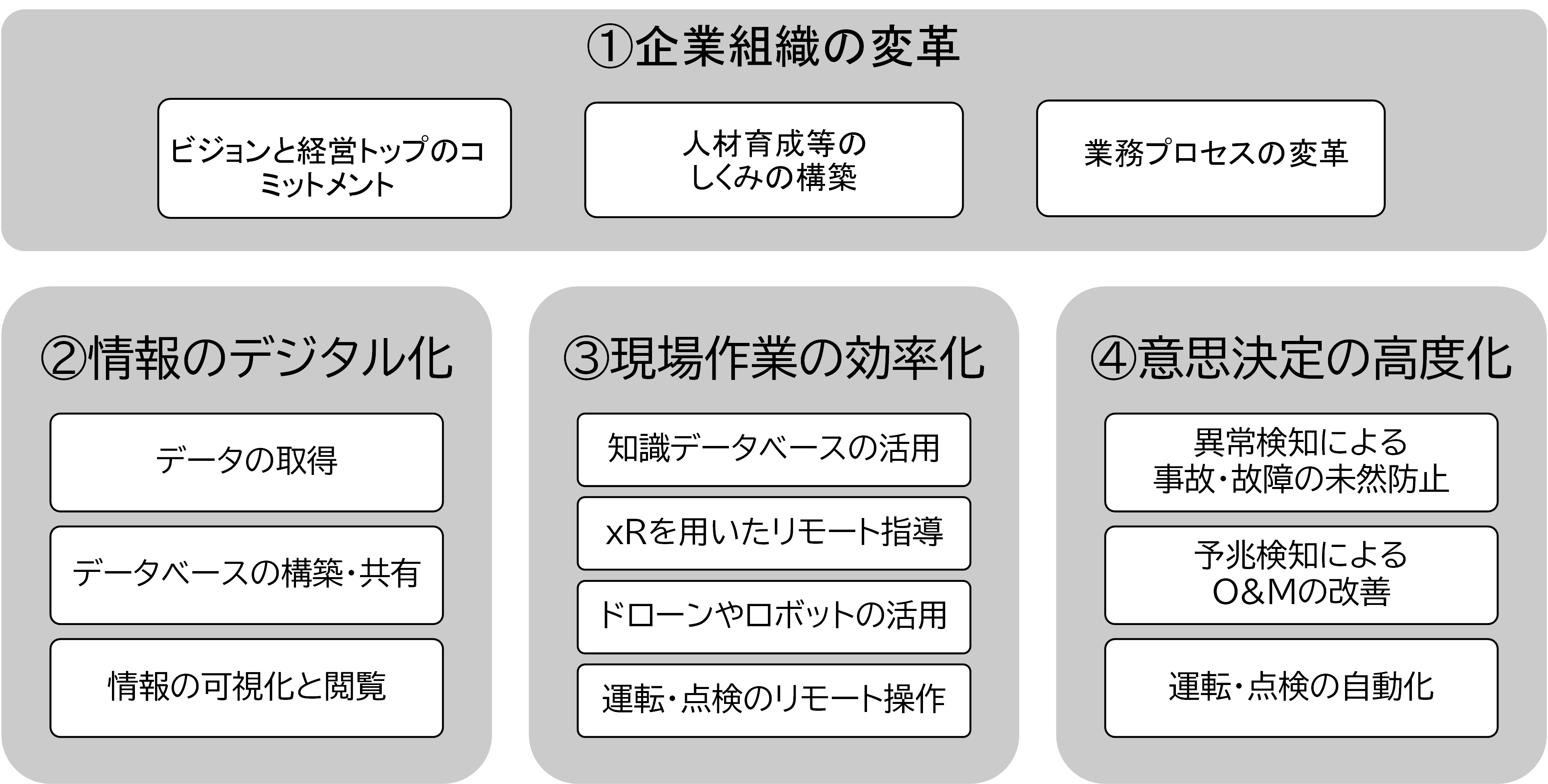
スマート保安に関する各社の最近の取り組み状況を見てみると,Digitizationに対応する情報のデジタル化から,Digitalizationに対応する現場作業の効率化や意思決定の高度化へと着実に進んできていることがわかる。意思決定の高度化の中でも,現在,最も注目されている技術の一つが,予兆監視・予知保全である。
3.予兆監視・予知保全
予知保全とは,連続的に機器の状態を計測・監視し,設備の劣化状態を把握または予知して交換・修理などを実施する保全方法である。類義語として予兆保全,状態基準保全,状態監視保全などがある。従来は故障が発生した後に実施する事後保全や,一定の時間が経過した時にメンテナンスを行う予防保全が一般的であったが,IoTやAIの活用によって予知保全が可能となった。予知保全には,連続的に異常や予兆を検知する状態監視が不可欠である。古くから研究・実用されてきた統計的プロセス制御などの異常検出の発展形として,いわゆるAIを活用した異常検知や予兆監視が研究され実装されてきた。このあたりの経緯や手法については,本誌の2021年3月号および10月号でも述べた3,4)。
スマート保安技術の海外展開を目指して設立された「日タイ スマート保安コンソーシアム」では,スマート保安にかかわる各社の様々な技術を整理したスマート保安デジタルカタログを作成している5)。そのカタログを見ると,現在,異常検知による事故・故障の未然防止に関する技術は21件,予兆検知に関する技術は17件が掲載されており,このことからも,予知保全に関連する様々なソリューションがすでに提供されていることがわかる。
4.最新の研究開発
スマート保安官民協議会は産官の取り組みであるが,化学プラントのデジタル化に関する産学の活動は,プロセスシステム工学分野の学会や研究会で広く取り組まれてきている。具体的には,国内では化学工学会の年会・秋季大会やシステム・情報・シミュレーション(SIS)部会の研究会などで多くの発表や議論が行われている。
中でも,日本学術振興会のプロセスシステム工学第143委員会の活動を引き継いだプロセスシステム工学分科会(通称PSE委員会)では,ワーキンググループや定期的に開催される研究会などにおいて多くの関連するテーマが取り上げられて発表や議論が行われており,多くの有用な成果が得られている。 国際的には,プロセスシステム工学分野で3年ごとに開催されてきたPSE国際シンポジウムを2022年6月に京都で「PSE2021+」として開催した6)。オンラインと現地のハイブリッド開催であったが,多くの海外からの参加者が現地を訪れ,熱心な議論が交わされていた。その中では,異常検出・診断のセッションや機械学習のセッションがあり,化学プラントのスマート化に関連する多くの最新の研究成果が発表された。 現在,機械学習などのデータ駆動型のアプローチが注目されているが,役に立つデータは必ずしも十分でないことも多く,物理モデルやシミュレーションとの融合を指向して,サロゲートモデルやグレーボックスアプローチ,デジタルツインの研究が活発であり,今後,これらの研究成果が実装されていくものと思われる。 5.おわりに ニューノーマル時代のものづくりにおけるデジタル化の重要性について述べ,スマート保安の最新の状況とプロセスシステム工学分野の活動を簡単に紹介した。 予兆監視や予知保全は,化学プラントのスマート化において,現在,最も活発に取り組まれている分野の一つである。安全性の向上のみならず生産性や効率性の向上や省力化,省資源化にも大きく貢献する技術であり,今後のさらなる発展と普及が期待される。 〈参考文献〉 1)経産省,厚労省,文科省:『製造基盤白書(ものづくり白書)2021年版』 2)スマート保安官民協議会, https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/ 3)山下善之:「プラントの異常検知・診断とAI活用」,『計装』, pp.9-11,2021年3月号
4)山下善之:「予兆監視診断のスマート化」,『計装』,pp.11-12,2021年10月号 5)「日タイ スマート保安コンソーシアム」,https://sisoaitc.go.jp/sisdc/ 6)山下善之・加納学:「プロセスシステム工学国際会議(PSE2021+)開催報告」,『化学工学』, pp560-561, 2022年10月号
ポータルサイトへ