

【インタビュー】
回転設備診断の新しい潮流:外乱振動に強い高調波センサ
パナソニック インダストリーは,高調波センサ(特許出願済み)という新しい電流センサを開発した。このセンサは制御盤内にある生産設備の動力線に取り付ける事で,設備の設置されている現場の環境(防爆や振動)に関わりなく,設備の発する高調波を測定できるというものである。
現在,設備診断は,生産現場の安定・安全操業に向けて対応しなければならない大きなテーマとなっている。この設備診断の主な手法は,振動センサなどを設備に取り付けるというものだが,現場には多様な振動がある事が課題となっている。これらが外乱となり,設備が発する振動だけを測定する事が難しくなっている為である。
そこで,編集部では,この課題を解決するために新しく開発された高調波センサと,それを活用したAI 設備診断サービスについて,パナソニック インダストリー株式会社 メカトロニクス事業部 サービス事業推進部 事業企画課 課長 近藤一哉氏(以下,近藤)にお伺いした。
――高調波とは,いわば交流のひずみ波ですよね。それが出ないように,装置側では工夫をしている。しかし工夫してもひずみ波は出てしまう。それを利用して診断に用いようという発想は,どこから出たのですか?

近藤:当社では松下電工の時代から,振動センサを用いた設備診断機器を製品化し,販売してきました。その中で,外乱振動によって導入不可と判断せざるを得なかった現場を多く経験しました。この経験から,振動が多い現場でも適用できる技術がないかを模索するようになりました。そのような時に東京大学・豊田利夫先生の電流微候解析MCSAなどの研究に出会い,モータ駆動の設備の機械部品に状態変化があると,振動以外に駆動電流にも微細な影響が出ることを知りました。電流であれば,現場の外乱振動の影響を受けません。これは課題解決に繋がると思い,当社でも検討を開始しました。そしてその後の様々な調査・研究の末,電流の中で,特に高調波成分 - 交流電流の基本周波数に対する,整数倍の高次周波数成分 - に状態変化の影響が表れやすい事を確信し,高調波センサの開発に着手する事となりました。
設備でなく制御盤に設置する,高調波センサ
――なるほど。しかし電流の中にある高調波を検出するのはなかなか難しいのでは?
近藤:そうですね,それを実現する為の技術については申し上げられないので,高調波のどのような変化を捉えているかについて説明させて頂きます。まず,機械部品に状態変化が発生すると,高調波に変化が現れます。これを捉えることで設備異常の兆候を把握することができるのですが,一例としては,正常時に現れるn次高調波の周りに,劣化時には側帯波という周波数ピークが現れます。設備種や動作状態によって変化の現れ方は他にも様々あるのですが,こうした変化を総合的にとらえる事で,正常時と現時点の変化の度合いを判定するのです。そのためにはAIを採用しているのですが,そちらについては後でお話しします(図1)。
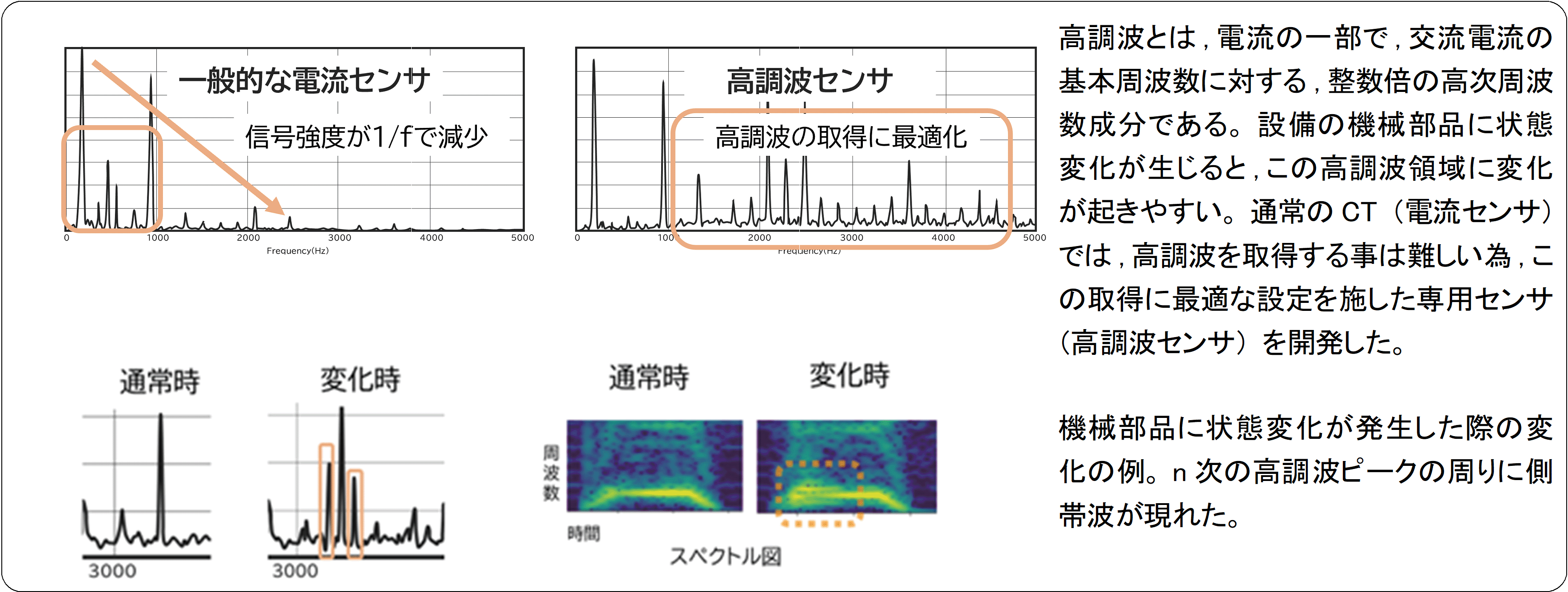
次にセンサの設置が容易であることをご説明させていただきます。(写真1)。

高調波センサは写真1 のように電力盤あるいは制御盤に取り付けます。つまり,設備が危険な環境であったり,あるいは防爆エリアやクリーンルーム内で稼働していても,制御盤がその外にあれば,対応工事などが不要で設置が可能となるのです。また具体的な設置方法は,引き込んだ三相交流の動力線の1 本に挟み込むだけですので,運転中でも設置可能です。
少量データのみ・異常データなしで始められる,簡単なAI
――クラウドAI というとディープラーニングが最近の傾向ですが,ディープラーニングは大量のデータや,何万から数十万回の試行錯誤を必要とします。実際にはこの点が,活用が広がるためのネックになっていると思われます。
近藤:当社では一般的なディープラーニングは採用しておらず,教師無しAIを採用する事で2つの現場課題を解決しています。一つ目は必要なデータ量についてです。小規模なAIアルゴリズムなので,少量データと少ない計算量での診断が可能で,約2週間の蓄積データで利用開始が可能です。二つ目は,異常データについてです。教師無しという手法を採用しているので,採取する事が難しい,設備の異常時・故障時のデータが不要となります。
しかしそれだけではありません。一つの設備からは,実に多様なデータが発生しており,全てを学習対象としても,なかなかAIの精度は上がりません。そこで,設備の一連の動作から,特定の動作パターンのデータだけを自動判定して選別する,オートクレンジングという機能を実装しています。つまり,全てのデータでなく,選別したデータのみを対象としてAI分析する事で,精度を高めるのです。
図2 を見てください。これは現場から上がってきたデータを元に,変化度をAIが分析し,グラフ化したものです。ここにユーザが閾値の設定を行えば,クラウドからアラートメールが届く仕組みとなっています。また,先日リリースした新しいバージョンでは,このアラートの通知手段を追加いたしました。メール発報に加え,API経由で他のシステムへデータ連携する事も可能です。これらを通して,当社の技術が皆様の生産現場の安定・安全操業の一助となれれば,大変嬉しく思います。
