

【プロセス分析/環境計測機器】
複数光源で適用工程を拡大した複合散乱光式汚泥濃度計
1.はじめに
家庭や工場から排出される汚水は,環境保全のために下水処理場や各事業場の排水処理施設で固形物を取り除き,浄化してから川や海に放流される。汚水から除去され集められた固形物は汚泥と呼ばれ,汚泥処理施設にて濃縮・脱水・減容化などを経て焼却処分や肥料として再利用される。これら汚水処理工程の安定操業には各処理工程での汚泥濃度の常時監視が必要であり,また,汚泥処理のための脱水機などの装置の運転にも汚泥濃度は重要な指標であり,信頼性の高い汚泥濃度計が必要とされている。
汚泥濃度計には超音波式や計量式,光学式,マイクロ波式など様々な方式の計測器があるが,汚泥性状や気泡による影響などの性能面あるいはメンテナンス性,価格,濃度測定範囲上の制約,リアルタイム測定か否かなど,それぞれにおいて一長一短があり,使用目的や汚泥性状に合わせた汚泥濃度計の選定が必要である。
弊社では下水処理場を対象とした光学式汚泥濃度計を製造販売している。光学式には気泡の影響を受けにくく,低濃度からの広い汚泥濃度測定範囲,設備が稼働中でも送泥する配管(写真1)から検出器を取り外して容易にメンテナンスが可能という長所がある。だがその一方で,汚泥色の変化の影響を受けやすく,黒色系の汚泥の測定には不向きであったり,検出部への汚泥付着により測定誤差が大きくなったりする短所がある。
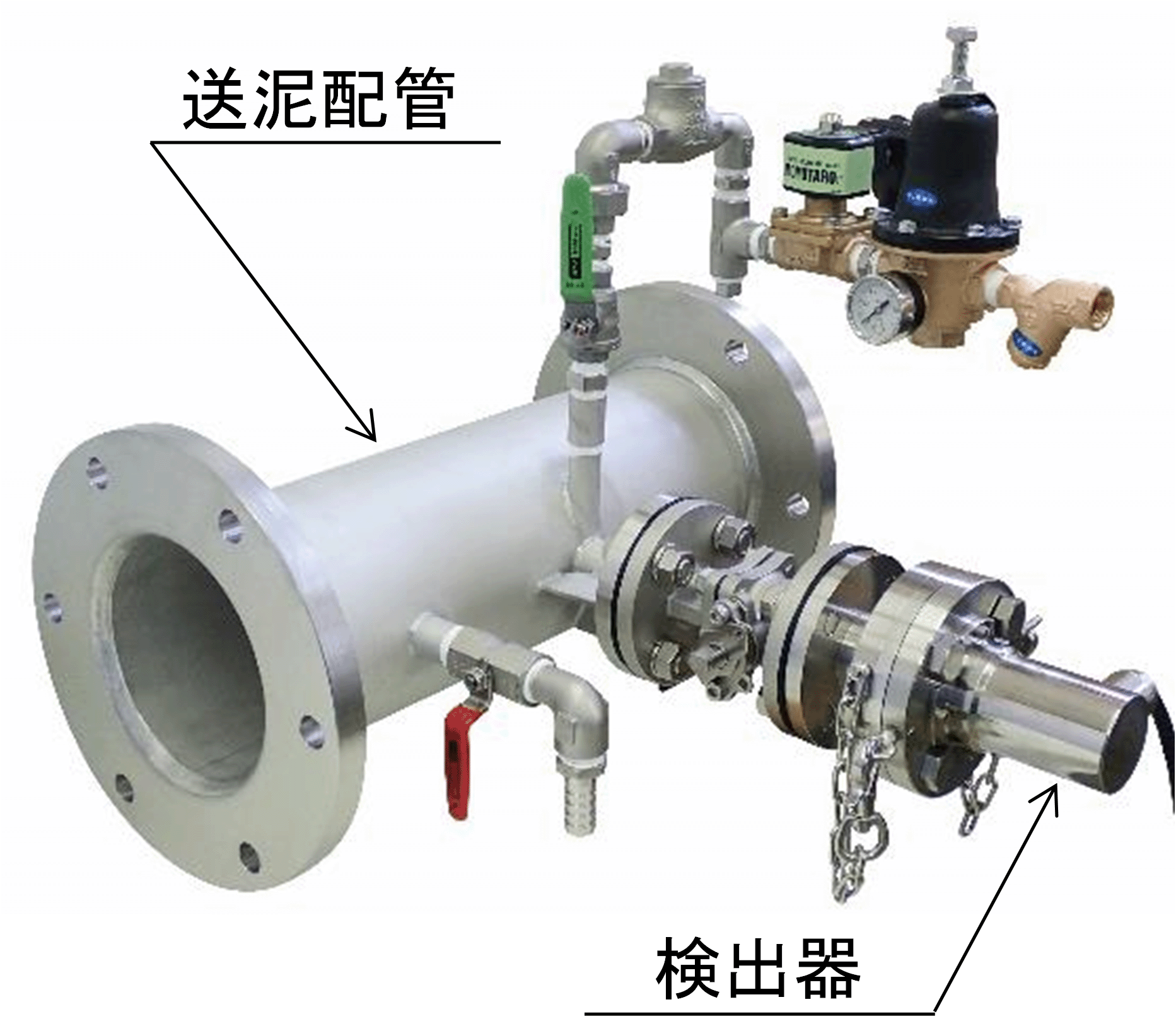
下水処理場内では図1のような測定場所がある。処理初期の初沈汚泥を含む汚泥は付着しやすく,処理が進行した汚泥は気泡を多く含み,黒色化するなど処理工程によっては汚泥性状が変化することで光学式の汚泥濃度計では測定が不向きになる場面があった。
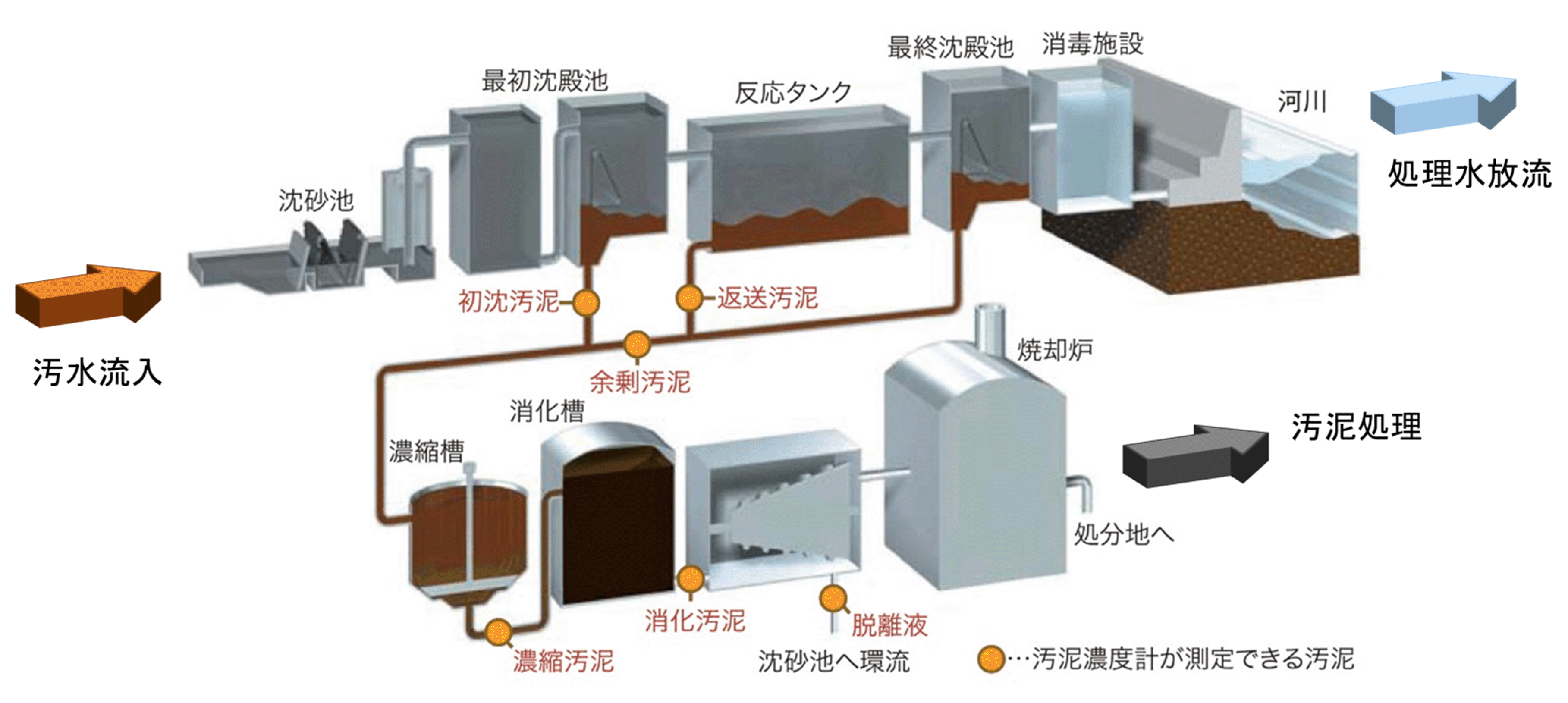
弊社では下水処理場での測定経験をもとに色味など汚泥性状が変化するような環境下でも測定できるように複数光源の出力特性差を利用して感度補正する演算方法を検討,また,検出部に汚泥が付着しやすい測定環境に対して検出部構造を見直すことで汚泥付着による測定影響を軽減するなどして,光学式の短所を克服して適用工程を拡大した複合散乱光式汚泥濃度計(写真2,表1)を製品化している。

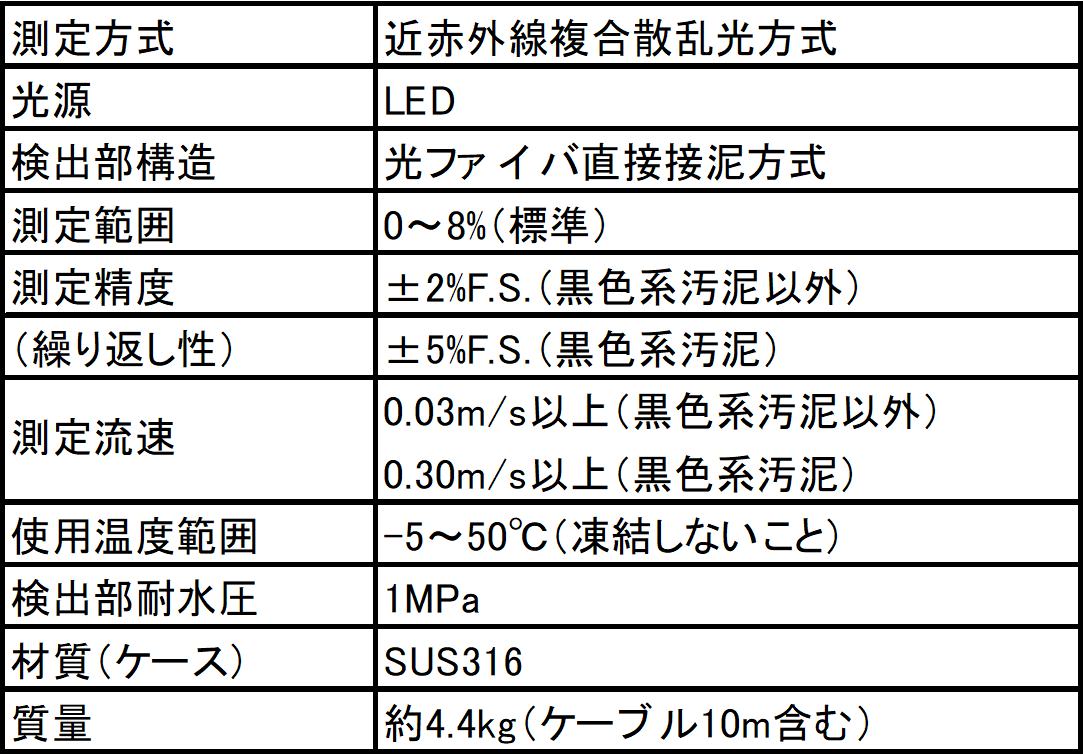
本稿では,汚泥色の変化や黒色系汚泥に対する対策について紹介する。
2.測定原理
光学式汚泥濃度計の一般的な単一光式の測定原理を図2に示す。近赤外光を光ファイバで導光して検出部先端より測定対象物に照射し,汚泥粒子で散乱した光をフォトダイオードで受光して散乱光強度を測定する。予め求めておいた散乱光強度と手分析汚泥濃度との相関関係から汚泥濃度を算出する。
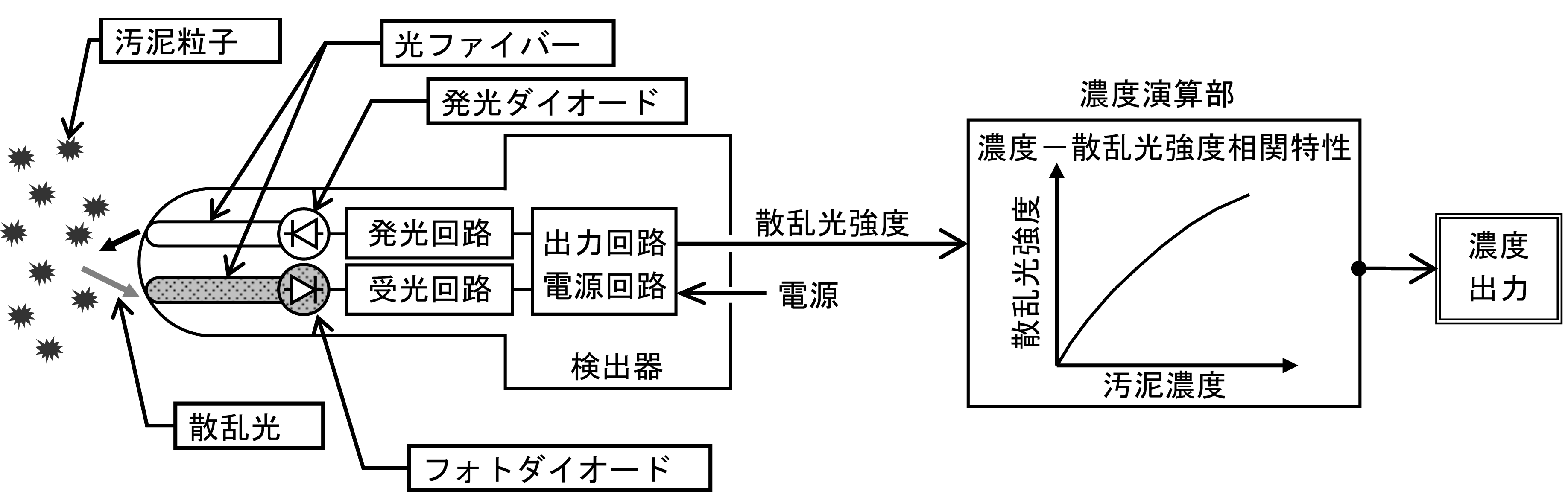
下水汚泥の色は腐敗や処理の進行により明るい茶色から黒色へ変化していき(図3),さらには季節によっても変化する。光の性質として黒っぽい色のものほど散乱が弱く,逆に明るい色のものほど強く散乱することから,汚泥色が変化すると散乱光強度と汚泥濃度との相関関係が図4のように変化する。このため,処理の進んだ黒色系の消化汚泥や色が変化しやすい汚泥の測定には従来の光学式は不向きであった。

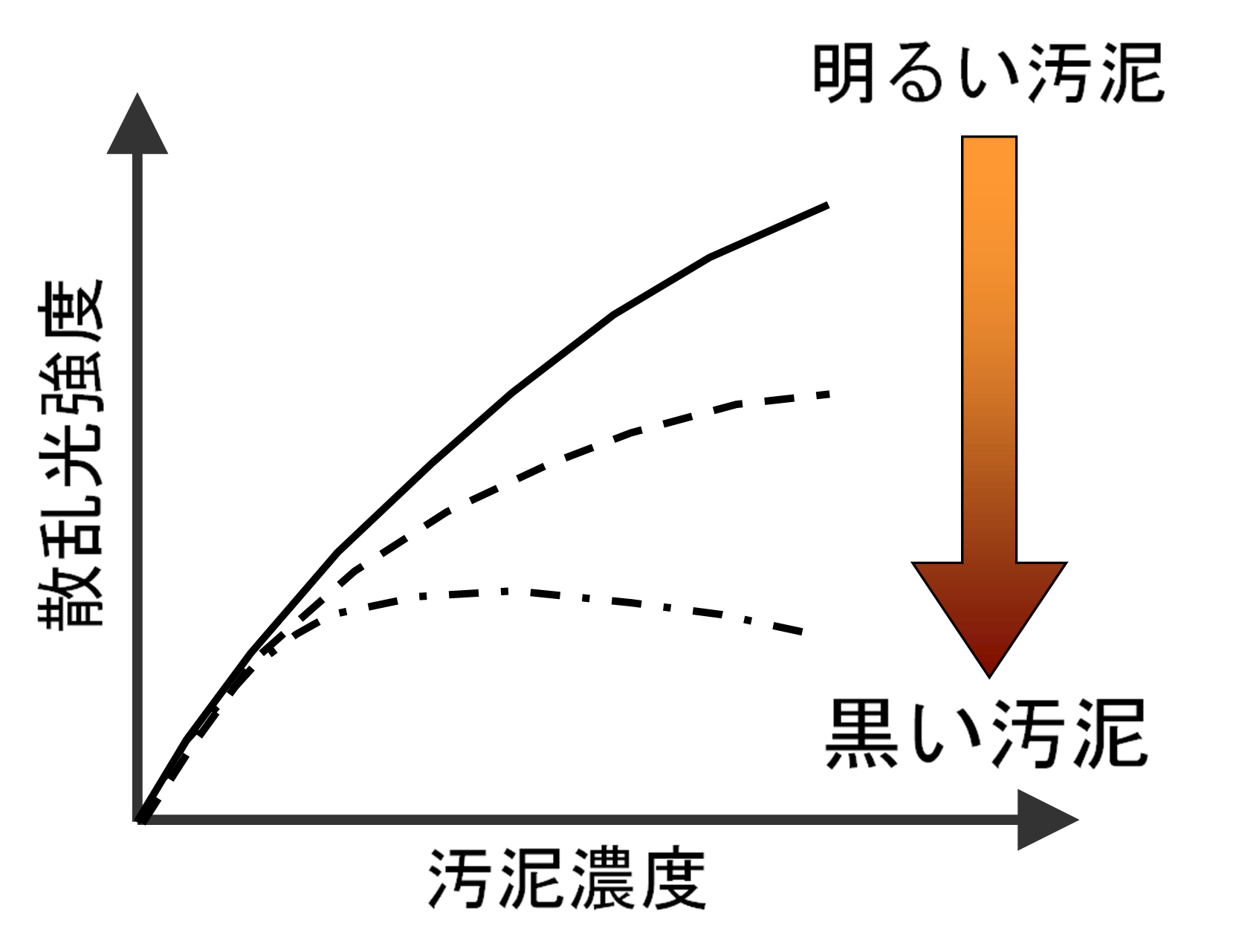
複数光源の出力特性差を利用して感度補正する複合散乱光式の測定原理を図5に示す。従来式が単一波長の光のみを用いていたのに対し,本方式では2種類の異なる波長a,bの光 A,Bを汚泥の含まれる対象物に照射する。汚泥色により散乱光強度と汚泥濃度の関係はどちらの波長も影響を受けるが,図6のように波長a,bごとにその影響が異なるので,散乱光強度比は汚泥色と相関を持つ。
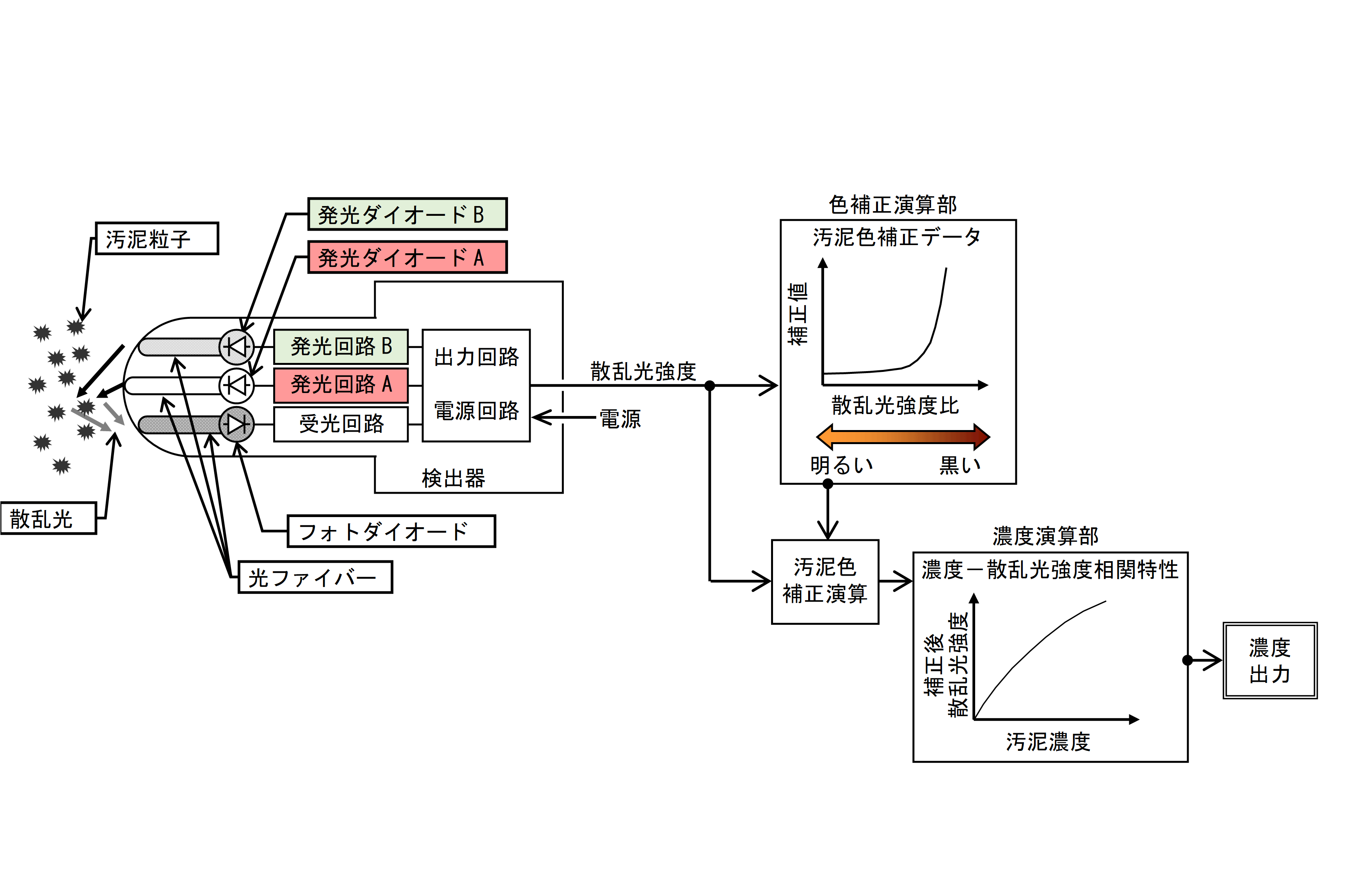
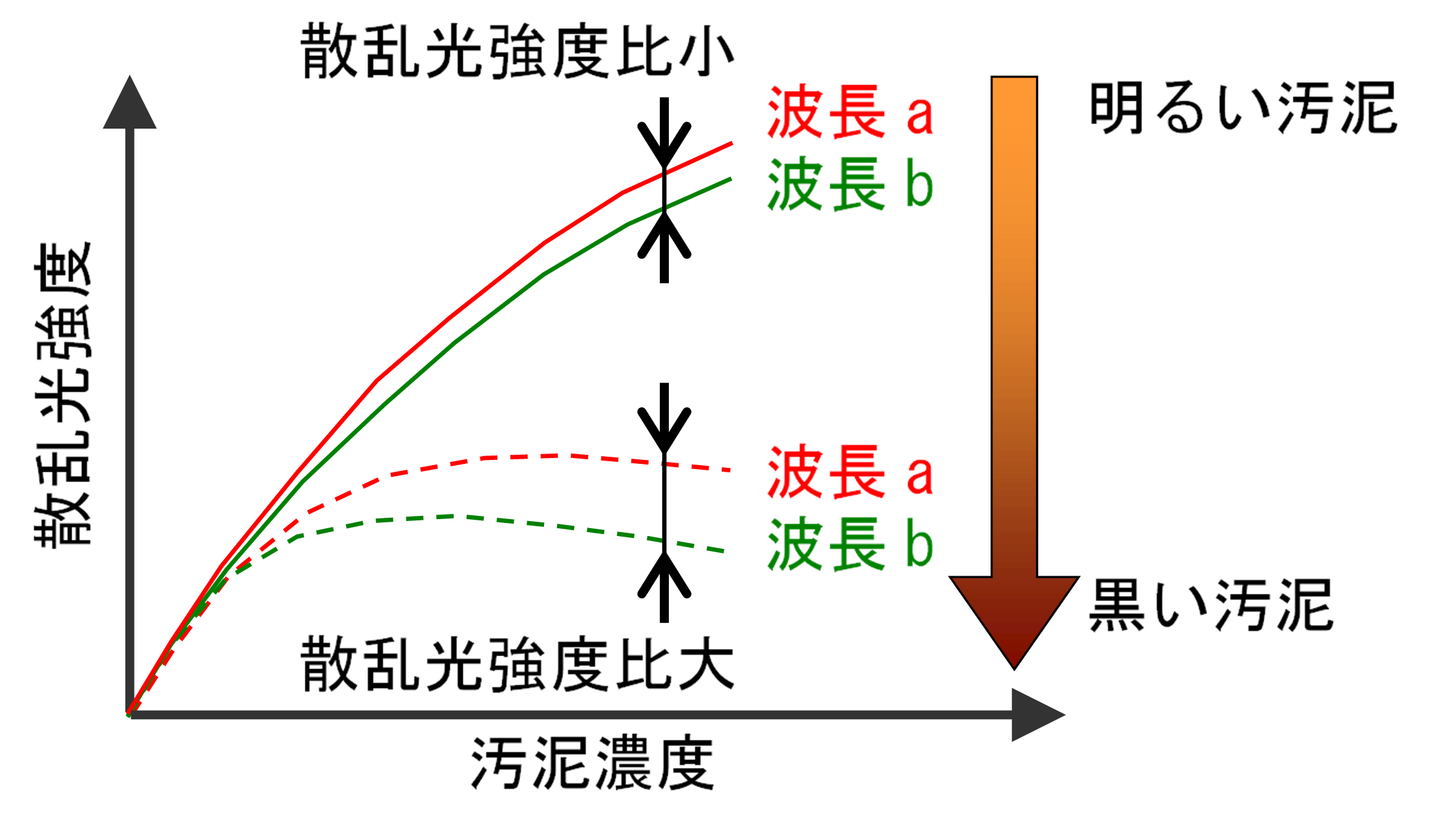
そこで,その相関を予め汚泥色補正データとして持ち,散乱光強度比から補正値を算出して汚泥色の影響を受けた散乱光強度を補正する。この補正後散乱光強度を用いて汚泥濃度演算することで,汚泥色変化の影響を受けにくい測定が可能となり,黒色汚泥の測定を実現した。
3.従来方式との測定比較
一般的な単一光による光学式汚泥濃度計と複合光を用いた複合散乱光式汚泥濃度計で色の異なる汚泥を測定した結果を図7に示す。
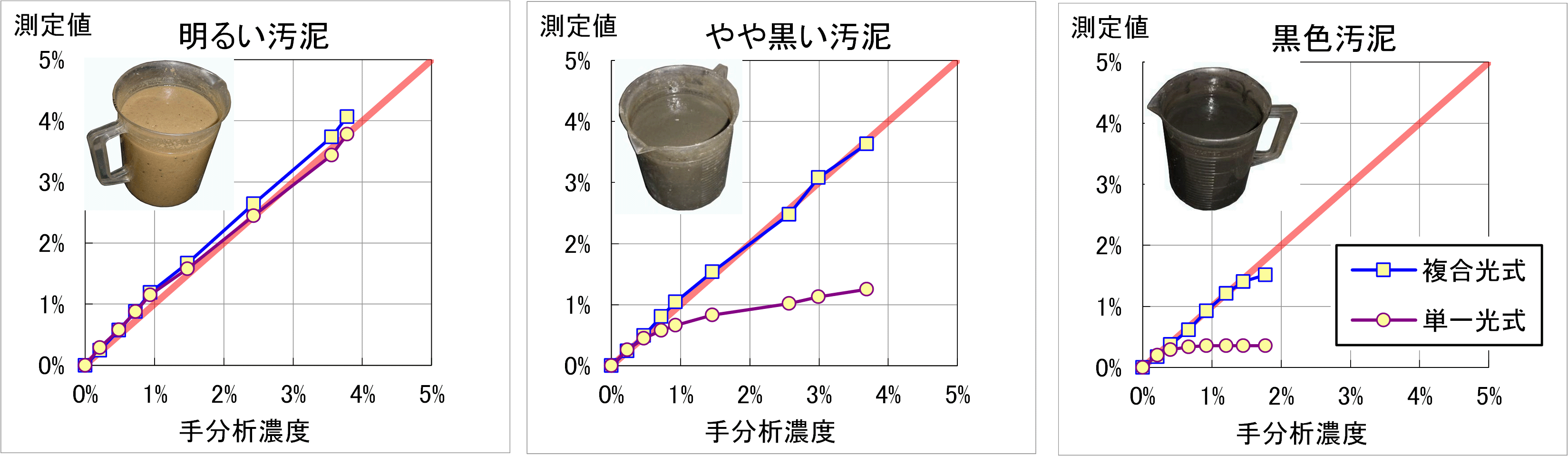
それぞれ明るい汚泥で検量線を作成した後,やや黒い汚泥,黒色汚泥を測定した。明るい汚泥は一般的な初沈汚泥,余剰汚泥,返送汚泥,濃縮汚泥に相当する。
いずれの測定方式も直線性が良く,手分析濃度とよく合っている。やや黒い汚泥は腐敗の進んだ濃縮汚泥で,集約処理場などの受入汚泥もこの色味に相当する。単一光式は直線性が悪くなり,検量線の変更や再校正が必要となる。黒色汚泥は消化汚泥相当で,単一光では低い濃度から測定値が飽和状態となっており,検量線の変更や校正では対応が不可能になる。一方,複合光式は直線性良く,手分析濃度とよく合っている。
4.消化汚泥の連続測定事例
下水処理場の消化汚泥配管(写真3)に複合散乱光式汚泥濃度計を設置して,約5ヵ月間連続測定した。消化汚泥は常時連続送泥され検出部の汚れを防止するため,1回につき1分間の水洗浄を1時間ごとに実施している。
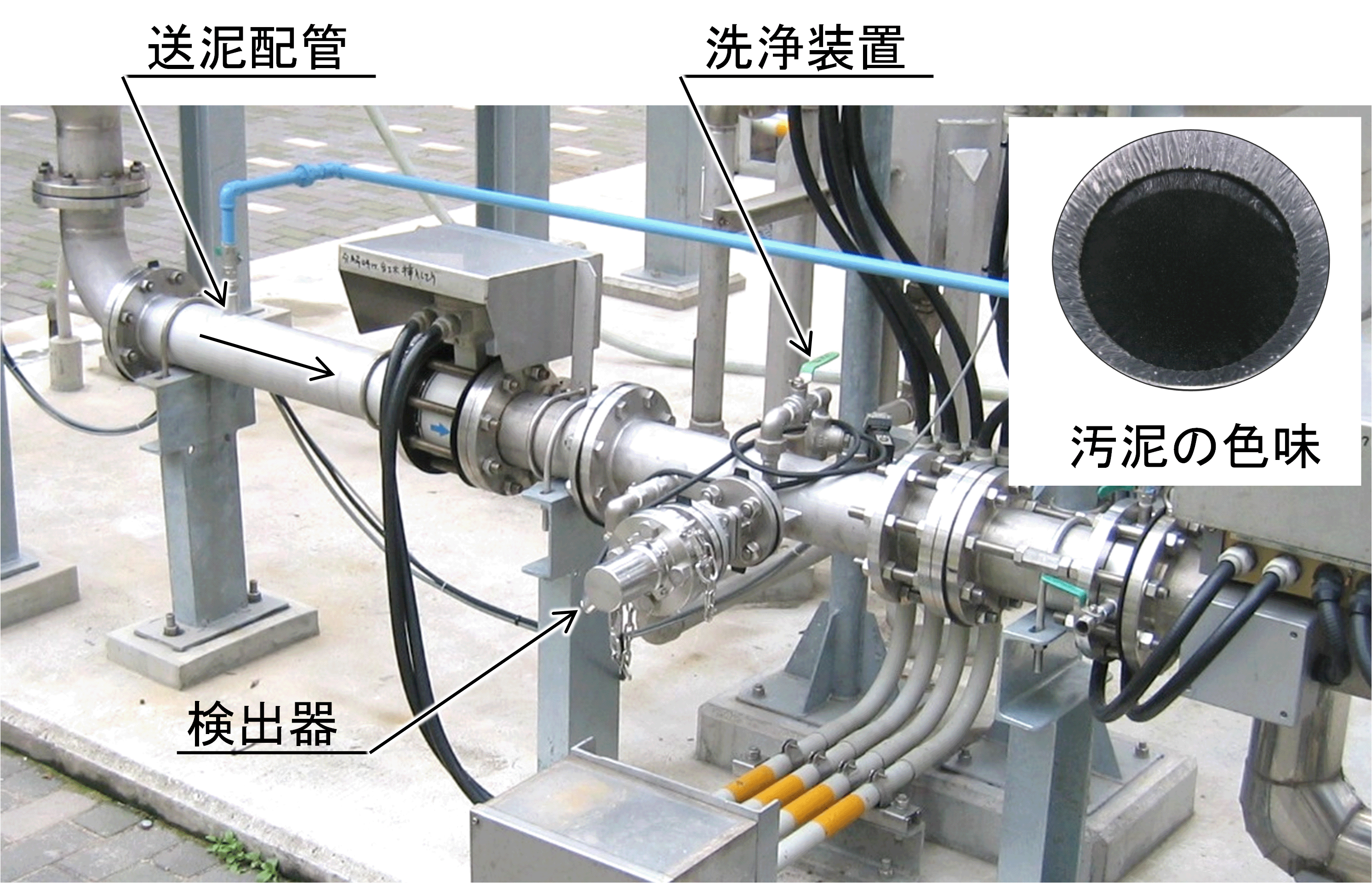
連続測定データを図8に示す。周期的な濃度変化を適切にとらえている。また,期間中に定期的に手分析を実施して汚泥濃度計測定値との比較を実施。定期的な校正をすることで精度良く測定できることが確認できている(図9)。
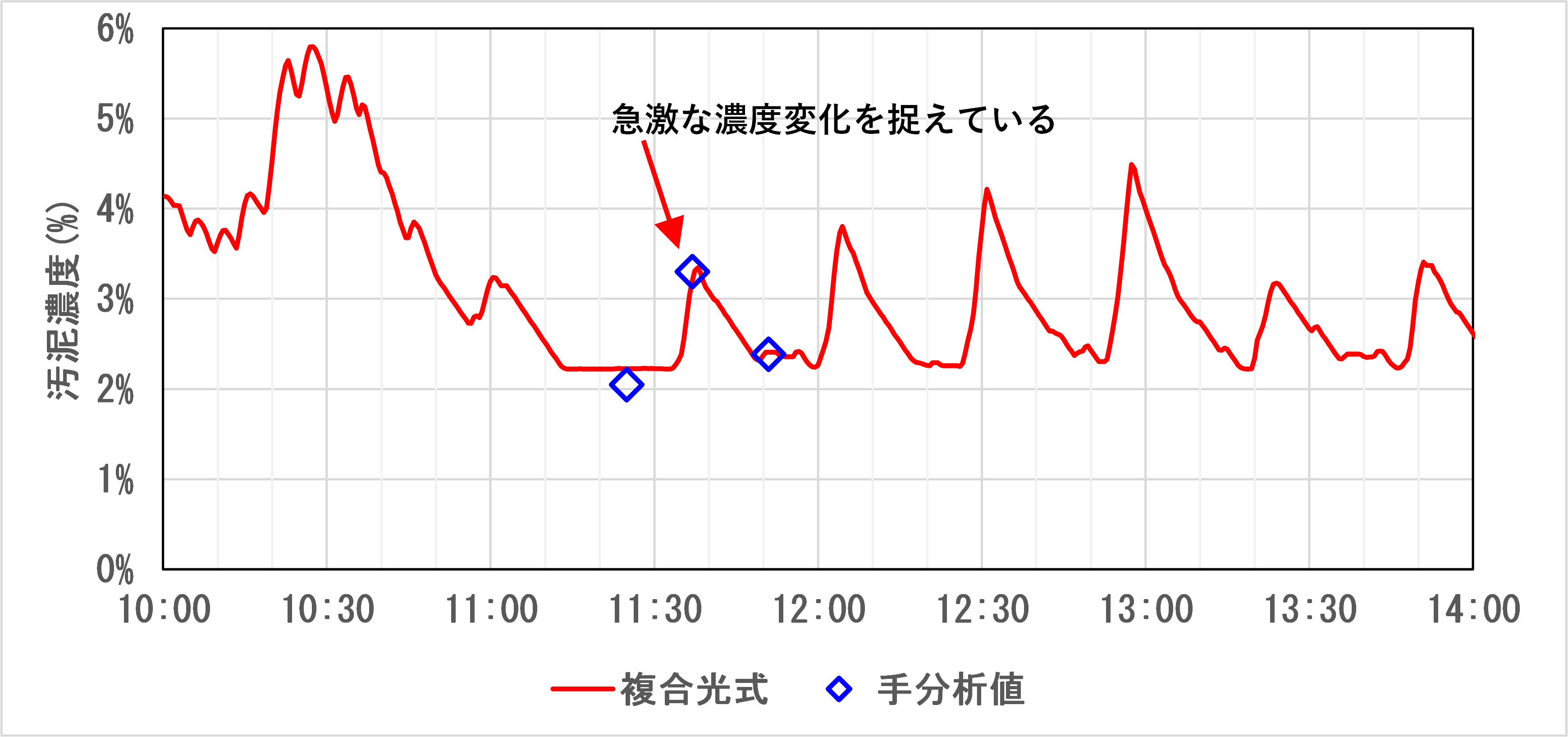

5.おわりに
複合散乱光式汚泥濃度計は,従来の単一光式では難しいとされていた汚泥色変化の影響を軽減し,消化汚泥などの黒色系汚泥が測定できるようになったことで,下水処理場における適用工程を拡大することができた。光学式の持つメンテナンスの容易さと合わせて顧客満足度の高い製品となり,下水処理場での採用実績が増加している。
近年は工場の排水/汚泥処理工程での導入についての問い合わせも増加しており,事前のサンプル測定やユーザ設備での実証試験を通じて採用可否を判断していただき採用いただくケースも増えつつある。今後も測定事例を重ねながら製品の適用先を拡大していきたいと考える。