

【Solution】
予知保全の可能性を提供する 高度診断技術とその実用例
1.はじめに
近年,AI技術の導入と設備に取り付けたセンサデータの解析によって,予知保全の実現が可能となってきた。これは,従来の保全活動では,熟練の技術者,作業者の長年の経験と勘によって,設備の異常に対する予兆診断を行ってきたが,熟練技術者たちの退社による人材不足を補うため,またAI技術が進歩したことから,可能となったものである。
一方で,AIによる予知保全システムを導入するためには,多種多様なセンサを設備に取り付け,データを収集し,学習データとしてAIに取り込んでいく必要がある。またAIを使いこなせる人材が必要であり,人材が不足している中でAIを使いこなせる人材を育成するという課題が生まれる。
それでは,製造設備に使用している機器が自ら診断を行い,保守のタイミングや運転の最適化の可能性を提供してくれるとしたら,どのように活用できるだろうか。本稿では,プラント運転の最適化や予知保全の実現に貢献する可能性がある診断技術について紹介したい。
2.現代のプラント運転・保全の課題
あらゆる産業のプラント運営に関わる技術者は,生産性を高く維持すると同時に,運用と保全コストを抑えることが求められる。また,各種法規制の適合,製品の品質維持と設備の安全運用など,様々な事項に配慮しなければならない。その結果,プラント計装に対する要求事項は,着実に増加していると考えられる。
効率的で安全な生産という大きな目標を実現するためには,計測機器に対しても,以下のような疑問や課題を解決するような機能や能力が求められているのではないだろうか。
①競争力を高めるため,稼働時間を最大化する必要があるが,プロセスを中断せずに高度な可用性を確保するには,どうしたら良いか?
②異常が発生した際に,原因と対処方法に関する情報をどうやって得るか?
③確実で効率的な運転の安全を確保するには,測定機器がどう役立つのか?
④計装機器が問題の発生前に,予兆を知らせてくれれば,保全業務を最適化できるのでは?
⑤効率的な運転をしたいが,人員の経験が不足している。誤操作のリスクを最小限にして,機器の操作で簡単に対応できないか?
これらの疑問や課題は,従来のアナログ計器では,解決できないと思われる。なぜなら,従来のアナログ計器は,機器の健全性を確認するためには,設備から取り外して点検を行う必要があり,原因と対処方法を知らせるような表示器のようなユーザインタフェースも搭載されていないことが多い(搭載されていてもLEDランプぐらいであろう)。また,予兆を知らせることは当然できず,操作などもオシロスコープを使用して信号を観測しながら,トリマを調整するなど,設定,調整にもある程度の経験が必要となるため,熟練の技術者であれば故障の予兆は判断できる可能性があるが,経験のない技術者には難しい。
デジタル技術を搭載した計器では,エラー番号の表示や診断メッセージを表示できるようになったが,診断技術が搭載されていない機器では,機器の健全性を確認するためには,アナログ機器と同様に,設備から取り外して点検を行う必要があるし,故障の予兆を知らせるような機能までは搭載されていないことが多い。
すなわち,生産性の維持,運用と保全コストの抑制を両立させるためには,アナログの計装機器や単純にデジタル化された計装機器では課題を解決できず,高度な診断技術を搭載した計装機器でなければ,両立できないと思われる。それでは,どのような診断機能やユーザインタフェースなどの基本機能を搭載していれば,課題の解決に貢献できるだろうか。
3.「Heartbeat Technology」
2章で指摘した疑問や課題に対する弊社Endress +Hauserの答えが,「Heartbeat Technology」という計測機器に搭載された診断技術である。
Heartbeat Technologyは,診断,検証,監視の3つのコンセプトで構成されている。
Heartbeat Technologyの診断機能は,IEC61508に基づいて,測定を行うと同時に機器自体の健全性を常に監視している。診断項目は製品によって異なるが,大きく分ければ,センサ部,メモリ部,メイン電子部,IOモジュール部などである。また,センサや測定機器の計測原理に関わる重要なパラメータなども診断の対象となっている。
診断の結果はNAMUR NE107に基づいて分類された診断情報を出力する。NAMURとは欧州のプロセス産業における自動化技術のユーザ協団体で,プロセス産業に関わる様々な技術仕様要求を取りまとめている。その技術仕様要求の一つであるNE107とは,プロセスおよび機器の診断情報に関するガイドラインである。NAMUR NE107では,機器の診断情報を表1の4つ(通常運転状態を含めれば5つ)に分類し,またその対処方法を機器が表示して,使用者に示すことを要求している。
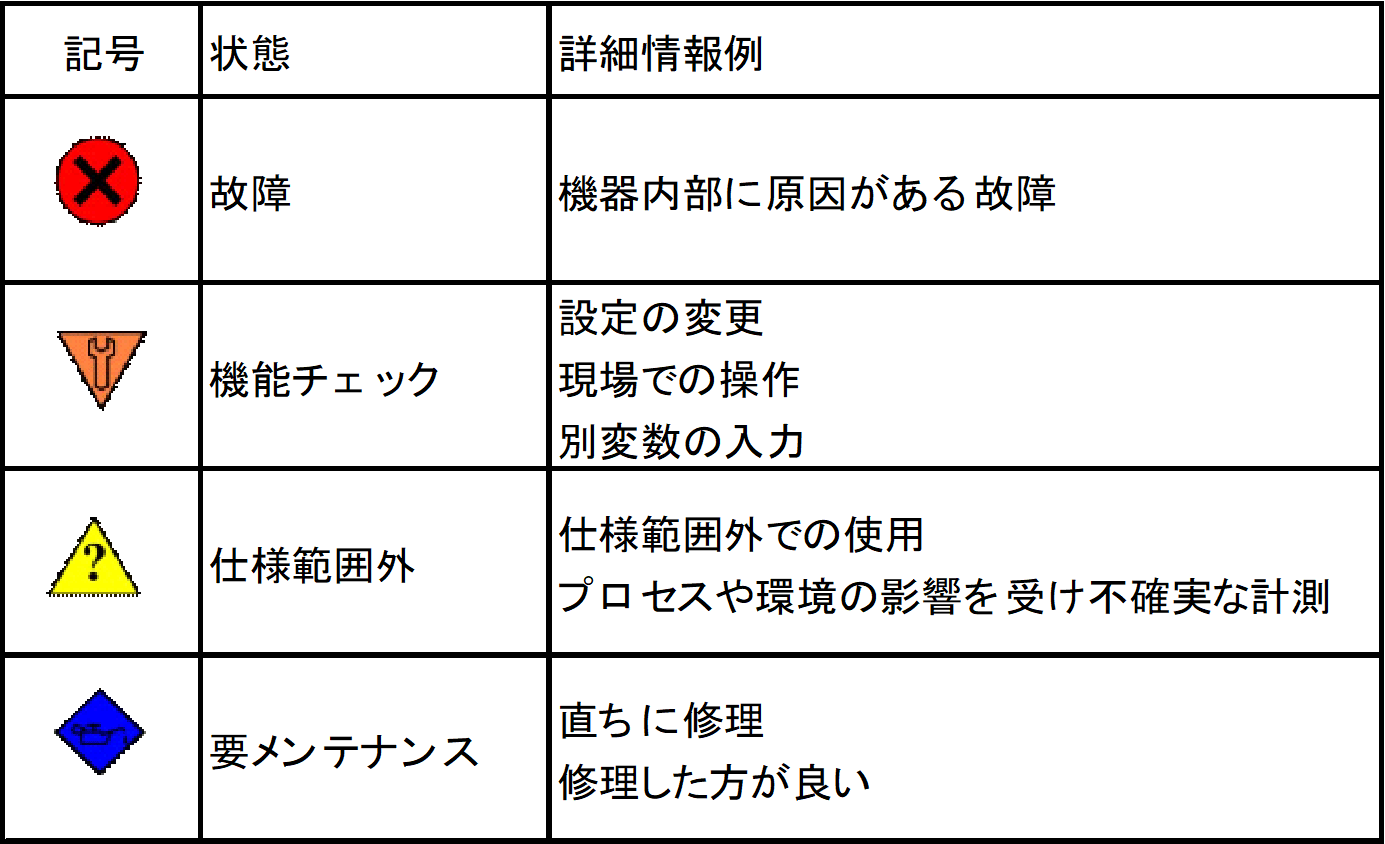
Heartbeat Technologyの診断機能は,機器の健全性の診断結果をNAMUR NE107に基づいて分類し,ユーザにどのように対処すべきかを機器に付属したディスプレイやWebブラウザ,弊社のスマートフォン,タブレット用アプリ「SmartBlue」,オープン化技術のFDT/DTM,Field Xpertといったツール上に表示する。
この診断情報を分類する機能やエラーの内容と対処方法を機器やツール上で詳細情報を表示する機能によって,前章で掲げられていた課題の②を解決することに貢献できる。また,⑤の課題を解決するヒントになり得る。
Heartbeat Technologyの検証機能は,前述の診断機能に基づいて,計測機器が仕様に応じた正しい機能を維持しているかを,計測を中断することなく検証する。また,この検証の実行はユーザがいつでも,機器を現場から取り外すことなく,WebブラウザやSmartBlue,FDT/DTM,Field Xpertといったツールによって遠隔から実行し,レポートとして生成可能である(図1)。
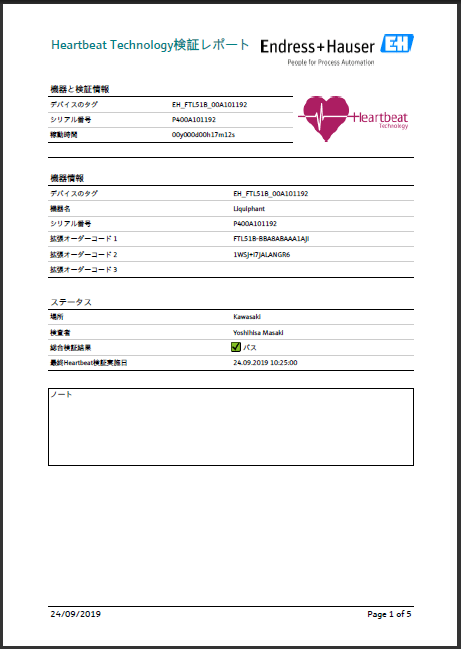
検証レポートは検証を実行した日付,場所,検査者の名前を入力することができ,前述の診断項目に対する合否判定を結果として記録する。また,この検証レポートの中には,検証を行う機器の基本情報(型式,シリアル番号,TAG番号),その機器の運転時間(電源が投入されていた時間),計測機器の計測原理に応じた内部パラメータなども記録される。機器によっては,過去に検証を実行したときの内部パラメータが記録されるため,経年による製品の特性変化を確認可能である。
計測を中断することなく検証作業の実行,報告書の作成ができるため,前章で掲げた課題①の解決に貢献する。また,検証の結果をいつでも確認でき,報告書として保存できることで,センサの経年変化や異常の検知にも役立ち,前章の課題④を実現する可能性を提供する。
Heartbeat Technologyの監視機能は,予知保全やプロセスの最適化に有効となる可能性のある追加のパラメータを提供する。たとえば,連続レベル計における泡検知機能や付着検知機能,音叉式レベルスイッチにおける振動周波数の監視などである。これらは,機器が稼働中においても,連続的な自己診断と監視を実行し,監視した値は外部システムに伝送することも可能であるし,無線接続した機器から確認することも可能である。この信号を使用して,メンテナンスタイミングの最適化を図ることが可能である。この監視機能は,フィールド機器の測定原理や測定変数によって監視するパラメータや外部に伝送できるデータが異なっている。
この監視機能によって前章の課題③に貢献する可能性がある。また,このような監視機能のない計測機器で同様の事象が発生した場合,熟練の作業者であれば計測機器の異常ではなく,プロセス変化の可能性を頭に入れて対処できるが,経験がない場合は判断が難しい。計測機器がこのようなプロセスの変化を検知することで,機器の異常ではなく,プロセス変化に対する対処を行うことがてきるので,課題⑤にも貢献できる可能性がある。
4.実例紹介
前章では,Heartbeat Technologyの機能の詳細について,紹介した。本章ではHeartbeat Technologyによって検知可能な機器に発生する故障の予兆やプロセス変化の事例を紹介したい。
4.1 腐食や摩耗によるセンサの減肉
センサ部が腐食性液体や摩耗性のある流体と接触している場合,経年によって徐々に腐食や摩耗し,センサが検出している物理量が変化してしまう。この物理量の変化によって,測定誤差が大きくなってしまったり,誤検出が発生したりといった不具合事象につながってしまう。つまり,腐食や摩耗は計測機器やセンサの信頼性や測定性能を低下させ,生産物の品質に影響を与えたり,プラントの安全運転に影響を及ぼしたりしてしまう可能性がある。(写真1)

Heartbeat Technologyを搭載したコリオリ流量計 「Promass」は,Heartbeat Sensor Integrity(HBSI)という内部信号を監視することができる。このHBSIは工場出荷時の基準値は0%として設定されているが,腐食が発生するとセンサの健全性が影響を受け,減肉が発生するとHBSIの値が上昇してしまう。このHBSIを監視することで腐食や摩耗が発生していないかを確認できる。
腐食や摩耗が発生している場合,HBSIの値が4%を超えるとその流量計は計測制度を維持できなくなるため,交換が必要になる。しかし,この指標によって腐食や摩耗の発生や機器の健全性を確認することで,適切な交換時期を判断することができる。(図2)
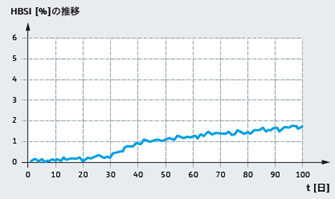
もう一つの事例としては,Heartbeat Technologyを搭載した音叉式レベルスイッチ「Liquiphant」である。Liquiphantの場合は,液体を検出するために,音叉部の振動周波数を監視しているが,Heartbeat Technologyの検証を実行した際に,過去8回分の振動周波数の履歴を記録することができる。
通常空気中にある時のLiquiphantの音叉部は,約1kHzで振動しているが,腐食や摩耗が発生するとこの振動周波数が高くなる。空気中の振動周波数より6.5%高くなると腐食アラームが発生し,使用できなくなるが,腐食アラームが発報する前に,交換することで予定外のプラント停止を防ぎ,計画的な保全活動を実施することができる。(図3)
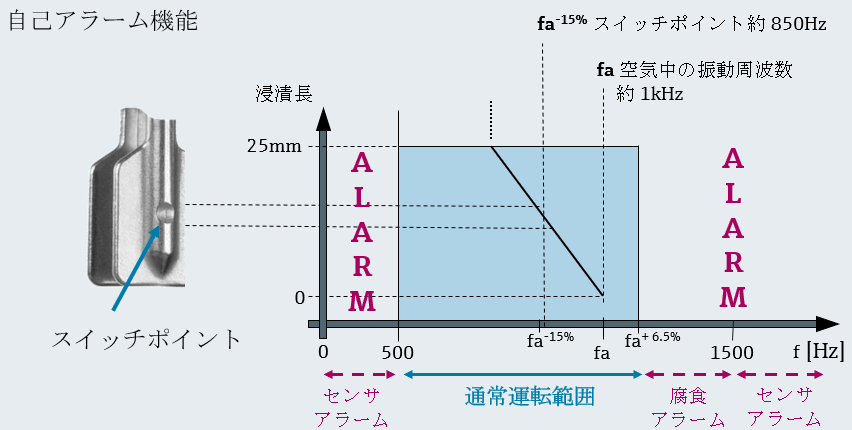
4.2 付着
粘度の高い液体や流体を処理するプロセスに使用している計測機器やセンサは,経年により付着が発生することが容易に予測できるし,それによって測定誤差が大きくなったり,誤検知が発生したりすることも容易に予測はできる。しかし,付着が発生したことによって測定誤差が大きくなっているのかを把握することやいつ誤検知が発生するかを予測することは難しい。(写真2)

たとえば,Heartbeat Technologyを搭載した音叉式レベルスイッチLiquiphantが振動周波数の履歴を取ることができることは説明したが,付着が発生した場合,振動周波数は低くなる。また,Liquiphantは空気中の振動周波数から15%低くなった時に液体を検出するため,付着が発生した場合に,誤検知となるほど振動周波数が下がる前に清掃を行うことで,予定外のプラント停止を防ぐことができる。
他の計測機器では,弊社電磁流量計であれば「付着インデックス」という指標を監視することで,付着の発生を監視することができる。これは測定流体と付着物の導電率の違いに基づき,測定管内の導電率の分布を解析し,付着が増加すると付着インデックスの値も比例して変化する。この変化を監視することで,適切な清掃時期を決定することができる。(図4)
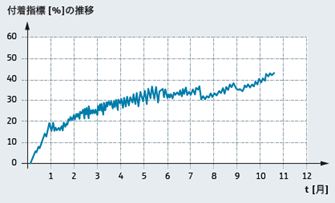
4.3 泡の発生や気泡の混入
前項までは,計測機器やセンサに発生する故障の予兆検知の事例を紹介したが,本項ではプロセス変化の検知の事例を紹介したい。
反応釜において,プロセス中に反応する泡は,プロセスの反応度合いを確認する指標に使われることもあるが,泡が大量に発生して天井まで届いてしまうと,設備を損傷させてしまうこともあり,設備に影響を及ぼす前に検知して対策をしたいという要望もある。(写真3)

レーダレベル計(電波式レベル計)は,測定物にマイクロ波を打ち出し,その反射を検出することで,レベルを測定するが,弊社レーダレベル計「Micropilot」はHeartbeat Technologyの監視機能として,反射の大きさを監視することができる。反射の大きさは,測定物の比誘電率の大きさによって増減するが,泡が発生した場合,泡の密度や厚さによって減衰度合いが大きくなる。この泡の発生によるマイクロ波の反射の減衰を利用して,泡の検知を行うことができる。(図5)
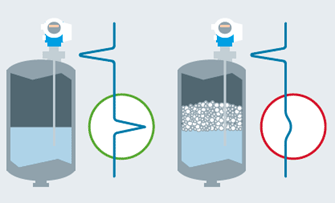
泡を検知した場合は,HART信号によって,3章で説明した診断情報の分類をM:要メンテナンスとして伝送することで,外部に通知することもできるし,オプションとして半導体リレーによる接点出力を設けることができるため,このリレーのオンオフによって,泡の発生を通知する。
また,泡の発生と類似の現象で流体への気泡混入が挙げられる。弊社コリオリ流量計「Promass Q」は,浮遊気泡インデックスという指標を監視することができる。流体中の気泡混入は流体が不均一となり,測定に影響を及ぼすが,アイスクリームやクリームチーズの製造プロセスにおいて,特定の量の空気を混ぜる場合もある。そのようなプロセスでは,この浮遊気泡インデックスを監視することで,製造品質の安定に貢献できる可能性がある。
5.まとめ
今回紹介したHeartbeat Technologyは,デジタル信号の活用で,上位システムで診断情報の詳細を受け取ったり,検証レポートの作成を実行したりすることができるが,最近の計測機器は,デジタル信号を活用しなくても,Bluetooth接続やWi-Fi接続の機能を搭載しているため,専用のアプリやWebブラウザを利用して,同じことが実行できるため,導入に対する敷居も低いと思われる。
予知保全と聞くと,様々なデータを収集し,AIによって分析することで実現するソリューションを思い浮かべる読者も多いかもしれないが,今回紹介したHeartbeat Technologyを搭載した計測機器を活用することで,より簡単に実現できる可能性がある。こうした機器を活用することで,あらゆる場所にAIを導入する必要はなくなるのではないだろうか。
現在はプラント設備を構成する機器にHeartbeat Technologyのような高度な診断機能が搭載されていないため,センサを設置し,データを集めてAIで解析をすることで,予知保全を実現しているが,将来的にはあらゆる機器に診断機能が搭載されて,AIを活用しなくても,予知保全を実現できるかもしれない。今後一層,今回のHeartbeat Technologyを搭載した機器を啓蒙することによって,プラント運営に携わっている方々の課題の解決を助けていきたいと考えている。