

【ソリューション】
信頼性の高い信号処理とコンディショニングに貢献する本質安全防爆対応電源
1.はじめに
昨今,デジタルトランスフォーメーション(DX)や産業IoT,スマート工場など,デジタル技術や無線技術が工場,プラントに関連する技術トピックの中心となっているが,本来安定した計測,制御を行うためには,安定した電源供給と信号伝送が欠かせない。電池で駆動して無線で測定結果をクラウドに送信するような機器であれば話は別だが,従来の有線で電源供給と信号伝送を行っている計装システムであれば,システムの根幹に関わるトピックであろう。
今回紹介するのは,2線式伝送器でも,4線式計器でもどちらにも使用可能な電源とアイソレータの機能を備えたインタフェースモジュールを紹介したい。
2.計装機器用電源の役割
プロセスオートメーションのシステムで使用される計装機器のうち,圧力計や流量計などの測定機器は,電源供給と信号伝送を異なるケーブルで行う4線式計器と電源供給と信号伝送を同一のケーブルで行う2線式伝送器の2種類に分類される。
4線式計器の場合,交流電圧もしくは直流電圧を供給し,独立した信号線に4-20mA 電流信号などによって測定値を上位装置に伝送する。
2線式伝送器の場合,直流電圧を供給して,電圧を供給しているケーブルに4-20mAの電流値で測定値を上位装置に伝送する。このような2線式伝送器用の電源の場合,電源に求められる役割としては,
・2線式伝送器を動作させるための電圧を供給する ・2線式伝送器から送られてくる電流信号を上位装置と電気的に絶縁する の2点である。 1点目の「電圧を供給する」については,電源の役割としては当然のことであるが,2点目の「絶縁」については, ・機器の保護 ・信号の回り込み防止 ・ノイズ影響の低減 といった目的で使用される。 線式伝送器からの電流信号は,DCSやPLCなどの制御装置に入力されることになるが,信号入力装置は複数の信号を入力できるようになっている。だが,計測機器側からノイズや異常電圧などが発生した場合,入力装置に回ってきて故障させてしまう可能性がある。故障が発生した場合に,信号入力装置全体を交換することになるため,計測機器と信号入力装置の間にアイソレータを入れることで,万が一ノイズやサージなどの異常電圧が発生したとしても,最悪のケースではアイソレータの故障に留まり,信号入力装置を保護することができる。ただし,雷のような高電圧に対しては,保護することが難しいため,別途避雷器を設けた方がより安全である。 電源供給と機器の保護という役割においては,本質安全防爆の計測機器と組み合わせて使用する本質安全防爆バリヤとしても使用される。この場合,組み合わせる計測機器と防爆バリヤとして使用する電源の定格が適合するかを確認する必要がある。 図1と図2に防爆認証に記載された防爆バリヤの定格と2線式計測機器の定格の抜粋を記す。 防爆バリヤの最大電圧,最大電流,最大電力が2線式計測機器の本安回路許容電圧,本安回路許容電流,本安回路許容電力を超えていないこと,2線式計測機器の内部インダクタンスと内部キャパシタンスに接続するケーブルのキャパシタンスとインダクタンスの合計が防爆バリヤの許容インダクタンスと許容キャパシタンスを超えていないことを確認する。 3.新型「RNシリーズ」 2022年4月より弊社Endress+Hauserでは,新たなインタフェースモジュールを販売開始した。 構成としては, ・AC100~240VまたはDC110~250Vを供給し,DC 24V/2.5Aの電源として動作するRNB22(写真1-①) ・RNB22などの電源からDC24V供給を受けて,2線式伝送器の電源兼アイソレータ(アクティブバリヤ)として動作する,または4線式計器のアイソレータ(パッシブバリヤ)として動作するRN22(写真1-③) ・RNB22などの電源からDC24V供給を受けて,RN22に電源を供給する際に電源の冗長化を行う,または入力回路の断線や短絡などの配線異常が発生した際にエラー伝送モジュールとして機能するRNF22(写真1-②) が代表的な製品である。 (そのほかにも,バルブなどの大きな負荷用のアイソレータやNAMUR規格の絶縁アンプなども用意している。) 実際に2線式伝送器や4線式計器と接続して,電源兼アイソレータもしくはアイソレータとして機能するのはRN22であるが,RNB22やRNF22と一緒に組み合わせることによって,電源の冗長化を構築したり,断線や短絡などの配線異常を検出したりすることができる。 RN22は外形寸法として,横幅12.7 mmであるが,最大2チャンネル搭載することが可能なので,RN22を1台設置することで,2台の2線式伝送器の電源兼アイソレータとして機能する。2つのチャンネル間は当然絶縁されているので,安全性を確保できる。 RN22はDINレールに設置できるバス給電コネクタ(写真2)によって,機器の背面から給電を受けることができる。これを使用するとRN22の電源端子に配線をする必要がない。 RNF22もこのバス給電コネクタに対応しており,RNF22にはDC24VをRNB22などから供給し,バス給電コネクタからRN22へ給電を行うことができる。また,RNF22にはDC 24Vへの給電端子が2組搭載されており,この端子に2台のRNB22からDC 24Vを給電することで,電源の冗長化を行うことができる(図3)。 電源の冗長化を行うことで,万が一電源が故障したとしても,計測機器への給電に支障を来さず,継続することができる。 RN22はバス給電コネクタから電圧供給を受けることによって,配線が少なくなり,電源が冗長化されることで,計測機器への電圧供給や信号伝達に支障がなくなる。RN22は本質安全防爆機器の防爆バリヤとしても機能するため,安定した電圧供給は計測機器の運転,ひいては使用されているプロセスを安全に運転させることに貢献できる。 4.既存計器のデジタル信号の活用 RN22の特長として,計測機器から出力されるHART信号を上位装置へ渡すことができる。 HART信号は4-20mA電流信号に重畳される周波数変調方式のデジタル信号であるが,HART信号を活用することで,計測機器が主目的で行っている計測値以外の内部信号やその他の情報を受け取ることができる。また,HART信号を利用することで,設定ツールやアプリケーションソフトによって,計測機器のパラメータ設定や診断なども行うことができる。 RN22には,そのような場合を想定して,設定用のアダプタを接続するための接続口を前面に設けている(写真3)。 本誌2021年9月号にて「無線技術によるフィールド機器の設定と診断」という記事を寄稿したが,この記事で紹介した内容と同じことがHART信号を利用することで実現できる。弊社の計測機器は,ほとんどの機器に4-20mA電流信号に標準でHART信号を重畳しているため,計測機器が測定に利用している内部信号をHART信号に割り当てて監視を行うことで,プロセス変化の予兆を検出したり,計測機器の付着や腐食などの予兆を検出したりすることができる。 たとえば,本誌2020年1月号で紹介した音叉式レベルスイッチの場合,当時はBluetoothで音叉部の振動周波数の伝送を紹介したが,現在HART信号バージョンも販売しており,振動周波数をHART信号によって監視できる。 HART信号を利用するためには,既存の上位装置がHART信号に対応していない場合,上位装置を更新しなければ対応できないと考えていないだろうか。今回紹介しているRN22には,オプションで信号分配機能を選択できる。このオプションを選択した機器に4-20mA HART信号を入力すると,4-20mA HART信号と4-20mA信号の2つの信号に分けて出力することができる。これを利用することで,4-20mA信号は,従来のDCSやPLCに入力し,4-20mA HART信号は別の機器に入力をして利用することができる。RN22を経由して分配することで,2つの出力は絶縁されるので,安全に使用することができる。 一方で分配したHART信号を活用するために,やはりHART信号対応のDCSやPLCを用意しなければならないかというと,そうではない。 弊社ではHART信号を入力して,任意のHART変数を選択して表示することができる表示器「RIA15」(写真4)を用意している。現場もしくは計器室で値を確認するだけであれば,こうした現場表示器が利用できる。 また,HART信号を入力して任意のHART変数を選択して記録する記録計「RSG45」(写真5)も用意している。 RSG45と組み合わせると任意の変数を選択して記録することもできるし,しきい値を設定してリレー接点を切り替えることもできる。また,Webサーバ機能を搭載しているため,IPアドレスを割り振ることで,汎用のブラウザで離れた場所から測定値を確認したり,しきい値を超えたり下回ったりした場合に,メールで通知を行ったり,接続された計測機器のパラメータ設定を行うこともできる。 このような仕様をする場合は,図4のようなシステム図の構成となる。 RN22とRSG45を組み合わせることで,計測機器の内部信号を活用し,予知保全につなげることができると考えている。また,RSG45にIPアドレスを割り当てることで社内ネットワークに接続し,遠隔監視などのIoT化を実現することができると考えている。 5.おわりに 計装システムに使用される電源には,まず計測機器を安定して動作させること,接続される機器の安全を確保することが求められるが,今回紹介したように,それらの基本を押さえたうえで,計測機器が持っている様々な機能を活用するための補助機能を持った製品も登場している。 我々としては,今回紹介した製品とつながる計測機器の機能や内部信号を活用した使用方法も紹介し,IoT化に貢献できる電源の活用方法を広めていきたいと考えている。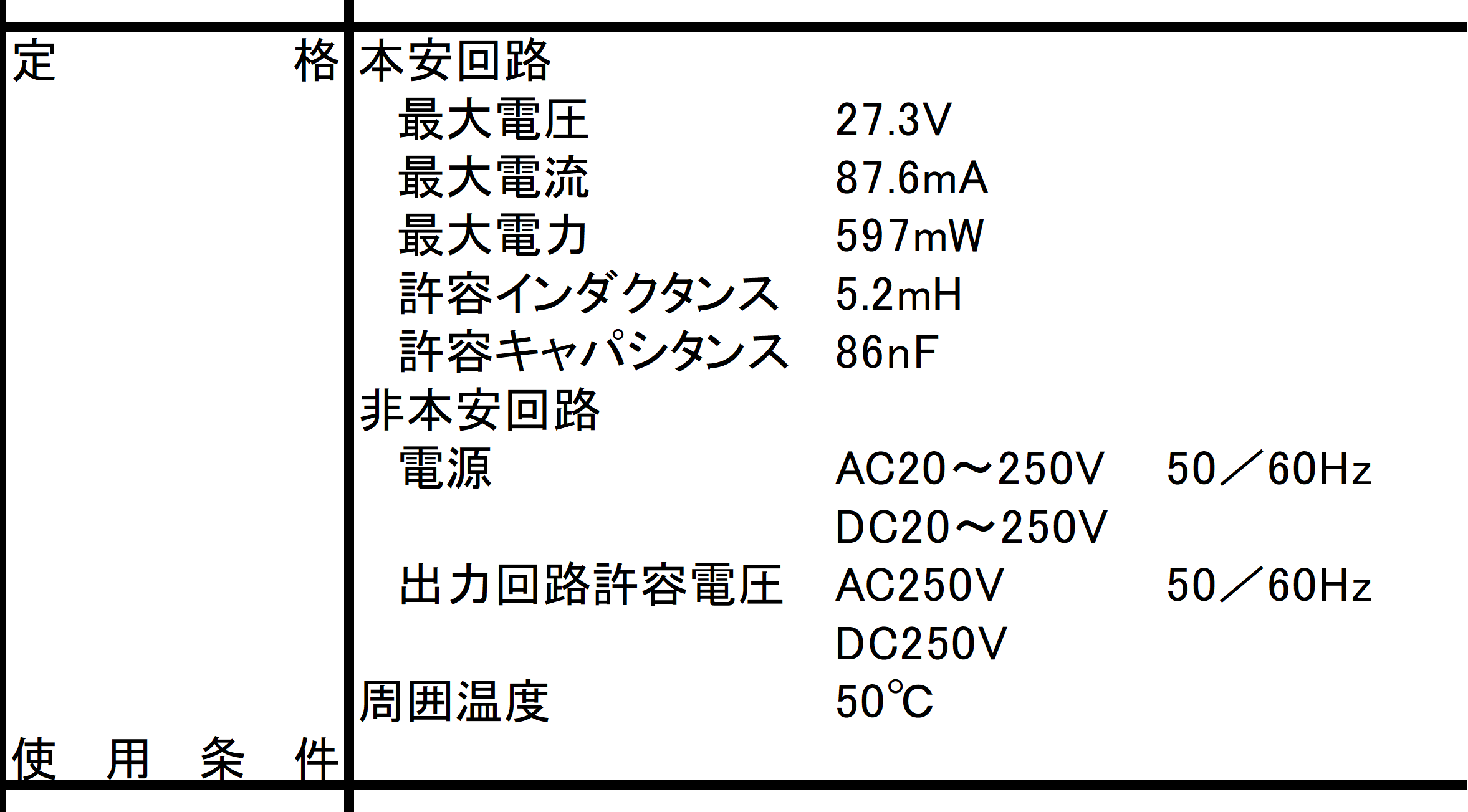
図1 防爆バリヤの定格例
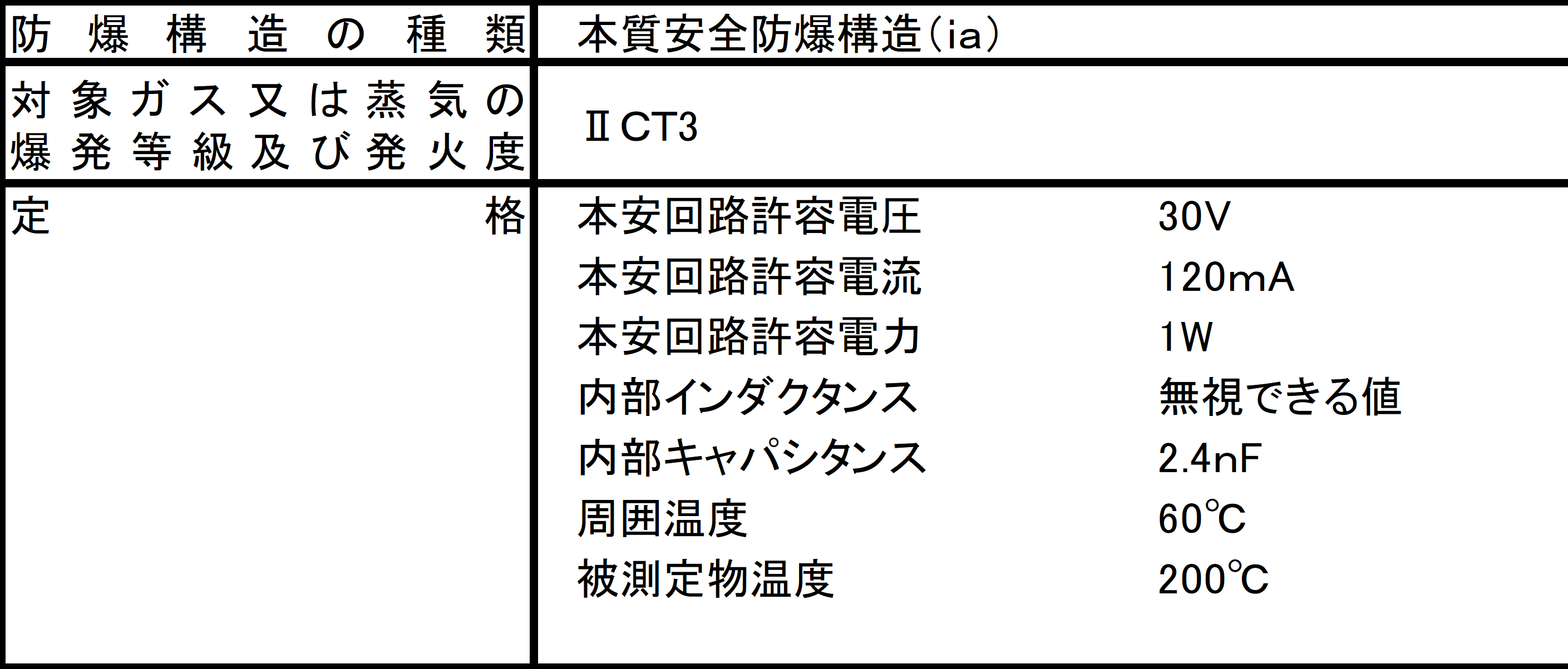
図2 計測機器の定格例
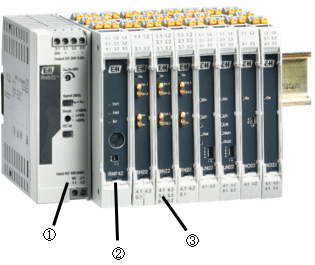
写真1 新型「RNシリーズ」外観

写真2 バス給電コネクタ
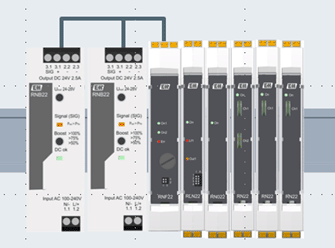
図3 電源冗長化構成例

写真3 RN22のHARTアダプタ接続口

写真4 表示器「RIA15」
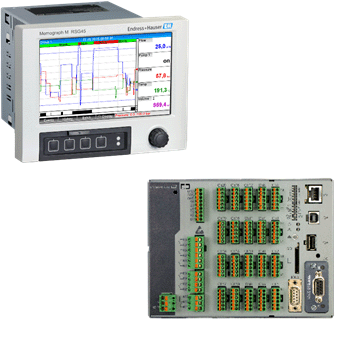
写真5 記録計「RSG45」
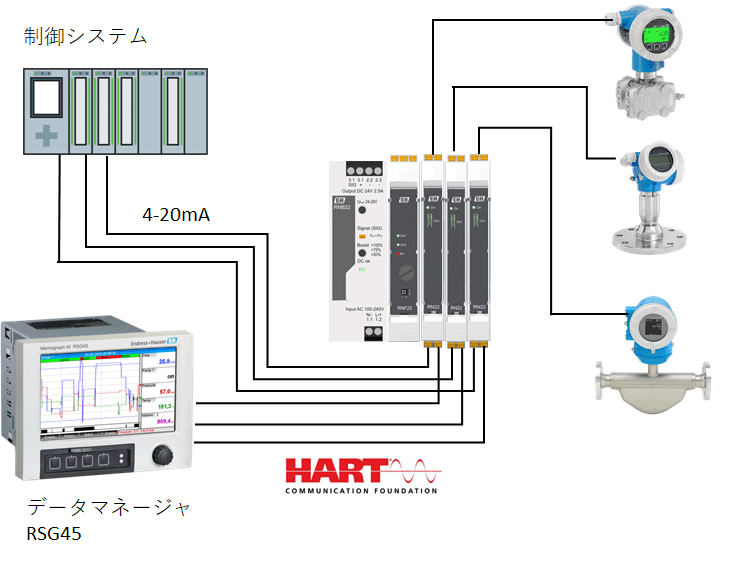
図4 RN22とRSG45を組み合わせたHART信号の活用
ポータルサイトへ