

【特別寄稿】
ITとOTを繋ぐDXを実現する オープンな標準「FDT UE」とそのソリューション
1.はじめに
従来からFDT技術は,様々なベンダが提供する各種機器や通信プロトコルを一つのツールで管理する標準化技術(IEC 63453)として発展してきた。2020年6月にFDT Groupは,データ駆動型でかつクラウドベースのアセット管理の機能拡張を施した新しいバージョンFDT 3.0のリリースを発表した。
これまでFDT3.0に関しては,拡張したサーバ機能に着目して,アーキテクチャ名称FITS(FDT IIoT Server)として紹介してきたが,今後は機器情報を保有するDTMの特徴も加えて,「FDT UE」(FDT Unified Environment)という新しいアーキテクチャ名称として紹介していく(図1)。
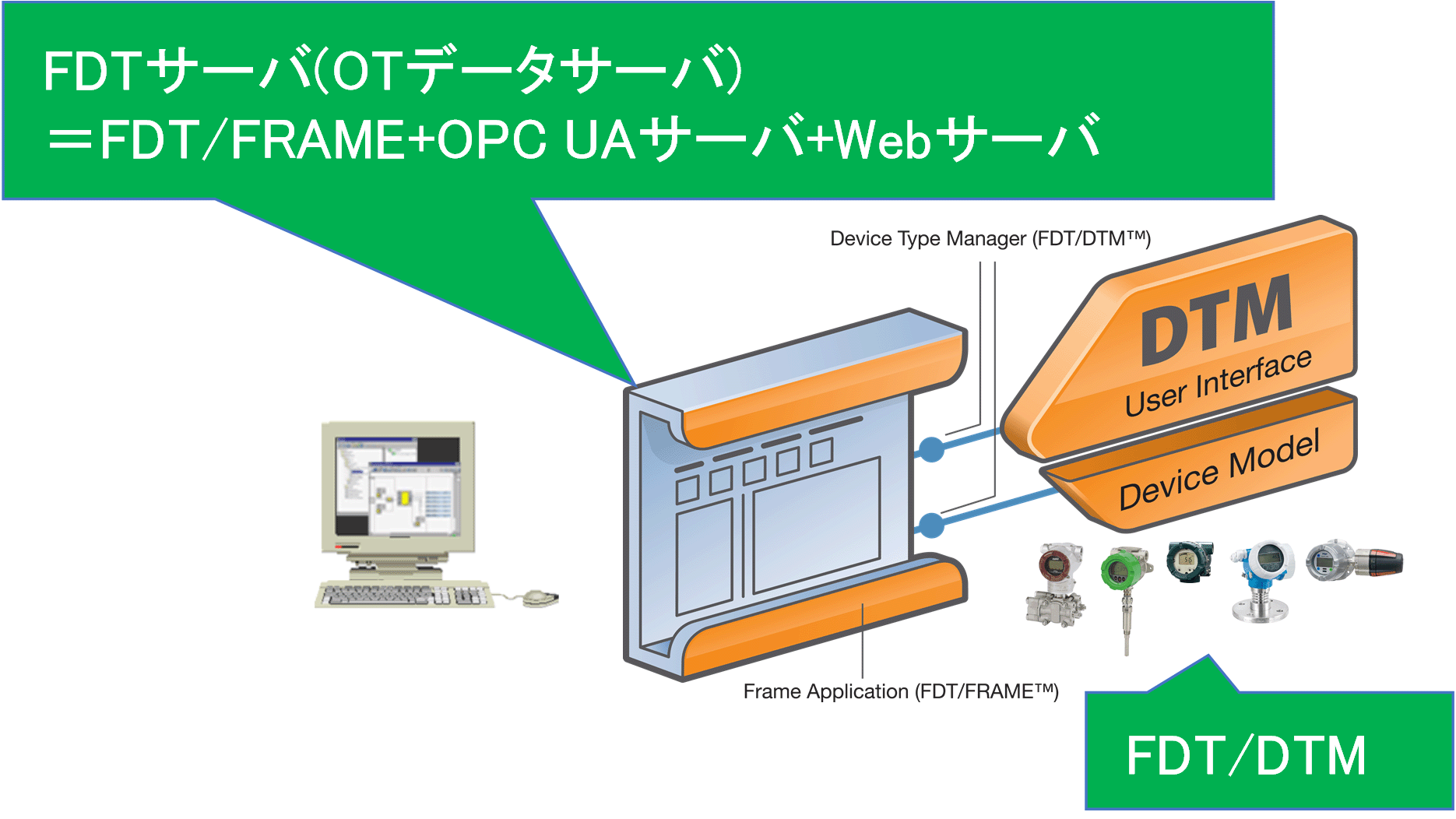
FDT Groupはベルギーに本部を置く非営利団体(NPO法人)で,2006年4月に日本支部を立ち上げ,セミナや展示会を通じてFDT技術に関しての普及活動を行っている。また,2019年から早稲田大学理工学術院総合研究所/産業用オープンネットワーク・ラボラトリー(IONL)に参画し,IONL FDTセクションの構成メンバとして,各種機器と接続可能なミドルウェア研究開発の位置づけで技術教育・啓蒙普及活動を実施している。
その一環として,IIoTの推進に対し必須となるセキュリティやデータガバナンスの観点で,NTTコミュニケーションズ㈱と連携して「FDT UEを活用した欧州GAIA-Xと製造現場をつなぐデータ連携基盤」の実証実験を開始した。本稿では,FDT UEの概要,デジタルツインにおけるFDT UEの活用,FDT UEを活用した実証実験の紹介を行う。
2.FDT UE(FDT Unified Environment)
IIoT(Industrial Internet of Things:産業用モノのインターネット)によって,制御システムや高度なアプリケーションによるインテリジェントセンサの監視,モバイル端末の利用,スマートシステムの構築が可能となり,スマート製造の新時代が切り開かれた。従来の運用・制御技術(OT)システムと情報技術(IT)システムの間の境界線もIIoTによって変わりつつある。産業界は,より良いビジネス上の意思決定を行えるよう,ITとOTを統合したシステムを求めている。
しかし,従来ITとOTは別々のテクノロジーとして扱われており,それぞれを異なる目的で設計,保守,運用してきた多くのメーカにとっては,この統合は一筋縄でいくものではない。ITと OTのシステムおよび運用慣行を統合したシステムアーキテクチャを使えば,それまでの非効率性や相互運用性の問題は解決され,設計時間は短縮し,運用効果も高まって,イノベーションはより加速する。
IT/OTの統合に対応した業界標準規格を活用し,センサとクラウドの統合とIT/OT間の情報交換をシームレスにすることで,インダストリ4.0の導入が実現できる。エンドユーザが主導する以下の2つのオープンな規格によってITとOTの統合が可能となり,プロセスやディスクリートでのアプリケーションにインテリジェントな卓越した製造手法をもたらしてくれる。
・OPC協議会:OPC Unified Architecture (OPC UA)
・FDT Group:FDT Unified Environment(FDT UE)
FDT GroupによるFDTサーバ用の情報モデルの開発はOPC協議会の支援を受けている。この情報モデルは,関連するコンパニオン仕様と情報モデルによってDTMから提供される情報に基づいており,これを使ってFDT UEのエコシステムを構築している。
この両団体の共同活動によってオープンで,センサからクラウドに至るシステム構築や通信に向けた単一ソリューションが実現している。このソリューションは産業,プロセス,ディスクリート,ハイブリッド製造業の中でオートメーションシステムやアセット管理システム,その他の工場や企業のシステムやアプリケーションとの接続も視野に入れている。FDTとOPCのアーキテクチャを調和したことで, FDT UEは今日のインフラと未来のインテリジェントエンタープライズに向けた技術,課題解決,人の融和を実現する。
FDT UEのエコシステムは,2つの主要なソフトウェアコンポーネントで構成されている。 (図2)

●FDT サーバ
FDTサーバは,センサからクラウドへの機器DTMのセキュアな統合や,データ交換,および見える化を実現するランタイム環境とアプリケーションインタフェースを提供している。サーバは重要なIIoTデータのハブとして,クラウド,オンプレミス,またはエッジにも広く展開が可能なアプリケーションの中心的な存在であり,これを使ってインテリジェントエンタープライズを強化することができる。
サーバには,ビジネスおよび運用の監視と制御/構成のためのサービスに向けたインタフェースが予め用意されている。最初から実装されているOPC UAサーバ(コンパニオン仕様「OPC UA for Devices」によってDTMから展開されるユニバーサル機器情報モデルも含まれている)は,IT/OTのデータ統合に加えて,OPC UAクライアントアプリケーションを使ったエンタープライズレベルからのデータアクセスもサポートする。Webサーバによって,FDTクライアントはブラウザやモバイル端末から最新の機器管理も行えるようになる。またコアサーバでトポロジーの集中管理やシステム構成を行うことができる。豊富な制御機能を使うことで,プロトコルやベンダに関係なくセンサからクラウドへの産業用通信が活用でき,スマートな製造手法を実現できる。
●FDT/ DTM
DTMは,ビジネスロジックとユーザインタフェースにより機器やネットワーク固有のデータ処理と機能を実行する。そしてDTMをFDTサーバのプラグインとして利用することで,OPCやFDTクライアントからのアクセスも可能となる。DTMを使うことで機器とネットワークの統合における課題を解消し,多層トポロジーやフラット化されたイーサネットベースのアーキテクチャにも柔軟に対応することができるようなる。
DTMはフィールド機器やゲートウェイ,プロトコルアダプタなどの通信インフラを構成する機器までカバーしている。DTMを使って,ライフサイクル管理(各機器やネットワークのシミュレーション,計画,試運転,運用,および診断)に必要なパラメータやプロファイルのデータ管理など多くの機能を実行することができる。
3.FDT UEによるセキュアなデータの見える化
FDT UEは,単一のデータマッピングにより情報を可視化する特徴を有しており,インダストリ4.0のアプリケーションに対してセマンティックデータモデルを提供する。FDTサーバは,FDT OPC UAユニバーサル機器情報モデル(すべての機器,ネットワーク,および様々なオートメーション業界向け)を活用しており,すべての機器およびネットワークパラメータプロファイルをサポートする互換性のあるインタフェースを定義している。
DTMはすべてのパラメータ値に対してセマンティック情報を提供することができる。詳細なエンジニアリングのためのECLASSの記述や,ライフサイクル管理用に機器の保守ドキュメントへのリンクを提供することなどが可能である。DTMはいわば機器に関する情報のデータハブとして機能することができる。(図3)
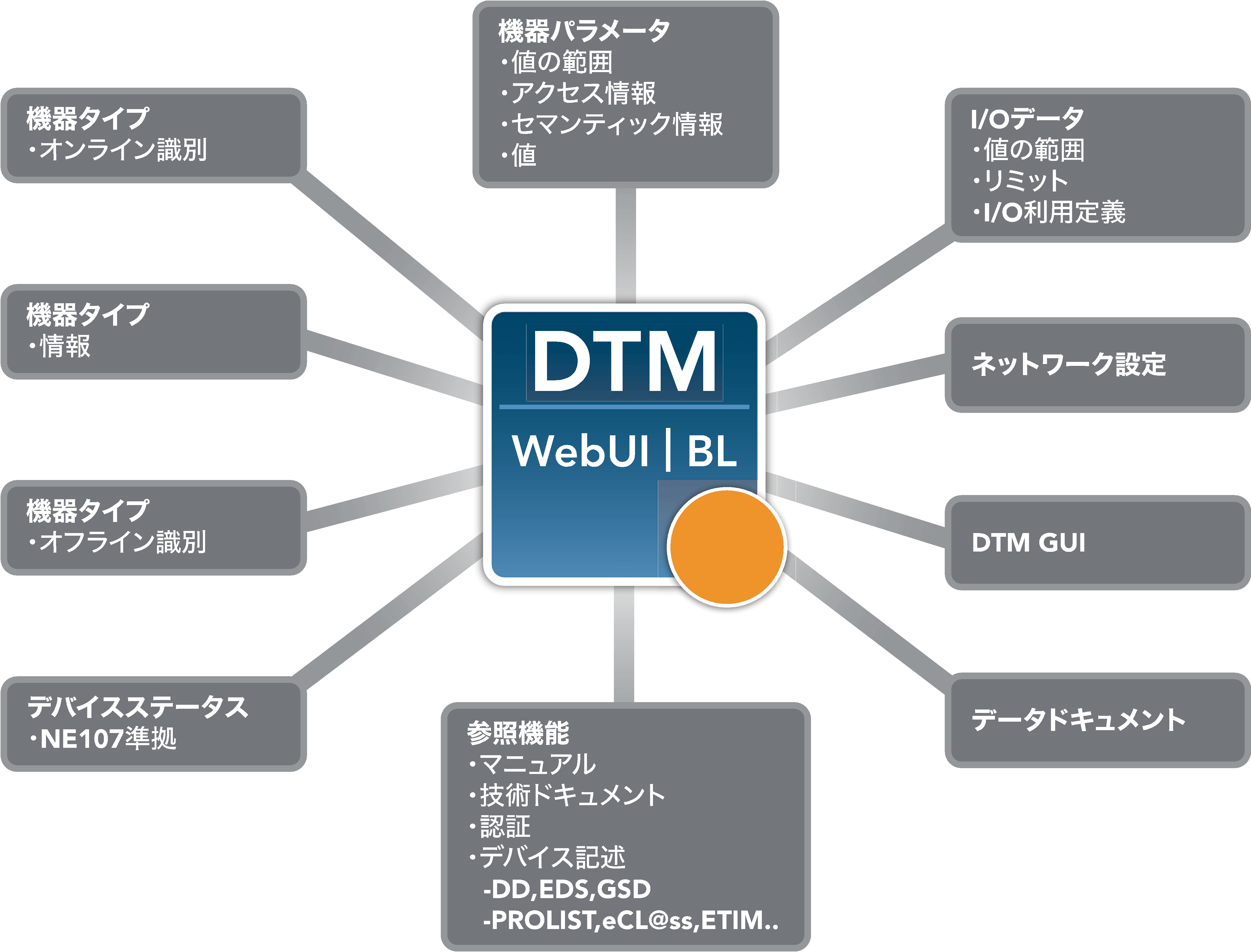
4.デジタルツインによるプラント設計と運用性能の改善
デジタルツインは,機器のようなシンプルなものから,ビジネスシステム全体のような複合したものまでも,そのままにバーチャルでコピーしたものである。センサテクノロジーによるデータを基に作成されたデジタルツインのデータを使って,ユーザは機器やシステムで起きていることを,構造と操作の両面でリアルタイムに観察することができる。
FDTは,ITとOT,およびシステムと機器の世界を統合する。FDTサーバ環境ではOPC UAサーバとWebサーバからなる2つのサーバが用意されているので,機器またはプロセスの様々なシステム構成とシミュレーションにおいて,運用上のメリットと経営上のメリットが生まれる。デジタルツインによって,データ分析と運用上の洞察が促進される。FDTサーバのOPC UAを使うことで,システムプロバイダはオートメーションシステム,I/Oシステム,およびプロセスのシミュレーションと仮想化にデジタルツインを利用することができる。
FDTにとって,機器に関する情報へのアクセスは決して新しいことではない。20年以上もの間,FDTが得意としてきた機能である。元来,この機能は機器アプリケーションの工程上の表現の一つであった。しかし,FDT UEでは,これを機器アプリケーション上の表現から機器のサーバ上の表現に昇華させている。FDT環境ではただ1つのサーバにより,機器の情報とサービスをパッケージとして提供できるようになった。そのためサーバは機器に関する,多種多様なユースケースに対応することができる。DTMはサポートするすべての機器タイプに関する情報をパッケージ化して提供する。このためシミュレーションやバーチャルコミッショニングに,DTMが使える。(図4)
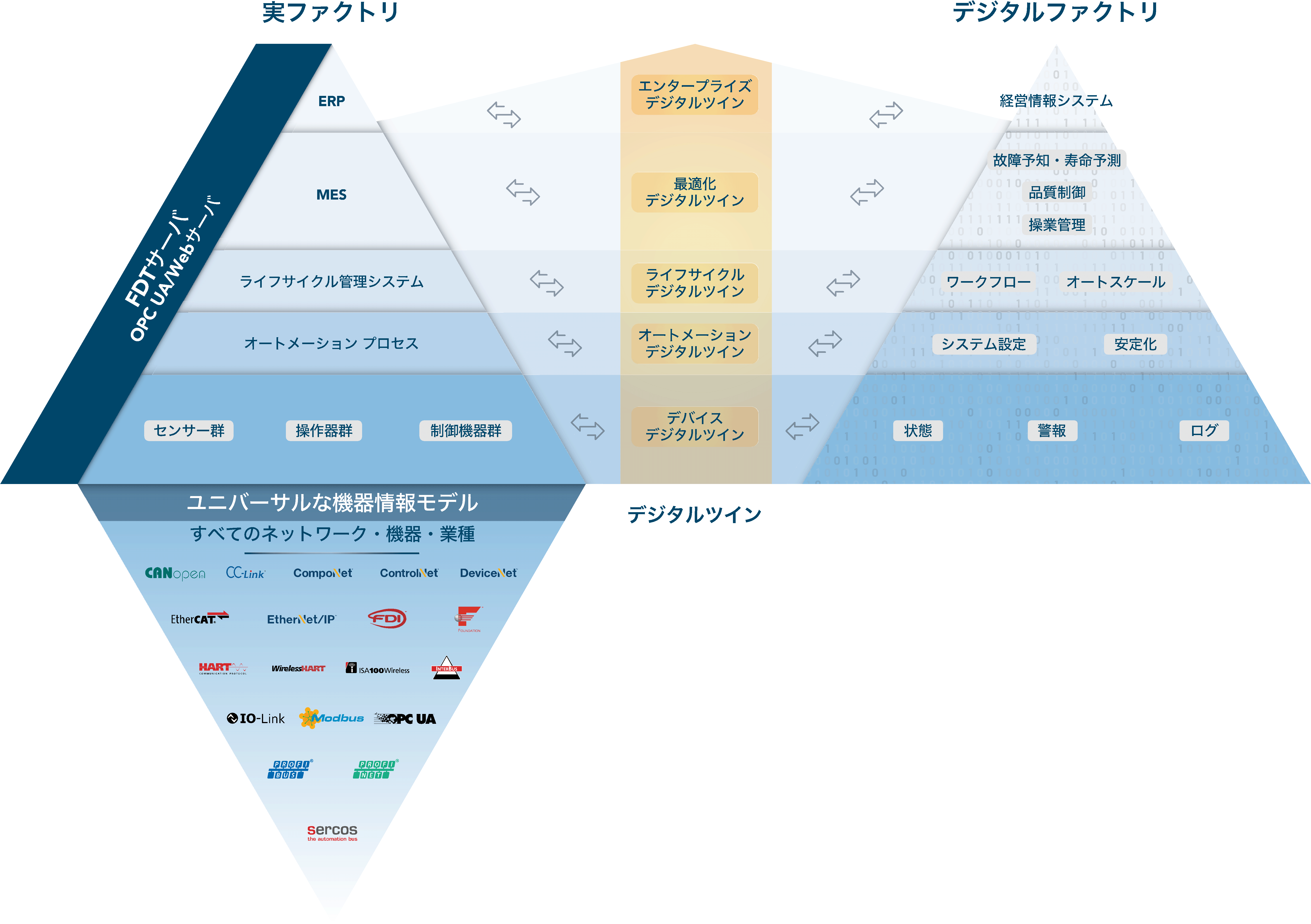
デジタルツインによってライフサイクル全般にわたり制御システムが改善される。セマンティック情報によるプロパティ情報の相互運用が確保されると,改善はプラント設計から運用効率まで範囲が広がる。もしプラント設計で使用した機器データにセマンティック情報を加えると,システム設計者と運用担当者は機器データや,設計データと機器の現在の設定内容についても両者で共通の認識を持つことができる。FDT OPC UA情報モデルを使うと,どんなユーザアプリケーションからもこの情報がアクセスできるようになる。
FDTは現在の産業活動に求められるオープンで,スケーラブル,そしてセキュアで相互運用性のある1つの基盤である。この基盤を通して人,プロセス,技術が互いに効率よく運用できるようになる。コミッショニングとスタートアップはデジタルツインにとって最も重要なユースケースと言える。というのも物理機器への依存性をなくすことができるからである。迅速な設定やシミュレーション環境でのライフサイクルプロセスの刷新において,デジタルツインの真価が生かされる。物理機器なしで,すべて正確に動作できることを考えてみて欲しい。シミュレーションでも機器は物理機器なしの環境でユーザにデータを返してくれる。これは機器から直接データを得られるのと変わりない。
FDTは実世界と仮想世界の橋渡しを行う。そのためにはいかなるプロトコルや機器をもモデル化し,いかなるネットワークやその階層構造も横断してセキュアな通信を行えるようにしている。デジタルツインがあれば,FDTを使って設定,シミュレーション,動作確認,意思決定,履歴研究ができるようになる。
FDTの制御における知見はデジタルツインに生かされ,ベンダやユーザも十分にメリットを実感することができる。(図5)
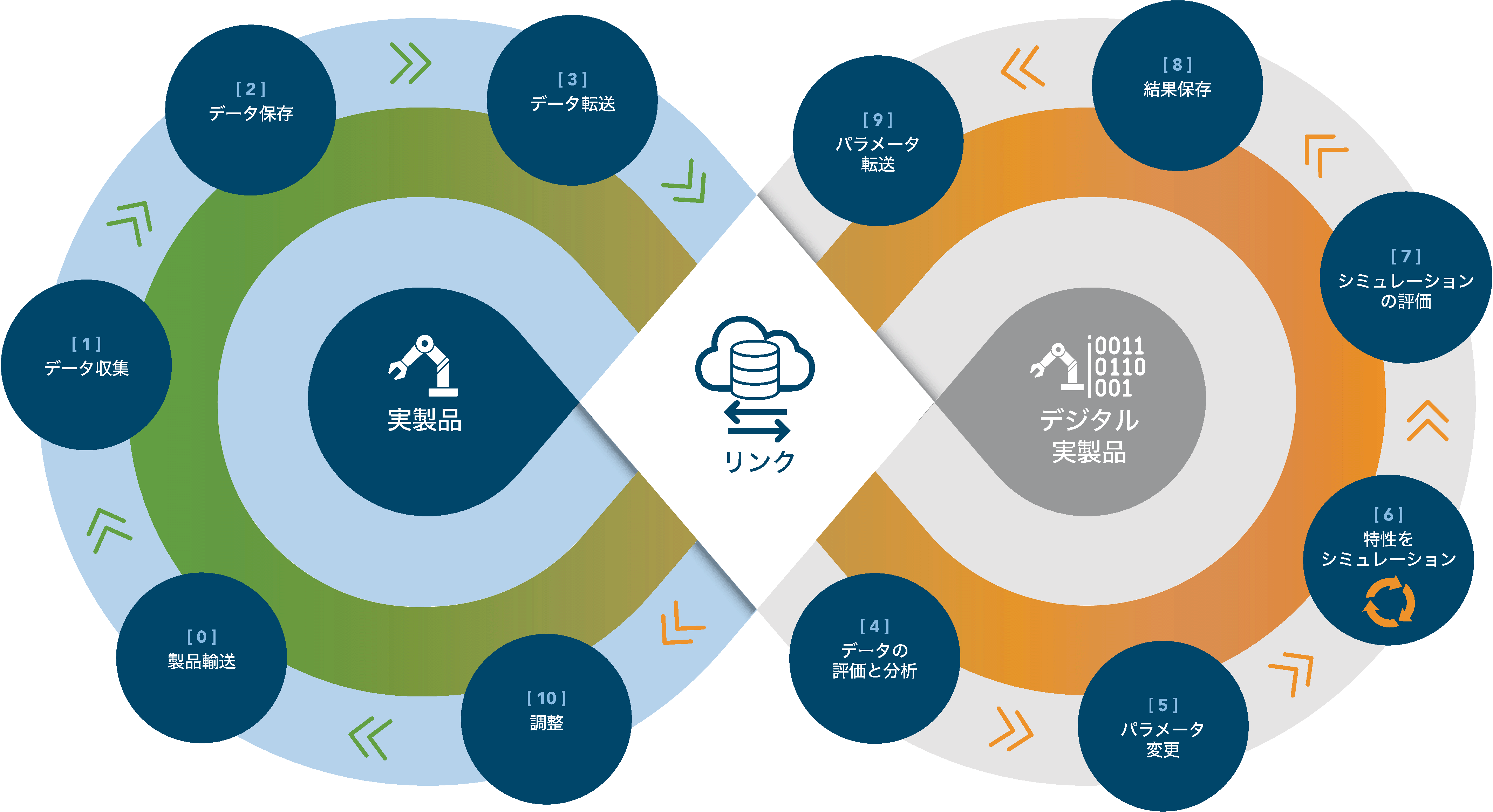
5.FDT UEを活用した実証実験の概要
FDTグループ日本支部は,IONLに参画して「FDT UEを活用した欧州GAIA-Xと製造現場をつなぐデータ連携基盤」の実証実験を開始している。この実証実験では,以下の内容で機器データを効果的に利活用する姿の検討を行うことを目的としている。
1)ベースとして,上位生産システムMES (Manufacturing Execution Systems)領域のDX (Digital Transformation)対応に関係するスタディをIAF(Industrial Automation Forum)と連携して行う。
2)トラストなデータ基盤上のビジネス領域における生産システム上の機器データの活用事例として,欧州GAIA-Xを活用したテーマとする。
3)近年重要性が増しているカーボンニュートラルの実現に必要とされる,炭素排出量データ国際取引を取り上げる。
図6に,実証実験設備の構想図を示す。図6中のFA側の設備として,製造用KPI(Key Performance Indicator)を活用するシステムをIAFと連携して構築する。具体的には,ベルトコンベヤと刻印機を使用して製品に刻印を行う作業を想定し,その際の炭素排出量をKPIとして産出するシステムを構築する。 また,IO-Link機器に対応するFDT 3.0 DTMをベースにして,前記システムとは別にFA側設備におけるPLCを介さないルートでのOPC UAサーバ機能の構築も行い,FDT UEの有効性の検証を行う。 PA分野としては,FAの組み立て工場で使用する素材・原料を生産する際の炭素量計算の役割がある。一つの事例として,生産工程で使用する蒸気の使用量や,供給側ボイラで使用する燃焼天然ガス消費量などの最適管理など,エネルギー管理における炭素排出量計算を想定する。この場合,PA側の設備におけるFDT UE活用イメージとしては,HART機器に対応するFDT 3.0 DTMをベースにした,DCSを介さないルートでのOPC UAサーバ機能の構築が対象となる。 今回実証デモ設備Phase1として,MES領域スタディと欧州GAIA-X接続(IDSコネクタによるデータ送受信テスト)を目的として,2022年1月26-28日に東京ビッグサイトで開催されたIIFES2022において,FA側設備のうちPLCを活用するルートをIAFと連携して構築した。ここでは炭素排出量データ国際取引として,想定した見積依頼,実績問い合わせ時の炭素排出量の模擬取引としている。 図7では,トラストなデータ基盤であるGAIA-Xで用いられるIDSコネクタを使用することで,取引先のみに必要十分な炭素排出量データが安全に伝達されることを確認した。今後は,FA側設備のうちFDT3.0機能を追加して,カーボンニュートラルの実現に貢献する機器データの効果的な利活用の検討を行う。 6.おわりに COVIDを契機としてデジタルトランスフォーメーションが急速に求められており,社会システムの複雑化や地政学的なリスク等,これまでにない不確かな時代に突入している。 FDT UEのオープンでデータ中心の統合アプローチは,産業オートメーションの新時代を実現する重要な技術となる。FDT UEは,標準化された内蔵モビリティとリモートアクセス,ネイティブなOPC UAの統合,強固なセキュリティ,プラットフォームの独立性を備えたオープンアーキテクチャを提供する規格であり,かつベンダが製品やソリューションをカスタマイズする拡張性も保持している。 FDT UEを活用すれば,製品ベンダはこれまでの製品を容易にIIoTのニーズに対応させることができるほか,新しい製品やサービスの開発も低コストで行うことができるようになる。こうした開発環境もFDTグループでは提供しており,入会することで無償を含めディスカウント価格で利用可能となる。 FDTグループ日本支部のセミナや展示会活動は,本誌の発行時期以降では以下の内容を計画しており,適時広告やメールなどでご案内している。ご興味のある方は,ぜひ参加していただきたい。 ・産業オープンネット展:8月2日~3日,セミナとリアル展示を実施予定 (https://www.sangyo-open.net/) ・FDT体験セミナ*:11月9日(Web開催) ・FDT技術セミナ*:11月10日(Web開催) ・IONL主催ユーザセミナ*:2023年3月頃(検討中) *IONLと共催 注) 本文中の団体名および技術名は,各社または各団体の商標または登録商標である。 〈参考文献〉 1)「IIoTやIndustrie 4.0に向けた新たな取り組み~FITS,OPC UA,AutomationML」,『計装』,Vol.60,No.10(2017年) 2)「製造業DXを支援するFDT3.0標準「FITS」のリリースとその進展方向」,『計装』,Vol.63,No.12(2020年) 3)T. Hadlich, M. Gundel, J. Chan, G. Schulz, T. Takeuchi, A. Ito,Leveraging IT technology into FDT3 specification realizes FITS architecture,SICE Annual Conference 2020, pp19-24 4)Schulz,伊藤,竹内:「FDT Groupがめざすもの」,『計装』Vol.64,No.9(2021年) 5)小川:「FDT技術の進化とその方向性」,『計装』,Vol.64,No.9(2021年) 6)亀井:「FITSで加速するプラントオペレーションのDX」,『計装』,Vol.64,No.9(2021年) 7)伊藤,竹内:「FDT3.0標準「FITS」に対するユーザ要求とそのソリューション」,『計装』,Vol.64,No.9(2021年) 8)安藤:「初級者のためのFDT基礎講座」,『計装』,Vol.64,No.9(2021年) 9)重冨:「FDT3.0に対するユーザ目線での期待」,『計装』,Vol.64,No.9(2021年) 10)堀越,境野:「セキュリティ・データガバナンス観点でのFDTへの期待」,『計装』,Vol.64,No.9(2021年) 11)「産業用機器管理とIT/OT間データ伝送を実現するFDT Unified Environment(FDT UE)」,『FDTグループ日本支部 ホワイトペーパー』,fdtgroup.jp 12)「デジタルツインによるプラント設計と運用性能の改善」,『FDTグループ日本支部 ホワイトペーパー』,fdtgroup.jp 13)伊藤,境野,茅野,堀越,藤島,小川,竹内,天野:「脱炭素社会に向けたトラストなデータ流通基盤GAIA-X上でのデバイスデータ利活用の検討」,『第9回 SICE制御部門マルチシンポジウム(MSCS 2022)』1F1-3 14)藤島,伊藤,茅野:「脱炭素社会の実現に向けた工場内炭素情報の“みえる化”」,『計装』,Vol.65,No.3(2022年) 15)藤島,茅野:「スマート製造のSMKL指標と,脱炭素に向けたGAIA-X接続」,『IAFシンポジウム』2022年3月 16)「トラストなデータ流通モデルに対するFDT技術の活用に関する研究の紹介」,『スマート製造とフィールド情報ユーザセミナ2022@早稲田大学』 *FDT UEとデジタルツインに関する詳細な解説は,FDT日本支部Webサイト(fdtgroup.jp)内の参考文献11,12を参照いただきたい。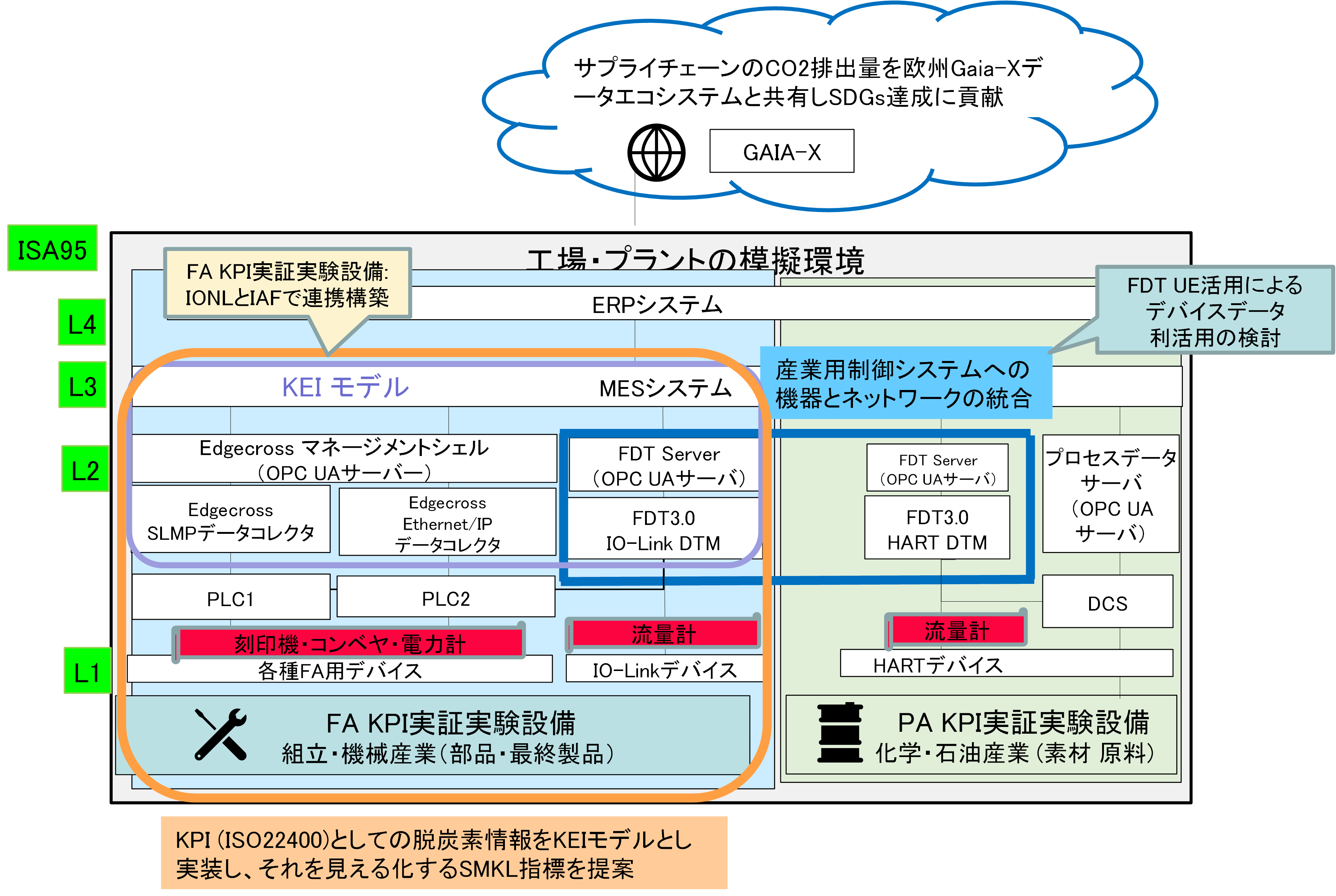
図6 IONL実証実験設備の構想
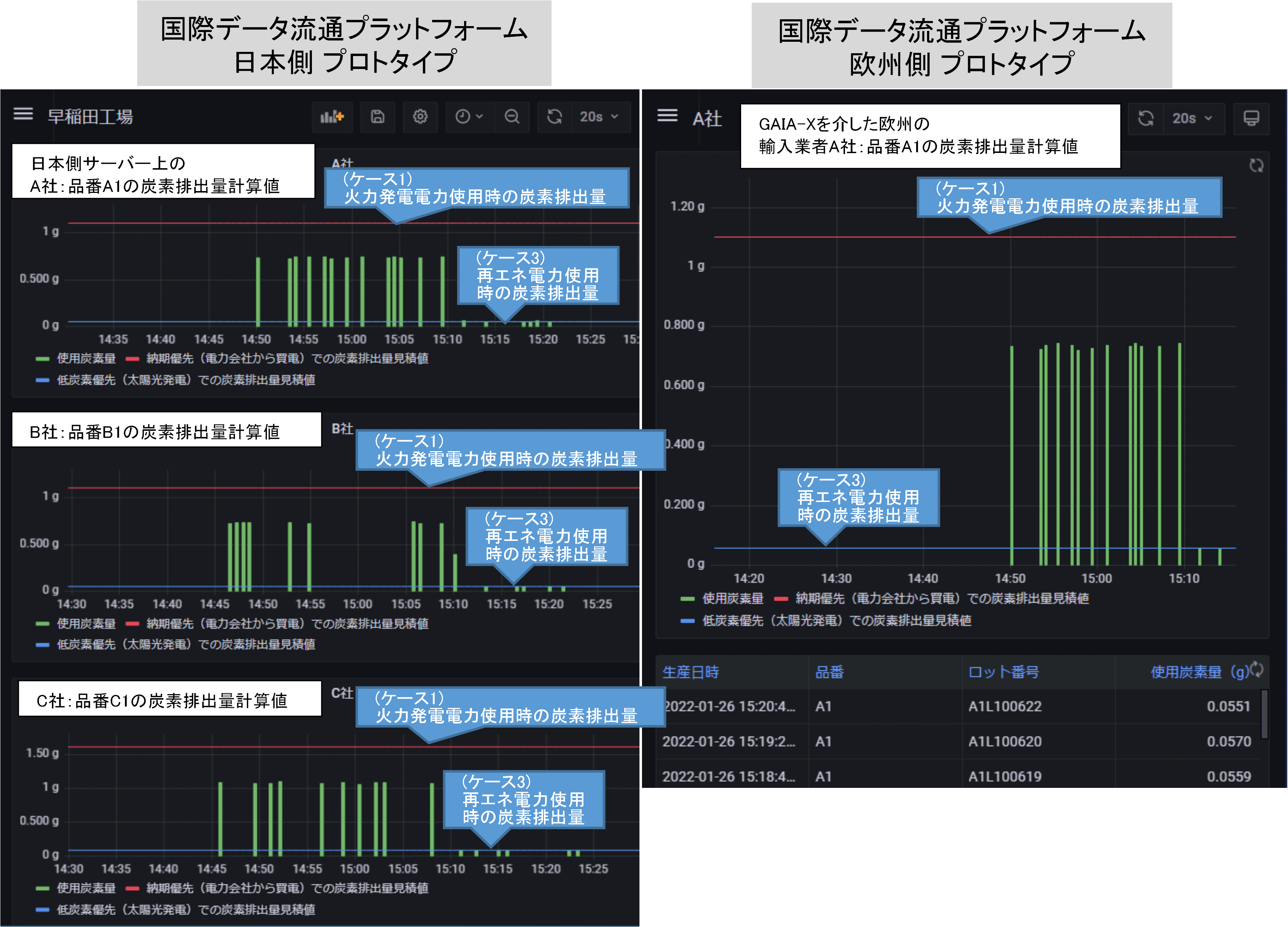
図7 炭素排出量計算値をGAIA-Xを介し,欧州の輸入業者に伝送するシミュレーション
FDT グループ日本支部 小 川 修 一/竹 内 徹 夫
ポータルサイトへ