

【ベンダ・プレゼンテーション】
デジタル技術の革新と制御システムの進化
1.はじめに
新型コロナウイルスのパンデミックにより人々の生活は大きく変化した。3密を避けるために,テレワークやオンラインでの授業が推奨され,多くの人がネットワークを介したコミュニケーションを頻繁に用いるようになった。また,ネットスーパー,ネットショッピング,ストリーミングビデオなど,ネットワークを介したサービスを利用する人はこれまで以上に増している。
このように,新型コロナウイルスのパンデミックは,デジタル化を生活に浸透させた一面がある。このような生活の変化はプラントの操業に関わる人たちにも影響を与え,制御システムにも新しいデジタル技術の適用に関する検討が進められている。
1975年に最初のDCS(分散型制御システム:Distributed Control System)が登場し,デジタル技術が本格的にプラント操業に使われるようになった。DCSは,デジタル技術を活用することで進化を遂げ,プラントの高度な操業に貢献してきた。
たとえば,90年代には,ベンダ独自のOSからUNIXやWindowsといった汎用のOSを採用するようになった。汎用PCや汎用ネットワーク技術を活用することが可能になり,大量のデータをリアルタイムで取得し長期保存することが容易になった。DCSの操作監視画面は大量のデータを用いた詳細なグラフィックの作成が可能になり,オペレータは瞬時に多くの情報を把握することが可能になった。長期保存されたデータは,汎用OSで動作する他のソフトウェアを使ってレポートを作成したり,データ解析に用いられたりするようになった。
このようにDCSは,その時々のデジタル技術を取り込みながらプラント操業の向上に貢献してきた。本稿では,DCSをはじめとする制御システムがこれまで以上の速さで進化するデジタル技術をどのように適用していくかについて紹介する。(図1参照)
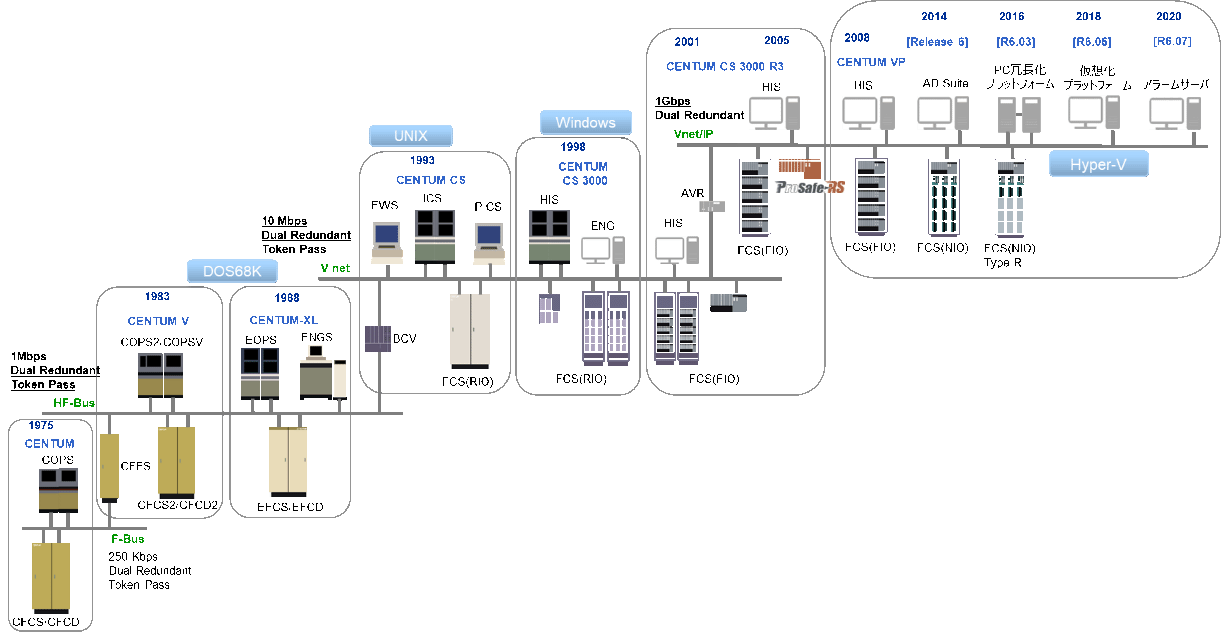
2.プラント操業におけるデジタルトランスフォーメーションの実現
デジタル技術の活用において,デジタルトランスフォーメーションという言葉がここ数年,頻繁に用いられている。「デジタルトランスフォーメーション」の定義は多岐にわたっている。使い方も人や場面によってまちまちであるが,ここでは,世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画で定義されている次の記述を用いる1)。
―「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション) 企業が外部エコシステム(顧客,市場)の劇的な変化に対応しつつ,内部エコシステム(組織,文化,従業員)の変革を牽引しながら,第3のプラットフォーム(クラウド,モビリティ,ビッグデータ/アナリティクス,ソーシャル技術)を利用して,新しい製品やサービス,新しいビジネスモデルを通して,ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し,競争上の優位性を確立すること」―
近年,プラントにおいても,IoT機器やロボット/ドローンを活用して従来とは異なった方法を用いたデータの取得,またAIやクラウド上のソフトウェアを用いて大量のデータを解析するような取り組みが活発になっている。それらの技術を使ってデジタルトランスフォーメーションを実現するには,現在のプラント操業を見直し,新しいデジタル技術を融合することでどのような新しい価値を創出できるか検討する必要がある。
DCSが主に使われている石油精製プラントや石油化学プラントでは,トラブルが発生したときの影響が大きいため,プラント操業において高度な信頼性と安全性が求められる。DCSは信頼性と安全性を担保するために,専用の閉じた制御ネットワークにDCSを構成する各コンポーネントを配置するシステム構成を採用していた。別のシステムとの連携は,ISA-95で定義される階層モデルにおけるレベル3にあるソフトウェアがDCSのデータ解析をしたり,一部のオペレーションを補助したりする程度にとどまっていた。
しかし,IoT機器やロボット/ドローンなどを配置したより多くのデータを活用した高度な操業を目指す場合,DCS専用の制御ネットワークで閉じている環境がデジタルトランスフォーメーション実現の障壁となり得る。また,それら新しいデジタル技術をプラント操業に適用して価値を創出するには多くのアイディアを試してみる必要がある。DCSの信頼性や安全性を担保しながら新しいデジタル技術の適用を試してみるには,そのリスクを許容できるアーキテクチャが必要である。
欧州の化学メーカを中心とした団体であるNAMURが提唱するNOA (Namur Open Architecture) では,既設のDCSなどの制御システムをCPC(Core Process Control)と位置づけ,それを置き換えたり大きな変更をしたりせずに新しいデジタル技術の採用をするアーキテクチャを提案している。CPCの外側にM+O(Monitoring and Optimization)と呼ばれる独立したドメインを付け加え,IoTセンサやロボット,ドローンおよび既設システムからデータを収集する。M+O ドメイン内でこれらのデータを元にデジタルトランスフォーメーションを実現するための高度な制御,解析,診断を実現するための試行を重ねることが可能になる。
3.統合情報サーバ
当社の統合情報サーバを用いて,既設システムと新しいデジタル技術を融合する方法について紹介する。
統合情報サーバは,当社のDCSで使われている専用の制御ネットワークに接続すると同時に,OPC UAやMQTTといった新しいデジタル標準技術を介してIoT機器や他社コントローラとも接続し,操作監視することが可能なプラットフォームである。NOAのM+Oドメインで使われることも想定している。統合情報サーバ上で,既設のDCSにより収集されたプラントのプロセスデータやアラーム情報と,IoT機器やロボット/ドローンから取得したデータを組み合わせることで,今までと違った操業を,既設のDCSに影響を与えずに試してみることが可能になる。(図2)
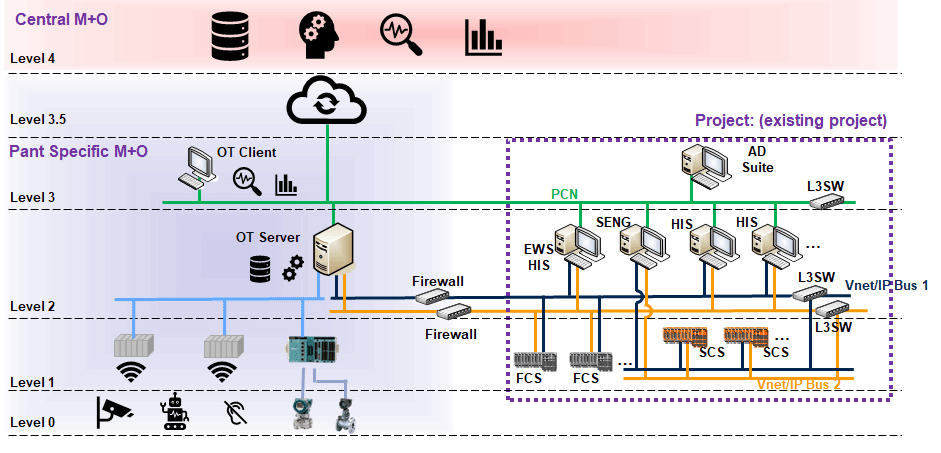
統合情報サーバによって複数のシステムから取得したデータを組み合わせて有効活用するには,それらが効率的に統合できる必要がある。これを実現するための仕組みが情報モデルである。情報モデルとは,複数のシステムの情報連携を効率的に行うための仕組みである。情報を意味のある塊(例:装置単位)とし扱うことが可能なため,複数のシステム間で煩雑なエンジニアリングをせずに連携させることができる。
たとえば,コンプレッサで扱われているデータを別のシステムで取り扱う場合,コンプレッサで使われている各データが何を意味するのかといった情報がわからないと,それらを適切に取り扱うことはできない。従来は,そのような定義情報をエンジニアが各システムに一つひとつ設定することでデータに意味を持たせていた。しかしIoTセンサを用いた大量のデータを効率的に扱おうとすると,データ量が膨大になり,エンジニアリングコストや設定ミスのリスクは計り知れない。
情報モデルを用いると,それぞれの機器が持っているデータとその意味をシステムが解釈することができるようになる。それにより,エンジニアリングをスムーズに行うことが可能になり設定ミスは削減される。また,情報モデルはメソッドをサポートしている。メソッドとは,一連の処理を一つの塊として定義したものである。これを実行することにより,複雑な処理を一つの命令として指示,実行させることも可能になる。(図3)
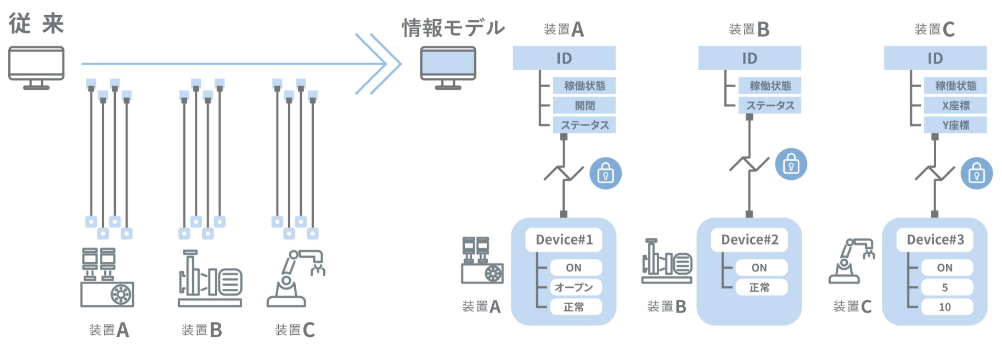
4.制御システムの近未来
統合情報サーバは,既設システムや新しいデジタル技術などのプラント操業に関わる,多種多様かつ膨大なデータを統一された形式で情報化し,プラント操業に関わるプラント全体の情報モデルを提供することで,プラント操業のデジタルトランスフォーメーションに貢献する。
当社は,製造業のユーザのデジタルトランスフォーメーションのゴールとしてIndustrial Autonomy(自律化)と,またそこへの道筋としてIA2IA(Industrial Automation to Industrial Autonomy)を提唱している。Industrial Autonomy とは,プラントの設備や操作自体が,学習し,適応する機能を持つようになることである。プラント自身が様々な事態に自律的に対応できるようになることによって人間の関与は最小限となり,オペレータはより高度なレベルの最適化に専念できるようになる。
Industrial Autonomyは,DCSなどの単体の制御システムだけで実現できるものではなく,これから登場するであろう新しいデジタル技術を使った様々なシステムを融合させることで実現できる。統合情報サーバは,従来DCSで自動制御を実現していたプラントに対し,さらに新しいデジタル技術を連携させ,Industrial Autonomyを実現する重要なプラットフォームである。(図4)
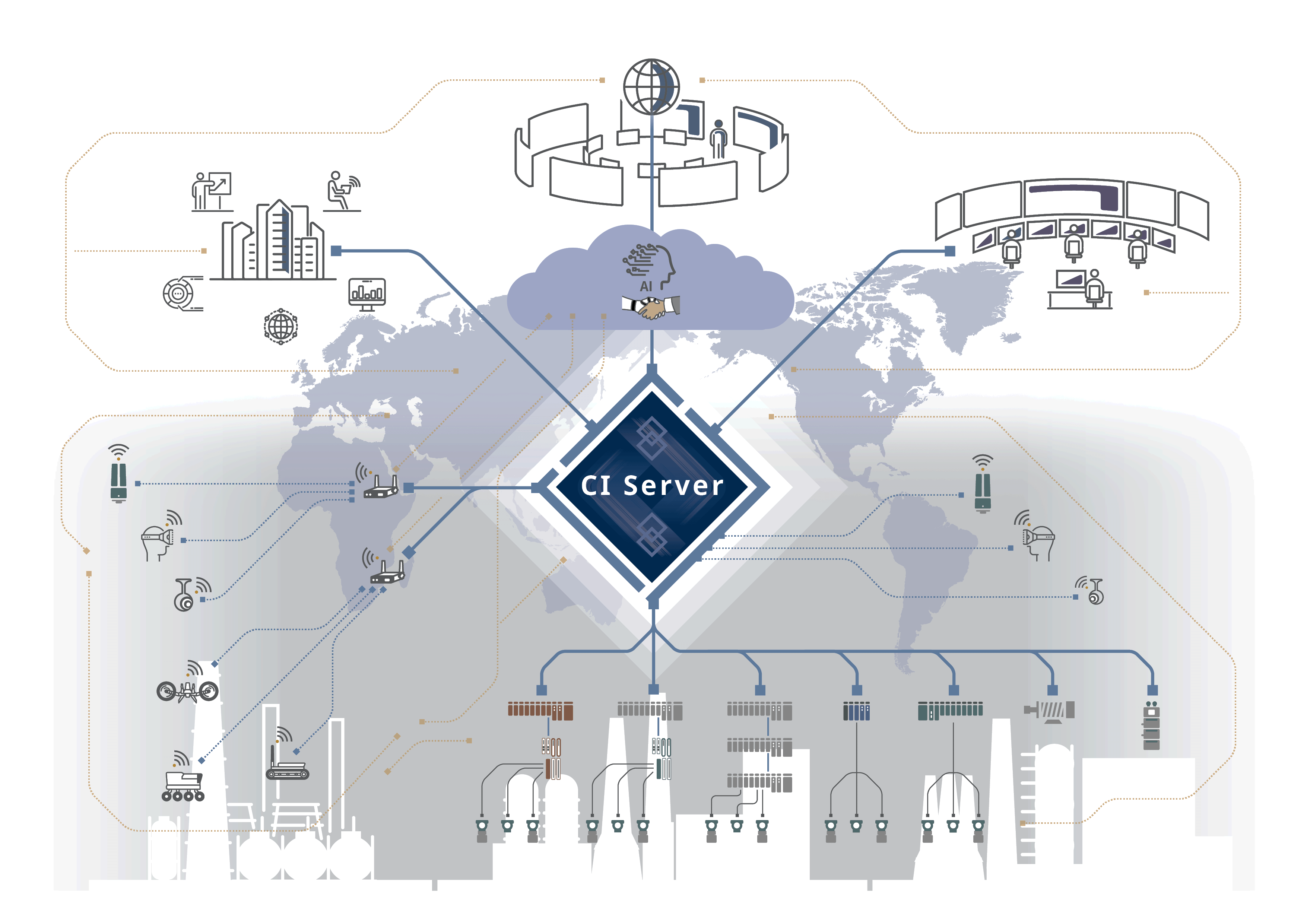
〈参考文献〉
1)情報通信技術(IT)総合戦略室,“世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年7月17日閣議決定)”,内閣官房