

【水処理計装ソリューション】
工場排水中のオンラインVOC濃度監視 ~GC-FID法を用いた安定測定法
1.はじめに
近年,各工業分野の生産過程において環境への配慮はより一層重視されるようになり,水質汚濁防止法等により,各事業主(企業)に対して厳格な数値管理が求められている。各企業では排水を最終的に排出する際の化学物質等の濃度をオンラインで監視・記録をすることは重要な事項の一つとなっている。また,工場内の各生産工程においても濃度の動向や異常を速やかに検知するために,最終の排水だけではなく,各工程において濃度管理・記録を行う動きがみられる。
そこで今回,弊社ジェイ・サイエンス・ラボが開発し,製造販売を行っている工場排水等中のオンライン水中VOC計「JVM-100」シリーズについて紹介する。
弊社では20年以上前から,ヘッドスペース(HS)法によるオンラインVOC計の製造販売およびメンテナンスを実施してきたが,近年の管理値の厳格化,特に平成24年の水質汚濁防止法(排水基準)で1,4-ジオキサン0.5mg/Lの測定項目の追加に伴い(適用期限は業種により平成26~30年),感度アップを図るためにヘッドスペース・パージ&トラップ(HS・P&T)法の開発を平成26年~27年に行った。以降は測定対象成分,濃度,夾雑などの影響を鑑み,HS法とHS・P&T法を選択し,装置構成を決定している。
2.オンライン水中VOC計「JVM-100」シリーズ
2.1装置概要
オンライン水中VOC計「JVM-100」シリーズは,河川水,工場排水等の水中の揮発性有機化合物(VOC)をオンラインで自動測定を行う装置である。(写真1)

揮発性有機化合物(VOC)としては,排水基準のジクロロメタン,1,2-ジクロロエタン,cis-1,2-ジクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン,ベンゼン,1,4-ジオキサン等の他,モノクロロベンゼン,パラジクロロベンゼン,トルエン,その他アルコール類等,様々な物質が対象である。
アナライザにはガスクロマトグラフ(GC)-水素炎イオン化検出器(FID)を用いることを基本としており,FIDは有機物に感度を有する検出器で,安定性・直線性に優れた検出器であることから,種々幅広い成分の低濃度から比較的高濃度領域の試料の測定に対応することが可能である。
本装置はヘッドスペース(HS)法またはヘッドスペース・パージ&トラップ(HS・P&T)法を採用しており,採水から気液平衡-(濃縮)-GC測定-結果の伝送-排水に至るまでそれぞれの工程を全自動で制御する。(図1)。特にOH基を有するアルコール類等親水性の高い試料等感度不足である成分に対しては,パージトラップ法による濃縮機構が効力を発揮する。
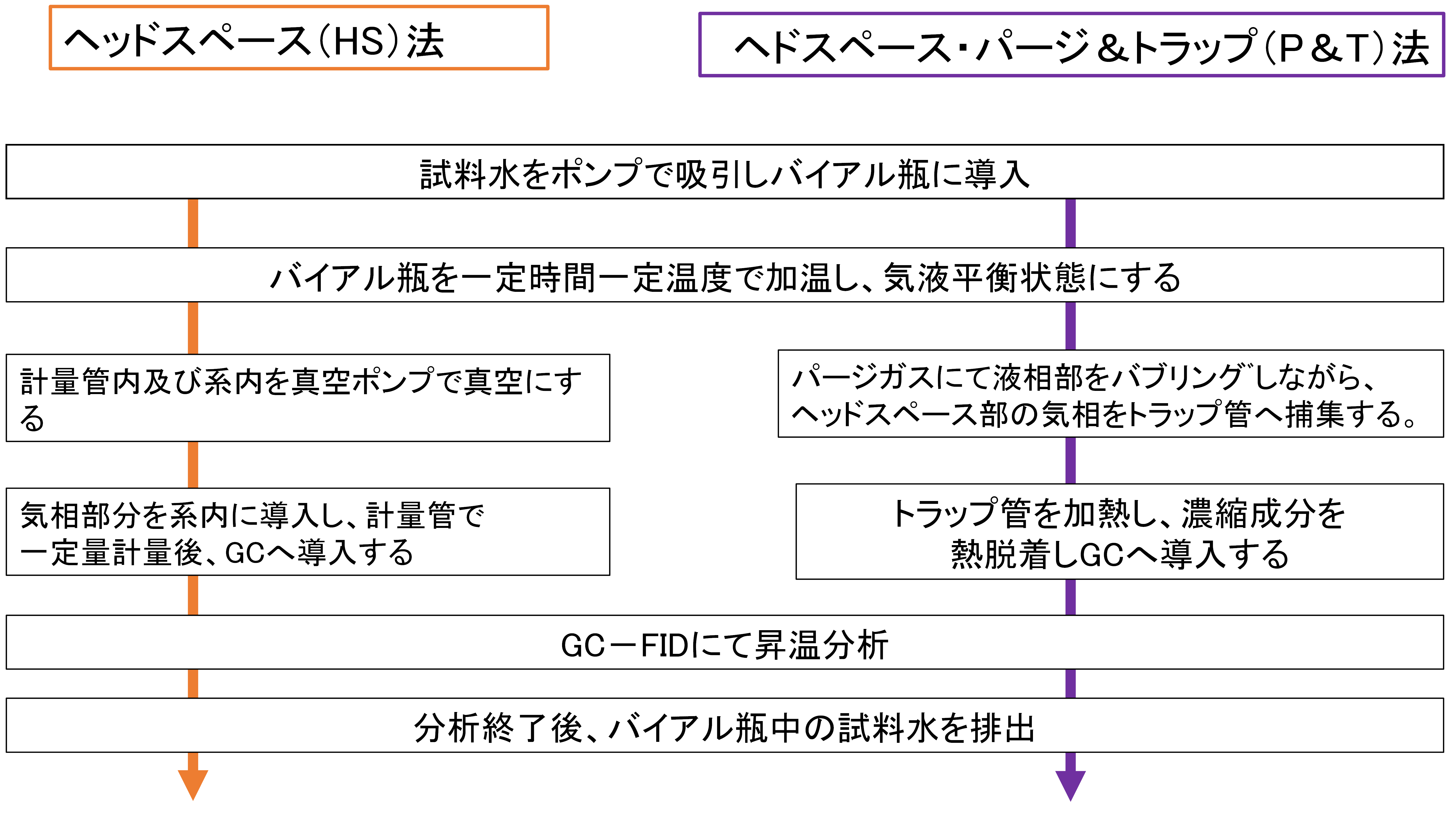
測定成分等により変更になる場合はあるが,おおよそ90分サイクルでの全自動オンライン分析が可能である。また月に1度程度を基本とした標準液による校正および,ボンベ交換,試料ラインの洗浄等の簡易メンテナンスは必要であるが(洗浄周期は試料水の状態による),それ以外は無人運転を基本としている。測定結果を保存するほか,4-20mAで上位への伝送,濃度異常時に警報発報などが可能である。
2.2 測定原理
本装置は測定したい成分および濃度により,HS法とHS・P&T法を使い分けている。
HS法とは一般にVOCを測定する際に用いられる分析手法の一種で,試料水を密閉容器内封入し一定温度に加温すると,上部の気相部分(ヘッドスペース)に水中よりVOCが移行(気化)する。一定時間,一定温度に保つと水中から気相へ移行するVOCと,気化していたVOCが水へ戻る量が一定となり,この状態を気液平衡状態と言う。この気液平衡状態に到達したヘッドスペースガスを一定量サンプリングし測定する方法をHS法と言う。
本装置では自動化するため,および分析精度の向上のためサンプリングバルブによる真空導入法を採用しており,予め真空にしておいた計量管にヘッドスペースガスを引き込み,計量管にて一定量計量後,GCへ導入する方式を採用している。
HS・P&T法は,前述のHS法とパージトラップ法を組み合わせた方式で一定時間,一定温度に加温した試料水をさらに不活性ガス(パージガス)でバブリングし,気相部分のガスをトラップ管へ捕集するのと同時に強制的に水中に残っているVOCを追い出し,捕集する方法である。(図2)
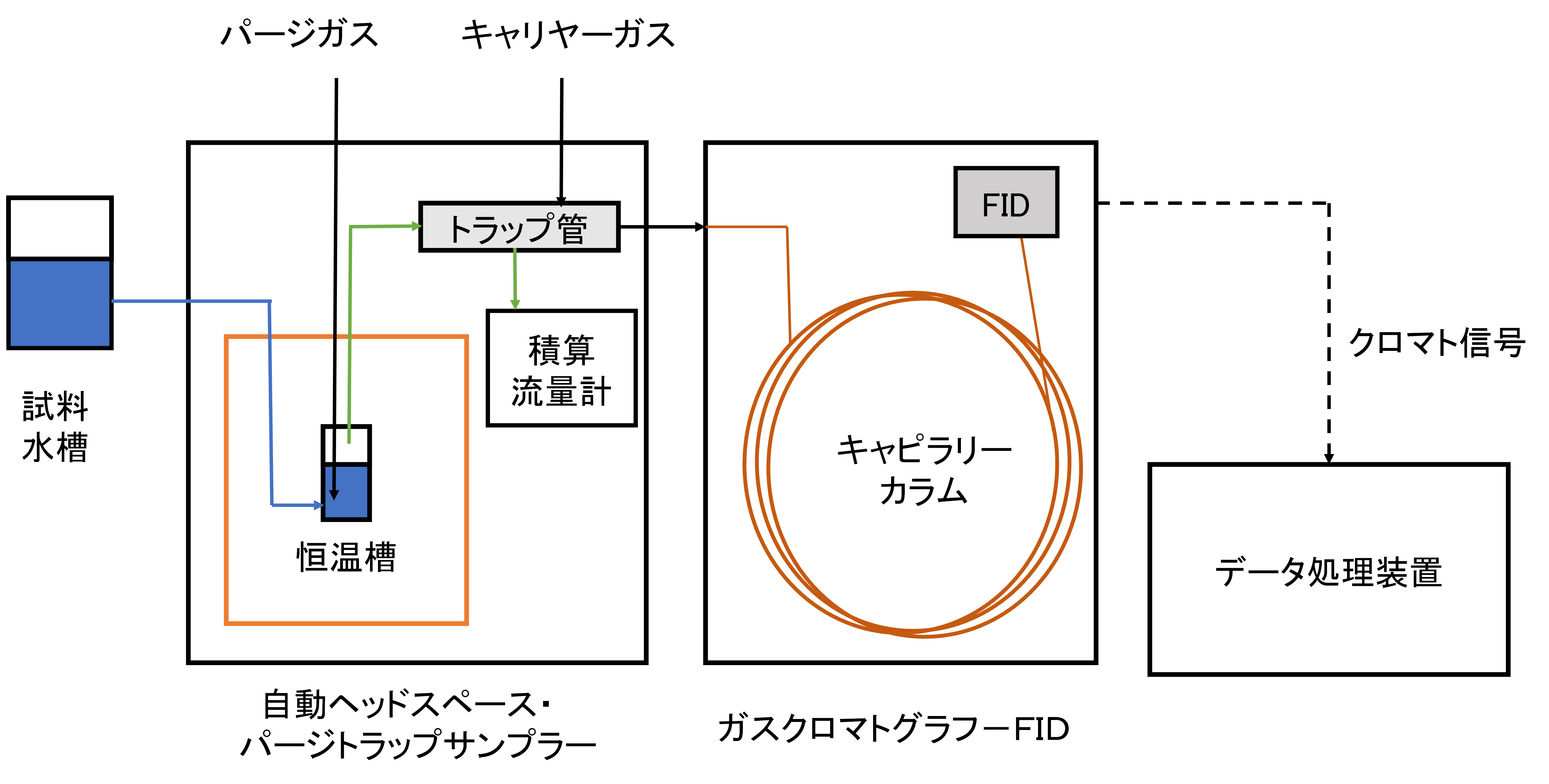
トラップ管には充填剤が充填されており,パージガスは通り抜け,目的のVOC等(共存成分含む)をトラップ管に一旦捕集する。一旦捕集されたVOCはトラップ管をGCのキャリヤガスでパージしながら加温することで,加熱脱離によりGCへと導入される。
測定するVOCの成分により,たとえばメタノールや1,4-ジオキサン等親水性の高い成分は元々HS法では感度が得にくい。そのため,HS・P&T法により感度アップすることでGC-FIDで高感度に測定が可能となる。ベンゼンやトルエン等親油性の成分はHS法で数ppb程度まで測定可能であるが,測定したい濃度領域によりHS・P&T法とすることでさらなる感度UPも可能である。異なる濃度領域(感度)の成分を同時に測定する場合は,FIDのレンジを変更し,2chモードで同時取り込みを行うことで,同時測定が可能となる。
FIDは安定性・および直線性に優れており,本装置では,HS・P&T法という濃縮を伴う分析においても変動係数(CV値)で数%程度以内という再現性を得ることができる。直線性においても優れた性能を有している。(図3)

2.3特長
本装置の特長を以下に記す。
・ガスクロマトグラフ法の採用により多成分の同時測定が可能である。
・水素炎イオン化検出器(FID)の採用により,安定性・耐久性・直線性に優れている。
・月に1度程度の簡易メンテナンス時以外は無人運転が可能な装置である。
・FIDはレンジを変更した2chモードでの同時取り込みが可能で,低濃度および高濃度試料の同時測定が可能である。
・FID-W(FIDを2基搭載する)とし,分析カラムを2系列とすることで,極性等の異なるカラムを接続し,夾雑成分とのさらなる分離やより多くの成分の同時測定を可能とするオプション対応が可能である。
・ヘッドスペース部は透明容器で操作過程が目視確認できる。試料水によるバイアル瓶および系内の汚れ具合などの確認が常時に行え,洗浄・メンテナンスのタイミングが容易に確認できる。
・漏水警報,試料水断警報,キャリヤガス等の圧力異常警報等各種警報を発報することで,装置の異常時には直ちに上位で検知することが可能である。また,測定結果の濃度異常等を複数段階設けるなど種々仕様の個別要望に対応することが可能である。
3.公定法との比較
環境省の定める「水質汚濁防止法」では多種類のVOCが有害物質に指定され,排水基準により許容限度が規制されている。
そこで,1,4-ジオキサンを例に本装置と公定法との測定結果の比較検証を実施した。
「水質汚濁防止法」では,GC/MSによる(1)活性炭抽出-GC/MS法,(2)P&T-GC/MS法,(3)HS-GC/MS法の3つの検定方法が定められている。1,4-ジオキサンの排水基準が0.5mg/Lであることから,今回は0.5mg/Lの試料を用いて活性炭抽出法と本装置との前処理方法の差異による測定結果を比較した。図4に示す手順にて前処理を実施し,本装置はHS・P&T法を用い,1Lのパージトラップによる測定を行った。
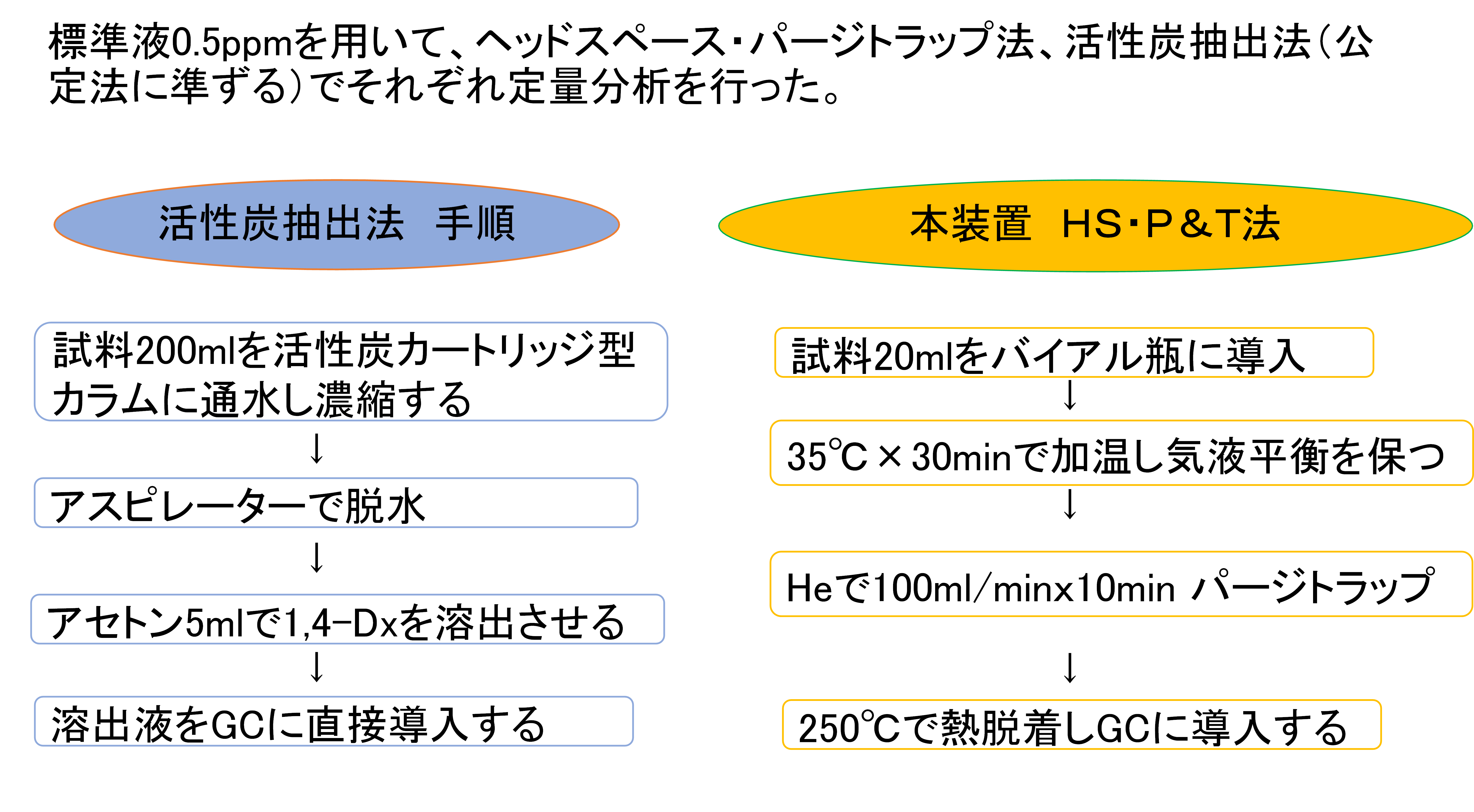
なお,前処理方法の差異による検証のため,測定はGC-FIDにてそれぞれ校正後に測定を行った。その結果,活性炭抽出法が0.547ppm,本装置が0.541ppmとなり,前処理が異なっていても同様の結果が得られた。(図5)
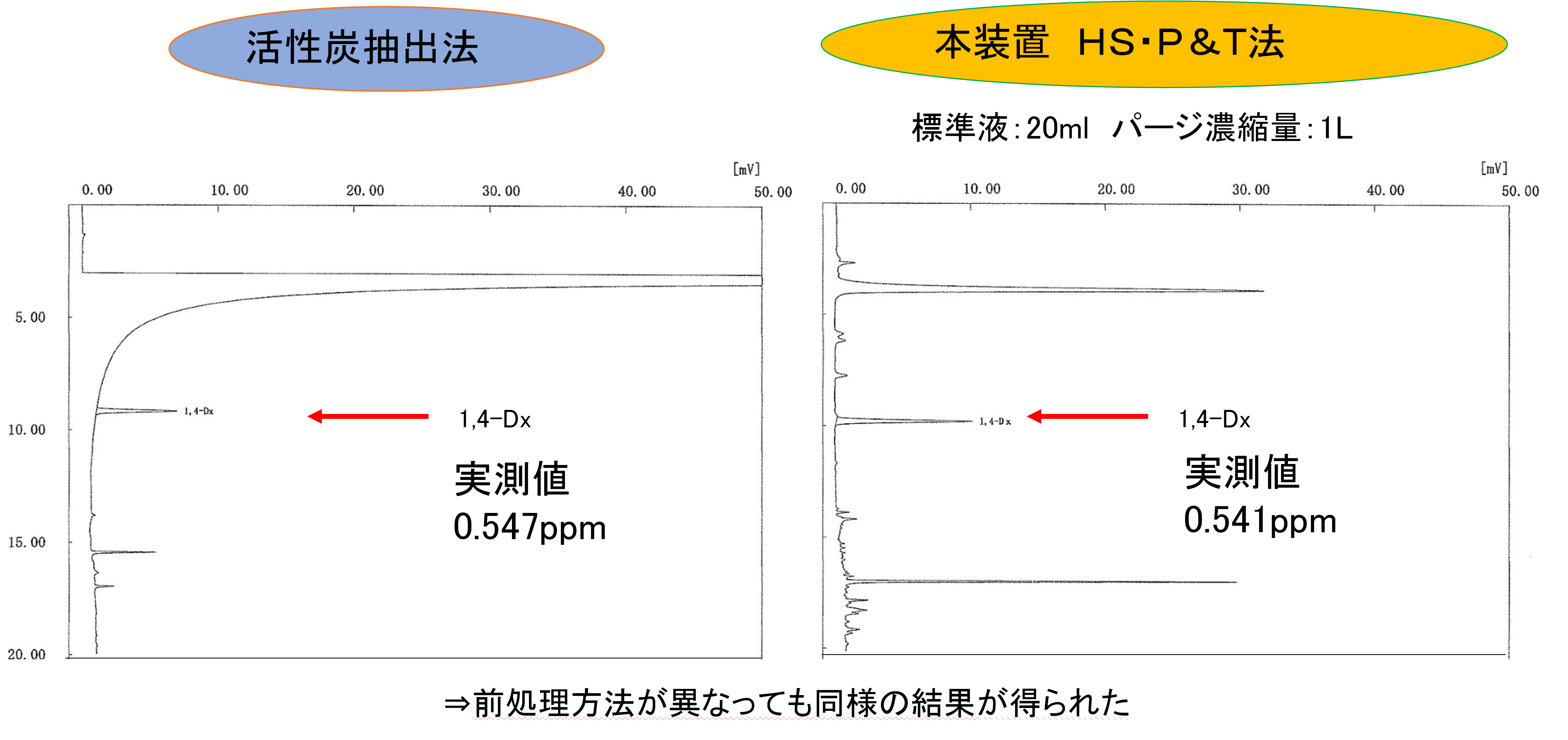
したがって,オンライン分析においては,自動化,耐久性および安定性の観点から,GC-FID法を採用している本装置は極めて有効な手法と言える。
4.納入事例
本装置の多くは工場排水中のVOC濃度のモニタを目的とし,石油化学系のプラント等および化学品,薬品工場等の製造現場を中心に納入されている。使用実例としては濃度管理が最も多く,ある一定のしきい値を超えると警報を発報する仕組みでの使用方法がほとんどである。2段階程度しきい値を設けている実例も多くある。
昨今では最終的な排水の濃度管理のみではなく,プラント等の各設備の直下で測定を行い,設備ごとの排水を管理することで,異常時に原因箇所が工場内で速やかに特定できる機構を構築する工場もあり,1つの工場に複数台の納入実例も増えている。また,プラントごとに測定成分を変更することもでき,プラントの操業状態・異常の有無等を排水の観点からモニタすることも可能である。
さらには別の使用実例として,大型のタンク等に一定量を貯水し,タンクの中の排水濃度を測定することで,しきい値を超えた場合は排水処理を設備のラインへ切換え,しきい値以下であればそのまま排水を行うなどのシステムを組むことが本装置を用いれば可能である。(排水設備は弊社範囲外)
工場排水以外の用途としては,河川水および地下水のモニタ,その他純水や水道水,工場用水等純度の高い水中の極微量のVOCを高感度に測定し,濃度管理を目的とした分野への応用例が挙げられる。
4.今後の課題,まとめ
今後の課題としては,ますます増えると予想される新たな測定成分に対する対応や,多成分の同時測定の要求に対応するため,カラム系統および検出器のデュアル化,さらなる感度アップ等の対応を検討していきたい。
本装置はGC-FID法を採用しているため,夾雑成分との分離確認が必須となる。そのため装置導入前には事前試験が重要であり,試料に対応した条件設定が必要となる。装置導入・稼働後に起こる工場稼働状況や排水処理装置の稼働状況等の変化に伴う夾雑成分の変化に測定成分が影響を受けることも予想される。そうした事象に対応していくことも必要であり,分離試験の追加実施等スムーズな対応策の検討が今後の課題である。
これまで構築してきたデータおよびノウハウを活用し,さらなる発展を遂げることにより,様々な企業等におけるより一層の環境対策の一助となればと考える。