

【製造 DX 実現への視点・論点】
化学工場革新の考え方と DX の役割
1. はじめに
DX(Digital Transformation)はあらゆる産業・分野で取り組まれており,最近では実際の成功例が各メディアで取り上げられることも増えている。弊社の茨城事業所もDX推進に取り組んでおり,初期においては高度なデバイスの採用によるデータの充実,それを支える通信インフラ整備などの基盤整備に注力していたが,現在はこれらの活用によるTransformationの段階に入ってきている。
本稿では,茨城事業所での事例を元に,取り組みを通じてどのように変わっていこうと考えているかをユーザの視点で紹介する。
2.DX実現へ向けた着眼点
化学プラントの操業における不変的な目標は,安全安定操業の維持,生産性向上による競争力強化である。従来は,高度制御の適用範囲の拡大,状態基準保全の適用等による競争力強化やアラームマネジメント,安全計装導入等による安全安定操業維持に努めてきた。そうした本来業務の推進検討はこれからも必要であり,続ける必要がある。
そこにDXという大きな流れが加わり,弊社も模索しながら取り組んでいるというのが実情である。DXの解釈は多様であるが,本質は,“Transformation=変わる”ことであり,デジタル技術はあくまでもそのための道具にすぎない。したがってデジタル技術の導入がゴール地点ではなく,それにより業務に変革を起こし,ビジネス的に顧客・市場の劇的な変化に対応しつつ,競争上の優位性を確立することを目的としている。
茨城事業所においても『化学工場における業務変革』を目指し,アジャイル的にDX推進を進めている。今回の投稿では茨城事業所での取り組みとして,オペレーション事例ではリモートDCS,データレイクの活用を,また設備管理事例ではバルブクラウド診断を紹介する。
3.オペレーション事例(リモートDCS)
図1左図は,現在のオペレーション形態を簡単な絵で示したものである。
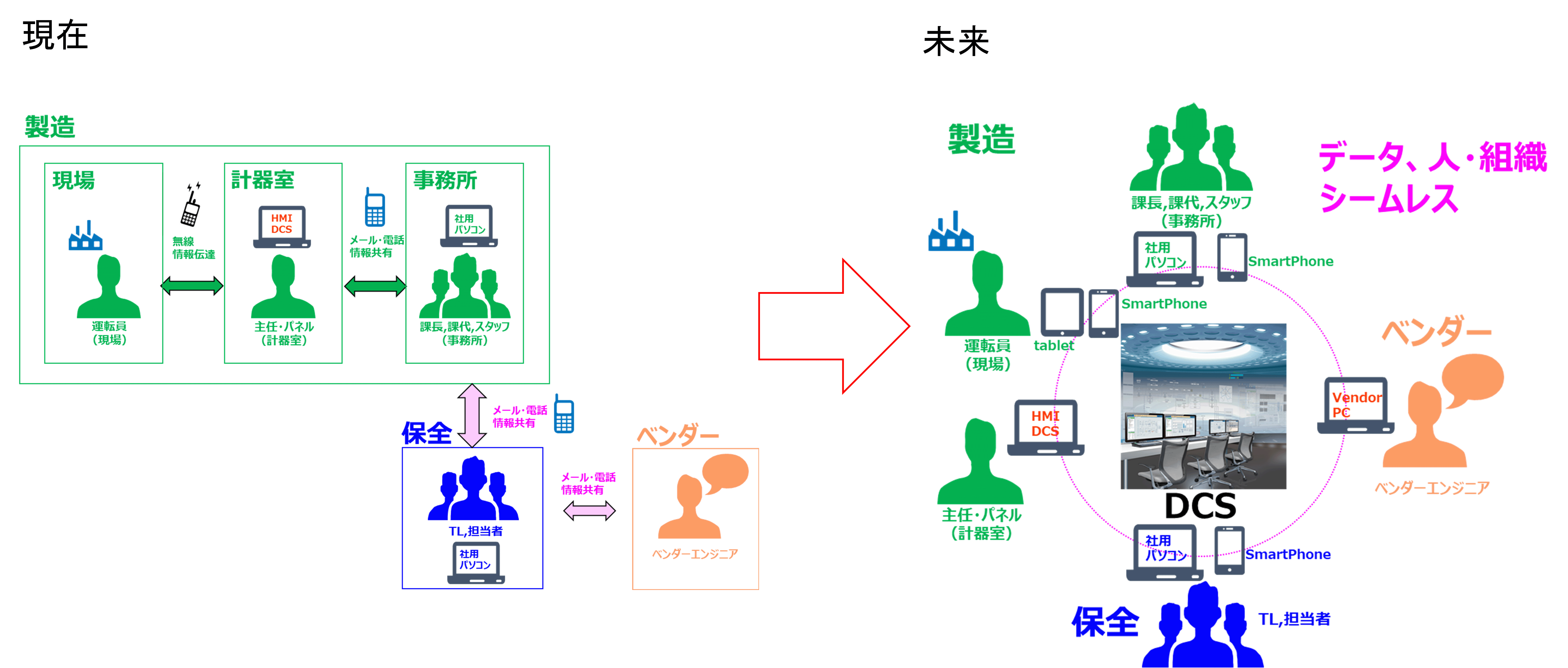
製造課は運転班と事務所で構成され,運転班はパネル(計器室)と現場で業務が分かれる。運転班の現場-パネル間のコミュニケーションツールは無線であり,業務を進めるSOP,指示書などほとんどのものは紙で運用されている。運転班から製造課事務所,関係部署への業務依頼はパソコンで運用する業務ツールに移行しているが,緊急時は電話での音声通話やメールで報告される。一部業務ツールは利用されているものの,根本的な仕事の仕方は30年以上大きく変わっていない。
DCSに関しては,基本的にプラントごとに独立した形で構成されており,統合計器室や課統合もされていない。したがって,コロナ渦の環境においても事業所に出勤するという形のオペレーションを余儀なくされている。こうした現状を踏まえると,将来を見据え,デジタルで働き方を変革する必要があると考えている。
変革のために改善したい点は以下である。
①基盤になるデジタルデータの拡充
②DCS等の製造現場で必要な情報・データのモビリティ向上
③音声に動画を加えたコミュニケーションの質の向上
今回は②についてリモートDCS,③についてデータレイクの事例を紹介する。
リモートDCSは,弊社のイントラネットに繋がっているパソコンやタブレットでDCS画面そのものを通常のHMIのように展開できるものであり,既に茨城事業所内の製造課・関係部署で運用している。これにより現場で作業する運転員もDCSを見ながらオペレーションが可能になる。また製造課のマネジメント層や設備管理部署等の間接部門も遠隔でDCS情報を確認でき,適切な判断やサポートが可能になる。導入により運転班の階層では図2のような変化が生じる。
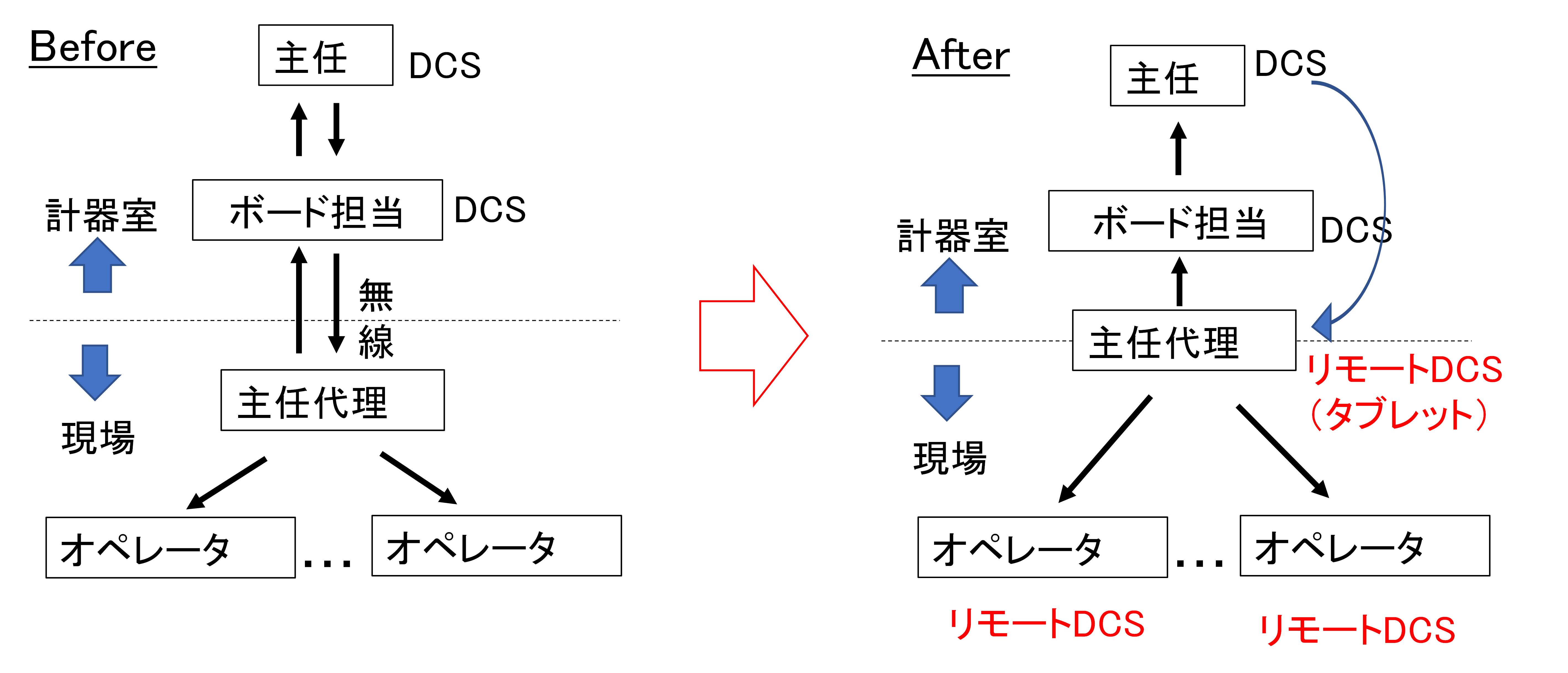
弊社運転員の構成は主任を頂点に,サブリーダとして主任代理,オペレータは現場組とDCSを監視・操作するパネル組(ボードマン)に分かれる。従来DCSは計器室にしかないため,主任代理が現場に行き,音声でボードマンに連絡し,ボードマンが主任と話し,主任からの指示をボードマンが主任代理に伝えながら作業を進める構造になっている。
リモートDCS(この場合はタブレット)を主任代理が持つことにより,主任代理自身がDCSを見ながら現場オペレータやボードマンを指揮する,あるべき姿の指揮系統となり,また同じDCSの情報を見る主任ともダイレクトにコミュニケーションを図ることが可能となる。さらに現場オペレータもDCSを確認しながらオペレーションに参画でき,現状よりも高いレベルの情報共有によるオペレーションが可能になる。
現時点ではリモートDCSによる設備への操作権限を与えていないが,それが可能となればボードマンの位置付けが現状と比べ,変わる可能性があり,新しい運転班の枠組みも模索することが可能になる。
また,現状のオペレーションは物理的な計器室を中心に構成されている。計器室にはHMIがあり,ここにプラント操業の情報が集まり,監視できるからである。今後はオペレーションに必要な情報・データ(DCSや電子化されたSOP等)のモビリティがスマートフォン・タブレット等のデバイス運用により上がり,かつデバイスの動画機能を用いた質の高いコミュニケーションが可能になる。近い将来には図1右図のように計器室はバーチャル化され,シームレスでリアルタイム性の高いオペレーションが可能となる。物理的な計器室に対応する形で構成された各組織の体制も現在と違う形に変化し,働き方や役割も変化していくと考えている。
ただし,深く考慮が必要なのは,そこに移行するまでの安全管理である。セキュリティ面はもちろんのこと,組織・人の変化に対する施策を十分に考える必要がある。
4.オペレーション事例(データレイク活用)
事業所には各プラントのDCSから得られるプロセスデータやHART(Highway Addressable Remote Transducer)/FF(Foundation Fieldbus)プロトコルを有したスマートセンサから得られる設備データ等の時系列数値データだけでなく,紙媒体のデータや画像・動画データなどほかにも多くのデータが存在している。DCSだけでなく,こうした事業所に存在する様々なデータを集めて,オペレーションや設備管理の変革に有効活用する必要がある。
現在,スモールスタートながらこうした構造化データや非構造化データを格納できるデータレイクサーバを設置した。収集したデータの種類や用途を考えると,「OT(Operation Technology)系のデータレイクサーバ」のような位置づけとなる(図3)。
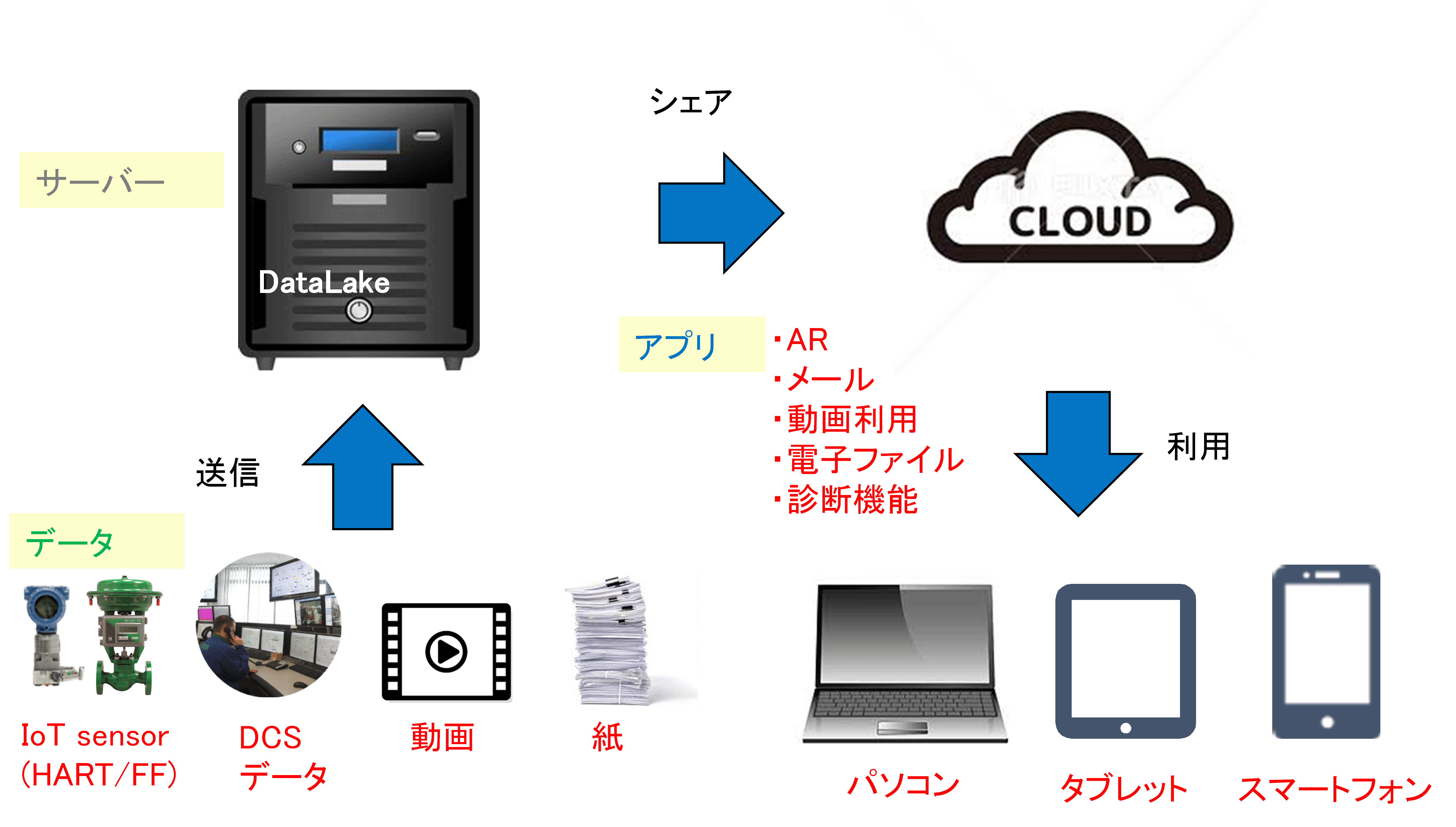
現在取り組んでいる使用用途は以下である。
・データのモバイルデバイス活用によるモビリティ向上
・異種のデータを用いた解析,AI検討
今回は前者のモバイルデバイスを用いたモビリティ向上について紹介する。
この事例では,データレイクに集まったデータをコンテキスト化して,スマートフォンを用いて製造現場で活用する事例を紹介している。今回のケースでは,HART等のIoTセンサのデータ利用と紙であったSOP情報のアプリ化活用をデータレイクサーバに繋がるモバイルデバイスで運用している事例となる。
具体的には現地で作業する際に以下の取り組みを試行している(図4)。
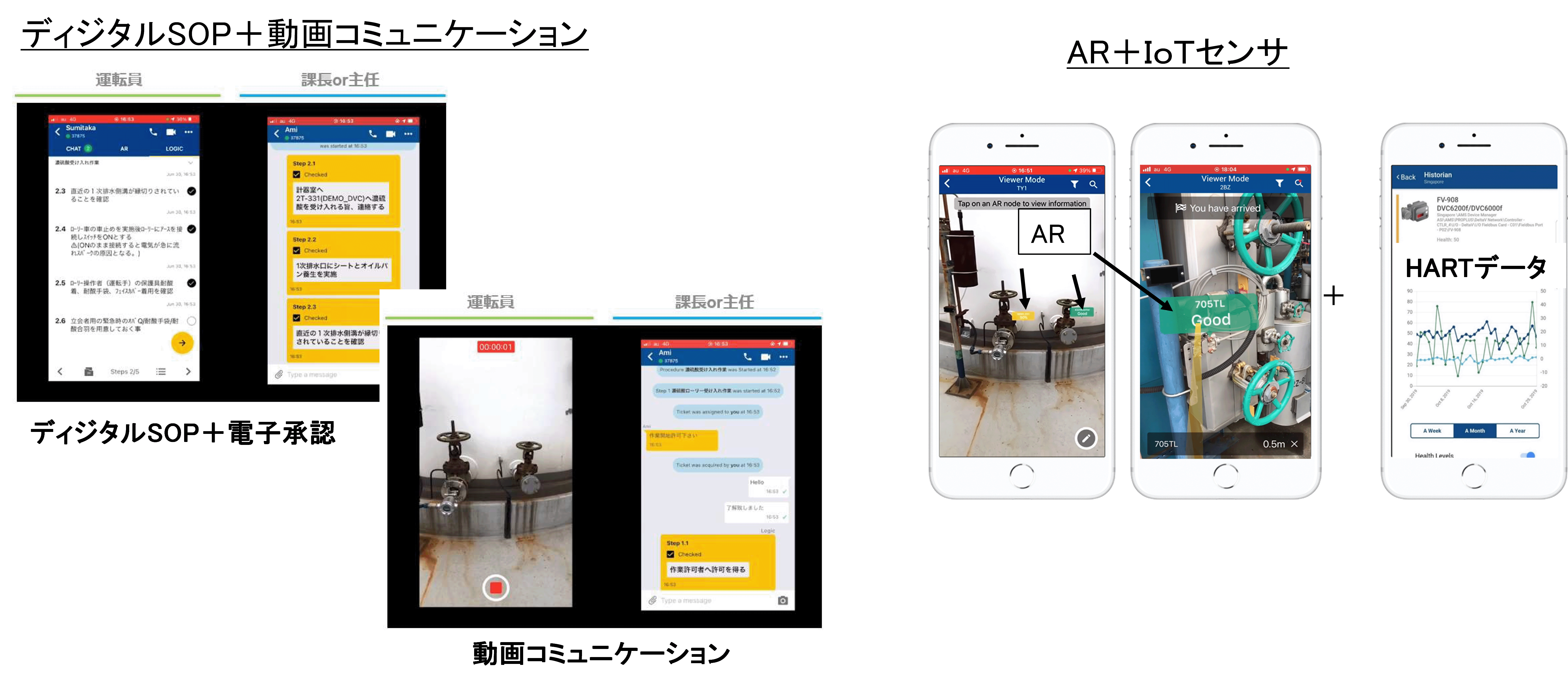
・周辺計器の状態を確認するために,計器HARTデータをARで表示させて現地で確認
・紙のSOPをアプリ化したものをスマートフォン上で運用
・SOPで管理者の承認が必要であれば,スマートフォンのアプリで呼び出し遠隔電子承認(必要に応じ現地状況を内蔵カメラにより動画形式で伝達)
従来は紙を持ち運びしてSOPの内容を確認し,承認者を探して押印をもらいながら作業を進めていた。現在は紙の運用をなくし,押印に伴う作業者と承認者の物理的な距離,移動をなくし,効率化している。また情報共有の側面でも問題は生じておらず,多様な意味で働き方に変化が起きている。
前述のリモートDCSも同じ狙いを持っているが,スマートフォンやタブレット等のモバイルデバイス利用により,現場に必要なデータのモビリティと動画通話・チャット利用によるコミュニケーションの質の向上を図っている。
いつでもどこでも誰とでも必要な情報の利用・共有化を可能にし,働き方や役割を変えることによる変革を目指している。
5.設備管理の事例(バルブクラウド診断)
オペレーション同様,設備管理についても仕事のやり方,役割,働き方,価値観の変革を目指している。本投稿ではバルブクラウド診断を例に,取り組み,狙いを紹介する。
茨城事業所では2001年頃より,HART,FFプロトコル機器の導入を進めてきた。HART/FFのデジタル信号には,機器のパフォーマンスを示す情報や設定パラメータ等の機器情報が含まれ,診断やコミッショニング等に活用してきた。機器情報はアセットシステムに収集されて,このシステムを起点として様々な保全活動を実施することになる。
しかし,アセットシステムから詳しい情報を得るには対象となるデータを抽出して分析する必要があり,相応のスキルが必要になる。同事業所のエンジニアの中でもアセットシステムのエンジニアリングやデータ解析を得意としないメンバもおり,データや各人の経験を活かしきれていない実情があった。
また,バルブのメンテナンスは,基本的にTBMがベースとなっているが,その確度については改善の余地がある。TBMでは一般的に8~12年周期が多いが,この手法で得られるデータは周期到達時に実施するオーバホールのデータが主であり,運転中のバルブに関するデータの入手は難しい。
最適なメンテナンス周期を設定するにあたり,限られた情報では限界があり,運転中のバルブ情報による劣化把握が必要になる。エンジニアとしてはデータさえあれば適正周期の見極めができるという想いがあり,ポジショナからの運転中のデータを活用することでバルブの不調やその予兆をいち早く捉え,メンテナンスの最適化を実現できると考えてきた。
この2つの課題を解決するために,バルブデータをクラウドに上げてデータを簡単に見える形にし,そのデータを有効活用できるエンジニアに渡すスキームを構築した。こうした取り組みにより,データドリブンな設備管理という方向に仕事のやり方,役割を変え,以前より取り組んできたHART/FFデータの活用を加速している。(図5)
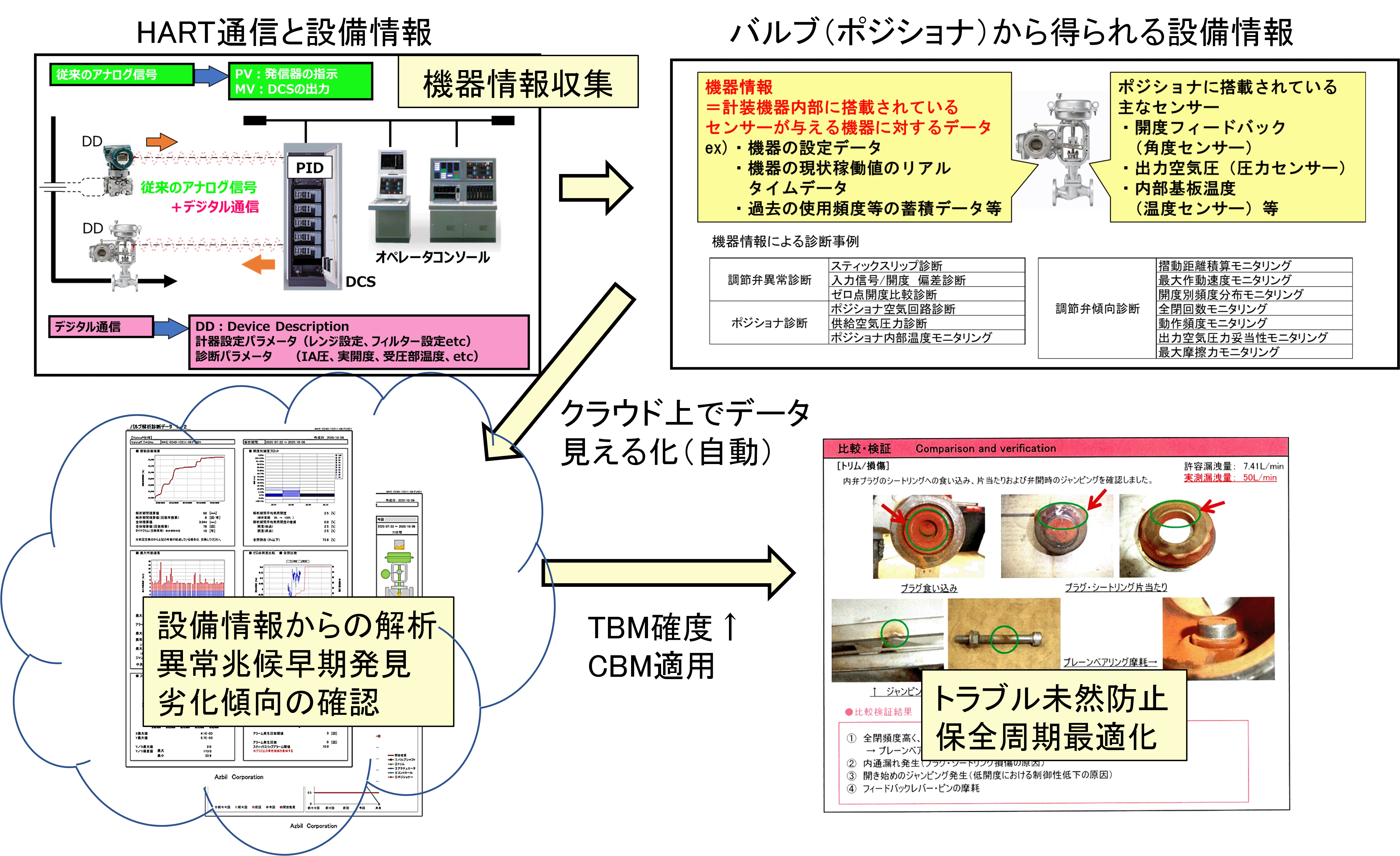
6.最後に
DXを通じた『化学工場における業務変革』の実現には,
・データを含めたデジタルの基盤整備
・データのモビリティの加速
・データドリブンな業務への移行
が鍵になると考えている。
今回紹介したデジタル化の取り組みを通じ,従来の仕事の仕方,仕組みそのものを変え,また価値観を変え,最終的には人の思考そのものを変えながら,新たな働き方・多様な働き方を追求していきたい。