

【製造 DX 実現への視点・論点】
DXによる運転と保全の情報連携
1.はじめに
DCSなどの基本制御システムは,安全安定操業を維持する上で重要な役割を担っている。また,上位計算機には最適化制御,ヒストリアン,ビッグデータ分析,ビューワーなどが導入され,それらも同様に運転の最適化や情報の見える化で重要な役割を担っている。
一方,保全分野では,保全作業に必要な処置起案,工事発注,予算管理,そのフォローを行うシステムや,過去の保全履歴や配管・機器の寿命推定などを行うシステムが導入され,こちらも安全安定操業を維持する上で重要な役割を担っている。
しかしながら,運転部門と保全部門は組織的にも別であるし,使用するシステムも異なり,業務サイクルや保全課題に対する関わり方も異なる。装置トラブルの原因追及や対策立案、定期補修のような装置の長期的保全課題を解決するには,運転部門と保全部門が持つ情報を密に連携し,それを装置保全に活かしていくことが重要である。
運転部門は日々の運転状態から得られるリアルタイムな情報を持ち,保全部門は過去の検査・保全履歴から得られる長期的な損傷情報を持っている。これらの情報を有機的に連携させることは,我々の目指す装置の信頼性向上に大きく寄与すると確信している。
今後,電気自動車などのカーボンニュートラルへの取り組みがより加速し,石油需要が低迷していく中,装置の信頼性を向上することは,我々石油化学業界の喫緊の課題であり,この運転部門と保全部門が持っている情報連携のすき間にまだ改善の余地があると考える。(図1)
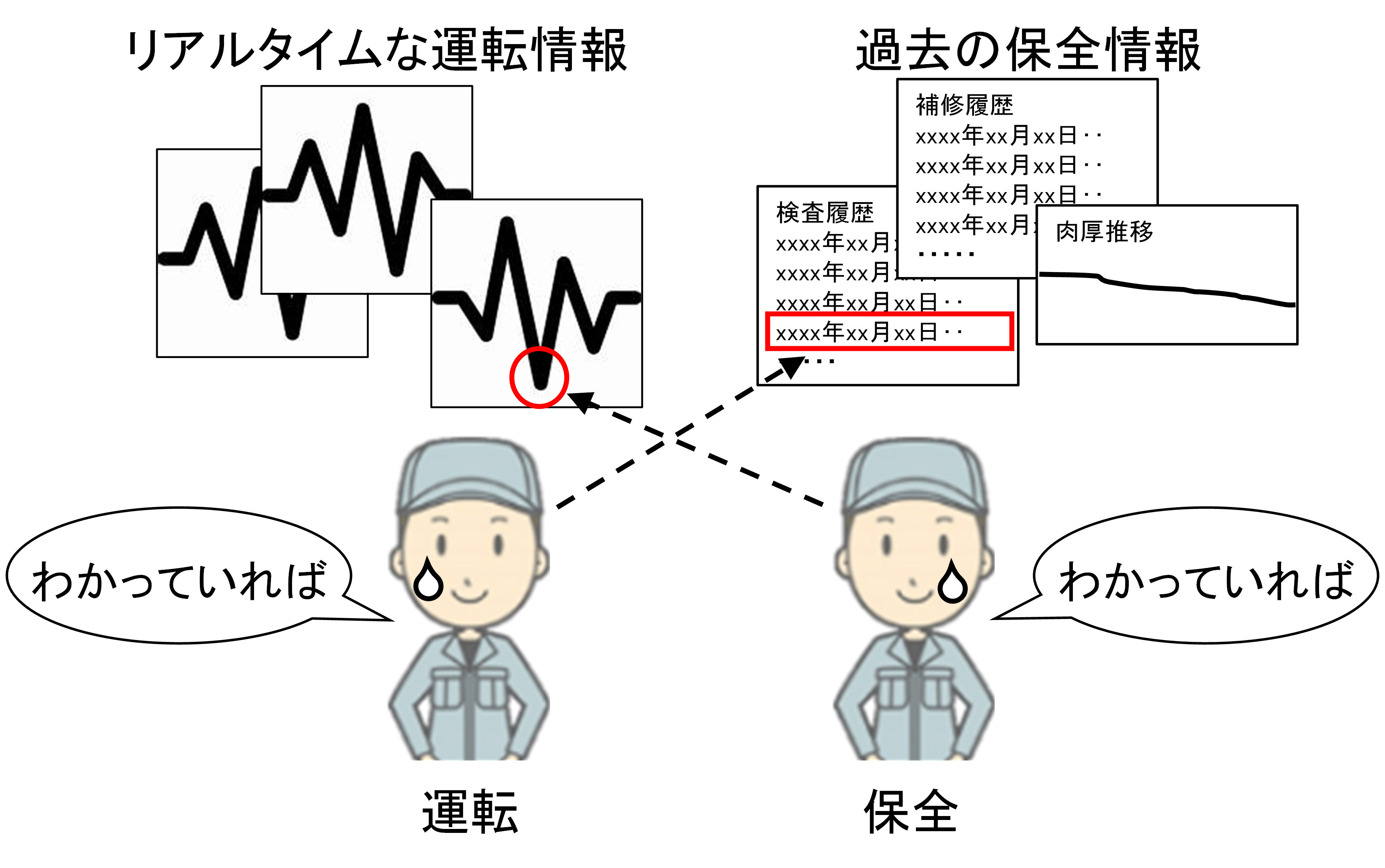
本稿では,DXとして取り組む中で見えてきた運転と保全の情報連携の改善について紹介する。
2.運転部門で見えた課題
運転部門は,主に制御システムを使った運転操作,機器の日常点検業務,運転データ管理などを行っている。日常点検業務としては,各直各担当が点検手順をもとに,そのデータを記録・保管する。運転データ管理では,定期的にヒストリアンからデータを収集整理し,装置ごとに管理すべき項目を一覧化して,分析・評価した内容を課内共有,必要に応じて関係部署に報告する。
DX化に先立ち,これらの作業を細かく分析した。
なお,運転操作に関しては従来から行われている自動化制御やアラームマネジメントの改善,日常点検は既に流通しているアプリケーションやIoTなどの導入による対応が可能で,障壁がないとは言えないが,解決するための道筋が見えているため,ここでは深掘りしない。
結果,データ収集整理と課内・関係部署との情報共有については,道具はそろっているものの,その作業自体にとても負荷がかかり,情報連携のボトルネックになっていることが判明した。ヒストリアンや見える化するビューワーは用意されているが,データを見える化するためのビューワーは,全社共通のユーザに対応したもので,特定の組織・ユーザのためのシステムではない。そのため,各ユーザが臨機応変に,自分の見たい・表現したい・他から要求された内容にしようと思っても即時に対応できないため,結局すべて自分で表現したいグラフや表を自作しているからと推測する。(図2)
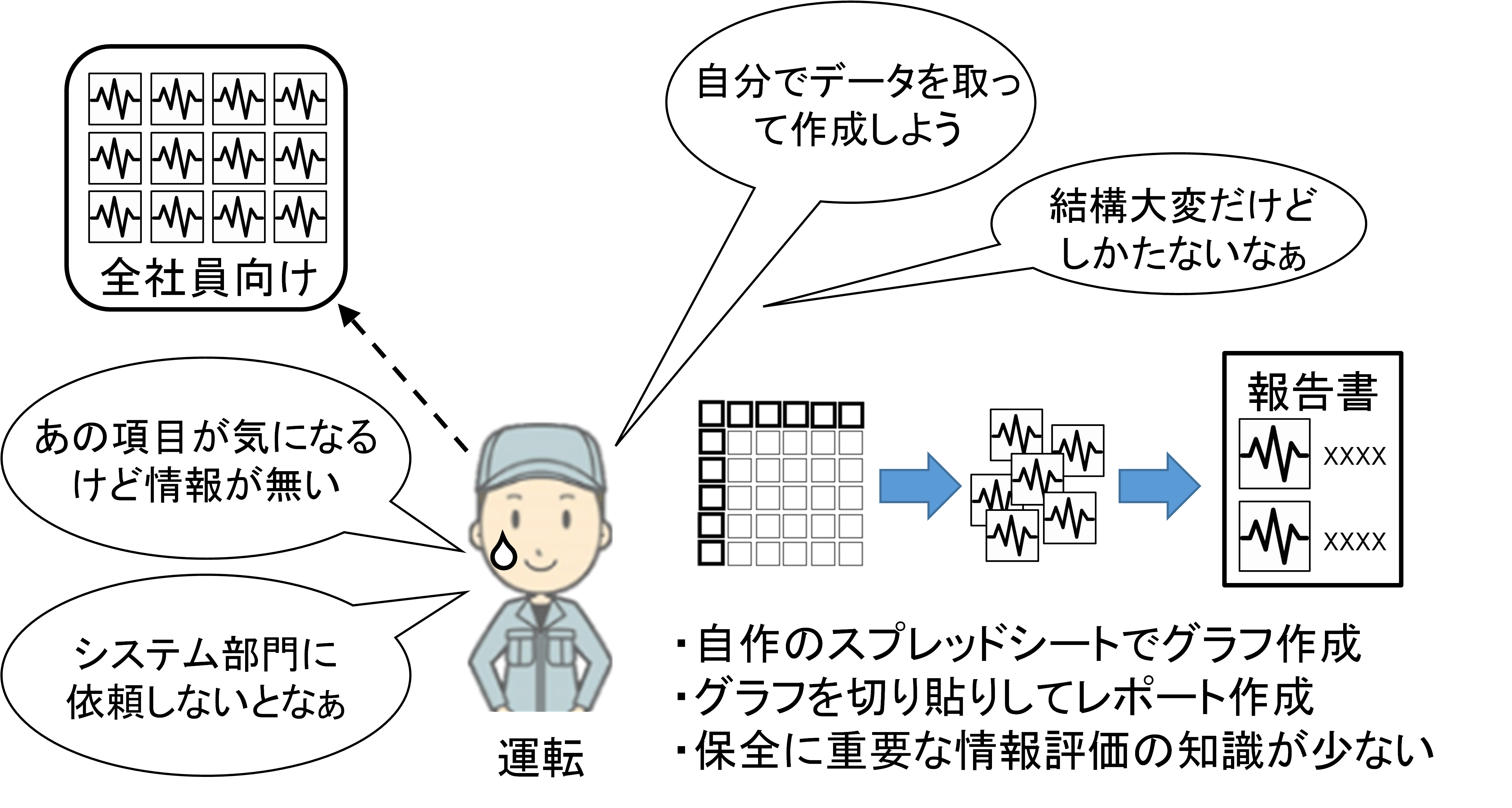
自作するということは,数百件の測定データを手動でヒストリアンから集め,それをグラフ化するためにデータを切り貼りし,見栄えの良いフォーマットにして報告資料に張り付ける。現場点検や日常課題の解決を並行して行う運転部門の担当は,この作業自体に時間を取られ,目的であるデータ評価に充分な時間をかけることが難しい。逆に言えば,この効率化が実現できればより質の高い検討が可能となると考える。
3.保全部門で見えた課題
保全部門は,装置・機器の検査・保全業務,また設備管理システムを使った保全計画,寿命評価,コスト管理,保全評価などを行っている。検査・保全業務としては,各担当が検査計画をもとに,装置・機器を外部作業員とともに検査し,その結果を評価・記録し,必要であれば補修依頼を行う。
安全安定操業を満たした上での保全コスト最適化を考えた場合,運転条件から損傷を受けている機器を的確にとらえ,補修が必要な機器のみ補修すること,過去の補修履歴,損傷要因から運転条件にさかのぼり,機器が損傷を受けないような運転条件・あるいは材質に見直すことが理想である。
そのためには,保全部門が運転状態を把握して保全計画を立てること,損傷回避策を運転部門にフィードバックすることがとても重要である。しかしながら,日々の機器損傷によるトラブル対応や定期補修工事の膨大な計画作業を行う中,保全部門が運転データを自ら収集分析して対応を取ることは容易ではなく,運転部門によるデータ評価情報に頼りがちになるのが実情である。(図3)
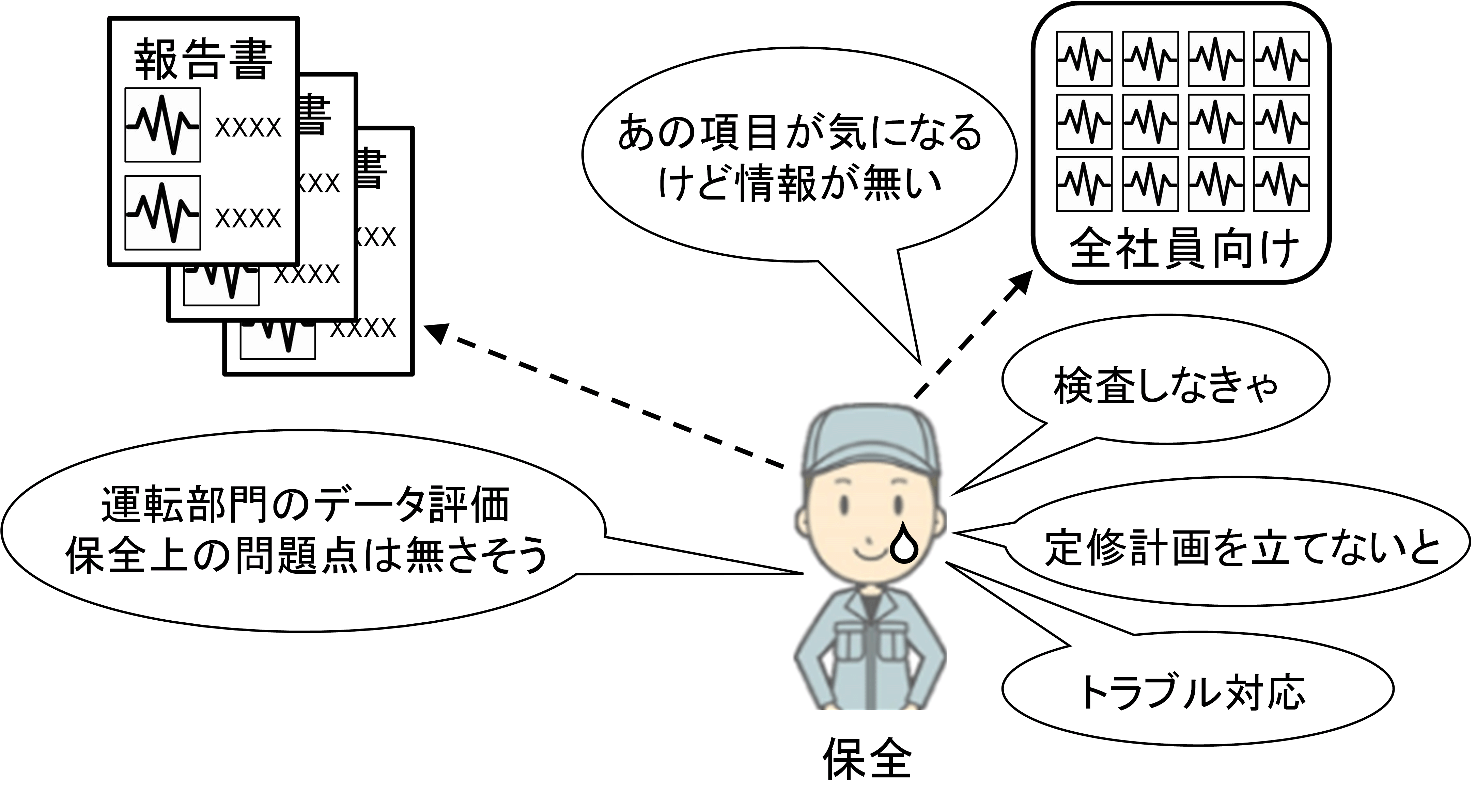
前述したように,運転部門によるデータ評価はとても負荷のかかる作業となっており,かつ保全部門が気にしている情報を運転部門がすべて把握しているわけでもないため,データ評価情報はあるものの,保全部門に必要な評価情報が強調されずに流れることもある。保全部門からすると「もっと早く状況を知っていれば・・・」ということにもなるだろう。
4.DXへの取り組み
運転部門が持っているリアルタイムな運転情報と,保全部門が持っている過去の検査・保全履歴情報の連携改善のため,まずは運転部門でボトルネックとなっている,データ収集・情報共有作業の負荷軽減に取り組んだ。ただし,それは既にあるデータの自動取得やビューワーシステムの充実ではなく,そもそもその作業を各担当がやらなくてはならなくなった根本原因の解決を主眼に置き,各ユーザが臨機応変に,自分の見たい・表現したい・他から要求された内容に即時カスタマイズできるシステムの開発・導入を行った。
また,保全部門から運転部門への情報連携として,過去の検査・保全履歴情報を,運転部門でも容易に確認できるよう,設備管理システムとの連携も行った。
5.ユーザがカスタマイズできるシステム
市販のアプリケーションには,このタイトルを謳うものは多い。ただし,ここでいうユーザとはお客様という意味で,自社内の誰でもカスタマイズできるという意味ではない。仮にできるとしても,その設定には特別な知識を必要とするため,誰でもできるというものではない。
また,全社員向けに導入されたアプリケーションの主管は情報システム部門で,維持管理とともに知識が必要な設定作業も同部門が担っているため,ユーザが変更したい場合は情報システム部門に仕様と変更依頼を行う流れとなり,ユーザが必要としている臨機応変な要求には対応しきれない。
そこで,情報システム部門に依頼しなくても,ユーザ自身が臨機応変にカスタマイズできるデータ取得・ビューワーシステムを構築した。(図4)
以下が開発導入したシステムの主な機能である。
①表示内容は各ユーザが特別な知識なしに設定可能な機能
②装置・機器ごとに異なる定修期間を設定し,稼働期間のトレンドを重ね合わせ表示する機能
③グラフ軸をデータ範囲から自動初期設定し,ユーザ調整なしにトレンドを見やすく表示する機能
④ヒストリデータを使ったユーザ計算値を汎用スプレッドシートで設定する機能
⑤各監視項目に評価欄を設け,運転・保全部門が定期・恒久的なコメントを保存できる機能
⑥電子レポート機能
⑦検査・保全履歴・損傷要因情報を該当する機器の運転情報と連携表示させる機能
6.開発の進め方
2021年5月から本課題に取り組み,リーダである社員と,運転・保全ユーザ,アプリケーション開発者,システムインフラ担当者でタッグを組んで,優先度の高い機能からリリースするアジャイル開発という手法を適用した。
当初はエクセルやパワーポイント上に表現した紙芝居をもとに開発者と方針をすり合わせ,ゼロから育て上げた。開発者が業務内容・改善目的を知った上で開発に取り組むことが重要と考え,単なる仕様提供だけでなく,開発者に現状の課題となぜそれをするのかについて議論を尽くし,チーム全員が納得した形で進めた。その結果,仕様には書かれていない,開発者側からの提案も反映した良いシステムに仕上げることが可能となった。
7.導入状況
2021年12月現在,代表的な装置を対象に運用を開始し,ほぼ要求を満たした機能が仕上がったため,事業所内の全装置に展開しようとしているところである。
今まで情報システム部門に依頼しないとできなかった,管理表の最新化や項目の追加変更などを全て運転部門のユーザが設定できるようになった。
また,手動で作成していたグラフやレポートも自動で作成され,運転部門は手間のかかる作業なしに,目的であるデータ評価から着手,最初から目的に注力できる。さらに,システム化することによって,今まで要領書に書かれていた管理値の形骸化や,管理不要な項目があることも見え,当初想定していなかった改善にもつながりつつある。
保全部門は,運転部門が定期的に用意する報告書が回覧される前に,気になる項目の状況をリアルタイムに見られるようになった。今後の保全計画にその効果が発揮されるであろう。
8.おわりに
今回紹介した取り組みは,IoTやビッグデータ解析,ドローン,統合データベースのような新たな機器・アプリケーションパッケージを導入するのではなく,道具はあるけど上手に使いこなせていない課題に対する解決事例を紹介した。
近年,新たな機器やシステムが盛んに登場し,それを使って何かをしようというDX事例も多いが,それはユーザ視点というより,導入側の視点であり,その解決策が必ずしもユーザにとって良い答えとは限らない。
身の周りであたり前のように行われているちょっとした作業の改善に焦点を当て,効果を上げることで,利用者がやる気をだし,さらなる改善につなげ,最終的に業務そのものを見直すことがDXの本質であると考える。