

【最新動向】
IO-Linkの最新動向 -相互運用とデータ活用を容易に実現
1.はじめに
インダストリ4.0の提唱は製造現場へのIoTの導入とデジタルトランスフォーメーションを促進し,スマートファクトリの実現を目標とした新技術の開発,採用を加速させている。
インダストリ4.0では,”相互運用”と”データ活用”が構成要素である。IO-Linkはこれら構成要素を実現するために導入可能なデジタル通信技術である。
2.IO-Linkの特長と技術概要
IO-LinkはIEC61131-9準拠のセンサ,アクチュエータ用デジタル通信技術である。産業用Ethernet,フィールドバス上のリモートIOターミナルから接続されるセンサ,アクチュエータのネットワーク接続が可能である。接続機器情報と生成データの見える化を新規,既存設備に対し迅速に実現できる。
IO-Linkでは多くの場合産業用Ethernet,フィールドバス上のリモートIOターミナルがマスタとなり,リモートIOターミナルから接続されるセンサ,アクチュエータがデバイスとなる。リモートIOターミナルの各ポートのマスタと接続されるデバイス間の1対1通信である。
既存の3芯または5芯のセンサケーブルを使用でき,コネクタは主にM12防水コネクタを使用する。配線,コンポーネンツで既存のデジタルIOシステムを踏襲できる構成である。
2.1 簡単な配線
マスタとデバイス間のケーブルの配線は,一般的にセンサを接続する場合は4番ピンを通信に,1番と3番ピンを電源に使用する。通信の4番ピンはIO-Link通信(IO-Linkモード)のほか,従来の接点入力モードとしても使用できる。2番と5番ピンは未使用または5番ピンにアナログ信号を接続できる。この配線をClass Aと定義している。
モータコントローラのような追加電源が必要な機器を接続する場合は,追加絶縁電源用に2番ピンと5番ピンを使用できる。この配線をClass Bと定義している。(図1)
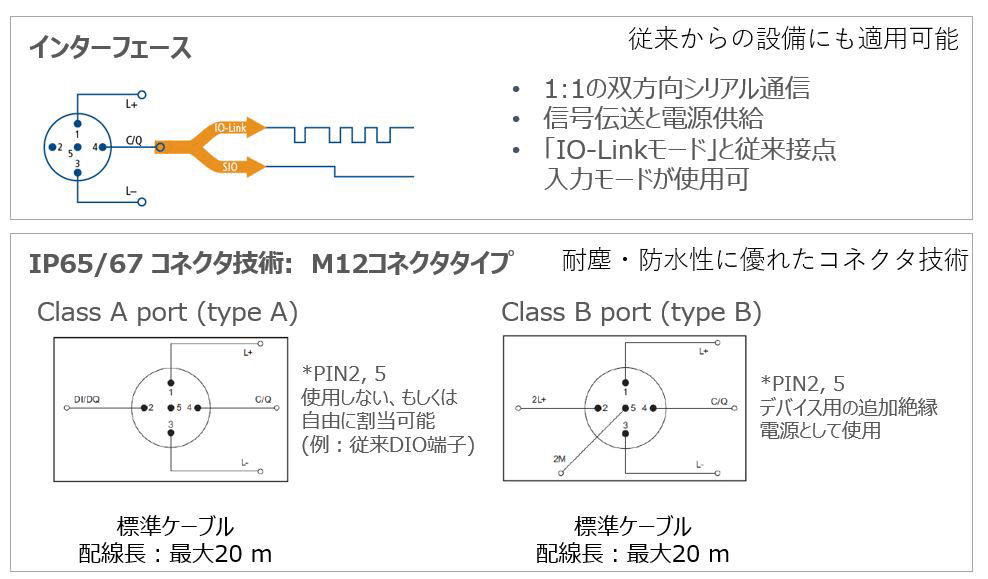
2.2 通信特性
通信特性は,20mの伝送距離で最大32バイトのプロセスデータを送受信できる。
ボーレートはCOM1からCOM3まで定義されており,COM1で4.8kbps,COM2で38.4kbps,COM3で230kbpsが選択可能である。COM2では2msecで交換できる。IO-Linkデバイスは定義された1つのボーレートを選択する。IO-Linkマスタは,IO-Linkデバイスの設定ボーレートを自動認識する。
2.3 簡単な設定
送受信されるデータタイプは,最大32バイトのプロセスデータのほか,接続デバイスのパラメータとなるデバイスデータ,入力データの有効,無効を判定するステータスデータ,デバイス故障,断線等を通知するイベントデータが定義されている。
IO-Linkのデータサイズ,データタイプの選択と設定は,電子記述ファイルと主にPCから操作するエンジニアリングツールから実行する。IO-Linkの導入は既存装置の大幅な変更が不要である。また設定,操作も最小限で導入が可能である。
3.IO-Link導入のメリット
3.1 最小限の導入コスト
IO-Linkの通信は,マイコンとトランシーバで構成される搭載機器のプラットフォーム上に,通信プロトコルのミドルウエアを実装することで実現できる。ミドルウェアには搭載機器のベンダ,デバイスIDが組込まれ,IO-Linkマスタとデバイスのスタートアップ時にこれらID情報も通信されるので接続機器,ベンダ名が常に識別可能である。
機器メーカでのIO-Link対応機器の開発は,低価格のマイコンとミドルウエアで実現できる。コネクタとケーブルも既存のものが使用できるので,製品価格への影響も最小限に抑えられる。ネットワーク対応時に直面することが多い導入コストの問題も解決できる。
3.2 センサ,アクチュエータの見える化
IO-Linkの導入により,製造現場に設置,稼動している膨大な数のセンサ,アクチュエータの機器情報と生成データを識別データとして収集,活用できる。そのほか,ステータスデータでの通信異常の判定,イベントデータでの機器の故障通知にも対応しているので不具合時の迅速な対応も実現できる。
IO-Link接続デバイスはエンジニアリングツールによるネットワーク設定が必要である。多くの場合,接続デバイスのID情報は機器ごとにベンダが用意する電子記述ファイルであるIODDファイルに含まれる。マスタは接続デバイスのIODDファイルをエンジニアリングツールに登録し,データサイズ,タイプを設定し通信を開始する。
IO-LinkではIODDファイルのデータベースとして,インターネット上にIODDファインダを用意している。世界中のIO-LinkデバイスのIODDファイルが登録されており,ユーザはエンジニアリングツールからアクセスし必要なIODDファイルをダウンロードして設定ができる。
IO-Linkのオープンな共通インタフェースは,異なるベンダのデバイス接続と交換を簡単なエンジニアリング作業で実現する。
3.3 上位ネットワークとの統合
IO-Linkは世界中の現場で採用され稼動しているCC-Link IE,EtherCAT,EtherNet/IP,PROFINET等の主要な産業用Ethernetの下位の位置付けである。産業用Ethernet上のリモートIOターミナルの各入出力ポートに共通インタフェースとしてIO-Linkマスタ機能を搭載,そこから接続されるセンサ,アクチュエータにIO-Linkデバイス機能を搭載する。
リモートIOターミナルは,産業用EthernetとIO-Link通信とのゲートウェイとして機能する。IO-Linkの採用によりリモートIOターミナルから先のセンサ,アクチュエータの見える化が可能である。膨大なセンシングデータを産業用Ethernet経由で上位,クラウドレベルまで識別可能なデータとして送信できる。(図2)
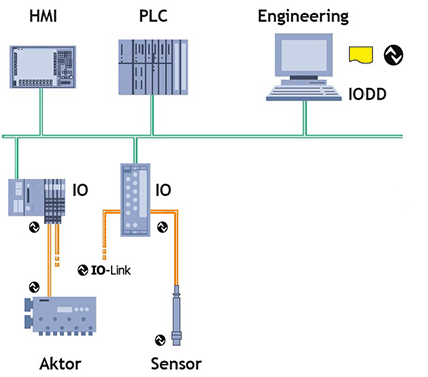
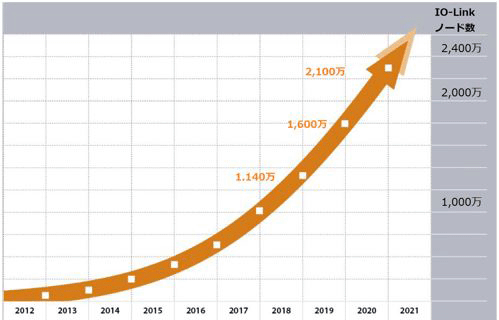
IO-Linkは機能拡張も続き
,安全通信IO-Link Safetyと無線通信IO-Link Wirelessの対応機器も2021年中にリリースされる予定である。4.1 IO-Link Safety I
O-Linkに機能安全IEC61784を付加した技術である。IO-Link対応機器のプラットフォーム上にIO-Link Safetyのミドルウエアを統合する。産機能安全対応で採用されているブラックチャンネル方式を採用しており,マスタ,デバイス間の通信はIO-Linkの通信技術を使う。製造現場には安全センサ,ライトカーテン,緊急停止ボタン等,多くの安全機器が設置されているが,これら安全機器は機種ごと,ベンダごとに異なる安全規格で接続されるので,安全コントローラ,安全IOターミナルは接続安全機器ごとにユニット追加が必要である。
安全IOターミナル,安全機器がIO-Link Safetyに対応すれば,安全機器間での共通プロトコルとなる。機器ベンダは複数の安全通信規格の対応が不要となり,安全
コントローラ,安全IOターミナルのユニットも削減が可能である。IO-Linkと同様にIO-Link Safetyマスタは,産業用Ethernetの機能安全ネットワークとのゲートウェイとなるので,製造現場の安全機器の見える化と安全データの活用を実現する。
4.2 IO-Link Wireless
IO-LinkにIEEE802.5準拠エアーインタフェースを付加した無線技術である。製造現場の監視,可動デバイス等,無線接続が要求される機器のIO-L-LinkにIEEE8ink通信を実現する。
エラーパケットレート(PER)10e-9での安定性に周波数/時間分割メディアアクセススキーム(F/TDMA)を採用し,2.45GHzの帯域で5msecのデバイス間通信が可能である。
IO-Link Wirelessマスタのエアーインタフェースでは,1つのセルで3つのマスタに対応する。各マスタは5つのトラックで各8台のIO-Link Wirelessデバイスとの接続が可能である。1つのIO-Link Wirelessマスタは40台までのIO-Link Wirelessデバイスとの通信が可能である。有線のIO-Linkとの統合も実現する。今後増加してくるワイヤレス機器をIO-Link通信によ IO-LinkはすでにIEC規格となって
5.IO-Link コミュニティジャパン
I 主に定期セミナの開催と展示会への出展を行っており,IO-Linkとメンバ会社のIO-Link対応製品,開発ソリューションを紹介している。 <定期セミナ> ・「IO-Link紹介セミナ」では,IO-Linkの概要,最新技術,メンバ会社のIO-Link対応製品,アプリケーション事例の紹介を午前中に行う。 ・「IO-Link開発セミナ」では,IO-Linkの開発手段,認証,メンバ会社の開発ソリュー 両セミナともに現在はオンラインで年2回程度の開催である。
・「IO-Link体験セミナ」は,早稲田大学理工学部施設での定員制セミナである。IO-Link対応実機を使用し,実際に設定し通信確認ができる。開催日の午前中に行う。
・「IO-Link技術セミナ」は,IO-Linkの通信プロトコル説明を体験セミナ開催日の午後に行う。 <展示会> 「IIFES」,「スマート工場展」等に出展し,IO-Linkの技術概要とメンバ会社のIO-Link対応製品を紹介し動作デモ機を展示する。 IO-Link Community(ドイツ)とも定期的なミーティングで連携し,最新情報を確認している。会員は常時募集中である。
6.最後に
IO-Linkはインダストリ4.0の実現に貢献し,迅速に,そして低価格で導入可能な通信技術であり,今後も機能拡張が続く。
IO-Linkコミュニティジャパンはメンバ会社と連携し,日本国内でのIO-Link採用と開発支援をしてゆく所存である。(図4)

図4 IO-Link コミュニティジャパンメンバ会社の製品とソリューション
ポータルサイトへ